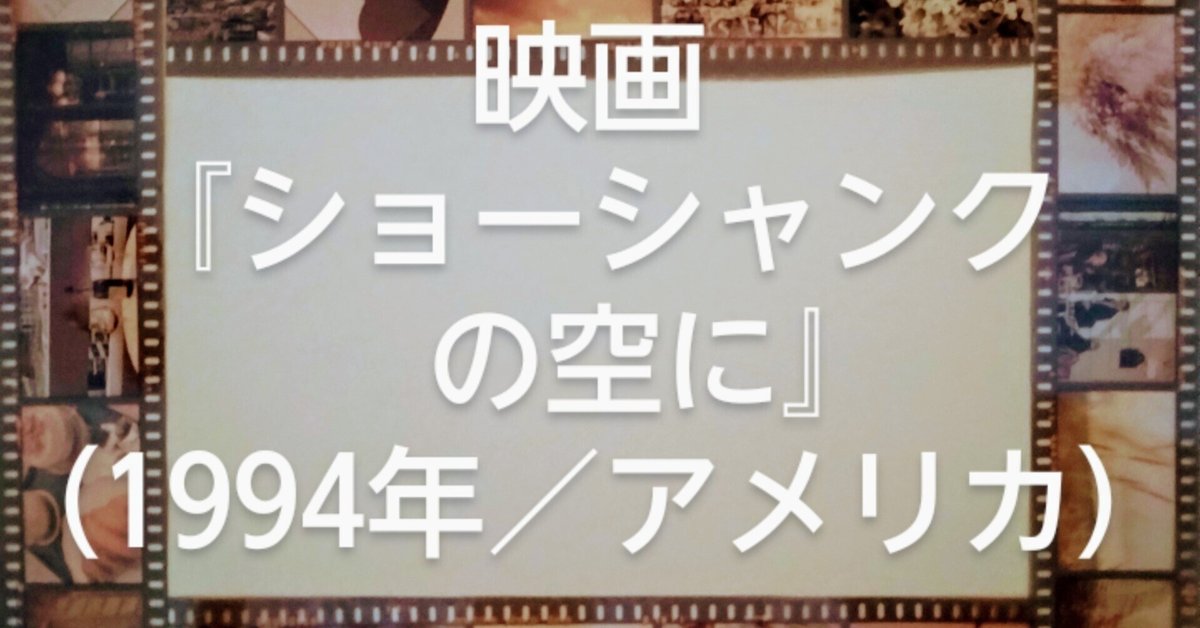
【映画】たまたま入った映画館で『ショーシャンクの空に』を観た…あの日確かに映画の神様がいたのかもしれない
人間性をなくした時が死ぬ時さ
【ショーシャンクの空に】
(1994年/アメリカ/監督 フランク・ダラボン)
■ジャンル/人間ドラマ、サスペンス、友情
■誰でも楽しめる度/★★★★☆(ある程度の大人、高校生位から)
■後味の良さ/★★★★☆(中盤は辛いけど、感動・・・)
(個人の感想です)

※以下、映画の内容にふれます
********************
■ただ泣きたくて、映画館に入った日
いま調べると、1995年の6月だったようだ。
私はその日、人生最大の失恋をした。まだ20年位しか生きてなかったけれど、そう思ったのだ――そのときは。
週末の、まだ日中だった。街なかをフラフラと歩いたが、泣きたくて、映画館に入った。我ながら良い案だったと思う。暗くて、少なくとも2時間はひとりになれる、いやひとりじゃなくても、誰も自分を気にしない。別にコメディ映画でもよかった。ひっそり涙を流すことができれば。
それは『ショーシャンクの空に』という、私にとっては特に前知識もないような映画だった。
映画館にあったチラシをざっと読んでみたが、フランク・ダラボンという全然知らない監督、ティム・ロビンスというあまり知らない俳優、モーガン・フリーマンという・・・この人だけは『ドライビング Miss デイジー』でかろうじて知っていた・・・という程度の情報量。
原作がスティーヴン・キングということに一瞬、おぉっ、とは思ったけれど、それだけで、期待はしなかった。
暗そうな内容なのも、逆にいいと思った。
ところがこれがとんでもない映画体験になる――というのは、どんな名作か知っている人なら予想がつくかもしれない。
公開から30年近く経ったいまなお語り継がれる名画『ショーシャンクの空に』のあらすじは、ざっとこんな感じだ。
1947年、メイン州ポートランド。若く優秀な銀行員であるアンディー(ティム・ロビンス)は妻とその愛人を殺した罪で終身刑となり、ショーシャンク刑務所へ送られる。
はじめは孤立するアンディーだったが、やがて所内で「調達屋」と呼ばれるレッド(モーガン・フリーマン)から趣味の鉱物採集に使う小さなハンマーを手に入れ、レッドと親しくなる。劣悪な環境のなか、暴力や理不尽な仕打ちに耐えながらもアンディーは、読書や音楽を通して仲間達に娯楽や人間としての尊厳を伝え、やがて所長の経理を手伝うようにもなる。人間らしく生きることを諦めないアンディーだったが、ある日彼の冤罪のカギを握る人物が入所してきたことで、運命が大きく変わることに…。
――なんか長いけど、これ以上削れない。
さてその日、失恋の痛みを抱えながらこの映画をなんとなく眺めていた私だったが、中盤からそう、すっかり前のめりになっていた。
■音楽や読書を愛する心は誰にも奪えない
刑務所で不当な暴力や仕打ちを受けながらも、我が身の不幸を嘆くわけでもなく、人間らしさを失わずに過ごそうとするアンディー。
それはもちろん「自分はやってない」という信念が土台ではあるだろうけど、レッドのような好人物もいて、チャンスさえあれば仲間たちの多くは、映画や音楽や読書を楽しむ「心」を持っているはずと感じたからではないだろうか。
刑務所内での限られた娯楽として、囚人たちが映画を楽しむシーンは印象的だ(出演する女優リタ・ヘイワースのポスターをレッドに調達してもらうことが重要な意味をもつことは、観た人なら誰でも知っている)。
「人間の心は石でできているわけじゃない」とはアンディーの言葉だけど、音楽や映画や読書の素晴らしさを知る人間は、それを「嫌い」ではなくただ「知らない」という人に、それを伝えたい、分け合いたいと思うことがある。友達になればなおさらだ。
冤罪を除けば、ここにいるのは確かに罪を犯した人ばかりだけど、根っから悪じゃない人間だっている。
だから。
アンディーがかけたレコードからモーツァルト「フィガロの結婚」のアリアが流れて、刑務所内に美しく響き渡るシーンで、私は泣いた。
囚人たちの大半は、誰がつくった何という曲かも知らないだろう。なのに、確かに美しいと感じているーーその表情。
そのとき観ていた私は、自分の涙の訳がわからなかった。まだ失恋の痛みかもしれなかった。
ただ思った――こういうの好きだ、と。

そして、レコードをかけた時のアンディーの嬉しそうな顔が素敵だった。怒られるってわかってるのにね。
人は、自分だけが楽しい時よりも、自分が人を楽しませることができたと思う時に、いい顔をするんだろう。なんとなく『ニュー・シネマ・パラダイス』でアルフレードがトトに、映写技師はキツい仕事だけど、自分がみんなに映画を楽しませてあげているような気分になるのだけが、唯一嬉しい・・・と話していたシーンを思い出した。
そして図書室の本を増やすことに力を注いでいくアンディ―。このことも私の心をワクワクさせた。
――心は奪えない。
人生最大の失恋をした(と思っている)私は、数時間前まで自分のすべてをなくしたような気持ちになっていた。
けれど映画や音楽や読書が好きという心は、誰にも奪えない私自身だ。アンディーの姿でそれを思い出す。
そして銀行員としての知識や経験を生かして看守達に納税や資金繰りのアドバイスをしたり、若い仲間に勉強を教えたりするアンディーは、殺人の罪で収監されているのにも関わらず、格好いい大人に見えた。
これはひとりの人間が職能を生かし、自分の置かれたコミュニティーを変化させていく物語でもあるんだーーと若い私もなんとなく理解した。
腐ってはいけない。
ただ、これだけで終わったのなら、自分のなかで伝説の映画というほど記憶に残りはしなかったかもしれない。本題はここからだ。
――脱獄である。

■え、脱獄映画? からの驚きと爽快なラスト
脱獄する映画だとは知らなかった。
いや、てっきり冤罪を晴らすものだと・・・(図書室の本をヒントに、自分でその方法を見つけるとか)。
ともあれ終盤、アンディーが果たした脱獄と、この映画の「悪」を一手に引き受けている刑務所長に行った復讐劇は、鮮やかとしか言いようがない。
これは私の知る限り、完璧な脱獄映画だ。
子どもの頃から、脱獄映画やニュースなどを見て「そんなことしてどうするんだ」と思っていた。
みんな脱獄そのものには知恵を絞り、時間をかけて準備もするけど、大抵はすぐに捕まる。逃げたとしても、資金や身分や潜伏先に困り、不自由なその日暮らしを強いられるのは目に見えているだろうに・・・という、かなり冷めた視点を持っていた。
いや、脱獄に温かい視点を持っている人はいないと思うけど。
ーーところがもう、アンディーったら!
すべてが用意周到、お金も身分も完璧に用意し、悪い奴はやっつける、この痛快さ。やはり知性と人間性はこういうことに使わなきゃ。
この結末にすっかり心を奪われた私は、出来のいい推理小説を読み終わったような爽快感に包まれていた。そう言われれば、伏線だらけだった。アンディーはずっと考えていたのだ。すごい。
捨てない希望も人間愛も良かったが、生粋のミステリー好きである私にとって、この完全無欠の脱獄劇は、気持ちいい以外の何ものでもなかった。レッドが語る「解決編」のような脱獄劇の顛末は、失恋で忘れかけていた私のミステリー好き魂を引っ張り上げたのだ。
まずい、これは面白いぞ。
そしてパーフェクトなラストシーンを迎え、映画館の片隅で私の顔は、なんだかわからない涙でグチャグチャになっていた。
人生最大の失恋は、さすがに映画1本観たくらいで癒えるものではなかったけれど、それとは無関係な自分の魂もここにあることを感じ、私はその後、家に帰った。
■忘れ得ぬあの年の、人間の尊厳の物語
『ショーシャンクの空に』はその後、何年も多くの人に語り継がれ、私は職場でもプライベートでも、この映画について何度かいろんな人と話す機会をもった。
「映画館には行けなくて・・・レンタルで観た」という人もけっこう多く、そのたびに「私は映画館で観ましたよ!」とちょっと自慢してみたりもした。あの日なぜ映画館に行ったかは、自分だけの秘密だ。
「刑務所にオペラが流れるシーンに感動した」「友情に泣いた」という人は多かったけれど、「あれは完全無欠の脱獄映画ですよ! ふつうは脱獄後、資金に行き詰まるものですが・・・」という私の熱弁は大抵、先輩や友達に苦笑いされた。でもそのマニア魂があの日、まぎれもなく私を救ってくれたものなのだ。いやもちろん、人間ドラマの感動は大前提として。
1995年は、日本人にとって忘れられない災害や事件が起こった年だった。私の失恋なんて本当なら笑い話だ。
アメリカでこの映画が公開されたのは前年で、撮影はもっと前だろうから、日本での公開はたまたまではあったけれど、多くの人があの年も、やりきれなさや不安を抱えて生きていた。
映画はただの映画。でも、ときに遠くの場所や国に住む名もなき人間に勇気を与えてくれることもある。たまたまあの日、この映画を観ることができたのは、私にとってなにか不思議な出会いだったのかもしれない。
あれからずいぶん時間が経った。当時好きだった人のことは、まるで前世の記憶かのように薄れてしまったけれど、『ショーシャンクの空に』の感動は少しも薄れることがない。


