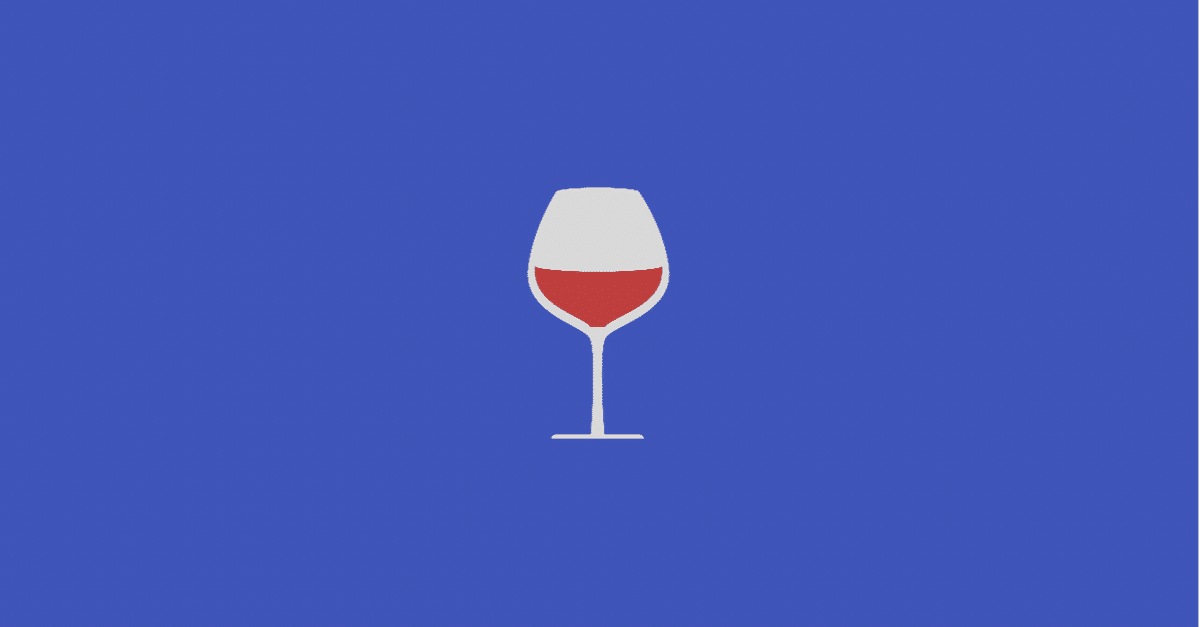
「長い別れ」をようやく読んでハードボイルドとは何かを知った
レイモンド・チャンドラー氏の「ロング・グッドバイ」をようやく読んだ。田口俊樹さんによる新訳が今春、創元推理文庫から登場したことがきっかけ。ハードボイルドとは何か、やっと少し分かった気がする。
ロング・グッドバイとは
1950年代刊行のロング・グッドバイは、清水俊二さんによる「長いお別れ」、村上春樹さんの「ロング・グッドバイ」が日本の読者に向けて訳出されている。田口さんの訳は新訳ということになり、タイトルも「長い別れ」で差別化されている。
ハードボイルドとは
コトバンクやウィキペディアの定義にはなるが、第一次大戦以降の文学スタイルで、犯罪など不道徳な事実についても価値判断を交えず、淡々と叙述することを指すそうだ。ヘミングウェイもハードボイルドに位置付けられる。
ロング・グッドバイもハードボイルドの系譜。本作は私立探偵フィリップ・マーロウが活躍する犯罪ミステリーもしくは推理小説だとカテゴライズできる。
このため、自分はハードボイルドは探偵とのつながりが強い印象を持っていた。語感として、無骨で、渋くて、タフな物語なんだと思っていた。
田口訳は読みやすい
どの版かは明記しないが、自分は過去、ロング・グッドバイに挫折した。ハードボイルドと聞いていたのに、文章が詩的で冗長に感じてしまったのが原因だった。少年の頃で若く未熟だったのも影響した。
今回通読してみて、詩的で、一つ一つのセリフ回しが洒落ているのはチャンドラーの原文が持つ美点なのではないかと認識が変わった。一方で、田口訳はかなりシンプルでクール、端的な表現が光り、詩的な魅力と見事にバランスしているように感じた。
あくまで主観だが、「長い別れ」はロング・グッドバイ初読者にとって読みやすいのではないかと思う。
ハードボイルドとは芯を持つこと
ハードボイルドとは、シニカルであることとは違う。むしろ、タフな芯を持ち、その芯をぶらさずに思考し、行動する主体的な姿勢のことだ。
物語の基本線は、探偵マーロウが酒場で出会ったある男の逃避行を助けること。その男が妻を殺したという容疑がかけられているのだが、マーロウは男との友情を信じる。これが「芯」だ。
マーロウはたしかに、殺人事件に対して冷静。あってはならないとか、逆にあってもおかしくないとか、評価を下さない。警察の横暴や、アルコール中毒、不貞行為といったさまざまな社会的タブーが出てくるが、マーロウはあくまで「それそのもの」として受け止める。
しかしマーロウは、酒場で出会った男との友情は疑わない。男に対する嫌疑が深まる状況に、やはり冷静に対応する。マーロウにとっての冷静さ、タフさは手段であり、性格や惰性とは違う。
ハードボイルドは知性である
マーロウのセリフの多くは、シンプルでクールだ。ほんのひと言を返す時もある。しかしそのワンワード、ワンセンテンスの中に、たっぷりの皮肉や、よくよく読み解くことで見えるひねりがある。
ハードボイルドは無駄のない叙述が特徴とされるが、それは単に表現を省くこととは違う。濃密な意味を込めることで、マーロウのセリフは鋭いナイフのように危険で、会話した相手の神経を逆撫で、激しい感情を引き出す。それが探偵術でもある。
ハードボイルドとは野性ではなく知性だった。
ハードボイルドとは精巧である
無骨というのは、荒々しいことでもあり、それはタバコやギャンブルやドラックや異性関係とも親和性が高いように思える。実際、マーロウは異性関係にはだらしないことを自称するし、奔放な一面も見せる。
だから、物語が「夢のように美しい女性とその夫」の関係修復を依頼されるパートに来た時、これは脱線なのかと思った。しかしそうではなかった。
今風に言えば、「伏線は見事に回収された」。でも「長い別れ」のそれは、精巧な工芸細工が最後に完成するように、納得感と美しさのあるものだった。
ハードボイルドに無駄はない。物語のシーンがあますことなく全ての要素が必要なものだという意味で。
ハードボイルドは傷跡である
ハードボイルドと戦争は切り離せないということも発見だった。ハードボイルドは第一次対戦後に生まれたとされるが、それはまさに、戦争の傷跡を内包する文学ということなのだろう。
マーロウが酒場で出会い手助けした男は、第二次大戦に従軍していた。その際についた大きな傷跡が顔に残り、さらに大きな傷を心の中に負っていたことが、物語の後半で見えてくる。
もちろんマーロウはトラウマや戦争の悲惨さに対してもクールだが、そこから目を逸らすこともない。むしろ男の傷跡にきちんと向き合ったのは、マーロウだけだったのかもしれない。
ハードボイルドは面白い
当たり前の結論も書き逃すべきではない。ハードボイルドは面白い。「長い別れ」はそれを証明した。
いいなと思ったら応援しよう!

