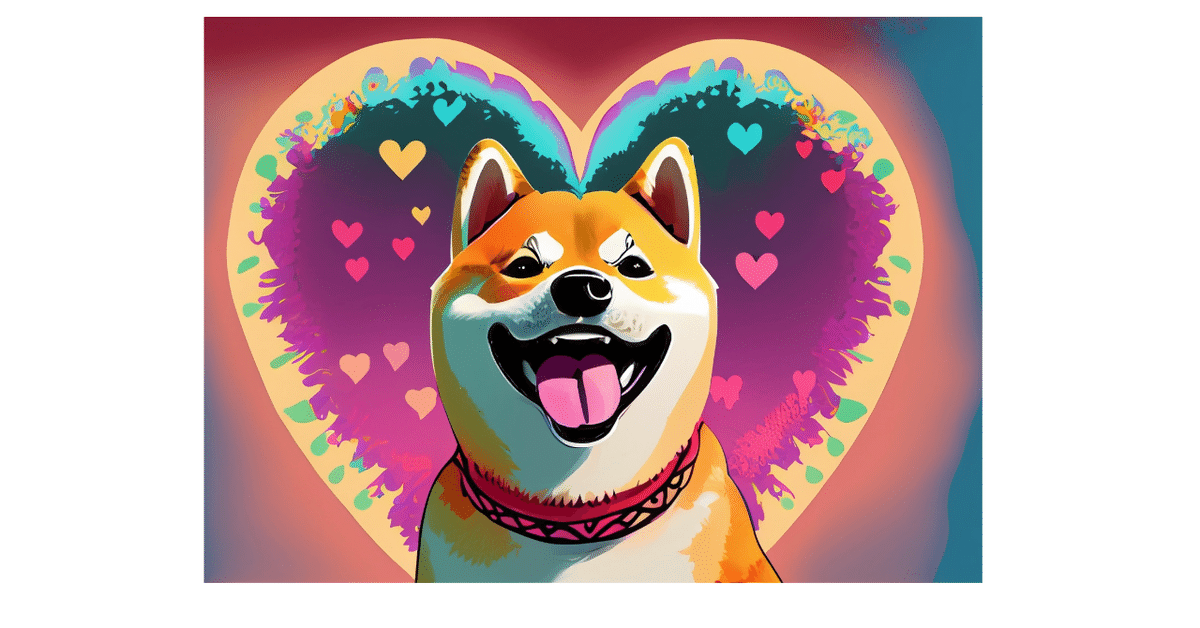
1月18日 Society of Performing Organizations 組織の評価基準
1月18日木曜日のランチタイムです。
今日の #ドラッカー365の金言 テーマは、
#Society_of_Performing_Organizations (組織のパフォーマンスを評価)
#組織の評価基準
組織の役割は何か。
その役割を果たすとどんな成果となるか。
その成果は顧客にとってどんな意味があるか。
その行為は、社会から、顧客から、会社ではどのように評価されるのかについても考えなくてはならないと思います。
“「この組織は、いかなる役割を果たすか。」 「この組織の成果は何か。」 「成果中心でなければならない」 ”
人事評価基準とは、社員やチーム、部署、部門がどのくらい目標を達成できたかを評価する基準のことです。 評価の項目は多岐にわたりますが、大きく分類すると、売上などの業績を基準にする業績評価、社員やチームの能力を基準にする能力評価、業務における行動を基準にする行動評価などがあります。
人事評価は成果、行動姿勢、能力という3つの要素から総合的に判断します。
成果は数字に代表される客観的成果であり、
行動姿勢は将来数字にも反映されそうなパフォーマンスを評価するものです。
能力に共通のルールはなく、業務上求められるスキルや知識などで判断します。
そして、不満が多いのも、人事評価制度です。
人事評価に対する不満として多いのは、基準が不明確である、結果に対するフィードバックがないといった内容があげられます。
評価が昇給・昇格などに結びつかない、評価の公平性が疑わしいといった不満もあるでしょう。評価の基準が会社の実情に合っていないことも不満が起こる原因です。自社の人事評価にこのような事情がないか、一度検証することも必要といえるでしょう。
今日のテキストは、『 #断絶の時代 』。手元にある昭和44(1969)年版だと、第9章 #組織のマネジメント 247ページ、278ページ、『 #ポスト資本主義社会 』1993年版 2章 #組織社会 97〜98ページ あたり。
#実りによって彼らを知れ 。
#あなた自身目標にふさわしい評価基準をもっていますか 。
どんなにあなたが正しいと思って行動したことも、あなたが所属する組織の評価基準と合っていなければ、正当化されません。組織の理論と個人の信条とがマッチしていないところに、悩みが生まれます。
組織が自社のAを売れ、と言いますが、組織の社員に雇われているSさんが専門家として客観的に判断したときに、他社製のBの方がいいよね、とわかっていたら、Aを勧められません。
だから、Sさんは「Aを改善したA‘にしよう」と提案する。ですが、「経費がかかる」と会社が拒否。それがエスカレートし不正にまで至った結果がダイハツ事件に発展したんだろうと推察されます。

誠実に、と提言したSさんは閑職に回され、組織は官庁に行政処分を受け、「誰が内部告発したんだ!」とキレて、犯人探し。
こういう組織になっていないでしょうか。
午後からもやっていきましょ!
いいなと思ったら応援しよう!

