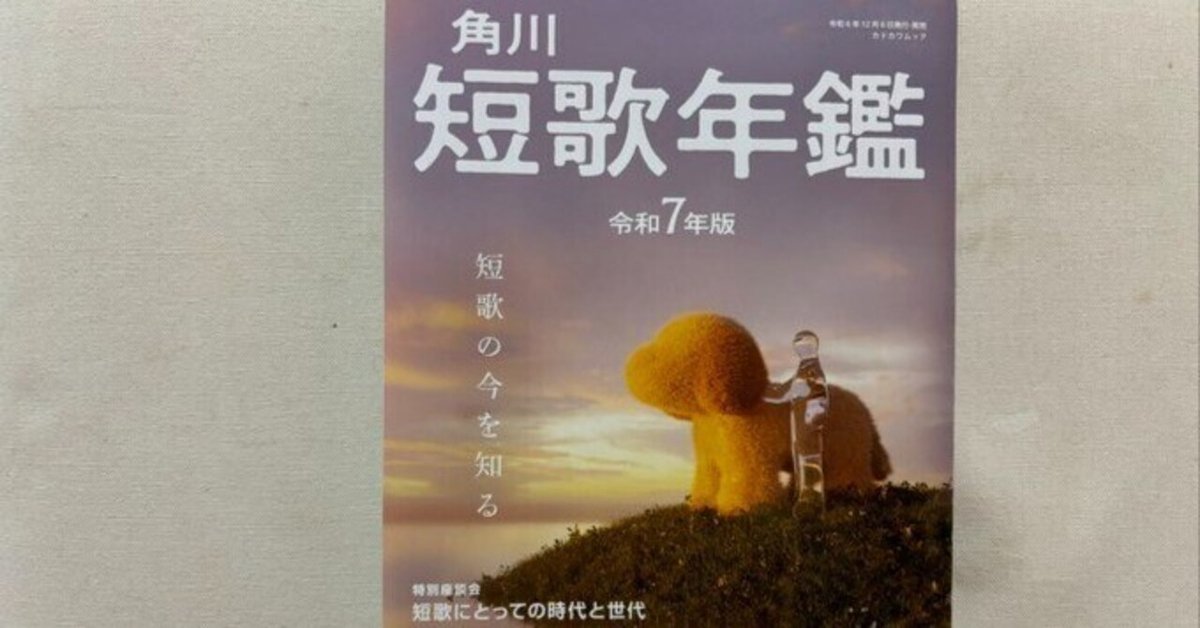
角川『短歌年鑑』令和7年版
①栗木京子「巻頭言」
〈このたびの『草の譜』を読んだあとには(…)作品をもっと煮詰めてから、あるいはもっと寝かせてから、歌集を編んでもよいのではないか、という思いがしてきたのであった。三十年は長すぎるとしても、七年か八年くらいは手元であたためて、テーマを絞り込んでから世に送り出してもよいのではなかろうか。〉
黒木三千代『草の譜』を読んでの言葉。先日『現代短歌新聞』から引いた井口可奈とは対照的な歌集の作り方と言える。これももちろんアリだろう。
〈ただし、私の場合は十年近く置いたままにすると、すべてを捨てたくなる可能性が高いのであるが。〉
先ほどに続く栗木の言。これには思わず同意。寝かせておいて熟成すればいいが、自分で嫌になるかも…。第一歌集を作る時みたいに古い作品を全部捨てたくなったりするかもしれない。
②「特別座談会 短歌にとっての時代と世代」
三枝昻之〈十年前わたしにひとりの妻がゐてわたしは彼女を引き止められなかつた 永田和宏 テクスト読みだけでなく、作者のデータを加味して読むことも、短歌の宿命的な鑑賞法だと思う。〉
無記名の歌会や作品の選考などではテクスト読みしかないが、作者の分かった歌集を読む時にデータを加味して読むことは読みを豊かにすると思う。そこでストイックになる人もいるのだが…。三枝は「宿命的」という言葉を使って柔らかく説明している。
③「特別座談会」
三枝昻之〈歌は近代以降は褻(け)の歌が中心で、私達の歌もほとんど褻の歌。だけども、そういう領域だけではなくて、晴(はれ)の領域の歌が短歌にもあって、そういう領域を意識をしておくことが、短歌の全体像を豊かにする。〉
確かにその通りなのだが、近代以降は褻の歌が中心過ぎて、もはや晴とか褻とかいう言い方が合わないような気すらする。晴というより公的な歌、褻というより私的な歌、という方が自分的にはぴったり来る。そう言ってしまうと、一般の歌人には公的な歌を詠う機会は少ないような。
今回三枝が挙げているのは長谷寺の梵鐘に彫られた歌。
「かぜのおとのとおきみらいをかがやきてうちわたるなりかねのひびきは 佐佐木幸綱」
この歌はいいですね。確かに晴の歌。あと思い浮かぶのは、歌人の作詞した校歌とか、そういうのが晴の歌、公的な歌だと思う。
④萩岡良博「作品点描3」
私の歌を4首挙げて評をいただきました。違う総合誌に載せた連作間の繋がりを考察していただいたり、初出と歌集掲載歌の違いにも触れていただきました。とても参考になり、励まされる評でした。ありがとうございます!
⑤「歌人アンケート 今年の秀歌集」
6人の方に川本千栄『裸眼』を選んでいただきました。本当にうれしい!ありがとうございます。私も三冊の推し歌集を挙げました。手に入る限りの歌集を読んだ上での渾身の推しなのでお読みいただければ幸いです。
2024.12.28.~29. Twitterより編集再掲
