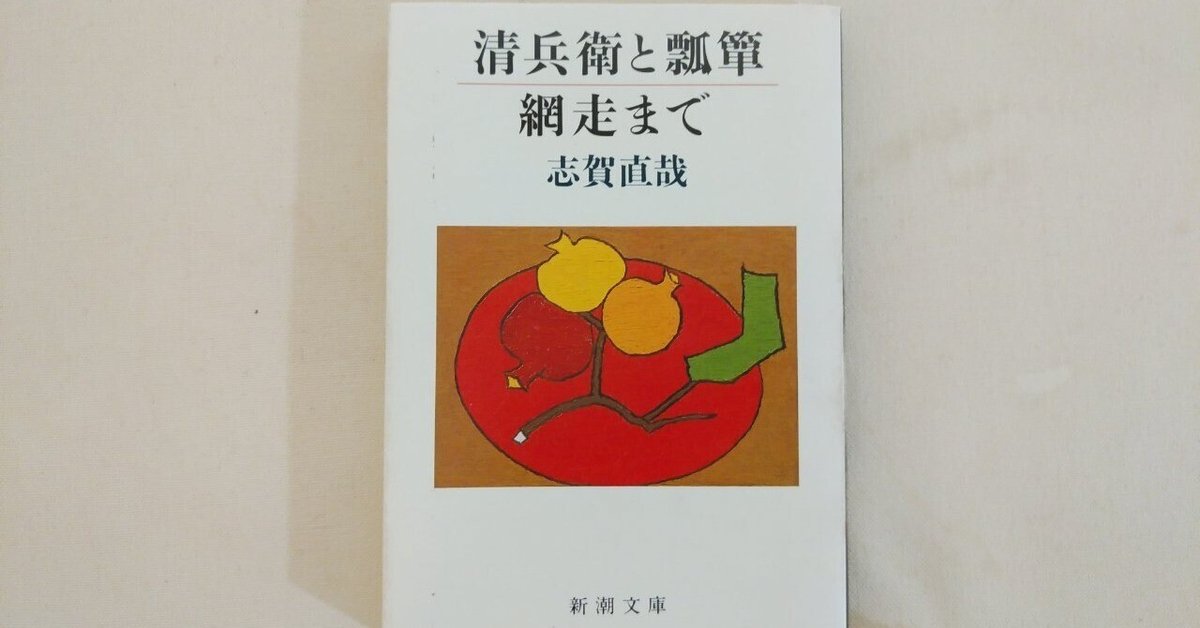
志賀直哉『清兵衛と瓢箪・網走まで』(新潮文庫)
短編集。収録作は「菜の花と小娘」「或る朝」「網走まで」「ある一頁」「剃刀」「彼と六つ上の女」「濁った頭」「老人」「襖」「祖母のために」「母の死と新しい母」「クローディアスの日記」「正義派」「鵜沼行」「清兵衛と瓢箪」「出来事」「范の犯罪」「児を盗む話」
私にとって、近代小説は読んでいる作家と読んでいない作家に分かれてしまっている。志賀直哉は読んでいない方。「正義派」だけは教科書で読んでいた。
今回、読んでみて何とも複雑な感想を持った。おそらく、しばらく小説を読んでいないことが原因だろう。短歌を始めてすっかり小説を読まなくなった。作り事なのが嫌だ、というのがその理由。しかし日本の近代小説における私小説の分野は作り事と事実の曖昧なところを突いている。そこが面白い人には面白いし、面白くない人には面白くない。短歌もそうだが、作り事、フィクション、ファンタジーと言っても、所詮は作者の実生活があってのこと、それを下地にしてどう膨らませるかということに尽きる。事実の無いところに作り事など無い。どんなに作り事に仕立て上げてもその土台には作者がいるのだ。
また、作者が見えるだけでなく、時代も見える。日本の近代小説家たちは個性を出そうとしのぎを削っただろうが、どこか時代の共通点、時代の気分というところは感じられる。短歌や俳句ではないが、作者名を隠して、あまり知られていない小品を読んだら、誰の作品か咄嗟に分からないこともあるのではないか。
志賀の小説を読んでその描写の細かさに驚いた。写生というのだろうか。しかし描写を省いて説明で話を進めるところは大胆でぐんぐん状況を説明する。心理描写も作者がしてしまう。その緩急のつけ方がやはり小説家と呼ばれるかどうかなのだろう。
個人的にはパワハラ、セクハラ、モラハラが嫌な感じを醸し出している小説が多いと思った。これは他の近代小説を読んでも度々思うことだ。時代的にしかたがないところだろうが。「鵠沼行」の主人公が家族に権勢を振るうのは読んでいて誠に耐えがたい。自分では当たり前のつもりなのだろうが、現代の視点で見ると即アウトのモラハラ。しかも振り回しているのがセコい権力。まあモラハラってそんなもんか。「清兵衛と瓢箪」の場合は父がパワハラだ。この父のパワハラは志賀作品の底流になっているのではないか。「網走まで」は同席した人妻の授乳場面をジロジロ見過ぎ。今ならセクハラでしょう。これ以外の「ある一頁」なども女を見るときは顔色と乳房の形状で表現している。細かい描写がまた嫌だ。どこまでが主人公の考えなのか作者の考えなのか私小説だけに線が引き難い。作者が当たり前と思っているのか、だめと思ってなおやっているのか。
小説らしい凄いオチがつきすぎるのと、つかない上につかないなりの情趣も無いという作品もあった。オチがつきすぎるのが「剃刀」。そんなことならないだろ!と絶叫したくなる。この短編集で一番面白かったのは「范の犯罪」(私小説ではない、私の考えでは、作者と主人公が分離している)だが、これもややオチがつきすぎ。逆に「母の死と新しい母」は、これ、小説?と言いたくなるぐらい拍子抜けだ。まあ、だから、オチに至る筋書きの面白さを味わうのではなく、そこへ至るまでの心理描写を味わうのが近代小説ということなのだろう。
〈風の吹く、気持の悪い日で、窓はすっかり閉めてあります。硝子を透す冬の夕日は社内を斜かいに仕切って射し込んでいる。日光の射す側には無数のほこりの漂うのが見える。すると、その側の人達は皆それを気にして、ハンケチか袖で口や鼻を被うています。私はそれに向きあった光の射さぬ方にいたのです。で、その時私は、ほこりが同じ密度で自分の目や口や鼻のまわりに飛んでいる事を知っていて、それで全く気にならないのを面白く思いました。見ると此方側の人達は皆平気でいる。更に向う側の連中を見ると、滑稽な位にほこりを気にしている。
どうせ、ほこりの中にいるなら、知らずに平気でいる人のほうが、幾ら幸福か知れないと思いました。〉「濁った頭」
こういう描写の部分、面白いと思いながら読んだ。
新潮文庫 1968.9. 本体520円(税別)
