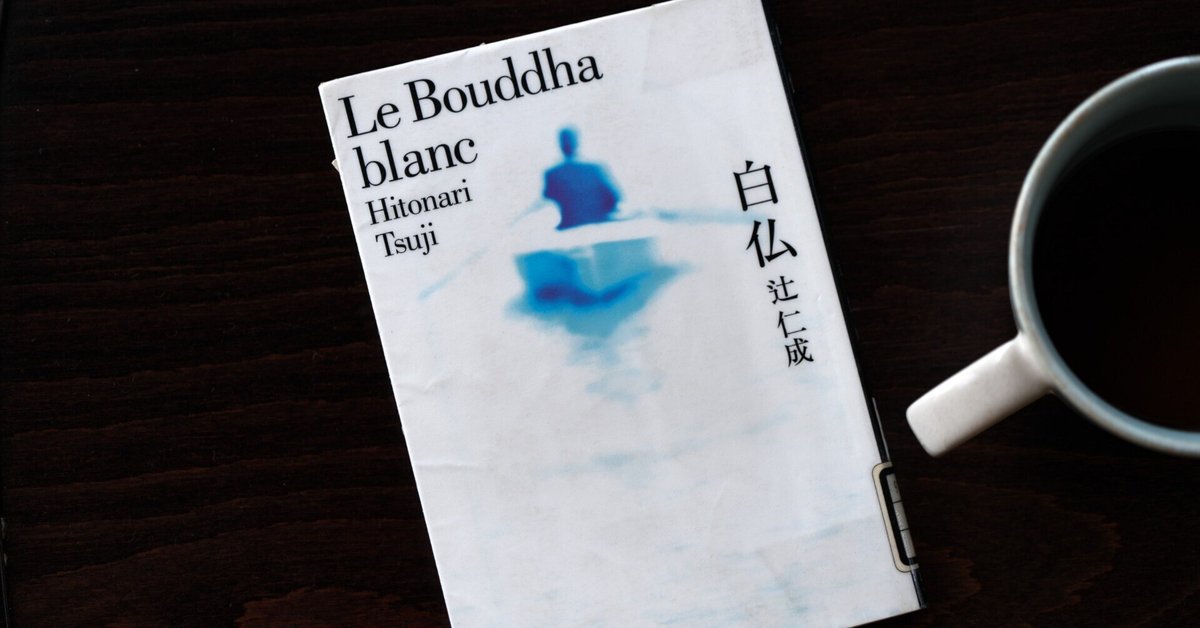
白仏を読んだ。
もし辻仁成の作品で「冷静と情熱の間」しか読んだことがないのならそれは本当に辻作品を読んだことにならないから「白仏」読んでみと妻に言われて読んだら凄かった。
「白仏」は辻仁成の祖父がモデルとなっていて、まったく凄いひとを祖父に持ったものである。その実際にあったこと、歴史が物語のバックボーンになっているがそうした事実関係を除けばあとの表現は辻仁成の創作であるとあとがきに書いてあった。
そのあとがきに続く書評で辻の文体はクラシカルで読みやすいものであると言われていて、その通りだと思う。先日読んだウルフの「灯台へ」はその書き方こそが新機軸であり特徴でそれが作品の価値を決定づけているわけだが、ぼくには実に読みにくい本だった。
そこへいくと「白仏」はすらすら読める。すらすら読めて心配になるくらいである。図書館で借りたのは正解で、期限の2週間を待たずに返却したほどあっという間に読み終わってしまった。
とても面白い本だったが感想文の書きにくい本である。
ただひとつ言えることは、人間はどんなに歳をとっても根底にある精神性は子供の頃から変わらないものなのだなあということだ。歳をとると周りからはその年齢相応の扱いを受けるわけだが、当の本人は昔と変わったような気はあまりしないものだ。だれもが自分自身に対して変わらぬ気持ちを抱き続けているにも関わらず、自分以外の人間と接するときは外見なり実年齢をもとにした対応ととるのはなぜだろう。
先日養老先生と田原総一朗の対談をYoutubeで観た。冒頭で司会者が二人合わせて百何十何歳と言っていて、養老先生がすかさず足してどうすると返していた。その通りだと思った。
さらに司会者は大量の昆虫標本を前にして、これ(養老先生が亡くなったら)どうするんですかと質問し、養老先生はすかさず「そういうのが嫌なんだよ」と答えていた。わかるなあと思った。
白仏の主人公は幼少期の初恋の相手を死ぬまで胸に抱き続けている。結婚して子どもができたからといって主人公の内面が変わるわけではない。その思い出は徐々に細部の詳細を失うことでより一層本質が光り輝いていく。そして都度主人公は変わらぬ自分を再発見するのであった。
物語は美しい抑揚をもって読者を終わりへと導いてゆく。すでに結末は定められており、そこにはどんでん返しもサプライズもない。ただあるのは彼が生まれてからあった生と、その生が終わったあとの死だけである。時間は流れていたようでいなかったとも言える。
いいなと思ったら応援しよう!

