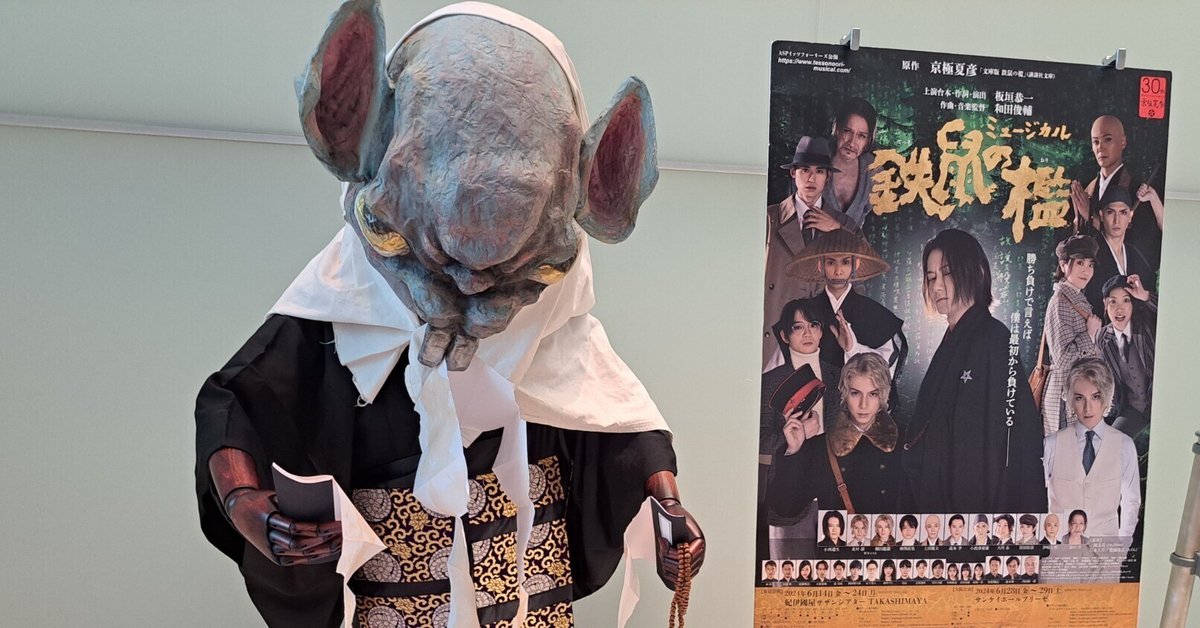
ミュージカル『鉄鼠の檻』配信のすすめ
○はじめに
『鉄鼠の檻』がミュージカルになった。
といっても、これを書いている時点ではすでに大楽を迎えている。2024年6月14日から6月29日まで東京大阪合わせて19公演、誰一人欠けることなく全公演完走した。昨年五類になった例のアレがまた流行り始めている中、非常にめでたいことである。
じゃあもう見られないのかといえばそうではなく。
実は6月22日~23日の昼夜計4公演は配信生中継があった。
一般に演劇の生配信といえばアーカイブ期間が1週間ほどだが、イッツフォーリーズという太っ腹な主催劇団様、なんと7月15日までの最大23日間という超ロングアーカイブ期間をくっつけた。
その間は定額見放題、何回見てもお代は同じ。
それも、今回は榎木津のみダブルキャストなのだが。配信4公演はそのダブルキャストそれぞれにスイッチング映像と全景映像を用意したもの。
なんていうか、こう、手厚い。こんな手厚い配信そうそうない。
さらに加えて、8月にはCSの『衛星劇場』というチャンネルでの放送も決定した。今のところ放送予定は1回だけだが、前作『魍魎の匣』も何度か再放送しているので、多分数ヶ月に1度くらいのペースで再放送がかかると思う。
…しかし、6月末に大楽を迎えて2ヶ月後にもうCS放送って速いなあ。
ところで。
ミュージカル『鉄鼠の檻』は、決して(時々見かける)「最初からリピーター客多数なのを前提で作られた演目」ではない。
だが原作がはらむ情報量の多さゆえに、1回見ただけではその情報を受け取るだけで手一杯。結果、「情報量が多い」が一番印象に残りやすいという、ある意味もったいない作品ではないかと思う。
※もちろん予備知識の量によっても違うし、1回見ただけで充分という方もいらっしゃうだろうが。
複数回見ることで色々なことに気づいたり深く考えられたり、そういうことが楽しいいわゆるスルメ演目だと思うのだが。いかんせん、東京16公演・大阪3公演は(普段大手制作会社の大劇場演目に慣れている身には)少ない。
リピートしたくてももう行ける日がなかった方も多かったのではないかと思う。
ところが上で書いたとおり、配信なら最終日まで何度も繰り返し見られる。CS放送も録画すれば半永久的に見放題だ。配信・放送の長所と演目の特性がマッチした作品といえるだろう。
というわけで、「ぜひとも配信&CS放送でミュージカル『鉄鼠の檻』を見て!」という、いわば作品のプレゼンをしてみたいと思う。
基本は原作未読の方向けに物語のネタバレなし、おまけは原作既読の方向けに物語のネタバレあり、という風に分けて書くので、ご自身の状況に合わせて読んでいただけたら幸い。
○そもそも、『鉄鼠の檻』って?
原作は京極夏彦先生著のミステリ小説で、いわゆる『百鬼夜行シリーズ』の4作目にあたる。劇団イッツフォーリーズ主催のミュージカルとしては『魍魎の匣』に次ぐ2作目。
舞台は昭和28年2月の箱根。ほとんど人に知られていない禅寺・明慧寺、老舗旅館・仙石楼、そして土砂に埋もれた謎の蔵、その3ヵ所を中心として物語は進む。
座禅を組んだ僧侶の死体発見から始まる「箱根山連続僧侶殺害事件」、十数年間成長しない振袖の少女、「あってはならないもの」が埋まっている蔵…一見するとまったく関係のない事象は時間の経過とともに徐々に繋がり、やがて物語は意外な結末を迎える―――――。
禅寺での出来事がメインなため、物語の中で禅について語られる部分が多い。
○ミュージカル版ってどんな感じ?
原作は1000ページを超える大作だが、原作既読勢の自分から見てミュージカル版はかなり忠実に作られていると思う。
もちろん小説と演劇では一言一句同じとはいかないし、これだけ長い小説をすべて演劇化しようとしたら何時間あっても足りない。なので削られているところはある。
個人的な感想を述べると、綿密に描写するところとバッサリ切るところとにメリハリをつけて話の筋を見えやすくしているのかな、という気がする。
『十牛図』のくだりを大胆に切ったり、物語の進行に直接関わりのないキャラクターを省いたりといったように。
それにプラスして語り手役を関口に集約することで話の交通整理をしている―――あの関くんが語ったら余計に混乱するのでは?という疑問はまあともかくとして。
そのうえで原作が持つ(悪い言い方をすれば)「小難しさ」、それを変にわかりやすくしすぎずに「なんだかわかったようなわからないような…」感をほど良く残していると思う。
前回『魍魎の匣』からさらにパワーアップした部分といえば、『背景に現れる文字』。台詞の中でわかりづらいと思われる単語だったり人名だったりが、文字情報としてキャラクター達の背景に現れては消える。
これについては賛否両論あるようだと、SNSの反応を見て感じたのだが。多分、原作を読み込んでいる勢とそうでない勢で意見が割れているのではないかなと予想している。
たとえば序盤の中禅寺の歌の中に出てくる「いさんきょうさく」。原作をよく読んでいれば「潙山警策」だと即座に漢字変換できるだろうが、そうでない人でぱっと理解できるのはよほどの博学か、そうでなければ学問としての禅に通じているかくらいだろう。
「え、今なんて言った?」とストーリーと直接関係ないところに気を取られてしまわないように、しつこいくらいに文字情報を出しているのかなという気がした。
原作の『鉄鼠の檻』は複数の場所にキャラクターが散っており、同時多発的に色々なことが起きる。
おそらくそれをわかりやすくするためか、舞台上に大道具はほとんどなく、プロジェクションマッピングと舞台後方の細い壁の動きで場面転換していく。
ミュージカル最大の要素・音楽は今回、和田俊輔氏が担当している。
なにしろ情報量が多い舞台なのに加えて曲数が多いため、劇場で見始めた当初は「頭に残らないな…」と思っていたが。
ところがどっこい、2度3度と見ていくにつれて様々なフレーズが日替わりで脳内で鳴るようになっていった。慣れると妙にクセになるのは音楽のせいでもあるらしい。
そしてミュージカルになじみのない方が気になっているであろう部分について。
よく(半分揶揄のように)語られる「ミュージカル=歌って踊る」、これは多分宝塚歌劇団や劇団四季あたりのイメージからきているのだろうと思っているが。ミュージカル、歌は絶対にあるがダンスはないことも多い。
『鉄鼠の檻』に関して言えば、歌って踊るシーンは一応2ヵ所あるにはある、が。別に世界観を壊すような造りではないのでご安心を。ネタバレになるので詳細は避けるが、基本的に踊っても違和感のない人が踊る。
「歌う京極堂」もよく話題になっていたが。あの長々した蘊蓄をほぼすべて歌にすることで頭に入りやすくしていると思う。
全部台詞だったら喋っている方も聞いている方も双方しんどいだろう。…いや、歌っている方はどちらにしてもしんどいだろうが。
○配信の「スイッチング」と「全景」って?
配信はダブルキャストそれぞれに「スイッチング映像」と「全景映像」が用意され、全4パターンの中から選んで購入することになる。
「スイッチング映像」は簡単に言うと「一般的なドラマのように複数のカメラを使って撮影された映像」。
引きになったりアップになったりを繰り返す。YouTubeなどで公開されている演劇のゲネプロ映像のようなもの、といった方がわかりやすいか。キャストの表情などはわかりやすいが、逆に言うとキャスト以外の背景映像などはほぼ映らない。
↓ゲネプロ映像の例(こちらはあまりカメラ動かないけども)
「全景映像」は定点カメラを使って後方から舞台全部を撮った映像。
基本的にカメラが寄ったりはしないので背景に出る文字情報や映像効果は見やすいが、細かい部分は見えづらい。
どちらを選ぶかは、あるいは両榎木津のどちらを選ぶかはその人次第だが。
原作を知っているなら文字情報がいらないのでスイッチング映像がいいのかなという気がする。
○ミュージカル版キャラクター
(※名前の順番はパンフレットに準じる)
・中禅寺秋彦(小西遼生)
おそろしく博識で顔が凶悪な古本屋兼神主兼憑き物落とし。呼び名『京極堂』は古本屋の屋号。憑き物落としとしての正装は黒一色に小物だけが赤の和装。
前作から引き続いての登板。中身さんの「台本に原作を書き写している」「稽古中は早朝に原作を読んでから稽古場に行き、帰宅してまた原作を読んでいた」などの逸話が示す通り、一挙手一投足が原作から抜け出てきたレベルの再現度高い中禅寺。本当に、驚くほどに中禅寺。
1幕後半と2幕終盤に行う歌う憑き物落としの迫力は圧巻。
・榎木津礼二郎(北村諒/横田龍儀)
旧華族の出で父親は財閥の長、だが本人は『薔薇十字探偵社』を運営する探偵。強烈な美貌と個性の持ち主。「人の記憶」が見える特異体質。
ダブルキャストで北村氏は前作から引き続いての登板、横田氏は新登場。北村氏は榎木津の不遜かつ人形のような佇まいな部分、横田氏は榎木津の破天荒で何をやらかすかさっぱりわからない部分を、それぞれ特にクローズアップしているのかなといった印象。
あるシーンで「榎木津ガールズ」というコーラス兼バックダンサーを引き連れて出てくるのがお約束。今回のアドリブ担当。
・関口巽(神澤直也)
物語の語り手、売れない小説家。性格はいわゆる陰キャの極み。中禅寺とは旧制高校の同級生で、榎木津は同じ高校の先輩。思い込みで暴走する癖がある。あだ名は猿。
こちらも前作から引き続いての登板。旧制高校三人組の中で唯一、主催劇団の劇団員。全編通しての語り手役なので原作より若干しっかりしているような印象。猿は猿でも小型のペット系洋猿っぽい。
・和田慈行(上田堪大)
明慧寺の禅僧。4人の知事の1人でひどく戒律にうるさい。人目を引く美貌の持ち主で癇癪持ち。終盤に大きな見せ場あり。ちなみに名前の読み方は「じあん」。
・山下徳一郎(高本学)
神奈川県警本部の警部補。原作よりスマートで若干キザな印象のエリート。性格はきつめだが打たれ弱い。いばっている時と意気消沈している時に落差あり。
・杉山哲童(小波津亜廉)
明慧寺の禅僧。関東大震災時に仁秀に拾われて育った若い大男。ミュでは触れられてないが障害があってあまり喋らない。力持ちさ加減を発揮するシーンあり。
・鳥口里美(大川永)
カストリ雑誌の編集者兼カメラマン。原作では男性だがミュでは女性。明るく調子がいい。口癖は「うへぇ」。
前作からの続投組で、敦子とペアで動く。主催劇団員。
・中禅寺敦子(宮田佳奈)
中禅寺の年の離れた妹。名門出版社の編集者。明るく活発、頭の回転が速い。前作からの続投組。どちらかというと現代の若い女性風の造形。主催劇団員。
・松宮仁如(伊﨑右典)
冒頭で鳥口と敦子が出会う旅の僧。鎌倉の禅寺からとある理由のために明慧寺を目指して歩いている。彼の思い込みが事件を複雑化させる。
本格的な出番は2幕から。
・大西泰全(森隆二)
明慧寺の禅僧。慈行の祖父の弟子で最高齢の僧。一見すると飄々とした好々爺。迷う今川を導く。二番目の犠牲者。主催劇団員。
・中島祐賢(吉田雄)
明慧寺の禅僧。4人の知事の1人で慈行と仲が悪い。修行熱心で面倒見の良い僧侶のように見えるが、実は?
『魍魎の匣』では木場修役。主催劇団員。
・飯窪季世恵(近藤萌音)
名門出版社の編集者で敦子の先輩。取材のために訪れた仙石楼で「宙に浮かぶ僧侶」を目撃する。「ヒトシ(とスズコ)」をずっと探している。主催劇団員。
・菅野博行(藍実成)
明慧寺の禅僧だが現在は精神を病んで幽閉されている。出家する前は小児科医で久遠寺が経営する病院に勤めていた。宿屋の主人と兼役。
・今川雅澄(小原悠輝)
古物商で待古庵の店主。性格は穏やかで「~なのです」が口癖。榎木津の軍隊時代の部下。了稔から『神品』の取引を持ちかけられ、仙石楼で彼を待つ。
・和田智稔/牧村托雄(岡田翔太郎)
2役。
智稔→慈行の祖父であり、山奥で半ば埋もれていた明慧寺を「発見」する。すべての始まり。
托雄→常信の行者(=従者)で若い僧侶。人当たりがいい。秘密がある。
・加賀英生/尾島祐平(山下真人)
2役。
英生→祐賢の行者で若い僧。子犬系小坊主でかわいらしい。秘密がある。
尾島→盲目の按摩師。彼が雪道で出会った「何か」が殺人事件の始まり。
※松宮父も演じる。
・鈴/松宮鈴子(身内ソラ)
鈴→不思議な歌を歌いながら山をさまよう振り袖姿の美少女。仁秀のもとで育つ。
鈴子→飯窪の同級生。13歳の時の火事で行方不明になる。主催劇団員。
・増田龍一(光由)
神奈川県警本部の刑事で山下の部下。いつも真面目にメモを取っている。1幕後半の禅のレクチャー時は明るい生徒役。主催劇団員。
・小坂了稔(志賀遼馬)
明慧寺の僧侶。4人の知事の1人で悪い噂が絶えない破戒僧。慈行・常信からは嫌われている。今川と取引予定だった。最初の犠牲者。主催劇団員。
・菅原剛喜(宮村大輔)
所轄の刑事。山下とは真逆のたたき上げ。幾分粗野で乱暴な警察官だがミュでは主に肉体労働で活躍する。地元の巡査と兼役。主催劇団員。
・桑田常信(松原剛志)
明慧寺の禅僧。4人の知事の1人で了稔を嫌っている。出家前は(進学率が著しく低い時代に)大学生だったインテリ。次に殺されるのは自分だと怯える。
・久遠寺嘉親(福本伸一)
仙石楼の客。元々は医師で病院を経営しており、前年夏の事件(※姑獲鳥の夏)で中禅寺達と知り合う。
了稔殺害事件に際し、探偵の榎木津を箱根に招聘する。
・円覚丹(内田紳一郎)
明慧寺の僧侶を束ねる貫首。華やかな袈裟をまとっている。了稔と共に明慧寺に入山した。重々しい物腰で警察らと対峙する。
2幕中盤までとそれ以降の落差がすごい。
・仁秀(畠中洋)
明慧寺のそばに住む年齢不詳の老人。老いて腰が曲がっている。浮世離れした雰囲気の持ち主。
明慧寺から施しを受けつつ、血が繋がらない哲童と鈴を育てている。
※他にアンサンブルキャスト兼影コーラスとして3人の女性劇団員が登場する。声が綺麗で歌がうまい。一番目立つ出番は「榎木津ガールズ」。何それ?と思ったら配信かCS放送で確認を。
○おわりに
以上、大きなネタバレなしでミュージカル『鉄鼠の檻』の概要その他をつらつらと書いてきた。
原作を読んだことがある人はわかると思うが、『鉄鼠の檻』は明るく楽しい話でも探偵役が難解な謎をズバッと解決する爽快な話でもない。でも面白い。
わからないことがあっても、難しくても、そのこと自体が面白いという不思議な作品だ。
原作を読んだ時の感覚をミュージカルで追体験するという稀有なこの作品をぜひ多くの方に見ていただきたい。そのための一助になれば幸いだ。
【おまけ】原作ネタバレありのおすすめどころ
まずはなんといっても歌う憑き物落としだろう。1幕後半のvs常信、そして2幕終盤のvs覚丹、vs仁秀。
ミュ版の中禅寺は原作より長身だが、その体躯を活かして上から相手の目を力強く覗き込んで歌う。相手の瞳を通してその中に巣くう憑き物―――今回は鉄鼠を捕らえるかのように。
相手もしぶといので憑き物落とし対決は迫力がすさまじい。
仁秀が圧巻の存在感。彼の前では中禅寺も「お若い人」にすぎないのだと思い知らされる。そんな彼が火事の中で見せる哲童・鈴の関係性が切ない。
慈行の放火、ただのプロジェクションマッピングではない迫力の仕掛けがある。余談だがあの放火、楽日に向かうにつれて派手になっていった。
物語は原作と同じで「拙僧が殺めたのだ」で始まる。文章ならまだしも、舞台でどう「盲目の按摩師が出会う殺人」を表現するのかと思いきや。そう来たか!となること請け合い。
余談だがこの按摩師の尾島が非常にうまいのでそこも注目ポイントだ。
その按摩師の尾島と兼役の英生、男性しかいない閉鎖空間でこういうタイプはそりゃモテるわ…と謎の説得力がある。托雄の回想シーンでの2人が妙にかわいい。
キャスト発表時に久遠寺先生がいて「姑獲鳥はミュージカル化していないのにどうするんだ」と思ったら。「それは別の物語」と語り手に言わせる傍ら、うっすら菅野のやったことを推測できる仕掛けになっている。
旧制高校3人組の「ベタベタ仲がいいわけではないが絶妙な距離感」がとてもよい。京&関、京&榎、榎&関、それぞれの関係がなにげないシーンで垣間見える。
関口の中身さんが3人で唯一の劇団員、しかも今回の公演委員長だそうなのだが。そのせいもあってカーテンコールでは中禅寺・榎木津の中身さん達から「原作の彼ららしく」立てられている。配信でも映っているので確認を。
鈴役の方は新人さんだそうだがとてもよい。最後の声は26歳なのだろうなとするっと入ってくる。

