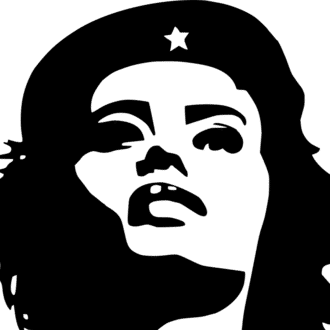2021年読んだ本 社会科学編
昨日の続きです。
今日は社会科学など昨日書ききれなかったぶんを。
とはいえ今年はHobbyとしての社会科学の読書はあまりできなかった。
『自由の国と感染症』の翻訳とかそれにまつわるお勉強がまあまあ大変だったからである。
とはいえ全く読まなかったわけではない。
例えば、みすず書房つながりでいえば、ミラノビッチ大先生の新著。
グローバリゼーションがもたらす、世界的な格差是正、または先進国内での格差拡大などのおなじみの論点や、資本所得と労働所得の割合の変遷、パワーカップル現象は日本だけじゃないことなど、安定の面白さだった。
今年はピーター・ターチンの著書を初めて読んだ。
数式満載で非常に読みにくいが、彼のエリート過剰生産論の骨子はつかめた。現時点では邦訳書はこれだけだが、より一般向けの『Age of Discord』の邦訳が進行中であると聞いている。楽しみだ。
MMT関連では昨日も触れたこの本は読んで良かったと思う。
これに触発されて、こんな記事を書いたのだ。
MMTは実物の問題を解決しないのだけど、問題なのは貨幣ではなく実物だと教えてくれたのはMMTだった。ここをごまかしてはならないと思う。
社会科学の本はあまり読まなかったけど、雑誌にはそれなりに目を通していた。
クライテリオン7月号は大澤真幸氏と飯田泰之先生の記事が面白かった。特に飯田先生も上述の、問題なのは貨幣ではなく実物という論点にも触れられていて、なんだか嬉しかった。
飯田先生、保守系のクライテリオンだけでなく、東浩紀氏の主宰するゲンロンにも登場されていた。保守とかリベラルっていう分類が無効になりつつあるということを象徴しているように思われた。
鹿島茂氏の新聞王ジラルダンの解説、井上智洋先生の論考なども面白かった。
ゲンロンでの飯田先生、井上先生、東氏の対談で貨幣の歴史について言及があり、『日本史に学ぶマネーの論理』を購入した。
貨幣史って通説がわりと簡単にひっくり返ったりするので面白い。というか貨幣とはなにかってのが分かってるようで分かってないのでスリリングなんだよな。
しかし今年は日本史の本をほとんど読まなかった。。。これと、加藤陽子氏の『天皇と軍隊の近代史』くらいかな。
去年買って読みかけになっていたが、なんとか読了した。やはり日本近現代史は面白い。来年はどれほど読めるかわからないが、関心は持ち続けるだろう。
あとは国連英検対策も兼ねていくつか国際政治的な本も読んだ。
天野之弥氏の回顧録、非常に良かった。福島第一原発事故のときにIAEA事務総長はこの人だったのだ。
国連で活躍した日本人で忘れてはならないのはこの人だ。内容はタイトルのとおり。これも面白い。
北岡伸一先生の国連体験記も面白かった。天野之弥氏の回顧録にも事務総長の生々しさが書かれていたが、国連本部の生々しさを綴ったのがこちら。外交の場における駆け引き、取り引きがいろいろ書いてあって面白い。
これらは志ある若者にはぜひとも読んでもらいたいなあと思った。
他にもいろいろ読んだが、まあこれくらいにしておこう。
来年はやはり今年あまり読めなかった、仏教や日本史に取り組みたいな。
本noteでは学習や読書の記録を主に綴っているが、来年もそれは変わらない。学び続けるとなにかいいことあるかも、ってことが伝わればいいと思っている。
いいなと思ったら応援しよう!