
ポールオースター 鍵のかかった部屋 極私的書評
ネタバレ有ですが、内容にあまり触れずに観念的な事ばかりが書いてあります。気になる方は是非読後にどうぞ。
何度読み返しても答えに辿り着けない小説、ガラスの街・幽霊たち・鍵のかかった部屋からなる、ポールオースター初期三部作・NY三部作ほど読めば読むほどに幻惑される作品は無いだろう。

大きい枠組みで言えば探偵小説の「ような」
ものである三作品だが、一般的な探偵ものと違って、ほぼ事件も起こらず、探している相手も見つからず。というより何を探しているのか分からなくなった瞬間から物語が動き出すという一風変わった作品群である。発表順にそれぞれのページ数は200、120、220ページとどれも厚い本では無いのだが如何様にも読み解ける作品の奥行きは沼のように無限で生半可な哲学書では辿り着けない人間の本質、深淵に迫る途方もない文学だと私は思います。

日本国内では殆ど総括的に批評されていないトリロジーを全てまとめて総評する!と言いたいところですが、他の書き物や読み物、全てがストップしてオースターにかかりきりになってしまいそうなので日和ました、てへぺろ。(ガラスの街の批評をした成瀬厚さんという方の論文を読んでみたのですがベンヤミン・ポー・ラカン・ボオドレール・ホーソーン・ボルヘス…とまぁ大学も出てないブックオフ野郎では太刀打ち出来ない事が早々に分かったので諦めました)
一筋縄ではいかないポールオースターの作品の濃さが引用されるメンツの濃厚さから伺えるでしょう。

「鍵のかかった部屋」に焦点を絞って自分なりの意見を書きたいと思います。
まずはざっくりとしたあらすじ。1993年リリース白水uブックスの背表紙からの引用です。
美しい妻と傑作小説の原稿を残して失踪した友を追う「僕」の中で何かが壊れていく…。緊張感あふれるストーリー展開と深い人間洞察が開く新しい小説世界。高橋源一郎氏が激賞する、現代アメリカで最もエキサイティングな作家オースターの〈ニューヨーク3部作〉をしめくくる傑作。
色々な意味で不在の人物を探しているという設定が共通しているトリロジーです。それぞれが独立していて1作品だけ単体で読んでも楽しめるのですが、最終章とも言える鍵のかかった部屋に関しては前2作を未読だと作品の魅力については充分に伝わらない、というよりきっと理解しにくいだろうと思います。(とりわけガラスの街は必読かと)
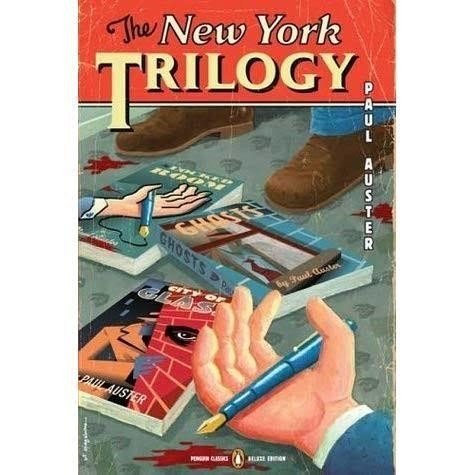
加えてトリロジー作品内のキャラクターは同じ名前で至る所に顔を出し、それが同一人物なのかどうかも分からず読者は混乱させられます。本作でオースターは文章を書くという行為によって生じる様々な事象について探求しており、ペンネームを用いる人物の心理について作品で言及している箇所もあります。単純に名前という記号・シニフィアン、だけに留まらずそこから自己同一性・シニフィエに至り、小説を書く行為を通じて、自分とは何か?何を持って自分は自分と言えるのか?というテーゼがトリロジー全体に掲げられているのではないかと私は考察しました。あらゆる事象の核となる部分とはなんなのか?というオースターの疑問をひたすらに突き詰めた3作なのだろうなと読み返しながら感じました。
作品の導入部分をまとめてみました。
幼い頃は双子の様に仲の良かったが現在では疎遠となっている古い友人・ファンショーの妻・ソフィーから手紙を貰い、彼が六ヶ月以上も前から失踪している事を告げられる主人公(ちなみに名前はありません)直接会って話を聞いてみると主人公が何やら奇妙な立場に置かれている事が明らかになる。
「ファンショーの身に何かあった場合にはファンショーの執筆した膨大な原稿の出版の有無を主人公に一任する。出版した場合には主人公は売上の25パーセントを受け取る。出版に値しないという結論の場合はソフィーに原稿を返却し、彼女は原稿全てを破棄する」
幼少期のファンショーの子供らしからぬ内面・ファンショーの過去や家族・ファンショーの原稿の反響・ソフィーと主人公の関係・名前の無い手紙…様々な出来事や回想が濁流となって作品に流れ込んできます。
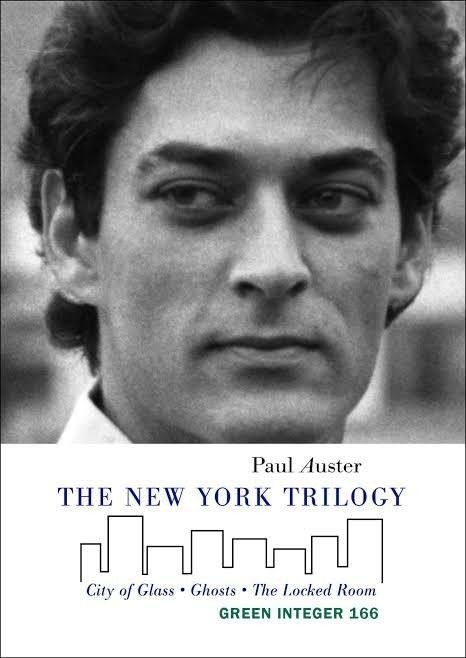
ここからは私なりの意見。
主人公にとって幼年期を共に過ごしたファンショーはヒーローの様な存在だった。疎遠になっているとはいえ、大人になってからもそれは変わらずの気持ちだった。ではファンショーの気持ちはどうだったのか。ヒーロー、或いは「優れている」とされている倫理観の持ち主にしか分からない苦悩というものは一般的な、市井の人々にとっては全く理解出来ないものなのではないかと推測します。
例えば地下鉄の中で聞こえる小さな舌打ちや買い物時に目にするクレーマー。些細な事、しかし誰にとっても気分が良いものではないのは分かりきっている。ではヒーローと目される人々にとってはどの程度、不快や悲しみを感じるのか?という点に着目してみます。
船乗りをしていた時期、ファンショーは黒人の調理助手と親しくしていました。白人乗組員の中で唯一だった。そんな折に典型的なレイシストの白人が乗船してきました。お分かりの通り、その調理助手に向けてぶつぶつと日々陰険に悪態を付いていた。そしてある日それが無視出来ないほどの罵詈雑言になり、度を超えた瞬間のファンショーの激昂っぷり、激怒の様子から彼のパーソナリティが紐解けるのでは?と私は考えました。
「他人の為に自身の全てを投げうつ事が出来る」と主人公が評している通り、ファンショーはどんな些細な事であれ全ての悪意や不条理に全力で悲しんだり、牙を剥いて生きて来たのでしょう。それは「このくらいの悪意や差別は世の中じゃ当たり前」という社会通念に1ミリも迎合しない高潔な魂を持っていると言えるでしょう。素晴らしい特性だとは思いますが、それは極めて「生きにくい」のでは無いかと思います。全ての不合理や他人の虫の居所に左右されるとなると世の人々はまずもってマトモに生きていく事は難しいでしょう。心が風邪を引くなんてもんじゃない、インフルと肝炎と脳溢血が一気に身体を駆け巡る様なもんでしょう。現代では酒場でクダを巻いて溜飲を下げて憂鬱な月曜日をまた迎える人間だらけだと思います。しかしファンショーの様な人間にとっては溜飲が下がる事など永遠にあり得ないのかも知れません。
生き続ける内に悲しみや怒りは発散の行き場も無く、どんどんと膨らみ続ける。その苦悩はきっと凡人には分からない。感度やものさしがまるっきり違うからだ。しかしだからこそファンショーはあくまで一般人としての主人公に一口には言えない感情で「僕がただひとつ望むのは、君がずっと自分自身でいてくれることだ」という親愛?諦念?希望?を込めて願いを込めたのでは無いかと思うのです。自分以外の全て、その代表としての主人公に。
双子の様に似ていた2人だがファンショーと違って主人公はファンショーを通した形でしか自己を認識出来ない。

ラカンの鏡像段階が作品を読み解くキー
終盤、パリの酒場で全く知らない男を見て主人公はファンショーであると定義した際にはもうすでに主人公の中からファンショーと言う幻想、自分自身を定義するのに必要不可欠だった存在であるファンショーという記号は、もう既に消え失せて、もうどうだっていいと、パラノイアックな錯乱に陥ったのでは無いのだろうか。
なので最後の鍵のかかった部屋越しの対話は主人公が初めて幻想・記号と決別し、自己の内面と対峙していく初めての一歩の様子を表しているのではないのだろうか。唐突に終わる小説の先こそが主人公にとって本当のスタートラインなのだと私は感じました。その先に希望が待っているかどうかは分からないけど、生き続けなければならない。
読んだ感想をまとめてみる。
克明な情景描写によって主人公の人生が行間から浮かび上がってくる純然たる文学作品だと感じました。言葉を書く行為、文章を生み出す事によって生じる苦悶や葛藤から言葉=コミュニケーションの原始に遡り、人間の意識の芽生え、自己の定義とは?自己と他者の本質的な意味での関係性までも追求する形而上学的宇宙が広がるポストモダンと呼ばれるに相応しい実験性と純粋に知的探求心をくすぐる優れた小説だと言えるでしょう。
初めて読んでのは7年前程。その他のオースター作品もそれなりに読み進めて来ましたがずっと心に引っかかっていた作品で、言語化出来ない想いをいつか自分なりに書いてみようと思っていました。簡潔で上質な感想を書ける様に精進していきます。(ドンキホーテ、ホーソーン、ロビンソンクルーソーを読みこんでから、またいつかニューヨーク三部作について考察を書けたらと思っています)
現代作家ガイド1 ポールオースター 彩流社
「すべてが始まる場所」を求めて
鍵のかかった部屋論文 高岡昌範
この2つ解説のお陰でかなり作品への理解が広がりました。現代作家ガイドには空腹の技法にも収められているオースターへのインタビューが掲載されており、オースターの持つ偶然性についての思い、考え方は作品を読み解く上で必読です。
高岡昌範さんの論文のおかげで作品を殆ど理解出来たようなものでした。分かりやすく、着眼点鋭く。大変参考になりました。
よろしければそちらも是非ご一読。

