
追悼 ディッキー・ベッツ 名盤と人 34回 『Eat a Peach』 オールマン・ブラザース・バンド
オールマン・ブラザーズ・バンドと言えば、不世出のギタリストのデュアンと白人離れした喉を持つグレッグのオールマン兄弟にスポットが当たりがちだが、ディッキー・ベッツの貢献も見逃せない。そのベッツが先月、その生涯を閉じた。ベッツが主導した名作『Eat a Peach』を深掘りしつつ、ベッツの栄光と波乱に満ちた生涯を辿る。
ディッキー・ベッツの死
オリジナル6は残り1人に
オールマン・ブラザーズ・バンド(The Allman Brothers Band)のディッキー・ベッツ(Dickey Betts)が2024年4月にフロリダ州の自宅で逝去した。

これで6人いたオリジナルメンバーの生き残りは、ダブルドラムの片割れジェイモー (Jaimoe)1人となった。

1971年デュアン(デュエイン)・オールマンがメイコンにてオートバイ事故で、24歳で死去。1972年ベースのベリー・オークリーもオートバイ事故により亡くなってしまう。
事故の2箇所が近く、同じオートバイ事故であったため、当時は悲劇的なバンドとして、そしてそこから這い上がった不屈のバンドとして伝説となる。
2017年にはデレク・トラックスの叔父でもあるドラムのブッチ・トラックスが拳銃自殺。
さらに2017年5月、グレッグ・オールマンがジョージア州サバンナの自宅で肝臓ガンの合併症で死去。69歳だった。
そしてディッキー・ベッツが逝去、80歳だった。
ベッツは2000年春にオールマン・ブラザーズ・バンドを解雇されるが、その後はバンドに戻ることなく創始者としては無念の生涯を終えたのだ。
ベッツの『At Fillmore East』での貢献
さてオールマン兄弟の陰に隠れ、その貢献度の割には目立たないベッツだが、過小評価と言わざる得ない。

ブルースロックバンドだったABB(Allman Brothers Bandの略。以下ABBとする)に、カントリーやジャズという両極の要素を加えて、音楽性の幅を広げ、全米随一のバンドに仕立て上げたのが彼の功績でもある。
デュアンの死後は、バンドの大黒柱としてギタリストだけでなく、ボーカリスト、ソングライターとしてもセールスにも貢献し、バンドの危機を救ったのだ。
今回はデュアンの死後、遺作としてリリースされ、ベッツが頭角を表すきっかけとなった1972年の作品『Eat a Peach』を取り上げてみたい。
ABBは1969年に結成され、キャプリコーン・レコードと契約、ファースト・アルバム『The Allman Brothers Band』をリリースする。
契約当初はレコード会社がオールマン・バンドと命名するも、その後はオールマン・ブラザーズ・バンドと変更される。結構適当なネーミングの経緯だが、オールマン姓がバンド名に入ったため、ベッツは活躍の割には世間には知られない存在となり不遇であった。
翌年には2作目『Idlewild South』をリリースするが、2作続けてセールス的には不振となる。

彼らの存在が全米に鳴り響いたのが、続いてリリースした1971年のライヴ盤『At Fillmore East』であった。


この2枚組はビルボードのアルバム・チャートの13位を記録するヒットとなり、ライブ盤でありつつも彼らの不朽の名盤として今も語り草となるのだ。
この中で最大の聴き物の一つがインストナンバーのエリザベス・リードの追憶 (In Memory of Elizabeth Reed)。これを作曲したのがベッツだ。
マイルス・デイヴィスの『Kind of Blue』に収録されているAll Bluesに影響を受けたことを、ベッツ自身が認めているが、フュージョンサウンドを先取りしたような展開は、ブルースバンドの枠を超えており、ジャズの領域に足を突っ込んでいる。
唯一の黒人メンバーであるドラマーのジェイモー(Jai Johanny Johanson)の影響で、ベッツもマイルスやコルトレーンに傾倒する様になるが、そこからこの曲が誕生したのだろう。
オーティス・レディングのバックにいたジェイモーのルーツは、ジャズドラマーで後にはジェイモーズ・ジャス・バンドを結成する。
マッスル・ショールズのセッションギタリストだったデュアンとジェイモーの出会いがABBのルーツとなるのだった。

Ramblin' Manの大ヒット
そしてベッツの存在を全米に知らしめたのが、1973年に作曲とリードボーカルを担当したRamblin' Manで、全米シングルチャート2位を記録する。これはABBにおいて最大のヒットシングルとなる。

カントリーロックテイストに溢れるこの曲は、ベッツのもう一つの側面でもある。
ウエストコーストロック派だった自分も、テンガロンハットに口髭の優男風のルックスで、鼻にかかった優しげな声のベッツは親しみやすく、当時はグレッグよりベッツ派だった。
自分が知ったのは発売数年後の1975年頃、Doobieの「Stampede」に夢中だった頃で、その流れで同じツインドラムのABBに興味を持ったのだ。
さらに、彼得意のインストロックの名作Jessicaも収録した「Brothers and Sisters」は全米アルバムチャート1位となる。
自分も時代を遡り「Brothers and Sisters」を手に入れて、マーシャル・タッカー・バンドなどカントリーテイストのサザンロックを掘り始めたのだ。
ブルースロックからサザンロックへ。その過渡期にベッツの果たした役割は絶大だ。
ベッツはカントリーテイストのボーカリストとジャズ的なインストの名手という2つの対照的な側面を持つミュージシャンとして評価を確立、全米を制覇したバンドのフロントマンとしても脚光を浴びたのである。
当初はブルースというメジャー化しにくいジャンルに止まっていたABBだが、ベッツの持ち込んだカントリーという大衆化しやすい要素により、ABBはセールスを拡大し、アメリカのトップバンドにのし上がったのだ。
『Eat a Peach』〜平和を願って
歴史的な名盤「At Fillmore East」、そしてデュアンの死。さらに全米一位の「Brothers And Sisters」の狭間というターニングポイントにリリースされたのが『Eat a Peach』(1972年2月発売)である。

歴史的ライブ盤と最大のヒット作に挟まれて地味な本作だが、バンドにとって初のトップ10入りを果たし、最高4位に達した。
前作に続いてA-D面のダブルアルバムで、プロデュースは引き続き、名匠トム・ダウド。
本作は録音中にデュアンが亡くなったため、変則的な構成になっている。
A面のスタジオ録音から始まり、B面のライブは長尺のため途中でフェイドアウト。ライブはC面の2曲目まで続き、再びスタジオ録音が3曲。D面はB面のライブの続きから始まる。
A
1.Ain't Wastin' Time No More(G. Allman)
2.Les Brers in A Minor(Dickey Betts)
3.Melissa(G. Allman)
B
Mountain Jam (live)
C
1.One Way Out(live)
2.Trouble No More (live)
3.Stand Back(G. Allman/Oakley)
4.Blue Sky (Betts)
5.Little Martha (D. Allman)
D
Mountain Jam (live)
デュアンの死により、スタジオ録音の尺が足りなくなりライブを付け足し、さらには追悼の意味でもデュアン生前のライブ演奏を足したのだろう。
副題は「Dedicated To A Brother Duane Allman」。
『Eat a Peach』と言うタイトルは長らく意図がわからずモヤモヤしていた。
事実は、インタビューでのデュアンの台詞の一つから来ていた。 「どうやって革命に貢献しているの?」と尋ねられ、デュアンは「私は平和のために全力を尽くしている」と答えた。 「そしてジョージアにいるときはいつも、平和を願って桃を食べる」と言う台詞から命名された。


A面のスタジオはデュアンの死後録音されているが、生前に録音された曲を最初に並び替え、録音の順に曲を並び替えたプレイリストを作成してみた。さらに本作収録曲のライブ演奏などレア音源も追加した。
敢えてA面からではなく、録音順でデュアン生前のスタジオ録音から曲を紹介するプレイリストを作成した。今はこの順で聴くと録音過程が理解できて、本作の理解が促進される。
デュアン最期の3曲
Stand Back(C-3)
デュアンの生前の録音はC面の3のStand Backから始まる。
Stand Backはグレッグとベースのオークリーの共作。前作がライブ盤のため久しぶりのスタジオ録音だが、事実上最後となるデュアンのスライドとベッツとのツインリードだと思うと感慨深い。
ベッツはデュアンについて以下のように語る。
「デュアンはエネルギーが溢れ出る男だった。彼の意欲と集中力、そして自分自身と私たちのバンドに対する強い信念は信じられないほど素晴らしかった。彼は私たち全員が自分自身を信じられるように助けてくれた、そしてそれがオールマン ブラザーズ バンドの成功にとって不可欠な鍵だった。」
ギタリスト2人は固い絆で結ばれていたのだ。
1998年のライブより。この後2年でベッツはバンドを解雇され、戻ることはなかった。
Blue Sky(C-4)
ベッツが初めてボーカルをとったBlue Sky。Ramblin' Manに連なるベッツが得意とするカントリーテイストの曲。
この曲はデュアン・オールマンがバンドとともに録音した最後のパフォーマンスの1つでもあった。 ベッツは当初、グレッグにこの曲を歌ってもらうことを望んでいたが、デュアンは「これは君の曲で、君らしく聞こえるし、君が歌う必要がある」とベッツに自分で歌うよう勧めた。
デュアンがそしてベッツが交互にこの曲のリードを演奏し、最後にはツインリード特有のハモリを聴かせます。

ベッツは、デュアンを同じギタリストとして尊敬し、長男デュアン・ベッツにデュアンの名をつけたほどだった。

まさか、これが最期とは知る由もなく自作の曲でのツインリードの共演を満喫したはず。だが、この録音が最期となり、デュアン・オールマンがバイク事故で天国へ逝ってしまったのだ。
Little Martha(C-5)
そして唯一のデュアンのクレジットによるナンバーLittle Marthaで、デュアン参加のパートは幕を閉じる。
デュアンとベッツの2人のアコースティック・ギター演奏によるインストナンバーである。夢の中でジミ・ヘンドリックスに教わった曲として伝わる。
実際の録音にはベースのオークリーも参加しているが、リリースでは外された。ここでは後日コンピレーション盤「Dreams」で公開されたベース音が入ったバージョンを紹介しよう。
そしてデュアンの後継者、ヘインズとデレクによる演奏。
Little Marthaを録音すると、悪化するメンバーのドラッグ問題に終止符を打つべくリハビリのため本作録音は中断される。
しかし、入院したヘロイン解毒センターをメンバーは抜け出す。
その後デュアン・オールマンは1971年10月29日、ジョージア州メイコンでオートバイ事故で帰らぬ身となる。
デュアンの死を乗り越える
Ain't Wastin' Time No More(A-1)
さてA面は、リハビリによる録音の中断、そしてその後のデュアンの死を経て再開され録音された楽曲で構成される。
敢えてデュアン抜きの新編成での3曲を冒頭に持ってくることで、バンドの旅立ちを宣言したのだ。
1曲目は時はもう無駄に出来ないという邦題のAin't Wastin' Time No More。
71年の12月に録音された本曲は、デュアンの死後間も無く録音された。
6人の彼らは5人となり、ベッツはスライドのパートを故人になり代わり受け持ち初披露。グレッグによる兄のための鎮魂歌となっており、彼らの代表曲でもある。A面の3曲はデュアン亡き後、悲しみを乗り越えて5人で制作された曲となる。

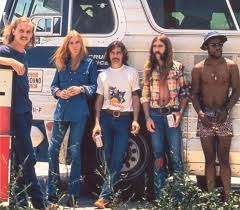
Les Brers in A Minor(A-2)
In Memory of Elizabeth ReedやJessicaでもわかるようにベッツはインストの名手である。この2曲があまりにも有名で知られていないが、Les Brers in A Minorもベッツ作のインストナンバー。
各メンバーのソロが存分に聴ける9:03の長尺インスト。デュアン亡き後も即興的な展開も可能であることを証明したかったのか。
ここでは一年後に悲劇が待つベースのオークリーの見事なベースラインが全体を引っ張る。

ベッツ脱退後の2009年の映像だが、この時期の彼らも充実していた。ウォーレン・ヘインズとデレク・トラックスのツインリードはデュアン、ベッツ期と比べても遜色ない。
Melissa(A-3)
Melissaは結成前の1967年に一度録音されたが、デュアンが好んだ曲で彼の葬儀でも演奏された。
ベッツは、グレッグの誕生日の翌日が録音だったので、「誕生日プレゼントがある」と伝え演奏した。そしてボーカルに寄り添うあの素晴らしいオブリガートが生まれたのだ。兄の死を悲しむ4歳年下のグレッグを兄貴分として勇気づけたベッツの優しさが伝わる。その後、決裂する2人だが当時は結束していた。

Live
Mountain Jam(B & D)
Liveでの聴き物である33分に及ぶMountain Jamは、B面でFade outし、再びD面でFade inし2面を使用して完結する長尺。1971年3月のフィルモア・イースト公演より、収録された。
フィルモア・イーストで、グレイトフル・デッドの前座としてABBが出演した時、ピーター・グリーンとジェリー・ガルシアと共にドノヴァンの「霧のマウンテン」(There Is a Mountain)をジャム・セッションを行ったときにこの曲に発展した。
デュアンのギター・ソロで始まり、その後グレッグがハモンド・オルガンでソロを奏で、続いてベッツのギター・ソロが続いた。そしてブッチ・トラックスとジェイモーによるドラムのデュエットがあり、その後ベリー・オークリーによるベース・ソロが加わる。その後、デュアンがスライドギターのクライマックスとなる。
若い頃は30分を超える長さに辟易したが、今ではジャズミュージシャンのような即興演奏が緊張感が途切れず続く様に感嘆してしまう。
C-2のTrouble No Moreも1971年3月のショーからのテイク。
One Way Out(C-1)
Elmore JamesとSonny Boy Williamson II のカバーOne Way Outのみ1971年6月27日の最終公演で、プロデューサーのトム・ダウドが録音したものである。ダウドは、これがこの曲における決定的なテイクだと考えた。
この曲は彼らのコンサートの定番となり、特にアンコールとして使用される頻度が高い。
Sonny Boy Williamson IIのバージョンに近いが、さらに彼らのアレンジでオールマン流ブルースロックとなった。
栄光と転落
オークリーの死と「Brothers and Sisters」
『Eat a Peach』リリース後に新作の録音が始まる。
しかし、1972年11月にはベースのベリー・オークリーが、デュアンの事故現場と近くで同じオートバイ事故で亡くなる。
ABB結成前、元々ベッツはオークリーと一緒のバンドSecond Comigで活動しており、デュアンに続いて古い仲間を亡くしたのだ。
この映像はオークリーの死の直前のライブで、チャック・リーヴェル(Chuck Leavell)加入直後の貴重な記録。
リリース前のRamblin' Manも披露されているが、Ramblin' Manの録音を終えてオークリーは無念の死を遂げる。
オークリーの後釜にジェイモーの知人で黒人のラマー・ウィリアムズを補充し、『Brothers and Sisters』を完成させ1973年の8月にリリース。
チャック・リーヴェルはグレッグの推薦でABBに加入したが、その経緯は以下の記事が詳しい。デュアンの後任はギタリストではなく、鍵盤奏者のリーヴェルとなるが、彼とベッツの大活躍が「Brothers and Sisters」を成功に導く。
特にベッツのJessicaでの彼のピアノとアレンジでの貢献は素晴らしい。
『Brothers and Sisters』は全米アルバム・チャートで初登場で13位。その後、ベッツ作のシングルRamblin’ Manとの連動効果で『Brothers and Sisters』は5週連続1位を記録し、ABB史上最高のヒット作となる。
ベッツはRamblin’ Man、JessicaそしてSouthboundなど4曲のソングライティングに貢献し、名実ともにバンドのリーダーとなるのだ。
まさにサザンロックという大輪の花が咲いた瞬間だったが、それも僅かな期間であった。
これぞレイドバック・サウンド。ベッツとリーヴェルが活躍するベッツ作のSouthbound。
ソロ活動と解散
1974年にはソロアルバム『Highway Call』を本名のリチャード・ベッツ名義でリリース。全米チャートで最高19位を記録した。
グレッグは前年にソロアルバム「Laid Back」をリリースしていた。
当初はジャズアルバムを計画していたが一転カントリーアルバムとなった、と言うベッツの振り幅を表すエピソード。
グラム・パーソンズが拡張したカントリーロックの世界の延長にあるような素晴らしいアルバムだ。

特にBluegrass風インストHand Pickedは今聴いても新鮮。
Fiddle、Pedal SteelにChuck Leavellのピアノ・ソロに絡むベッツのギター。
現在のパンチブラザーズなどがリードするBluegrassシーンに置いても遜色のない聴きごたえだ。
ABBとしての次作「Win, Lose or Draw」は1975年8月にリリースされ、全米5位とセールス好調は続いた。
ここでもベッツはインストのHigh Fallsを提供。カントリーとフュージョン風のインストと言う2枚看板が個性となる。
しかし、グレッグ・オールマンは南部からLAに本拠を移しバンドと距離が生まれる。またシェールと交際し1975年6月には結婚するが、彼らの関係はしばしばタブロイド紙のニュースになり、他のメンバーとの軋轢が生じた。

「Win, Lose or Draw」の評価も悪く、その他のゴタゴタも続き76年にバンドを呆気なく解散する。
ディッキー・ベッツと言う存在
『あの頃ペニー・レインと』とベッツ
ディッキー・ベッツの影響は音楽のみにとどまらず、そのルックスは映画史にも影響を与えた。キャメロン・クロウ監督による2000年の名作『あの頃ペニー・レインと』(Almost Famous)には、ベッツをモデルにしたビリー・クラダップ演じる70年代のロックスターが登場する。

One Way Outが使用されたワンシーンだが、ベッツ似の男が登場する。
インタビューの中で、キャメロン・クロウは次のように語っている。
「ビリー・クラダップのルックス、それ以外の要素も、ディッキーへのオマージュなんだ。ディッキーは一見静かな男のようで、その瞳の奥には深い感情や洞察力、危うさ、遊び心のある無鉄砲さを秘めていた。彼は偉大な存在だった」
バンドからの離脱
1976年解散したABBだが、再度始動するが1982年には自然消滅した。
そして1990年の「Seven Turns」で再々結成する。
2人目のギタリストとして、ベッツのバンドからウォーレン・ヘインズが参加。彼の存在が起爆剤となり、再度ABBは息を吹き返す。
そして1991年1月に待望の初来日を果たす。
運よく自分も中野サンプラザの初日公演を観ることが出来た。
(観てないので)初期と比べようがないが、伝説のバンドの演奏に遭遇し、かなり興奮したのを記憶している。
生存している創設メンバーのベッツ、グレッグ、ジェイモー、トラックスにウォーレン・ヘインズが加わったツインリード、ツインドラム体制は全盛期を彷彿させるものだった。

しかし、その後はベッツはアルコール依存症が悪化し、演奏スキルは大幅に低下していく。
優しい歌声からは想像がつかないが、彼は気性が激しく、若い頃は牛を撃ち殺して逮捕され、この頃も警官への暴力で逮捕されていた。
そして映画『あの頃ペニー・レインと』が公開された同年の2000年の4月、ベッツはバンドから解雇通知を受け取る。
そして、その後は再びABBに戻ることはなかった。
ABBはブッチ・トラックスの甥であるデレク・トラックスを迎え、ウォーレン・ヘインズとのツインリード体制で最後の全盛期を迎えるのである。
ヘインズはGov't Mule、デレクはテデスキ・トラックス・バンドという現代を代表するバンドを率いており、そのクオリティは折り紙付きだ。
2018年、Dickey Bettsの息子、Duane Betts、Gregg Allmanの息子Devon Allman、そして、Berry Oakleyの息子であるBerry Duane OakleyによってTHE ALLMAN BETTS BANDが結成される。
今回はバンド名にBETTSが入りベッツも喜んだことだろう。
(2024 FUJI ROCKにも来日予定だから、今年はABBの年かも)

親の代での遺恨は引き継がず、次世代に再び彼らのBlood(血)は交差する事になった。
デュアン・ベッツとデレク・トラックスによるBlue Sky。ここでも第二世代の交流が。
R.I.P. Richard "Dickey" Betts


