
《大学入学共通テスト倫理》のための王陽明
大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・学者を一人ずつ簡単にまとめています。王陽明(王守仁)(1472~1528)。キーワード:「陽明学」「良知」「心即理」「万物一体の仁」「致良知」「知行合一(ちこうごういつ)」主著『伝習録』『大学問』
これが王陽明

明の時代の儒学者で、中国で知識人だけでなく民衆にも大人気だった「陽明学」の開祖です。また、王陽明は儒者にして軍事家として功績をあげた珍しい人物。この肖像も、そんな強い王陽明のたたずまいをかもしていると思います!
📝王陽明の偉大さは「孔孟朱王」という言葉があることでも窺えます!
孔孟朱王,即儒家历史上四位大哲的简称(略)王守仁,即“孔孟朱王”中的“王”,心学集大成者,明朝大儒。(フリー百科事典「維基百科」、孔孟朱王のページから引用)
「『孔孟朱王』とは、歴史上の四大儒者の略称である(略)王守仁、「孔孟朱王」の「王」である彼は、心学の大成者、明朝の大儒である」が拙訳。孔子、孟子、朱子に継ぐ存在として語られているのが王陽明です。これはすごい。あと、心をめちゃくちゃ重んじた陽明学は「心学」とも呼ばれます。
📝王陽明のものすごくテンションの高い認識を読みましょう!
天地万物は、人間と本来一体のもの
天地萬物は、人と原是れ一體
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p484/p483から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
儒学にあって、およそ天地にあるものは同じ原理(理気)によってある。それならば、それはそもそも同じものだ。こんな感じのテンションの高い認識があります。また、このあと見ていくように「心で把握されるものだから全ては一体なのだ」という「心学」的な発想があります。とにかく、王陽明はさっとすごいところに切り込んでいます。「天地萬物、與人原是一體」
📝王陽明が万物一体と認識する背景に、心のポテンシャルがあります!
心は魚鳥を忘れて自ら流形
(『王陽明全集第六巻 詩』(安岡正篤監修、明徳出版社)p289から引用)
「心は魚鳥を離れてそれ自らが流体である」が拙訳。「睡起寫懐」が題の寝て起きた直後の心を描いた詩の一句です。なにかが心を占めるとき、生きている心はその形象を象(かたど)るように変化していく。つまり、王陽明にとって、心は万物をまるごととらえるものすごい変化のポテンシャルをもつことになります。「心忘魚鳥自流形」
📝心は万物をとらえるばかりか「良き」本性をも司ります!
人間の本性は善でないことはないのだから、知も良でないことはない。
性は善ならざる無し。故に知は良ならざる無し。
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p294から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
これが王陽明の「良知(心の善なる本体)」。孟子の言葉を受け継いで、万物をとらえることが本領の心とその認識が「善」であるという発想は、王陽明にとって決定的な意味があります。それはいまここに息づいている心が万物の善なる中心になる認識へとつながっている。これはものすごい話。かつて孟子は心の善をいうために世界が善であることを根拠の1つとみましたが、王陽明はその逆に、心が万物で善である点に現実世界を善にしていく根拠をみています。彼は「同じことだ」と言いそうですが、よりダイレクトに人間の心の善がこの世界の善に広がる可能性を信じています、現実がたとえまるきり善とは見えなくても。「性無不善、故知無不良」
📝こんな感じが王陽明の「心即理」です!
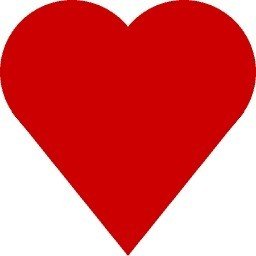
「心即理」は、現実に主体的に働くこの心が、そのまま世界の本質であり要である「理」であるという陽明学の主張です。「心即理」は宋学の朱子の「性即理」と対立するもの。「性」と呼ばれる理性的な働きでなく、現実的な心のまるごとが世界の「理」となる感じの発想です!
📝心は「万物一体の仁」=世界大の愛がポテンシャルです!
君臣・夫婦・朋友の関係から、山川・鬼神・草木に至るまで、真実にこれらを親愛することによって、わが心の万物一体の仁が実現しない場合のないようになって、はじめてわが心の明徳は完全に明らかとなったのであり、そしてまた真実に天地万物と一体とすることができたのである。
君臣や、夫婦や、朋友や、以て山川・鬼神・鳥獣・草木に至るまで、實に以て之を親しんで以て吾が一體の仁を達すること有らざる莫し。然る後に吾の明德始めて明かならざる無くして、眞に能く天地萬物を以て一體と為すなり。
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p578から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
これが王陽明の「万物の一体の仁」。万物をうけいれる愛を全開していくことで心が磨かれていき、さらに、そのことでグレートな世界観が開かれているという話です。「君臣也、夫婦也、朋友也、以至於山川・鬼神・鳥獣・草木也、莫不實有以親之以達吾一體之仁。然後吾之明德始無不明、而眞能以天地萬物爲一體矣。」
📝「致良知」という言葉にもこのすごさは込められています!
知を致すのは、後世の儒者が言うように、知識を充実し広げる意味ではなく、自己にある心の良知を残りなく尽くすことに外ならないのである。
知を致すと云ふは、後儒の所謂其の知識を、充廣するの謂の若きに非ざるなり。吾が心の良知を致すのみ。
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p589/p588から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
これが王陽明の「致良知」。これは「良知をいたす(個人が主体的な心の能力を発揮すること)」、つまり道徳心を磨く行為を指しますが、「万物一体」の領域に自分を開くすすめでもあります。こんな風に、1人1人がグレートな領域に生きる教えを力強く説きました。(ちなみに、「致良知」には「格物致知」という言葉をめぐる朱子との対立があります。それは四書の1つ『大学』に淵源する対立で、「物に対して知識を充実し広げる」という朱子の「格物致知」に対して、その言葉を解釈して「心自体の充実を強めたもの」が王陽明の「致良知」です。大切なのは物じゃなく心という話。)「致知云者、非若後儒所謂充廣其知識之謂也。致吾心之良知焉耳。」
📝高い認識と現実のつながりの両方を得た自負の言葉も読みましょう!
わが儒者は心を養うけれども、決して社会の事象から遊離することがなく、天然自然の法則に順応する
吾が儒の心を養ふは、未だ嘗て事物を離(卻)れず、只だ其の天則の自然に順ふ
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p480/p479から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
仏教的な悟りレベルのテンションの「万物一体の仁」に立ちつつ、現実のリアルへのつながりを失わない手応えを王陽明は感じています。儒者のつねに変わらないリアルへの自負がここにあるでしょう。さすが「孔孟朱王」の1人という感じ。「吾儒養心、未嘗離卻事物、只順其天則自然。」
📝「知行合一」も良知をフルに現実で発揮する志向です!
知は行の目的であり(略)行は知の完成である。
知は是れ行の主意(略)行は是れ知の成なり
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p41/p42から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
これが王陽明の「知行合一」。ここにも「心」観は大きく働いていて、「知(認識)」も「行(行為)」も同じ心の本体から発するコインの両面であること。また、回転するコインのようにどちらも進めていけば、円なる完成に近づくというニュアンスもあります。こんな思索も行動もがっつり肯定していくところが、日本の中江藤樹に伝わっています。また、この藤樹先生由来の日本陽明学が「革命のための思想」といえるほどの行動主義になっていく流れがあると言えるでしょう。「知是行的主意(略)行是知之成」
📝最後に王陽明が万人に哲理をシェアしようとする感覚をみましょう!
君は町中の人が皆聖人であると見たであろうが、町中の人は反対に、君が聖人であると見たであろう。
你は満街の人の是れ聖人なるを看たるも、満街の人は到つて你の是れ聖人なるを看(在)たるならん
(『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p526/p525から引用、ただし、書き下し文のルビを全て略した)
これが王陽明の「満街聖人」。ここまでみた心学が本当になしうるならば、本当に、全ての人間が最高の善を発揮し聖人となれる。こんな希望をもって、こんな希望をごく当然のようにみなして、王陽明は万人を肯定し励ましてともに認識の高さに至る教えを説きました。中華式メシアニズムの達成といえるかもしれません! 「你看満街人是聖人、満街人到看你是聖人在」
あとは小ネタを!
文豪森鷗外が妹に宛てた雑談の要約。「王陽明の知行合一という考えは面白い。食べたい心が食べる行為を生み、さらに食物という現実さえ作る。ドイツの新しい心理学とも一致するところがある」。ちなみに、この妹小金井喜美子はSF作家星新一の祖母である。
以下は、王陽明が最愛の弟子の徐愛を失ったさいに書いた追悼文の一節。「あなたの言葉は私の耳に、あなたの顔は私の目に、あなたの志は私の心にある」。深いかなしみを感じる。」『王陽明全集第七巻 外集』(安岡正篤監修、明徳出版社)p219を訳しました。ところで、王陽明の主著『伝習録』の上巻はこの徐愛が書き取ったものですが、彼が自分の筆録について「もしわれわれが何時までも先生の門に居れるなら、このようなことをする必要はないのであるが、ただ何時か先生のそばを去らなければならぬようなこと」や他の事態が起こるかもしれないと徐愛が書くところに、人間の運命の数奇さを感じます。徐愛は先生が亡くなってしまう未来を何よりもおそれていたようなのです。(この徐愛の言葉は『新釈漢文大系13 伝習録』(近藤康信著、明治書院)p24から引用しました)
