
【新書が好き】『葉隠』の武士道
1.前書き
「学び」とは、あくなき探究のプロセスです。
単なる知識の習得でなく、新しい知識を生み出す「発見と創造」こそ、本質なのだと考えられます。
そこで、2024年6月から100日間連続で、生きた知識の学びについて考えるために、古い知識観(知識のドネルケバブ・モデル)を脱却し、自ら学ぶ力を呼び起こすために、新書を学びの玄関ホールと位置づけて、活用してみたいと思います。
2.新書はこんな本です
新書とは、新書判の本のことであり、縦約17cm・横約11cmです。
大きさに、厳密な決まりはなくて、新書のレーベル毎に、サイズが少し違っています。
なお、広い意味でとらえると、
「新書判の本はすべて新書」
なのですが、一般的に、
「新書」
という場合は、教養書や実用書を含めたノンフィクションのものを指しており、 新書判の小説は、
「ノベルズ」
と呼んで区別されていますので、今回は、ノンフィクションの新書を対象にしています。
また、新書は、専門書に比べて、入門的な内容だということです。
そのため、ある分野について学びたいときに、
「ネット記事の次に読む」
くらいのポジションとして、うってつけな本です。
3.新書を活用するメリット
「何を使って学びを始めるか」という部分から自分で考え、学びを組み立てないといけない場面が出てきた場合、自分で学ぶ力を身につける上で、新書は、手がかりの1つになります。
現代であれば、多くの人は、取り合えず、SNSを含めたインターネットで、軽く検索してみることでしょう。
よほどマイナーな内容でない限り、ニュースやブログの記事など、何かしらの情報は手に入るはずです。
その情報が質・量共に、十分なのであれば、そこでストップしても、特に、問題はありません。
しかし、もしそれらの情報では、物足りない場合、次のステージとして、新書を手がかりにするのは、理にかなっています。
内容が難しすぎず、その上で、一定の纏まった知識を得られるからです。
ネット記事が、あるトピックや分野への
「扉」
だとすると、新書は、
「玄関ホール」
に当たります。
建物の中の雰囲気を、ざっとつかむことができるイメージです。
つまり、そのトピックや分野では、
どんな内容を扱っているのか?
どんなことが課題になっているのか?
という基本知識を、大まかに把握することができます。
新書で土台固めをしたら、更なるレベルアップを目指して、専門書や論文を読む等して、建物の奥や上の階に進んでみてください。
4.何かを学ぶときには新書から入らないとダメなのか
結論をいうと、新書じゃなくても問題ありません。
むしろ、新書だけに拘るのは、選択肢や視野を狭め、かえってマイナスになる可能性があります。
新書は、前述の通り、
「学びの玄関ホール」
として、心強い味方になってくれます、万能ではありません。
例えば、様々な出版社が新書のレーベルを持っており、毎月のように、バラエティ豊かなラインナップが出ていますが、それでも、
「自分が学びたい内容をちょうどよく扱った新書がない」
という場合が殆どだと思われます。
そのため、新書は、あくまでも、
「入門的な学習材料」
の1つであり、ほかのアイテムとの組み合わせが必要です。
他のアイテムの例としては、新書ではない本の中にも、初学者向けに、優しい説明で書かれたものがあります。
マンガでも構いません。
5.新書選びで大切なこと
読書というのは、本を選ぶところから始まっています。
新書についても同様です。
これは重要なので、強調しておきます。
もちろん、使える時間が限られている以上、全ての本をチェックするわけにはいきませんが、それでも、最低限、次の2つの点をクリアする本を選んでみて下さい。
①興味を持てること
②内容がわかること
6.温故知新の考え方が学びに深みを与えてくれる
「温故知新」の意味を、広辞苑で改めて調べてみると、次のように書かれています。
「昔の物事を研究し吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること」
「温故知新」は、もともとは、孔子の言葉であり、
「過去の歴史をしっかりと勉強して、物事の本質を知ることができるようになれば、師としてやっていける人物になる」
という意味で、孔子は、この言葉を使ったようです。
但し、ここでの「温故知新」は、そんなに大袈裟なものではなくて、
「自分が昔読んだ本や書いた文章をもう一回読み直すと、新しい発見がありますよ。」
というぐらいの意味で、この言葉を使いたいと思います。
人間は、どんどん成長や変化をしていますから、時間が経つと、同じものに対してでも、以前とは、違う見方や、印象を抱くことがあるのです。
また、過去の本やnote(またはノート)を読み返すことを習慣化しておくことで、新しい「アイデア」や「気づき」が生まれることが、すごく多いんですね。
過去に考えていたこと(過去の情報)と、今考えていること(今の情報)が結びついて、化学反応を起こし、新たな発想が湧きあがってくる。
そんな感じになるのです。
昔読んだ本や書いた文章が、本棚や机の中で眠っているのは、とてももったいないことだと思います。
みなさんも、ぜひ「温故知新」を実践されてみてはいかがでしょうか。
7.小説を読むことと新書などの啓蒙書を読むことには違いはあるのか
以下に、示唆的な言葉を、2つ引用してみます。
◆「クールヘッドとウォームハート」
マクロ経済学の理論と実践、および各国政府の経済政策を根本的に変え、最も影響力のある経済学者の1人であったケインズを育てた英国ケンブリッジ大学の経済学者アルフレッド・マーシャルの言葉です。
彼は、こう言っていたそうです。
「ケンブリッジが、世界に送り出す人物は、冷静な頭脳(Cool Head)と温かい心(Warm Heart)をもって、自分の周りの社会的苦悩に立ち向かうために、その全力の少なくとも一部を喜んで捧げよう」
クールヘッドが「知性・知識」に、ウォームハートが「情緒」に相当すると考えられ、また、新書も小説も、どちらも大切なものですが、新書は、主に前者に、小説は、主に後者に作用するように推定できます。
◆「焦ってはならない。情が育まれれば、意は生まれ、知は集まる」
執行草舟氏著作の「生くる」という本にある言葉です。
「生くる」執行草舟(著)

まず、情緒を育てることが大切で、それを基礎として、意志や知性が育つ、ということを言っており、おそらく、その通りではないかと考えます。
以上のことから、例えば、読書が、新書に偏ってしまうと、情緒面の育成が不足するかもしれないと推定でき、クールヘッドは、磨かれるかもしれないけども、ウォームハートが、疎かになってしまうのではないかと考えられます。
もちろん、ウォームハート(情緒)の育成は、当然、読書だけの問題ではなく、各種の人間関係によって大きな影響を受けるのも事実だと思われます。
しかし、年齢に左右されずに、情緒を養うためにも、ぜひとも文芸作品(小説、詩歌や随筆等の名作)を、たっぷり味わって欲しいなって思います。
これらは、様々に心を揺さぶるという感情体験を通じて、豊かな情緒を、何時からでも育む糧になるのではないかと考えられると共に、文学の必要性を強調したロングセラーの新書である桑原武夫氏著作の「文学入門」には、
「文学入門」(岩波新書)桑原武夫(著)
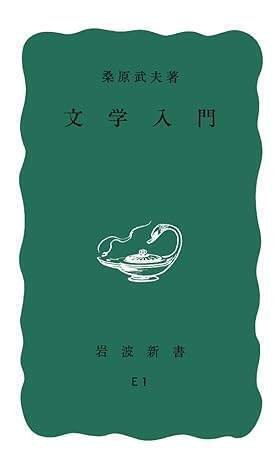
「文学以上に人生に必要なものはない」
と主張し、何故そう言えるのか、第1章で、その根拠がいくつか述べられておりますので、興味が有れば確認してみて下さい。
また、巻末に「名作50選」のリストも有って、参考になるのではないかと考えます。
8.【乱読No.29】「『葉隠』の武士道 誤解された「死狂ひ」の思想」(PHP新書)山本博文(著)

[ 内容 ]
武士道と云は死ぬ事と見付たり―あるべき武士道を説いた「死狂ひ」の書として高く評価されてきた『葉隠』。
だが泰平社会を無難に世渡りした著者・常朝に「死の哲学」などあったのか。
佐賀藩・鍋島家の「豪気な家風」とは対照的に、勇ましいだけの言葉で飾られた常朝の思想。
それは生き抜くための思考を放棄した、老人の「たわ言」に過ぎなかった。
本書では、その「机上の空論」を明らかにするとともに、名誉に命を懸けた本物の武士(曲者)の姿に迫る。
誤解され続けた「葉隠武士道」に新たな見地を拓く一冊。
[ 目次 ]
第1部 鍋島家の家風(竜造寺家から鍋島家へ;戦国武将・鍋島直茂;初代藩主・鍋島勝茂;世子・鍋島忠直の夭折;慈愛に満ちた二代藩主・鍋島光茂)
第2部 武士を取り巻く世界(武士らしさとはなにか;死への渇望;『葉隠』の女性たち;すくたれ者を嫌う藩主;赤穂事件と武士の「一分」):第3部 『葉隠』の「思想」(「主君への没我的奉公」の正体;常朝における諫言の姿勢;武士道は死ねばよいのか;処世術としての『葉隠』)
[ 発見(気づき) ]
結局のところ、「武士道」という言葉が日本でもてはやされたのは、明治になってからのこと。
しかもそのブームを引っ張った『葉隠』も新渡戸『武士道』も、武士道本来の姿としては異端の部類に入るというのが専門家の通説である。
「武」をことさらに強調しなければならなかった佐賀藩の背景。
島原での敗戦を期にそれまでの宗家・龍造寺家が没落。
臣下であった鍋島家が藩主になった。
ここから、「忠義」と「武辺」をことさらに称揚する佐賀藩の精神的素地が用意される。「葉隠」を口述した山本常朝が自身では戦場にたったことがなかった「ポスト関ヶ原」世代の人間であること。
加えて、若い頃君主の学友でもあった。
「葉隠」本文中に散見される退屈な処世訓めいた警句の数々。
例えば、換言は自身の出世に響かない程度にさりげなく、深酒の翌日は化粧して顔色をごまかせ、家老になるのが奉公の至極、など。
これらは、あきらかに「死ぬことと見つけたり」的な境地とは正反する。
「いかに世間体をとりつくろうか」といった、自己保身的なというか「ながいものにはまかれろ」的出世至上主義、な、処世訓である。
[ 問題提起 ]
『葉隠』は、武士たちに日本一の増長慢、天下第一の高慢チキになれと叱咤激励しているのか?
そして直ぐ言葉をついで、そのめざす大目的は日々の立ち居振る舞いの謙虚な反省によって裏打ちされると説く。
ここが『葉隠』を読み解くキーポイントのひとつだろう。
『葉隠』にはかの有名な「武士道といふは死ぬ事と見付けたり」を筆頭にしたエキセントリックな極論が多い。
○ 「成仏などはかつて願い申さず」
○ 「忠も孝も入らず、士道におゐては死狂ひなり」
○ 「武篇は気違ひに成らねばされぬものなり」
○ 「武士道は死狂ひなり」
○ 「武士道一つにて他に求むる事あるべからず」
○ 「武士は命を惜しまぬに極まりたり」
○ 「御家は我一人して抱き留め申す」
○ 「我一人にて御家を動かさぬ」
○ 「士は義理のために身命を捨つるこそ本意なれ」
○ 「恥をかゝぬ仕様は別なり、死ぬまでなり」
などがその類である。
だが、その一方で現実を見据えた冷静で客観的な見方も数多く提示する。
たとえば、
○ 「人はいづれ一度は死ぬものにて候」
○ 「人間一生、誠にわずかの事なり」
○ 「武士道は分別出て来て、武勇成るべきかな」
○ 「我が為ばかりを思ふきたなき人が多く候」
○ 「水至って清ければ魚住まず」
○ 「世界は皆からくり人形なり」
○ 「大事の思索は軽くすべし」
○ 「その時代々々にて能きようにするが肝要なり」
○ 「気を脱かさず正念なる所が基にて候」
○ 「難儀のとき、大形(おおぎょう)にする者は腰抜けなり」
○ 「教訓を悦ぶ人、寡(すく)なし」
○ 「我が為悪しくとも、人の為に能きやうにせよ」
○ 「物が二つになるが悪しきなり」
○ 「大事の相談は潜かに批判させたるがよし」
○ 「口を慎しみたるがよし」
○ 「心の友は稀なるものなり」
といった人生や世間についての達観した見方である。
このバランス感覚が『葉隠』の基調低音を奏でているように思う。
極端に走ると見せかけて、しっかりと奔馬の行く手を定める絶妙の手綱さばき。
では、「武士道」とは何か?
「武士の道です」といえばそれまでであるが、日本の国も二千年前後の歴史を有し、島国とはいえ外国との関係も相当あったわけで、武士の道もいろいろと変化してきた。
また、武士道に関係の深い「切腹」の意義などを考えると、それは国家観の問題につながっていく。
その変化を知ることが、「日本の今」を知ることになる。
難しくいえば、「武士道とは、行政主体(国、公共団体、幕府、藩)を担う公務員や武士の職業倫理ないしは統治の理念である」といったところであろうか。
歴史を辿ってみると、武士道には2つのタイプがあったことがわかる。
葉隠武士道と徳川武士道。
そして 葉隠武士道は、竜造寺隆信型と鍋島直茂型に、 徳川武士道は、水戸型、会津型、そして、徳川本家型に別れる。
そもそも葉隠は、1716年、享保元年に、九州の佐賀藩に成立した本です。元鍋島藩士だった山本常朝という隠者が、田代陣基という若侍に語った内容を、陣基がまとめたものといわれている。
ちょうど徒然草みたいなものといってもあながちまちがいではないだろう。
では、この武士道の違いは、どのように発祥してきたのか?
時代を遡って明が滅亡した時代、中国の色々なものが本格的にわが国に入ってくる一方、明のあとを継いだ清は、1600年代から1700年代にかけて康煕帝など中国の最高の時期を迎えます。
日本もそれに負けてはいられなくて、上記のとおり、日光東照宮のようなゴテゴテの建物を建て、家康を東照神君という神様にして中国に対抗しました。
その思想的バックボーンとして明の遺臣により日本に入ってくるのが儒教の思想です。
中世では仏教的なものが基礎にあって、儒教はあくまでも僧の教養だったのだが、このときから法制度としてドンと入ってくる。
そこで「上方風の打上がりたる武道」と、葉隠から批判されるような日本的儒教をバックボーンにした統治の原理としての武士道が生まれたのである。
このことは、佐賀藩も同じで、三代藩主綱茂は、聖堂を建てたり将軍綱吉に儒教の講義をしたほどのいわば儒教マニアであった。
そのころは、藩主の葬式を本来の曹洞宗ではなく、黄檗宗で行おうとして大もめにもめたこともあった。
そして、その黄檗僧を追い出し、本来の曹洞宗での葬式を強行したのが山本常朝の仲間だったのである。
つまり葉隠は、世の中が滔々と「上方風」つまり一種の中国風に変わっていくことに対して、中世武士道こそがよいものであると異を唱えた書であるということができる。
では、上方風武士道とはどんなものであったのか?
即ち仁義礼智信という人倫五常の道などということを正面に据えての武士道、新渡戸稲造の「武士道」などがそれである。
一般には武士道というと、これのことだと思われていて、ながい間、葉隠も、それといわば「十把一からげ」にされているのである。
そういう儒教的な武士道というものが、このあたりででき上がった。
この武士道は情や実の中世武士道に対して、合理的で知性的で、悪くいえば形式的です。そしてそのことが法的な意味を持った典型的な事例が、例の赤穂浪士の処分なのである。
赤穂浪士が敵討ちをしたときに、彼らをどう処断しようかということが問題になった。
幕府がいろいろな学者に聞いたところ、儒者荻生徂徠曰く、「これは私情としてはかわいそうだけれど、公的にみると明らかに違法なんだから責任とってもらいましょう」と。
そしてそれが通った。
大義名分というものをピチッと通さなきゃだめと、違反したものは違反という、いわゆる「法治主義」。
形式を重視する主義が出てきたというわけである。
徂徠には「明律国字解」など明の法律を解説した大著があることが思い出される。
先に述べたとおり、この法治主義に資する武士道というのが儒教的武士道であり、その典型は明の遺臣朱舜水がブレーンになって作られた水戸の武士道である。
水戸の義公、あの水戸黄門であるが、彼は儒教をきわめて大事にした。
そして逆に、仏教系の特に淫祀邪教は厳しく取り締まった。
正に合理性あるいは知性があったわけである。
これこそが、多くの人が観念する秋霜烈日ともいうべき武士道であろう。
このことをもう少し詳しく調べてみると、水戸黄門は、水戸学の祖であり、彼は18歳のとき、司馬遷の史記を読んで、特にその中の伯夷、叔斉の伝に心を打たれた。
これは、紀元前中国の殷の紂王という人がメチャクチャな政治をして周の武王のために牧野の戦いで破れ、周王朝が成立したことに関係する。
この伯夷・叔斉という兄弟は、例え紂王であろうと王様というものは絶対に悪いことなんかしない。
悪いのはそんな王様にしてしまった家来、即ち「君側」の人なのだから、もし統治者たる主君に不始末があった場合には、官僚すなわち「君側の奸」が責任をとるべきなのだ、というのである。
そして、王様をやっつけた周の飯など食べられないといって、首陽山、別名西山に籠もって、蕨を食べて餓死しする。
まさに「King can do no wrong」の発想である。
この話に心を打たれた黄門であったが、しかしそうなると、天皇家を京都に押し込めている徳川幕府は、正に武王以下であり、一方、自分がそれを支えるべき御三家の1つであることとの間には矛盾が生じる。
この矛盾は水戸藩を徳川幕府の「獅子身中の虫」化させ、幕末に桜田門外の変のような形で現実化したのであった。
一方、黄門とともに、同じ「君君たらずとも臣臣たらざるべからず」の論理によりながらも、会津の保科正之(徳川家光の異母弟)の場合は、ここにいう「君」を将軍とすることにより、黄門のような論理矛盾からは開放されるのだが、幕末には、大君、即ち将軍に最後まで殉ずることになり、もっとも手痛い目にあうことになる。
しかし、こうして主君に殉ずることこそ徳川武士道の貫徹であり、精華であるといってよいであろう。
ただ、これら徳川武士道の論理の前提には、国民の自由、財産を、君主が当然に上から制限できるという専制的な国家観がある。
これが儒教的な武士道である。
[ 教訓 ]
ところが、こうした国家観に対して葉隠は、中世的な一揆、あるいは君民協約的な国を理想とし、「主君との一味同心」を標榜したのである。
この一揆や一味同心は、皆が盟約しあって一つの組識を作り、共同して事に当たる中世の観念である。
つまりは、水戸、会津、葉隠を比べることは、正に国家観の違いを探ることにほかならず、極めて今日的な問題なのである。
そして江戸時代と明治時代とでは、上の「君」が将軍すなわち大君か(会津型)天皇か(水戸、明治型)という違いだけであり、以来、「悪をなさない」将軍や天皇が責任を負わず、官僚の責任や自己犠牲の精神に国家の運営が任されてきたのである。
逆に中国では、先に述べたとおり、農民軍に追い詰められた明の崇禎帝は自身責任をとって、ある意味で民主的に自殺したわけである。
こうして最も国粋的とみられる水戸、会津の発想は、その本質が中国では捨てられた制度を輸入したものなのである。
先に「あくまでも中国を参考にしながらも、というのがこれからの話しのミソです」と述べたのはこの趣旨である。
ですからこのことにより、それまで日本にあったよいもの即ち「身の丈」を大事にする発想などの内で、失われたものも極めて多かったことを反省する必要がある。
特にこのようないわゆる大君体制は、先に述べた伯夷・叙斉伝のような主君の無謬性という、本来あり得ない「神話」に依拠している上、神様のような主君が国民を撫する「撫民思想」になってしまうことである。
現在、問題になっている様々な「規制」の本質もここにある。
つまり、こうした撫民体制は江戸時代も明治維新後も変わっていないわけで、明治維新の「文明開花」に目を奪われ、それを「維新」だなどという見解は大いに考えものであるのかもしれない。
さて、この徳川型武士道を「上方風の打ち上がりたる武道」と非難するのが葉隠武士道です。
先ず葉隠の成立について確認しておく。
鎌倉時代以来の九州の御家人の動きをおさらいすると、中世の肥前に支配権を持ったのは、太宰の少弍に補されたことにより武藤から少弐へと改姓した少弐一族であった。
しかし、少弐一族は山口の大内一族との多年の抗争により疲弊し、西暦1559年に滅亡する。
そして、龍造寺、更に鍋島家が台頭してきた。
豊臣秀吉による1590年の全国統一を前にした九州平定にあたり、最後の勝利者になったのが鍋島直茂である。
そしてその子勝茂、忠直、光茂、綱茂と続いていくことになる。
この忠直の死に際しての家来の殉死に心を痛めた佐賀藩主鍋島光茂は、1661年、追腹停止令即ち殉死禁止令を出した。
そのため、幼いころから光茂の側に仕え、情としては、殉死したくて仕方がなかったのに殉死できなくなってしまった光茂の家来・山本常朝は、僧になって佐賀市北郊に隠棲。
そこを訪ねてきた若侍、田代陣基に対して話しをした内容を陣基がまとめ、享保元年(1716年)に脱稿したのが葉隠ということになる。
ですからこの葉隠は、徳川武士道のような儒教的な「知性」よりも、中世や戦国時代の「一味同心」であった君臣の「情」や「実」を大事にするのである。
そのことは、切腹の意味づけにおいても違っている。
戦国時代には、戦争で負けたからといってすぐに腹を切ることは当然には予定されていなかった。
そんなことでは次の戦争ができないためである。
また、時にはわざと負けて敵を欺くこともある。
これらの考えが「実」である。
そして、主君と一緒に戦い、優しく、時には自分を許してくれた殿様が死ぬときに、「情に感じた」家来は「追い腹」するのである。
であるから、無理矢理切腹させられるわけではない。
それだけの根拠、実があるわけです。
こういうことを理想としていた常朝からすれば、殉死禁止令などもっての外ということになる。
もちろんこれはどうみても、儒教的な「官僚の責任」をとっての切腹、というのとは趣旨がちがっている。
その意味からも、切腹を責任の取り方としてとらえ、その官僚の責任に依存してきた現代は、徳川武士道の延長の時代であり、それならそれなりに、キチンと責任が取られなければならないのに、それが取られていないところに現在の日本の様々の問題の根本があるように感じる。
また、山本常朝の思想の源流に位置する人の中には多くの仏教者がいる。
例えば盤珪という坊さんが出てくる。
この盤珪は「不生禅」という禅を説いた。
不生禅というのは、「不生」、生まれないというわけである。
生まれない禅、つまり生まれて死ぬということになると、そこに「時間」があることになってしまう。
でもそうじゃないんだと。
例えば、曹洞宗の道元禅師の著書「正法眼蔵」の中にある「現成公案」という部分を読むと、薪が燃えて灰になるのではない。
薪は薪の位として存在する。
灰は灰の位として存在するのだと。
いわゆる一期一会である。
目の前にある現在、これが一番大事だという。
これが禅的な考え方である。
葉隠の中で最も有名な言葉は「武士道というは死ぬこととみつけたり」であるが、この「死ぬこと」も、単なる物理的な死ではない禅的な無我の境地を言っている面が非常に強いといえるのかもしれない。
それなのにこれを物理的死とのみ考えたのが戦争中の風潮であった。
そうなってくると葉隠は、政治体制としての徳川幕府中期以降の現状に対して、不満があるわけである。
明の滅亡によって入ってきたところの、いわゆる官僚国家、それに対してそんなのはよくないと。
昔の戦国時代のように殿様と家来とが「実や情」で結ばれる社会こそが理想であると、そういう話しがあちこちに出てくる。
佐賀藩の藩祖鍋島直茂や初代勝茂などもそうした人物として描かれいる。
そのあたりに、また、それを言うために引用されている中世、戦国の事例に、葉隠から政治論を汲み取る切っ掛けがあるだろうと思われる。
もちろん、人生の書として面白いことも当然ではあるが。。
そこで、葉隠の政治論を考えるために、英米法系社会のコミュニティや、東洋の「社」と日本の中世という事を考えてみたいと思う。
日本の中世は、荘園制度というものがそれ以前にもちろん確立されていた。
ただし、それが崩壊していくという過程の中で、自然に民主的自治組織ができたわけである。
例えば「惣」というもの。
あるいは「寄り合い」というようなものがあって、早く言えば田んぼの水をどうするとかいうようなことを自分らで決めなければいけないわけで、そのような自治的組織ができてきた。
また、英米法系の国ではコミュニティというものがよく言われるし、東洋には社というものがあった。
「社長」などという言葉もそこから出ている。
つまり自然発生的に社会、村とか町とかが生まれてくるわけである。
これも「実」の一例であると考えられる。
例えばアメリカというのは、その国全体がよい意味での「カルト」いわゆる小さな宗教集団からできているとよくいわれる。
ヨーロッパからメイフラワー号でやってきて、1つ州をつくりましたと。
次の船でやってきた者は別のところに州をつくったとか。
中にはモルモン教徒がユタ州という1つの州をつくるとか。
そういうふうなことがあった。
そこでの民主的自治組織ができるわけである。
で、日本も中世においてはそれがあった。
自分で自主的に作ったのだから、これこそ人工的ではない本当のナショナリズムの発現といってよい。
ところがそれは明の滅亡によって流入した儒教的な管理国家ができることによってズタズタにされる。
あるいは明治維新以後ますますそういうことになる。
また上記のカルトの面からみると、宗教は江戸時代に寺請制度というようなものができて、いわゆる葬式仏教になってしまった。
神奈川県の金沢文庫にいくと、鎌倉時代に繁栄した称名寺では、お墓というものがお寺の中にはないわけである。
結界という赤い糸で結んだ外側にしか墓はつくらない。
しかるに、今や寺しか、むしろ寺の主たる営業は墓であるなんていうことになってしまっていて・・・まったく大間違いの実情にあるわけである。
もちろん水戸黄門が行った淫祀邪教を取締まるということは大事であるが、現代日本はそういうことでもないわけである。
こういうことからいくと、この英米法でいえばコミュニティ、東洋でいえば社、日本でいえば中世の惣的な社会というものを改めて見直す必要があるかもしれない。
江戸幕府以降の官僚国家、法治国家は、最近に至るまで大君とか、天皇とかいう基軸なり、バックボーンを持って、優秀かつ責任を持った官僚によって今日の日本をつくったのだけれど、今日、その基軸がくずれ、官僚の責任感の喪失を指摘せざるを得ない実情をみると、今度は自分自身が、やっぱり国民自身が責任感を持ってそういうことをしていかなきゃいけない。
これこそが「民主主義」である。
つまり武士道を考えることは民主主義につながるのかもしれない。
だから、憲法や国の行政も、その見地から検証しなければならない。
徳川武士道の大君体制による撫民の社会ではなくて、我が国が過去400年の間に作ってきた制度というものの中に、葉隠的なもののよいところを入れていく、そして調和をしていくということがよいのではないかと思う。
それが葉隠の生かし方ではなかろうかと。
そんな気がするわけである。
[ 結論 ]
ここで、中世の死の思想を観てみる。
そこで、鎌倉の覚園寺と国宝館をとり上げると、覚園寺は北条義時の持仏堂から発展した寺であるが、最も鎌倉らしい雰囲気を残した寺といわれている。
覚園寺の本堂である薬師堂は柱と柱との間が貫で貫かれていて長押ではなく、花頭窓や柱の下の礎盤の存在など、中国(宋)の影響を受けた極めて国際色豊かな禅宗様式の建物であるということができる。
つまり最も鎌倉らしい建物は、最も国際色豊かな建物であるわけである。
その点に中世というものの持つ奥の深さや面白さがあるのだと思う。
そしてもう1つ、鎌倉国宝館には、鎌倉彫刻の代表的作品が寄託されているが、地蔵尊や初江王像の真に迫った描写は、中世「十王思想」の、正に反映といえるもので、ちょっと感覚的かもしれないが、「これぞ死ぬことと見つけたり」と言いたい素晴らしいものである。
ここで、「死ぬことと見つけたり」について考えてみる。
我が国の中世は、正に殺戮の時代であった。
保元、平治の乱から豊織政権に至るまで、中世人の目の前には、ほぼ数年ないし数十年おきに大きな戦乱が引き起こされ、人々はいやでも死を見、あるいは死に直面することになった。
そこに平安末からの末法思想や、天文知識の不足が加わり、人々は死後の世界に対する恐れをいやがうえにも抱かされた。
人間は、死ねば十人の王の前に引き出され、裁きを受ける。
その裁判で助かるために、残されたものが追善、即ち、善行を積むことをなした。
そうであるから、人々は死ねば一刻も早く極楽に往生することを願った。
例えば鎌倉に近い三浦の海に船を浮かべ、その上に、阿弥陀如来を初めとする仏の面を被った人々が乗って、鎌倉政権の統治者の前に極楽へのお迎え然として次々と現れ、それを見た者らは、随喜の涙を流して喜んだと吾妻鏡にある。
この行事即ち練り供養は、現在でも京都の寺院等で行われている。
こんな現象は、現代から見れば、迷信ともいえ、むしろ、それを種にして一儲けを企む者さえいることを考えると、危険であるともいえるが、「死」を正に正面から受け止める中世の人々の真剣な姿であったことは間違いない。
更にこのような殺戮の時代は、一方、経済上の競争の時代でもあった。
平安末より、人々は中国・朝鮮との貿易に精を出し、我が国の交易船は、勘合貿易、朱印船貿易と海外に雄飛し、時には官貿易の規制を排して、正にビッグバンの盛況を呈した。
そんな発想は、後に、堺、博多、安土などの自由都市を生み出す原動力ともなった。
こうして、戦争と競争とからは、強大な権力や多大な富が生まれるとともに、一方、「死」が、あるいは「敗者」が数多く排出されることになったのである。
そんな中世であったが、死者や敗者の存在が、先に述べたとおり、人々に対して、常に「死ぬこと」を意識させ、死を恐れる一方で、生を尊重し、これを慈しむことが行われたことを忘れてはならない。
吾妻鏡によると、毎月15日の不成就日には、鶴岡八幡宮において放生会が行われ、魚を池に放すことが行われた。
あるいは、鎌倉の入口である横浜市六浦の上行寺には、大きな牛馬供養の宝篋印塔が立ち、旅人や物資を運んでくれた動物への感謝の念が示されている。
さて、「武士道というは死ぬことと見付けたり」と喝破したのが、永らく「武士道書」と位置づけられてきた葉隠である。
第二次大戦中において、この葉隠の「死」は、死に突入することを意味する、とのみ読まれ、痛ましい特攻隊の精神的バックボーンにもなった。
しかるに戦後は、そんな読み方の不当さが指摘され、これを仏教的な無我の境地と読む見解がそれなりに力を得た。
だが、葉隠が、戦国時代以前の中世武士の生活を良いとし、徳川の体制を否定していることを考えると、この「死」を、一種思弁的な「無我」とのみ読むことにも問題があり、むしろ、中世以来の、死を見すえ、物理的に「死ぬこと」を覚悟し、そうであればこそ、生をたたえ、生きるものを慈しむ姿勢をあらわしたものとも読んでいくべきではないだろうか?
また、武士道というと、一般に江戸幕府以降の武士道がイメージされ、新渡戸稲造の「武士道」などもその論で書かれているが、それは、どうみても「殿様だから忠を尽くせ」という権力的、儒教的な響きが強く、合理性はあるものの冷たい。
これに対して葉隠の理想とする社会は、仏教的な、いわゆる「一味同心」の社会であり、主君と家臣とは情や互いの合意の関係で結ばれ、そのような「実質的な情」があるからこそ、主君が死ねば、自然に「追い腹」することも行われたのである。
それは我が国にもかって存在した民主的な国家像であるともいえるわけで、徳川時代以降とは相当に異なる。
現にこうした時代の法は、御成敗式目など、我が国固有の慣習を元とした自分達の身の丈に合ったものであり、例えば中国の影響を受けた律令法では女子が養子をとることを禁止していたが、御成敗式目は、それは当然許されるとしてこれを認めている。
こうして、「死ぬこと」や「戦争をすること」を常に考えなければならなかった中世は、そうであるからこそ、より人間の本質を捉えた実や情の生き方に沿うものであったといえるだろう。
最近の世の中では、神戸の事件をはじめとして、このところ、おびただしい少年の凶悪犯罪が世間の耳目をそばだたせている。
そして他方「ビッグバン」が喧伝され、今後、国家間、会社間の競争はますます厳しさを増すだろう。
だが、そこでも、死者や敗者が次々に生み出される。
こんな時代、宇宙船地球号を標榜する我々は、中世的ビッグバンを実現しつつ、死をおそれ、敗者や生き物に心を配り、生きていることの素晴らしさを讃えた中世日本人の行き方をもう一度みつめ直すべきではないか。
それは端的には、「死」の意味を、深く深く皆で考えるということであろう。
先にあげた十王の像も、鎌倉のそれは、一様にこわい仏として、真にせまった彫刻がなされているのに、江戸時代以降は、まるでまねき猫の態といわざるを得ない。
すなわち、中世においては、正に死ぬことを胸にあてることが行われ、そうであるが故にこそ、こうした素晴らしい芸術が生み出されたのである。
私達は近世といわれる時以来の過去数百年間、こうして「死」を忘れた民族になってしまったことを、どれだけ反省しても、足りることはないというべきであろう。
ここで少し倫理学の面から考えてみる。
形而上の定義である抽象と観念。
抽象は具体と反対の意味を持っている。
この二つは、表現のあり方を表すときに使う。
「もっと具体的な言い方でお願いします」みたいな感じで。
観念は実体と対比的に用いられる。
実体は「そこにある・存在するもの」という意味で使い、観念は「目には見えないが存在するもの」というように定義される。
つまり、どちらも存在はしているのである。
これらのような言葉たちは形而下の世界で用いられる言葉である。
形而上と形而下ではレベルが違うのだそうだ。
超越した存在だとか、超自然だとかが形而上の世界の中にはあり、形而下の世界のものに影響を与えたり、そのものの根拠となったりするそうである。
前近代では、<私>は<無私>になることによって、善の行いができると思われていた。
一番有名なのは『葉隠』の一節で、「武士道は死ぬことと見つけたり」というもの。
「本気(正気)にては大業ならず」で、「士道は死狂ひなり」。
つまり、<私>が持っているような、私利私欲も「忠・孝」も忘れて、<無私>になり、人を殺さねばならないという意味である。
確かに、あんなにたくさんの人間を殺さなくてはいけない状況下で、正気でいたら何もできない。
そして、<無私>になった心(頭)に神が降りてきて、世界と一体化できるのだそうである。
しかし、近代に西洋の人間中心主義が導入されると、世界の見方が全く変わってしまう。その思想の中では、生まれたときから人は世界であり、神であって、一人一人が孤立して自分の世界を持っていると考える。
だから、前近代の考え方のように、「私利私欲を除かねばならない」とか、「『忠・孝』すら忘れなければならない」とかいう難しいことはしなくても、人は簡単に<無私>になることができ、誰でも正しい行動ができるものだという考えを持つようになったのである。
なぜなら、「神」であるのだから。
この西洋の思想に基づいた考えは、正直、「そんな簡単に善が行えたら苦労しないって」と突っ込んでしまいたくもなる。
同じように考えて批判したのが『善の研究』で有名な西田幾多郎であった。
西洋では、主格は自分であり、それぞれの事物と単独でつながっていると考えるのであるが、日本古来の考え方では、主体と客体は未分化であり、西田氏は、その中でこそ善を行うことができると考えた。
[ コメント ]
日本では、<無私>に至り、己の損得を忘れて何かをすることこそが「まこと」だと考えられていた。
「まこと」というのは、真実と誠実の二つの意味がある。
これにはもちろん関連があって、誠を尽くせば、真実となる。
つまり、天との一体化が果たせると考えられていたために、このように同じ言葉に二つの意味が付与されたのだそうである。
さて、この「誠」であるが、日本では、どうも感情的な面に流されてしまうところが多かったようである。
つまり、「誰かを悲しませないため」とか、「かわいそうだから」とかいう理由で<無私>になろうとしていたようである。
それが問題点だとされている。
なぜ「誠」が情に流されてはいけないのか?
それは、情というのはやむにやまれぬものであり、自分ではコントロールできないものだからである。
コントロールできないものに流されて、自分がコントロールできない状態=<無私>に陥るということはとても危険なことだからだという。
そう言われれば、確かにそうなんだろうと納得するのであるが・・・
私は、情に流されてそんな危険を冒してしまう、「馬鹿」といってしまえばそれまでな日本人がかなり好き。
そのままでいいと思う。
9.参考記事
<書評を書く5つのポイント>
1)その本を手にしたことのない人でもわかるように書く。
2)作者の他の作品との比較や、刊行された時代背景(災害や社会的な出来事など)について考えてみる。
3)その本の魅力的な点だけでなく、批判的な点も書いてよい。ただし、かならず客観的で論理的な理由を書く。好き嫌いという感情だけで書かない。
4)ポイントを絞って深く書く。
5)「本の概要→今回の書評で取り上げるポイント→そのポイントを取り上げ、評価する理由→まとめ」という流れがおすすめ。
