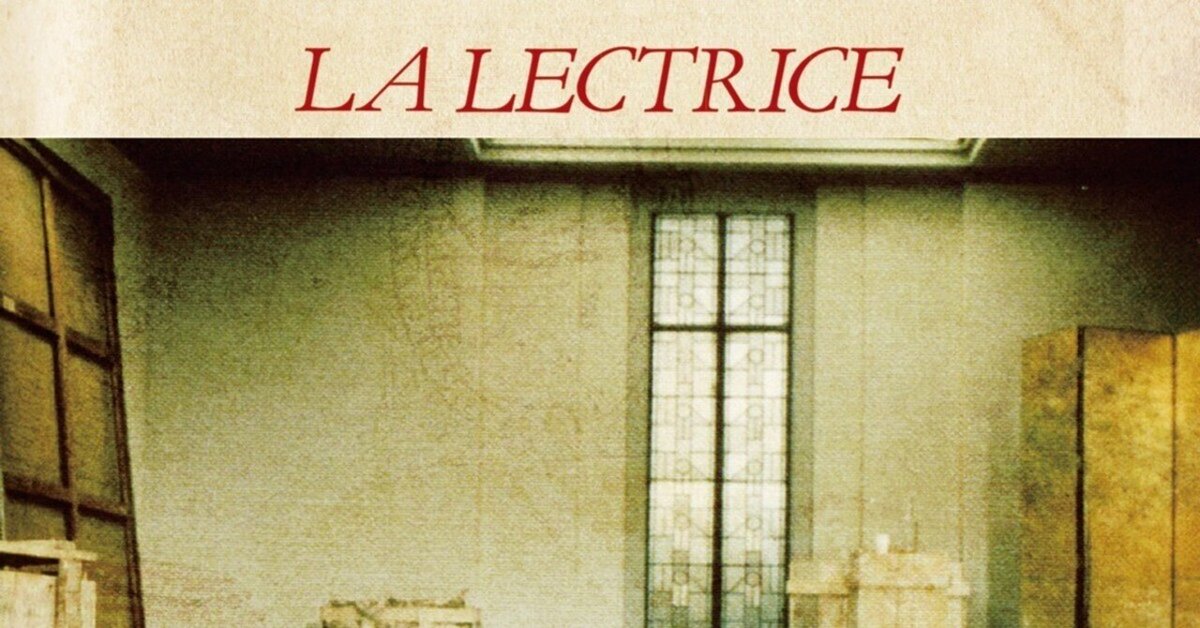
女性たちの朗読会✧♡
シズピーが主催者なので、朗読会を聴きに行った。
以前も一度、観たが、本を朗読すると言うのは、演劇ほど演劇的ではないが、作家の作品はすでに世界が立ちあがっているので、それなりに印象的である。私が前に観た時の会場は客席が暗くて、照明や、プロジェクターで何か写していたりと演出は凝っていた気がするが、今回は出演者も観客も同じく明るい会場でシンプルに朗読だけが行われていた。
最近の私はamazarashiの秋田ひろむのまるで詩の朗読か?というような歌をカラオケで歌っている。歌うと言うよりほとんど朗読調の歌もある。
だから、この会にもし自分が所属していたとして、ランボオ詩集とか、秋田ひろむの歌詞を朗読したら、顰蹙(ひんしゅく)を買うのか、ほどよいスパイスになるかどっちかなと思いながら、朗読を聴いた。(←たぶん、前者)
短歌の会の人も来ていたし、読書会の人も来ていた。両方に所属している人もいて、かなりかぶっている。
たしかに平日の木曜日、14時の美術館に駆け付けられる人など、仕事から解放されている自由人に限られている。
もしかして、私、一番若い?大笑
でも、そういう年齢の人々が、連日、読書会とか、朗読会とか、文化的、芸術的な行事に参加できることの、幸福を想う。
これはもはや僥倖でしかないのかもしれない。
それで、朗読と言うと必ず思い出す本がある。
「読書する女」
面白い小説だった。映画にもなったから映画も観たが、本の方が好きである。

他人に本を読んで聴かせるという、異質な商売を営む女性を描いたロマンティック・官能作品。声のきれいなマリーはある日、友人からの勧めで新聞にお宅で朗読しますと言う広告を出す。早速下半身不随の青年や、劣等感に満ちた中年実業家などの客が付く。
主人公のマリーは他人に朗読をするというシゴトで、いろいろな顧客に本を読む。その内容は多種多様だ。
下半身不随のマザコン気味の少年にはモーパッサンの「手」。
ボードレールの『悪の華』「宝玉(宝石)」
エミール・ゾラの「制作」
マルクスの『反デューリング論』(エンゲルス)
デュラスの『ラマン・愛人』
『不思議の国のアリス』
「盲者と下肢麻痺者」
ジョアシャン・デュ・ベレーの『哀惜詩集』
マルキ・ド・サドの『ソドム百二十日』
読んだことあるのは、「ラマン」と「アリス」の2冊ぐらい。
ただ本を読むだけの仕事なのに、エロティックなことに巻き込まれたり、なにか不思議なことが彼女の周りに起こってくるのである。
なんだか本を朗読するということは。
本人が思うよりもいろいろな何かを動かしてしまうのではないか?という空気に満ちていた。本を他人に読んで聞かせる行為は、簡単にしてしまってはいけないような気にさせる小説だった。
そこが面白かったのである。
シズピーは、小学校に、読み聞かせをしに行っているらしい。
私は、本を朗読してみたいけれども、学校に関わる気はない( ´艸`)。
でも、そういえば小学校3・4年の時の担任が、時々、小説を読んでくれたことを思い出した。「路傍の石」という小説だった。先生は小学生に向かってタイトルの意味をていねいに説明してから読み始めた。私は、そんな静かな朗読の時間が好きだった。また、別な日、先生は、列車を止めるために自分の身を投げ出した人の話をされた。その話を中学生になって、小説に見つけた時にはずいぶん驚いたものだ。三浦綾子の「塩狩峠」という小説だった。子供の柔らかい頭に、朗読による本の力は、何かを残すと思う。
今回、この朗読会を聴いて、いろいろな感想を持った。
一つは、朗読者のスキルの高さ。静かに落ち着いた声で、じっくりと、読んでいく。いきなり私が読んでもこうはいかないだろうと思わされる。
中には、本当に紙芝居というか、物語がそこに出現するかのように読む人も居た。この人は、元は小学校の教師ではないかと勝手に推測した。
声の質も、体格も、声も、年齢、さまざま、朗読者、それぞれである。
そして、そのそれぞれが、たぶん、本人が好きだと思われる本を選んで、朗読する。
noteを読むことの面白さは、作家のエッセイを読む面白さではなく、市井の人々の、今までは読めなかった随筆や創作を読めることなのだと、noteで出会った高木さんが言い、なるほどそうかと感心したことがある。
今回も、俳優ではなく、芸能人ではなく、それぞれの人生を生きている普通の女性たちの朗読を聴いたのである。
7名の女性が、朗読をした。
金子みすゞの詩を朗読した人もいたので、ほんとうに、それぞれ、みんな違ってみんないい、というふうに感じた。
誰の朗読を好きか、誰の語りが心に残ったかは、たぶん、人によって、違うのだろうと思う。
私は、今日の朗読では、山口礼子さんという方の朗読が一番心に残った。
選んでいる物語、詩のチョイスから、彼女の声のトーンや抑揚、読み方、すべてが気に入った。
彼女が読んだ郷土の作家「三浦哲郎」の「おふくろの夜回り」
作者のおふくろが、夜に、家族が皆、寝ている部屋を見まわる。それは、家族の寝ている布団を上から「ほたほた」と叩いて「夜具の冷気」を追い出して回るのである。その「ほたほた」という音とか、袢纏を来て、皆を起こさないように静かに各部屋を回る母親を想像すると、涙が零れた。
自分の母親もそのような人であったと懐かしく思い出した。
いつも朝起きてぐじゃぐじゃになった布団をきちんと直して夜を暖かく過ごせるように、常にしていた人であった。
坂木司「迷子」も、よかった。娘にさんざん反抗された父親が、初めての孫に好かれるために、道に迷ってみると決心して実行する話。
もう一つ、涙が流れたのは芝恵美子さんが朗読した重松清「バスに乗って」。
母の入院する病院にまだ小学生の子供がバスの回数券を買って、見舞いに行く話である。各家庭に父と母がいるが、父に申し訳ないけれど、父の欠けた家庭より、母の欠けた家庭の不幸をより大きく想像してしまう。
母の温かく無条件に差し伸べられる手を知っているのは万人のことだろうからと思うのである。
だから、自分の読む本を選ぶ時に、普遍的な家族という題材を選んでいる朗読者には、とても共感してしまうなと思った。
でも、それが全員である必要はない。
泉鏡花を選んでいる人、小泉八雲を選んでいる人、色々な人が居て、自分が読書を1人でするのはもちろん面白いのだが、他人に、他人の好きな本を読んでもらうという経験はとても面白いのだと感じた。
友人のシズピーは、高い優し気な声で、京都弁で物語を読んでいるのもとてもいいなと思った。
最後に、山口礼子さんが朗読した詩をここに置く。
自分の感受性くらい 茨木のりこ
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
気難かしくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか
苛立つのを
近親のせいにはするな
なにもかも下手だったのはわたくし
初心消えかかるのを
暮しのせいにはするな
そもそもが ひよわな志にすぎなかった
駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
ガツンと来た。
これが詩という事だと思う。
やられた。
詩人の言うとおりだと、言葉にひれ伏すこと。
ぎりぎりする私の心。
夜更かししてしまう今日の夜。
ばかものよ。
