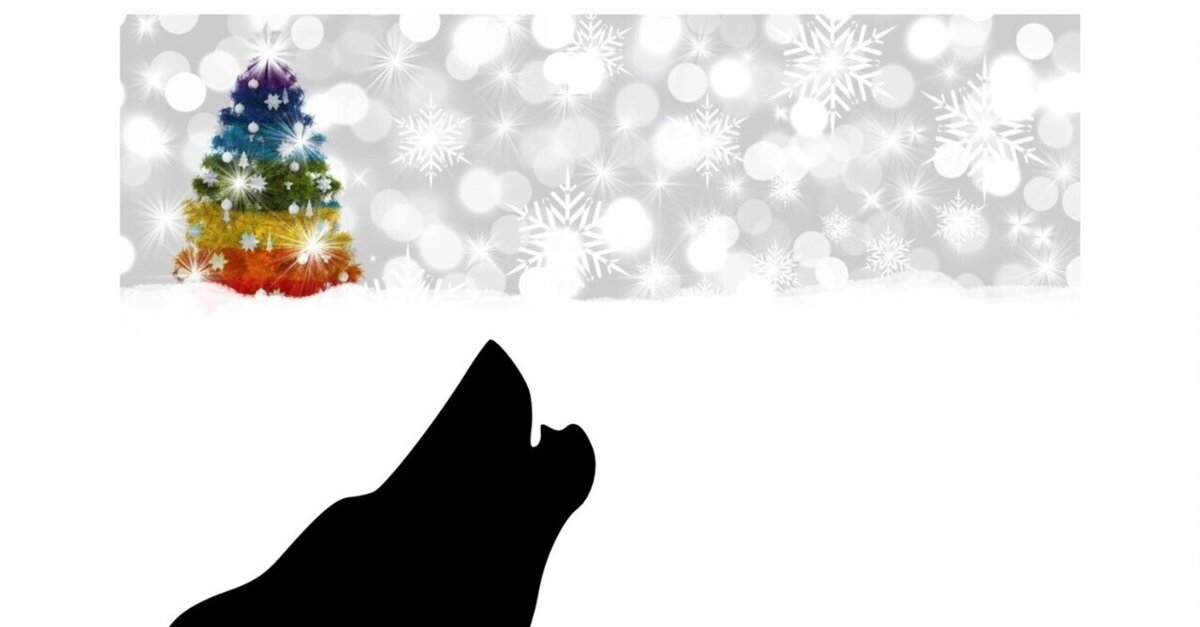
(小説)おおかみ少女・マザー編(三・十二)
(三・十二)ラヴ子十三歳(その1)・中学入学
二〇九三年、ラヴ子(ゆき)、十三歳の年である。
ゆきは港町第一小学校を無事卒業し、続いて公立の根岸中学校に入学した。この中学校は完全に旧人類専用の学校で、校長、教師のみ人類という構成であった。私立の中学校は既にすべて人類のみの学校となっており、ゆきたち旧人類の子どもたちは、近くの公立に通うしか選択肢がなかった。
この年横浜の冬の平均気温は0.7℃を記録。人類(クローン人間)と旧人類との全世界の人口差は、約十三億人(人類が約二十九億人に対して、旧人類が約十六億人)に開いていた。
完全に旧人類しかいない学校の中で、生徒たちは比較的落ち着いていた。真面目に勉学に励み、部活動も普通に行っていた。ただ身体能力は、人類の生徒の方が圧倒的に高かった。従って人類の中学と試合をしたところで、旧人類の学校が勝てる筈はない。その為やっても無駄だからと、人類対旧人類のスポーツ試合は次第に行われなくなっていった。これは日本全国また海外でも同様で、更に中学は勿論、高校、大学、実業団等に於いても同様の傾向にあった。
ゆきのクラスも落ち着いた雰囲気にあった。クラスの三分の一位の生徒が港町第一小学校出身で、顔馴染みも多かった。クラスは違ったが、鈴木ミホもいた。だから決して寂しくはなかったのだが、ゆきとしては何か物足りなかった。そして不満でもあった。
「同じ人間なのに、どうしてここまで分ける必要があるのよーーっ!まったく」という気持ちである。
篠田ナミを始め人類の子どもたちとも顔を合わせる機会がめっきり減って、段々と疎遠になっていく。一方ナミたちの方だって同様。いつも人類とばかり顔を合わせているから、矢張り自然人類同士だけで仲良く付き合ってゆくようになるものである。
こうやって日本全国また世界中で、子ども時代から人類と旧人類とが分断されてゆくのである。だから大人になっても、そのまま分断された生活を営んでいく。ひとつの人類社会でありながら、丸でその中にふたつの社会、世界が存在しているかの如くにである。
ゆきのクラスは一年二組。その中に駒田真弓という生徒がいた。五十音順の席順で、ゆきのひとつ前の席に座っていた。真弓は無口で地味な少女であり、家は極貧であった。
この時代、旧人類の家庭といえば裕福な家など殆ど無く、何処も似たり寄ったりの貧しい生活を強いられていた。斉藤健一郎のように頭脳労働を続けられるケースは珍しく、従って斉藤家は勿論例外である。しかしそんな中にあっても、真弓の家は更に貧しかった。主なる理由は、シングルマザー、母子家庭だったからである。真弓を長女として、下に弟が二人、妹が一人いた。真弓の母親が細腕で幾ら懸命に働けど、極貧生活から抜け出す事は容易ではなかった。働けど働けど我が暮らし楽にならず、である。家計を助ける為に真弓としてはバイトをしたかったが、中一ではまだ年令的に早かった。それに旧人類の子は皆家を助ける為バイトを希望する者が多く、その為旧人類の高校生ですらバイトを見つけるのは至難の業であったのである。
自らの家の貧しさゆえか、駒田真弓は小さい頃から何事にも消極的な子であった。自分の方から話し掛けていくタイプではなく、友だちもいない。小学校の教室では、いつもひとりぼっちで過ごしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
