
【意訳】エド・ルシェ:変化する言葉と都市、その記録
Ed Ruscha: He Up and Went Home
By M.H. Miller Jan. 15, 2020
Source: Ed Ruscha: He Up and Went Home - The New York Times
※英語の勉強のためにざっくりと翻訳された文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のTwitterアカウントへご指摘を頂けると助かります。

アーティストのエド・ルシェは1956年からLAを拠点としている。60年間の大半をこの都市の図像学の探求に費やし、日常性と哲学性の間を揺れ動く無表情なスタイルへと落とし込んできた。
彼は記録を続けている──時には白黒写真を用いるが、ほとんどは油絵だ。例えばガソリンスタンド、駐車場、スイミングプール、売れない俳優達の住む区域の住居、有名なハリウッドの文字看板(晴れた日には、彼の昔のスタジオからも見えていた)、昼食会で何度も耳にするような話し言葉などを描いたテキストペインティングを制作してきた。(例えば、 “そうでしたが、今はこうです”、 “ハニー、今日は酷い渋滞に巻き込まれちゃったんだ”、 “4月までは一切支払いません”、そして象徴的な“Oof”(うっ)などだ)
アメリカ的象徴主義を超過剰に表現したルシェ氏の画期的な作品では、現代における話し言葉の奇妙な進化が主要テーマであり続けている。
なお、ルシェ氏本人はどこ出身かわかりにくい西部訛りの英語を話す。ネブラスカ生まれだがオクラホマ育ちという彼の出自が、西海岸で過ごした長い時間を感じにくくさせているのだ。俳優のジョン・ウェインを除いて、ルシェ氏よりも寡黙な人物は戦後に存在しないのではないだろうか。
彼にとってそれは褒め言葉だ。ルシェ氏が部屋に入ってくる様子は、最後のロデオに向けて身なりを整えたカウボーイを見ているかのようである。彼の歩みはぎこちなくゆっくりだが印象的な慎重さがあり、82歳の今もムービースターのようにハンサムだ。
ある朝、カルバーシティのスタジオ(灰色の古い建物の中にあり、以前は映画小道具の倉庫だった)で、エド・ルシェ氏は木製の机の前に座り、最近の自作品の写真をめくっていた。通常のキャンバスの代わりにドラム用の丸い山羊革に描かれたその異色作は、ルシェ氏が南西部で暮らした過去を明確に参照しており、彼の子供時代を思い出させるフレーズが描かれている。


“これは何というか奇妙な──どう呼べば良いんだろう?オクラホマ特有の、ジャーゴンみたいな方言なんです。オクラホマの人は面白い喋り方をしていて、下手な英語を使ってるみたいなんですよ。 ‘I can’t find my keys nowhere.’(どこにもない鍵が見つからない)みたいな二重否定とかね。こういう言い回しは文学でも目にすることがある。例えばジョン・ステインバックの『二十日鼠と人間』では、‘ Yes, they were incorrect, but they had a punch to them’とある。”
このドラム用の革の作品は、オースティンのテキサス大学にあるブラントン美術館でのルシェ氏の新しい展示に出展される。ここでは有名作から発展系の最新作まで、膨大なアーカイブが展示される。新作のテキスト・ペインティングには、ルシェ氏が80年代初頭に発明して以降使い続けているフォント、“ボーイスカウト・ユーティリティ・モダン”が用いられている。ルシェ作品の典型と同じくこのフォントの名前も、文字通りの説明とお洒落なギャグの間を狙ったものだ。
だが、彼の描いた “I don’t hardly disbelieve it” や “He up and went downtown” という言葉に皮肉は少なく、強いノスタルジーが込められている。
この新作は制作に長い時間が掛かっているとも言える。ルシェ氏はこのドラム用革を約50年前にLAの革製品店で購入しているのだ。これらは目立つ傷があったために安売りのテーブルに積まれていたもので、ルシェ氏はそれ以来この革を持ち続けてきた。“いつもその革を見ていましたが、その上に絵を描くきっかけが何も思い浮かびませんでした。”
このように無作為とも思えるオブジェクトの発掘はよくあるようだ。ブラントンの展示を企画したキュレーターのヴェロニカ・ロバーツは、ルシェ氏のスタジオを “美術史家の夢” だと説明した。“すべての画家には歴史があります。” 彼女は、ルシェ氏がくるみ割り機のコレクターであると知らずに自宅の裏庭の木から採ったくるみを渡したとき、彼が興奮気味にコレクションを披露したことを思い返した。
終わりなき現在が続くLAと共に根付いた表現をおこなうルシェ氏にとって、最新の絵画は過去を振り返るきっかけとなった。ルシェ氏の父は、オクラホマシティで保険の監査員として働く“公平で真っ直ぐな男”だったと語る。まさしく朴訥だった彼の少年時代は後に、道路標識、屋外広告、20世紀FOXのロゴといった伝統的なアメリカ像を描くことで、相容れない抽象化された作品へと解体されていく。“オクラホマで暮らした日々は、まるで古い白黒映画のように思い出されます。毎朝1本の牛乳を飲んで新聞を読む。それが私のルーティーンでした。”


彼はまた、多くの時間をカントリーミュージックやジャズを聴いて過ごした。“2つの音楽には大きな違いと対立がありますが、雰囲気の良い音大にいるような感じですよ。”
彼は特にLum and Abnerなどのカントリー・ラジオ番組が好きだ。これはアーカンソー州にある架空の小さな街を舞台にしたコメディ番組で、そこで話される言葉が彼の作品にも大きな影響を与えた。“ラムはたまにすごく抽象的なことを言うんです。またアブナーはこんなことを言う。‘Oh don’t get so testamystical with me.’ こういうアメリカ的口語の考え方を作品に取り入れたかったのです。”
ドラムに描かれた彼の若い頃の言葉には、かなり子供っぽい無垢さが見て取れる。他にも、“I ain’t telling you no lie”(嘘なんてつく訳なんてない)、“I never done nobody no harm”(誰にも危害なんて加えたことなんてない)といったフレーズが描かれている。だかルシェ氏曰く、こういった言葉を家で使ったことは無いらしい。“こんな喋り方はしませんでした。もしこんな言葉を使ったら両親から即訂正されたでしょうね。”
オクラホマを離れてシュイナード美大に通うためにカリフォルニアの南部に移住したとき、ルシェ氏には看板画家になりたいという思いがあった。その進路に関して父親は特に否定的ではなかった──少なくとも、ここの学生の多くが出資者であるウォルト・ディズニーのアニメーションスタジオに就職していると聞くまでは。
シュイナードはのちにカルアーツへと名前を変え、アメリカの前衛芸術の発展においてどんな機関よりも大きな役割を果たした。この大学はルシェ氏の第一希望ではなかったが(本当はアートセンター・カレッジオブデザインを志望したが落ちたのだ)、幸運にも良い選択となった。アートセンターには厳しいドレスコードがあった。50年代当時はビートニクの時代だったが、学生は髭を生やしたりベレー帽を被ることを禁止され、学校でボンゴを叩くと規律違反とみなされた。
一方でシュイナードはボヘミアン達の中心地だった。そこでルシェ氏は抽象表現主義と、それに対して皮肉な反証を試みる、若きジャスパー・ジョーンズの毅然とした象徴主義作品(ターゲット、地図、アメリカ国旗)について独学した。


また彼は、修学旅行でクラーク・ライブラリーに行き、そこでタイポグラフィと印刷に興味を持つことになる。
ルシェ氏は学生の時に、思わぬ場所でウォルト・ディズニーに出会った。それはトマス・ピンチョンとドクター・スースの出会いを連想させる出来事だった。ルシェ氏がダウンタウンのホテルで、奨学金プログラムに応募してきた学生のポートフォリオ選出を手伝っていた時のことだ。
“彼が私のところまで歩いてきて、‘ハイ、私がウォルト・ディズニーだ。’と言ったことは絶対に忘れないだろうね。ホテルを出て路上に一歩踏み出したとき、ウォルトと彼の妻がフォード・サンダーバードに乗っていたのを覚えている。そうそう、まるで新車みたいだった。”彼は未だにすっかり感動しているような口調で付け加えた。
シュイナードで側に置けない間柄となったのが、ルシェ氏の教師であり生涯の友人となったロバート・アーウィンだ。自然光とその場所特有の要素を使って生み出される究極的にミニマルなインスタレーションで知られるアーウィン氏は当時、水彩画を教えていた。
彼は生徒にドラマチックな準備をさせるのが好きだった。ルシェ氏が言うところの“絵画の儀式”である。生徒に硬い裏板を何層ものテープで覆わせ、その上に紙を乗せて濡らす。そうすると紙を固く跳ねるように張れるのだ(まるでドラムのように、とルシェ氏は机を指で叩きながら説明した。)
真っ白な紙と向き合う不安の全てを、平面を準備するシンプルな作業へ注ぎ切ってしまうため、学生が最初の一筆を描くときには不安感が和らいでいる。“彼は思考を柔軟にし、自由な発想が生まれるように演出する方法を知っていました。そして過剰に心配させないための方法も。”
ルシェ氏は素晴らしい語り手だが、自作品の解説や説明はしない。彼の初期作品のひとつ、 “Hurting the Word Radio #2,” (1964)(痛がっているラジオの文字)はまるっきり文字通りの作品で、広告っぽい文字で描かれた作品タイトルが2つの万力で引っ張られている。最近ではクリスティーズで5,250万ドル(54.9億円)で落札されたが、この絵画は元々コレクターのジョアン・クイン(そして2017年に亡くなった夫で弁護士のジャック)へ数百ドル(数万円)で売ったものだとルシェ氏は振り返る。

“その話題は単に興味をそそるだけのものです。”そう言って彼は話を終わらせた。“それはただ金銭の取引が行われているだけで、いくら金がシュンシュン流れていこうと、我々は今ここにいる。無力で小さい生き物ですよ。” 彼が一点だけ言及したのは、LAをすぐには気に入らず(とても煙たかったらしい)、今もサンフランシスコが世界で最も美しい街だと思っていることだ。ではなぜ彼は別の場所に住まないのか?彼は笑いながら答えた。“えぇ、まぁ、住んでないだけです。今ここで暮らしているので。”
おそらく、忍耐が彼の性格の鍵である。その忍耐力が、廃棄されたドラムの革を50年間ほど持ち続けた後でそこに絵を描くという決心を可能にする。彼の最も有名な作品のひとつ、“Every Building on the Sunset Strip,” (サンセット街道の全ての建物)は1966年から自費出版している蛇腹状に折り畳まれた本で、 “Twenty-Six Gasoline Stations” (26のガソリンスタンド)と同様に、タイトルそのままを表現した写真作品だ。数年ごとにルシャ氏はこの通りの写真を再撮影しており、他のLA中心地の主要道路、たとえばハリウッド・ボールバードや、最近ではメルローズ・アヴェニューも、街自体の変化以外を除いて全く同じ方法で撮影している。
彼は70年代からサポートしてくれている兄弟のポールと共に、1日半ほど掛けてこの撮影を行う。しかしサンセット街道のオリジナル版を除いて、ルシェ氏はこれらの写真を出版も展示もしていない。現在はゲッティが所有しており、デジタル画像として利用可能となっている。
この50年間のLAの進化を捉えた記録として、これ以上素晴らしいものは他にないだろう。ルシェ氏は、都市の変化はとても頻繁に起きるのではっきり記録しておくべきだと考えている。
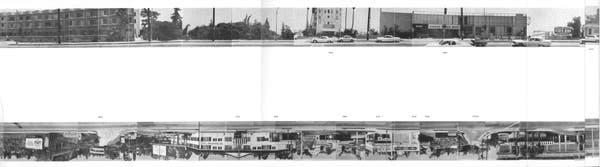
60年代にこのプロジェクトを始めた理由をルシェ氏はこう語る。“この街が悪いかたちで腐敗していくのが見え始めたんです。目に見えていた価値あるもの全てが除去され、代わりに何か不快な物が建設されていった。それは現在に至るまで続いています。私には過剰な人口の住人が暮らすための純粋な機能のために、この街が強く圧縮されてしまったように見えます。それに路上を歩くたびに、何かが少し変わっていると気づくのです。そう、‘あぁ、あれが無くなっている’と。”
このインタビューを行った2週間後、ジョン・バルデッサリが88歳で亡くなったニュースが広がった。ルシェ氏と同程度の長い間、南カリフォルニアに関与してきたアーティストは彼ぐらいだろう。
“ジョンは自分でボートを運転してたけど、プリンセス・クルーズ社のものではなかったよ。”ルシェ氏は彼の絵画に描かれている様な皮肉な言葉でメールに返信してきた。
60年代中盤頃のルシェ氏の作品の中には、ラ・シエネガにあるノームズ・ダイナーや、ウィルシェアにあるLACMAといった、この都市の象徴的な建物が炎に包まれている絵画がいくつかある。ルシェ氏はキャリアを通して暗い予兆──救いようのない退廃的な文化が自らを食い荒らす、という破滅的なヴィジョンを描いてきたが、近年、この街の歴史はそれを具現化している。彼がキャリアをスタートした時からLAに変わらず残っているものといえば、ハリウッドの文字看板、そしてエド・ルシェ本人ぐらいだろう。
