
ゲーム脳??受験脳??
「ゲーム脳」という言葉は、ぼくが中学とか高校とかのときによくメディアで取り上げられていた印象なのですが、
その当時、「ゲーム脳」という言葉は、簡単に言うと「ゲームをするとバカになる」という意味して使われていました。
でも、最近は「ゲームするとボケが改善する」や「ゲームをしたほうが、脳の処理能力が高くなる」というような話題もでてきて、どっちが正しいのかよくわからない、という印象の言葉になっているかもな、と思っています。
そんなよくわからない「ゲーム脳」
これを図工の現場の感覚から伝えてみたいな、と思います。
「思いつきません」
ゲームをするから頭が良くなる、悪くなる、という点については正直、わかりませんが、
図工を教えていて、ゲームが好きな子供に共通している点は、「発想が偏っている」ということでした。
図工のなかでは、好きなことを好きなように描く、作る活動もあれば、「材料を限定してテーマは自由」「テーマを限定して方法は自由」「すべて教員が決める」など、子供の発達段階や特性に合わせて、変えることがあります。
そんな中、ゲームが好きな子は、テーマが自由な題材では同じゲームのモチーフばかり。
また逆に教員がテーマの大枠を決める題材(いきもの、のりもの、せかい等)では「思いつかない」というメッセージが多いことに気が付きました。
ここからは、自分の経験則からの予測でエビデンスはないのですが
これはゲームによって発想の能力が乏しくなった、というよりも、好きなものが一つなので、インプットしている情報が少ない、ということではないのか、と思うようになりました。
つまりゲームしか自分の中にエディットできる情報がないので、ゲームにないようなテーマが設定されると、思いつかなくなる。というような構図なのではないでしょうか。
そう考えると、実はゲームが好きな子だけがそうなっているわけではないことにも気がつくようになりました。
四六時中、
野球のことしか考えていない子も
電車のことしか考えていない子も
もちろん、それ以外のものでも、
1つのことばかり考えている子は、
発想するものが偏る、自分の好きから外れたときに思いつかない
という傾向が高いことに気がつきました。
ひとつ、勘違いがないように注釈しておきたいのは、
好きなことがあることは悪いことではない、ということ。
その学年で、または6年間で色々なテーマに触れ、自分でテーマやアウトプットのやり方を考えることが活動の主である図工では、考えが偏っていると困ってしまうことがある、ということです。
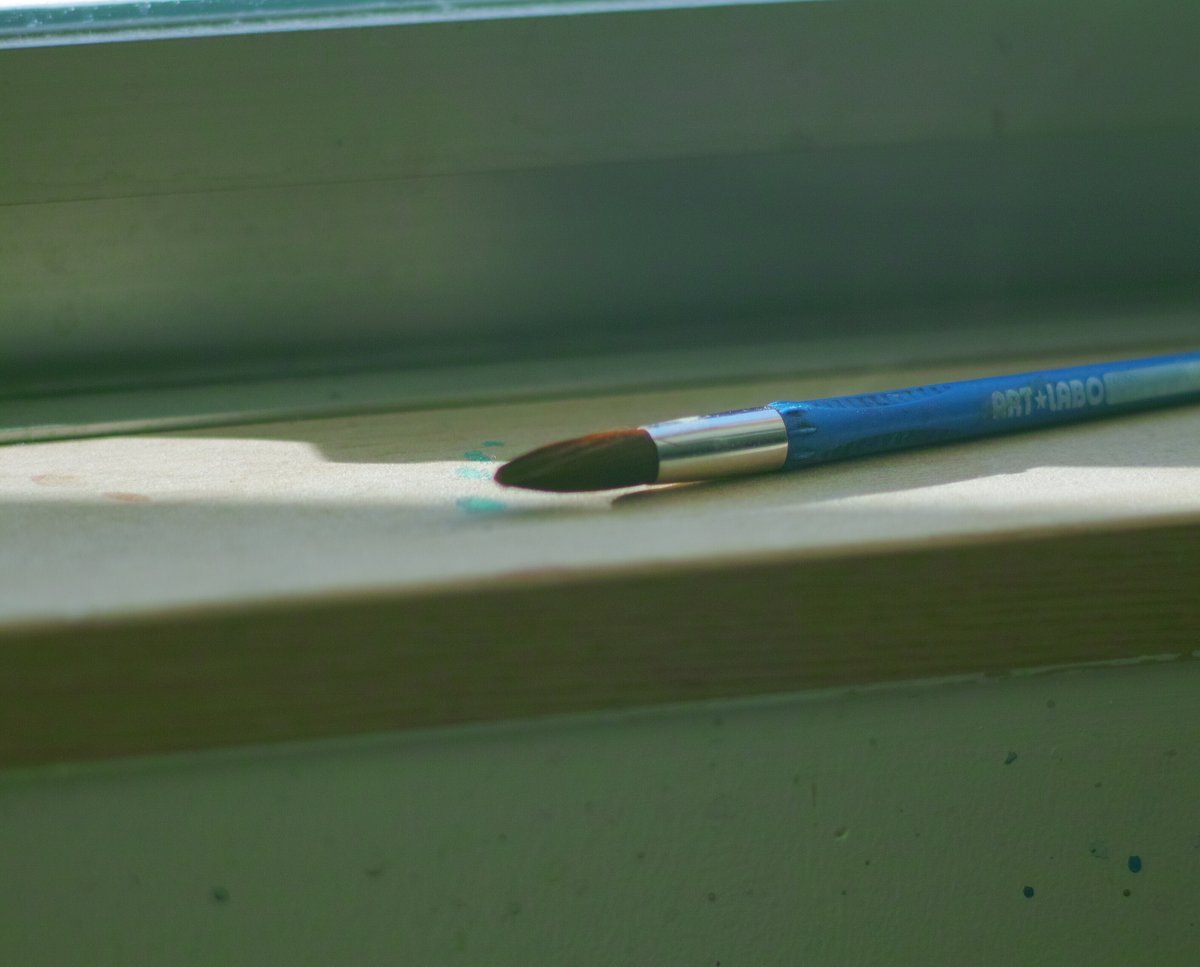
受験脳
また、1つのことだけで頭がいっぱいになる、という意味では、
受験を控えた子も、図工が苦手になる子は多いです。
勉強はしているので、知識はあるのですが、やはり、休みなく勉強ばかりしていると、
何かを考え出す余剰が頭の中からなくなったり、
自分が好きな物を作ったり描いたりすればいいのに、
正解を探そうとしたりする様子が増える子もいます。
小学生が全員、図工が好きで図工が得意にならなければいけないわけではないし、図工の重要度はその子その子によって違います。
なので、図工で困ることがあっても、何か1つのことだけを考えるのは悪いことではありません。
ただ、これからの社会は、色々なことに興味をもって、それらの興味の点を繫げてクリエイティブな発想をしていくことが社会の中で求められる時代だとも思っています。
1つのことを考えることを大事にしながらも、他のことにも興味を持てるだけの心や頭や時間の余剰の大切さも、伝えていきたいな、とも思うわけです。
