
『あまえ子育てのすすめ』を読んで
我が家には、実家からの支援で毎月絵本が届きます。
絵本の中にたまに親にも読んで欲しい本が混ざってます。
この『あまえ子育てのすすめ』が届いたのは息子が5ヶ月ぐらいのときだったと思います。が、読む気力もなくそっと本棚に置いてました...。
息子が1歳になり、まだまだ息子の前で本を読む機会をなかなかつくれないのですが(息子が本を食べるので)、いずれ息子には本を進んで読むようになって欲しいので、まずは親がお手本に...!と思い、月に1冊は読みたいなあと考えました🤔
そこで、1冊目は『あまえ子育てのすすめ』。
本棚から引っ張り出してきて、主にひとりでゆっくり入浴できる機会に本をお風呂に持ち込んで湯船に浸かりながら読みました。
読書&リラックス&代謝アップで一石三鳥...!
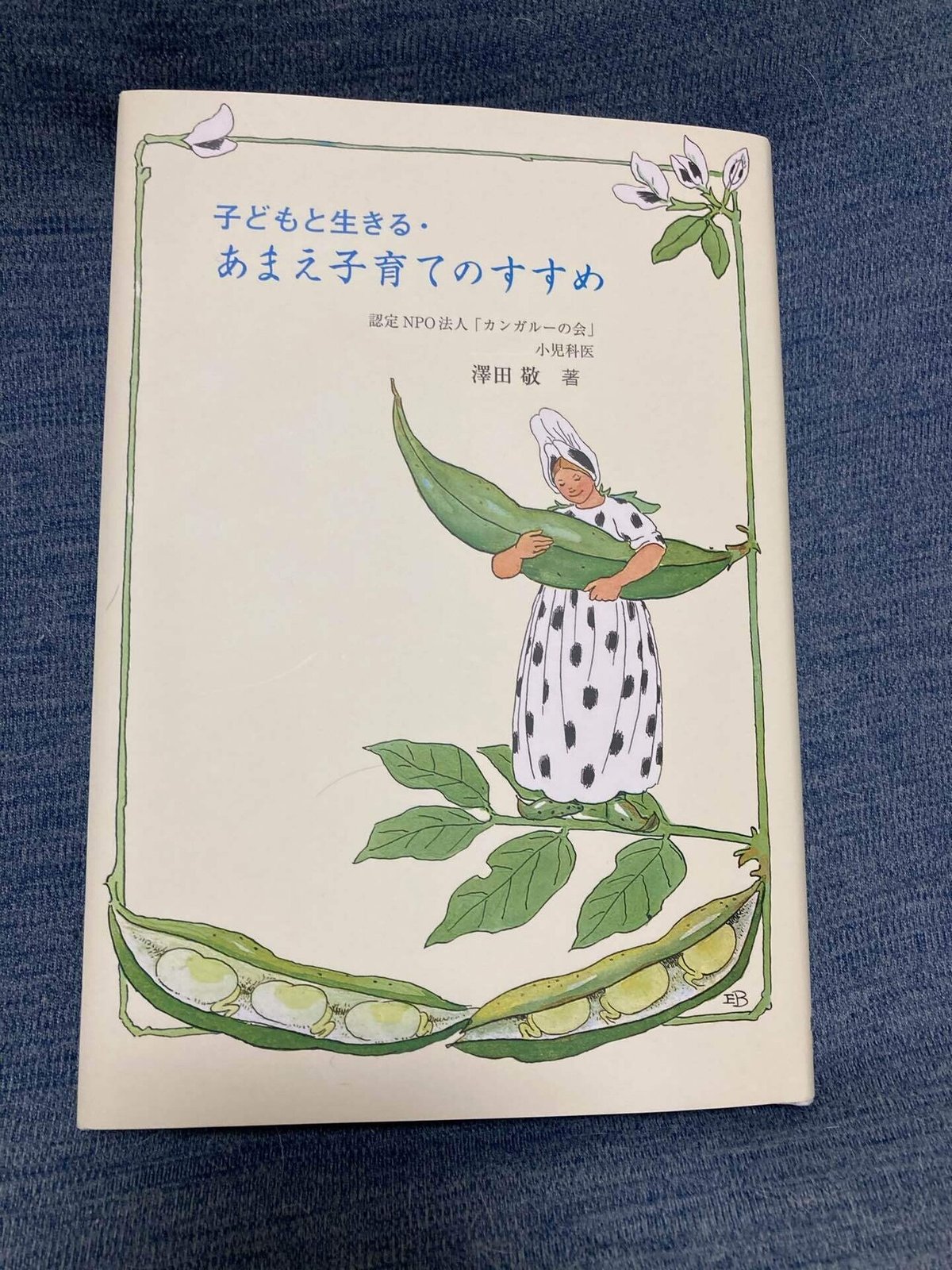
↑↑↑
子どもと生きる・あまえ子育てのすすめ
澤田 敬 著
古くから、母親がおんぶして家事したり、一緒のお布団で寝たり、一緒にお風呂に入ったりなど、子育てする人間と子どもが一緒に過ごす時間が長いのは日本の文化。
筆者が日本の子育て風景を海外の学会で発表したときには、海外の学者さんたちが非常に驚いたとか(特にお風呂風景)。
欧米では、お風呂はベビーバス、別室ベビーベッドは当たり前のこと。
日本の子どもと大人の体がぴったりくっつくおんぶ紐は絶賛されたようです。
また、本の中で引用されてましたが、幕末のイギリス外交官のオールコックは日本を“子どもの楽園”、アメリカ人のモースは『世界中で日本ほど、子どもが親切に取り扱われ、子どもに深い注意が払われる国はない』など言われたことがあったそうです。その他、1878年にイギリス人のイザベラ・バードが来日したときには『これほど自分の子どもをかわいがる人々を見たことがない』と述べたのだとか。
日本には古くから子ども想いの文化が根付いてるのだなと読んで解釈しました。なんでも欧米化が進む中で、日本の育児に誇りをもっていいんだなとちょっと鼻高々に思えました(笑)
(このあと、欧米の子ども観と日本の子ども観の比較が語られ、これまた興味深かったですが省略します...!)
息子は未だにおっぱいべっとりの卒乳なんて夢のまた夢みたいな状態で、夜中も一緒じゃないと泣くし、悩ましい限りでしたが、日本の文化のよさのひとつを知ることができて、まあこれはこれでいいか!と前向きに捉えられるようになりました。
本には、「子どもが満足するまであまえたいだけあまえさせる」とありました。
息子が転んで泣いた時、いつも抱っこしてあやしますが、いつも以上に優しくぎゅーっと体を合わせながら抱っこするように意識しました。
息子が泣き止んでからも暫く抱っこしてると、息子が「降りたい」の意思表示をして、まっすぐに玩具のところへ行きました。
これが「満足した」ということなのかなあと直感的に思いました。
最近は、夫が仕事から帰ってくると息子の抱っこおねだりがあり、抱っこタイムです。大体10分ぐらいは抱っこしてるのではないかと思いますが、その間夫の肩に頭を預け気持ちよさそうにべったりくっついてます。
満足したら、自分から降りて遊びにいきます(笑)
では、「あまえ子育て」のメリットとは??
本の中では細かく記されてましたが、端的に述べると「子どもがあまえたいときにあまえる経験を得ることによって、親と子の間に絆ができ、それを基に安心して様々なことを体験することができ、それが将来的な自己肯定感や自立に繋がる」だと思いました。
親としてもやらなくてはいけないこともあるし、いつどこのどのタイミングでどれだけ子どもに「あまえ」させてあげるのか。
迷うときは多いですが、できる限り「あまえ」の時間を大切にしようと思ってあげられる機会を得た1冊でした。


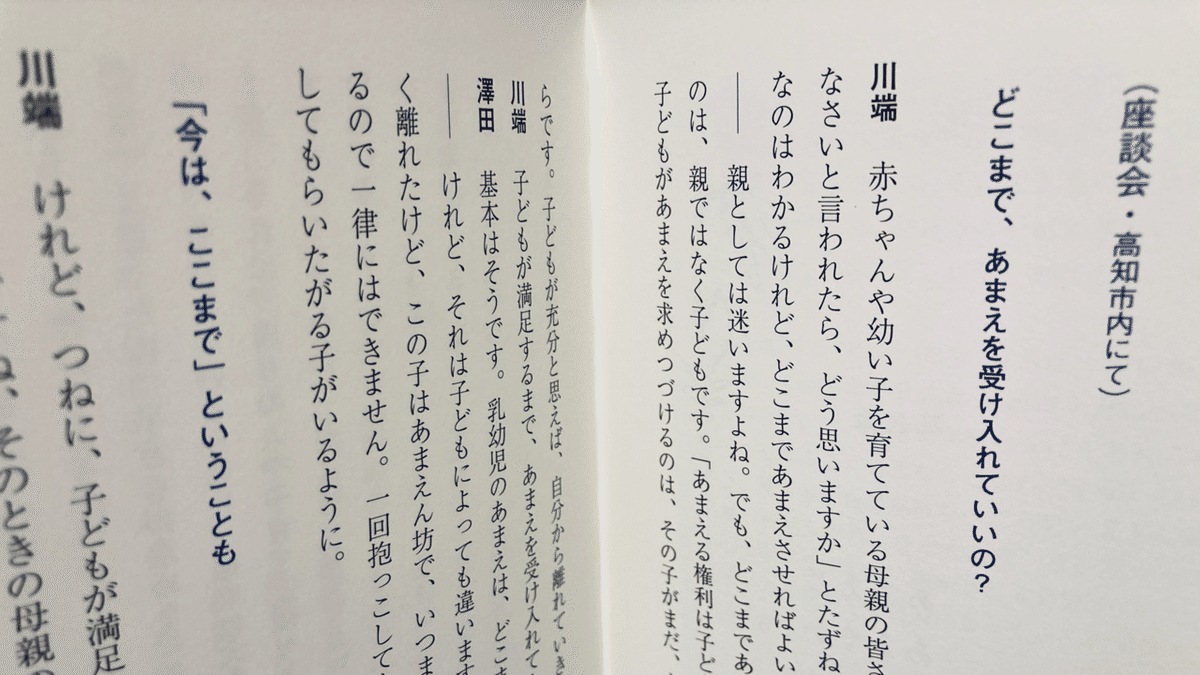
↑↑↑
特に印象深かったページ
