
古文で生成AI活用~
2024年度は高2の古文(古典探究)で、ときどき生成AIを活用しています。
といっても、生徒に自由闊達に使ってもらっているわけではなく(本当はその方がいいのですが)、私がAIにつくらせた問いや解答をつかっているだけではありますが。
まぁ、学校によっては保護者の同意も取りにくかったりすることもあると思うので、文部科学省のガイドラインに沿った活用をして、いろんな学校で使いやすいような事例を開発中といった感じです。
文部科学省のガイドラインはhttps://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html
はじめは、AIの回答の「間違い探し」からはじめました。
AIって、間違った回答をさも本当のことを言っているかのようにつくって出すという、ハルシネーション(hallucination:幻覚)のことを理解して、かつ、間違っていると指摘するためには、古文の内容を十分に理解しなければならないので、古文の理解もすすむ、といった論法です。
例えば、『堤中納言物語』の「虫めづる姫君」についての次のようなAIの回答の間違いを指摘してもらいました。
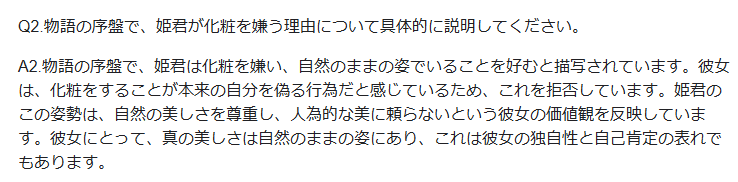
本文では、姫君自身のことばで次のように化粧をしない理由を語らせています。
「人はすべて、つくろふところあるはわろし。」とて、眉さらに抜き給はず、歯黒め、さらに、「うるさし、きたなし。」とて、つけ給はず
「人は総じて、体裁を整えるところがあるのはよくない。」ということで、眉毛をまったく抜きなさらない。お歯黒は、なおさら「煩わしい、見苦しい。」といって、おつけにならない
としか言っていないので、「自然の美しさの尊重」とか、「真の美しさ」とか、「独自性と自己肯定」とまでは言えません。こうした内容は、おそらくですが、蝶よ花よと大事にされている隣家の大納言の娘を見て述べた次の言葉によっているのかなと思われます。
「人は、まことあり、本地たづねたるこそ、心ばへをかしけれ。」
「人は、誠実な心があって、物の本体を探し求めているのこそが、心のありさまとして趣がある」といった意味です。
こんな分析をするためには、古文の内容をよく理解している必要がある、ということです。
ただ、ハルシネーションのことばかりだと、古典文学作品の学びのオモロいところには行きつかないので、最近は別の方法も取っています。
例えば、「なぜAIはそうした回答をつくったのか?」という問いについて、本文の内容から考えるといったことです。間違い探しと似ているのですが違うのは、AIの回答がおおむね正しいところです。
実際には、「更級日記」についての分析を生成AIにつくってもらい、生徒にどうしてそういう回答をAIがつくったのか分析してもらいました。
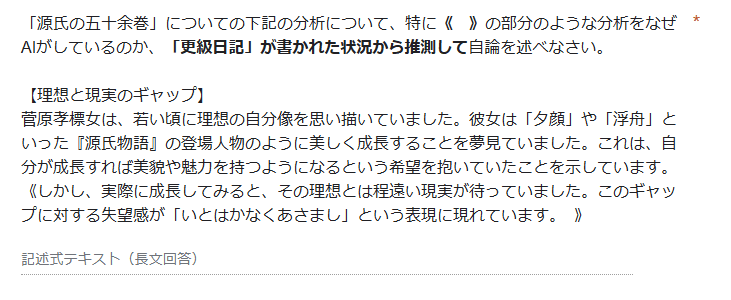
物語のことをのみ心にしめて、われはこのごろわろきぞかし、さかりにならば、かたちもかぎりなくよく、髪もいみじく長くなりなむ、光の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめ、と思ひける心、まづいとはかなくあさまし。
「私は今は器量がよくないことよ、(だけれど)年頃になれば、容貌もこの上なく美しくなり、髪もたいそう長くなるだろう、光源氏の夕顔さまや、宇治の大将の浮舟の女君さまのようになれるだろう、と思っていた気持ちは、(今思うと)どうにも他愛なく、あきれたものである。
『更級日記』は、作者の菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が、50代になってから回想して書いた日記ですので、上記は50何歳かの孝標女が13歳ごろの自分を振り返って評価している部分です。
問いにある『更級日記』が書かれた状況、とはそういうことです。したがって、孝標女が「自分自身をどうとらえ意味づけているのか、それはなぜか?」といった自己へと向かう視点を問うことができます。
そんなことをねらってみました。ただ、生徒の皆さんの回答を読むと、もっと丁寧にそのへんのことは問いを共有して考える時間を取ればよかったと反省中でもあります。
2学期以降も試行錯誤を続けるつもりです。
