
体育のNKS【「ええ場」のつくり方】
実習生の授業から感じたこと
「『安全』に関わる知識の指導って意外と難しい?」
子どもにとって
体育を学ぶ場として「『ええ場』だ」と
感じるのはどのような場だと思いますか?
その問いが生まれたのは、
先日、教育実習生の授業を見ていたときのこと。
単元はじめの授業を任せました。
運動の面白さに迫りたいと燃えていた実習生
思いとは裏腹に、
第1時、子ども達が運動に集中できていないように感じました。
それと同時に
「『安全』に関わる知識の指導って意外と難しい?」
という問いが頭の中にポッと生まれました。
「安全に関わる指導とは?」という問い(Q)を基に
自分がしてきた安全に関わる指導を
振り返りながらNKをしてみました。
安全にかかわる知識の視点(Kの視点)を示しながら、
より具体化し(Nの視点)
できる限りシンプルにまとめてみました。
安全に関わる指導は
Qとして、教える側が単元の前半で問い、
視点を明確にし、
子ども達と一緒に確認(S)するとよいと私は思います
子どもにとって「ええ場」と感じる場とは?
それは、自分自身の安全と安心が確保されている場です
安全に関わる知識を子どもに手渡す
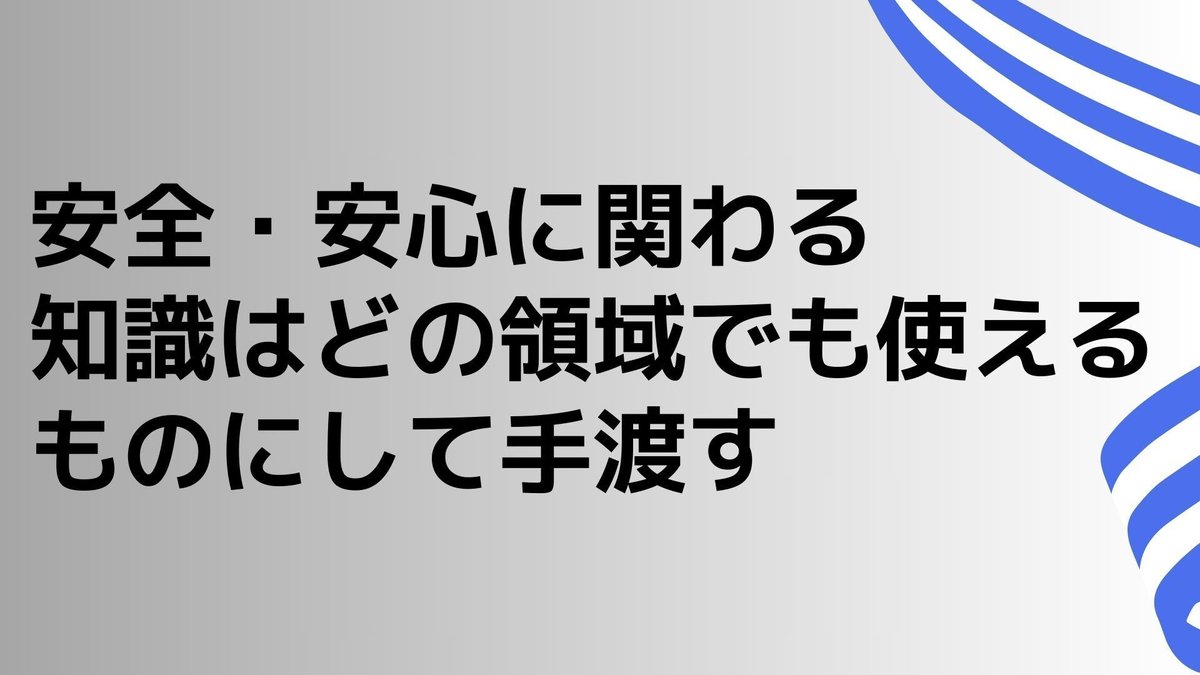
毎単元のはじめのあるある目標
学びに向かう力、人間性の
「安全に気を付けて運動に取り組むことができる」
この部分に関わる知識を重ねていくようなイメージをもっています

その単元だけに通用する言葉のサイズではなく、
どの単元でも使える言葉のサイズ感で
つくる知識を手渡すことができれば、
あれやこれや細かいことを言わずして、
子どもが自分たちで安全・安心をつくることができ、
子ども達がより自走できる体育になると考えます
ええ場とは?

わたしは、
子どもにとって運動の面白さに集中できる場のことを
「ええ場」と呼んでします。

ええ場には、条件があります
一つ目は、「安全」であること
二つ目は、「安心」できること
です。この二つの視点を基に説明していきます。
ちなみに、ええはAA(エーエー)からきていて
Aは安全のA(あ)
もう一つのAは、安心のA(あ)からきています
ええ場のN⇔K図(マット運動)

子どもの様子や学習カードの記述を見ていると、
子どもの関心は
まず、安全。
その後、安心。
そして、運動の面白さと
移行していくように感じています
実習生が行っていたマット運動を具体にまとめていきます
安全について(マット運動)

どのような場をつくるか?
苦手な子どもが多いなら、より柔らかくです。
その場に用意されたものがずれたり、壊れた時にどのようにするのか?
ずれたら、直す。次に行う人に「いいよ!」と伝える
用意された場をどのような向きで使用するか?
マットなら、転がる方向を一方通行
けがしやすいところはどこか?どんなけがが起こるのか?
準備運動として、首や手首の状況を確認させます
安全に関わる知識は、仕組みとして子どもに委ねるイメージ。
その維持ができているかを見守り、
できていれば、しっかりほめ、
できていないときは、
「これで大丈夫?」と尋ね
少しずつ、自分たちで維持できるようにしていきます。
できる限りシンプルに書きました。詳しく知りたい方は教えてください。
安心について(マット運動)

技能差があることを全員に伝える
「好き」「きらい」「得意」「不得意」と尋ねると
参加するメンバーに違いがあることが確認できます。
もし、手を挙げることに抵抗感がある場合は、
事前にアンケートをとり、実態を伝えるとよいと思います
技能差が感じることができないくらいどんどんやってみちゃう
苦手な子は、人から見られることを嫌う傾向にあります。
単元始めは、
横転がり→しゃがんで横転がり→手足をつけずに横転がり…と
微細な違い(少しずつ難しくする)を伝えて、どんどん行わせます
できない場合は、できた動きを繰り返せばいいよと伝えておきます
そうすることで、
実態を把握できますし、互いの技能について知ることができます
取り組む順番や場所を明確に
マット運動なら、どこに並び、どの順番で行うのか
始めは、示してあげた方がよいと考えます
なくてできるのであれば、子どもに委ねてあげてもよいと思います
痛くない・怖くないを確認→実感へ
マット運動の場合は、できないの理由がほぼ「怖い」に集約されていきます
柔らかく、痛くない場をつくり、そこで運動させることで
少しずつ「やっても大丈夫」という思いをもたせていきます
安心に関わる知識は、
何度何度もその価値を先生が語り、伝え、確認し、
子どもの中で成熟させていくイメージ
子どもの実態にもよると思うので
子ども一人一人の実態把握に努め、
安心をつくるのも
体育の学びであるという意識をもてるようにする必要があると思います
詳しく知りたい人は、教えてください。
「ええ場」をつくる知識も大切

体育では、
安全や安心に関わる知識を学ぶことが求められています
その知識を子どもに手渡すことができれば、
子ども達が運動の面白さを味わう時間が増えます
子どもにとっても
大人にとっても
笑顔があふれる
笑笑(ええ)場になることを願っています!
「ええ場」がつくれる子どもは遊ぶことがうまい!
本当にそう思います。
トラブルがあっても解決できる
なんなら、トラブルが起こらない仕組みを考えます。
また、下の学年と遊ぶのも上手です。
運動会が終わり、
いつもの体育の授業がもどってきていると思います
先生ががんばって
「ええ場」を保つのではなく
先生ががんばっていることが
何であるかをまとめ
少しずつ、子どもに委ね、
そして、評価する
失敗していいんです
失敗から学べるようにデザインすることが大切
そうすることで、
ええ場をつくる知識を手渡していって
ほしいと思います
けがやトラブルなく教室に
「帰す」ではなく、
「帰れる」ことが大切
よければ、参考にしてもらえたらと思います。
また、気が向いたらnoteに考えをまとめてみます
