
心理学の原理から学ぶ効果的な記憶方法〜リハーサル効果編〜
こんにちは。今日は心理学的側面から見た「記憶」についてまとめていきたいと思います。
以前にも記憶についてまとめているので、記憶の基本的な原理については、こちらの記事をご覧ください。この記事で扱っている基礎的なことを頭に入れていると理解しやすいと思います。
この記事では、記憶の原理の発展編として実用的な記憶方法の一つ「リハーサル効果」を紹介していきます。
リハーサル効果
リハーサルとは、記憶すべき内容を声(意識の言葉)で復唱することです。
例えば、英語の授業での復唱です。
このリハーサル効果には二つの効果があります。
1)リハーサル中は短期記憶の中に保存される
2)長期記憶に転送される確率が高くなる
しかし、英語の復唱の経験から分かる通りただ単にリハーサル(復唱)をしても長期記憶として覚えておくことはできません。
リハーサル効果の特徴をお話ししていきます。
リハサールは量より質
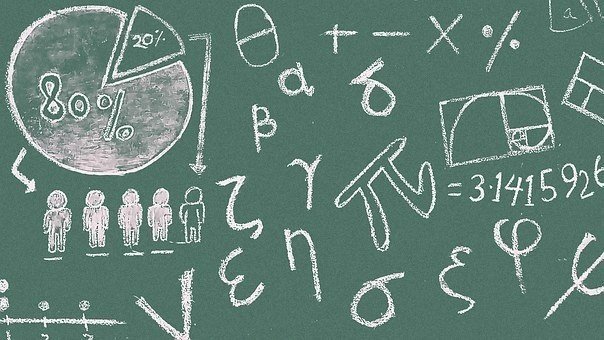
みなさん学生時代に受験勉強や定期試験対策として、歴史の年号や英単語を何度も復唱して覚えようとした経験があると思います。
しかし、いざ定期試験や受験の時に思い出そうとすると「勉強したのに思い出せない!」や単語帳を確認すると復唱した時につけるチェックマークがついているのに「やった記憶がない」という状態になった経験ありませんか?
それはリハーサル中(復唱中)は短期記憶の中にあるから”覚えている”と認識してしまっているからです。実際に時間が経つと短期記憶から失われてしまっているのです。
何度もリハーサル(復唱)をすることで長期記憶に移行する確率は高くなりますが、ただ単に確率が高くなっているだけです。
逆に今でも覚えているような単語はありませんか?
・1192年→鎌倉幕府が始まった
・710年→平城京に遷都
これは何度も「1192年は鎌倉幕府が始まった。1192年鎌倉幕府。1192年鎌倉幕府・・・・。」と覚えていたわけではありませんよね?
これらを覚えていた人は、下記のように覚えていた人が多いと思います。
・1192年(1185年)→いい国(ハコ)作ろう鎌倉幕府 など
・710年→なんと綺麗な平城京 など
ここから分かる通り、冒頭でもお話ししたリハーサルは量より質ということがわかります。
科学的な根拠をある実験からお話ししていこうと思います。
Craik&Tulving(1975)の実験

英単語を1語づつ短時間提示する→ある質問をする→全ての単語が提示された後にテストを行う
(ただし、被験者にはテストがあることを知らせていません。)
このプロセスのある質問で異なる4つの質問をしていきます。その質問は下記の質問です。
①活字:その単語は大文字で書かれていますか?
「apple」ならNo、「APPLE」ならYes
→形態的処理
②音韻:その単語は「couple」と韻を踏みますか?
「orange」ならNo、「Apple」ならYes
→音韻的処理
③文章:その単語は文章の空欄に入れられますか?
『彼は_______を食べた。』
「play」ならNo、「Apple」ならYes
→意味的処理
その結果テストのの正答率は
①活字:その単語は大文字で書かれていますか?
「apple」ならNo、「APPLE」ならYes
→形態的処理
は、Yesの場合、約18%の正答率
Noの場合では約20%の正答率
②音韻:その単語は「couple」と韻を踏みますか?
「orange」ならNo、「Apple」ならYes
→音韻的処理
は、Yesの場合、①の2倍の約40%の正答率
Noの場合でも30%の正答率
③文章:その単語は文章の空欄に入れられますか?
『彼は_______を食べた。』
「play」ならNo、「Apple」ならYes
→意味的処理
は、Yesの場合、①の4倍・②の2倍の約80%の正答率
Noの場合でも約50%の正答率
という結果になりました。
この実験から言えることは、意識的に覚えようとしていない単語にもかかわらず、意味づけして覚えた単語は思い出しやすいと言えます。
意味づけをすることは長期記憶にするには非常に効果的です。
多くのことを永遠に覚えておくことも可能です。
この実験の結果はあらゆる場面で利用することができるでしょう。
・歴史の年号を覚える時に語呂合わせで覚える
・人の名前を覚える時にストーリー(意味づけ)を作って覚える
例)
山下純子さん→山の下で純粋に育った子なんだ。優しそうな顔しているし似合うなぁ。
新村龍之介→新村って子が、昔クラスにいたなぁ。あいつサッカーうまかったよなぁ。この人は反対にちょっと知的な感じ、だけど龍之介って名前は芥川龍之介みたいで、似合っているな。
・英単語を何度もにらめっこしたり、復唱したりして覚えるより、例文で使い方を見て関連づけて記憶する など
これは、単なる小手先のスキルというよりは、これまでの原理を知っているからこそ、様々な場面で工夫し利用することができます。
ぜひ場面にあったリハーサル方法を考えてみてください。
以上でリハーサル効果についての解説を終わります。もっと詳しく知りたいという人はこちらの記事も併せてご覧ください。
いいなと思ったら応援しよう!

