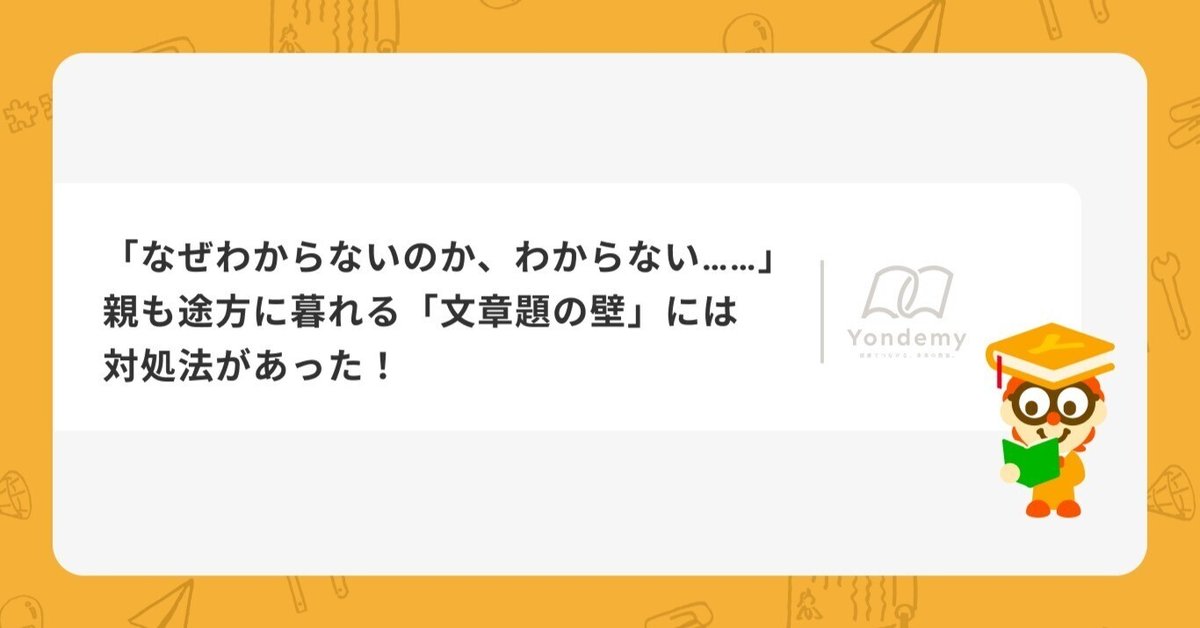
「なぜわからないのか、わからない……」親も途方に暮れる「文章題の壁」には対処法があった!
「文章題が解けない」=「算数が苦手」?
「算数の問題、特に文章題が本当に解けないんです……」
これは保護者さまから実際に届いたお声です。
「この計算式は、一体どこから出てきたの……?」と不思議に思い本人に聞いてみると、
「数字を適当に組み合わせただけ……」というパターンもあるんだとか。
「なんでこんな計算しちゃうの!」と喧嘩になってしまうこともあるそうです……
しかし、そんなお子さんも、もしかすると「算数」ができないわけじゃないのかも。
もっと別のポイントでつまずいている可能性があります。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが…… 算数の文章題って実は「国語」の問題に近いんです。
(▽詳しくはこちらの記事でもお届けしています)
またこちらは、ヨンデミーが毎週お届けしている「ヨンデミーセミナー」第13回でのひとコマ。
東京大学の3年生・Mさんとの対談回でした。
【M】実は算数にセンスは関係ないと思っていて、かなり高度で専門的な段階に行く前までは、文章が読めるかどうかの戦いです。 小学校の問題、見たことありますか? すべて日本語なんです。 文章だけで「あ、このパターンの問題だ。じゃあこういう計算をすれば解けるんだろうな」と想像がつくものばかりなんです。
【笹沼】確かに。でも、保護者さんからすれば、算数より数学の方が記憶に新しいので、ギャップを感じるかもしれませんね。
▽ヨンデミーセミナー第13回はこちら!
「でもうちの子、文字もしっかり読めるし文章だってそんなに苦手じゃないのに……」
そんなふうに感じる保護者さまもいらっしゃると思います。
しかし、注意しなければならないのは、算数の文章題は「ただ読めるだけ」では太刀打ちできないということです。
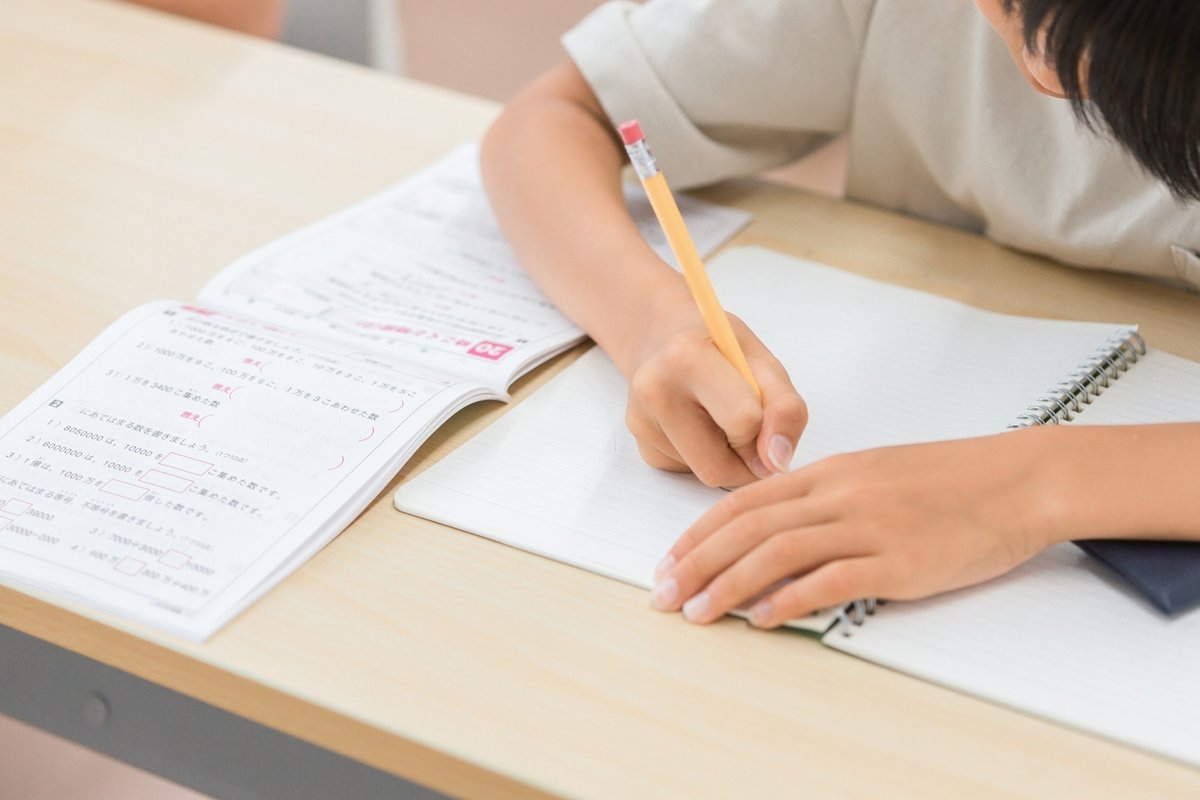
「ただ読める」だけでは足りない!? 文章題の落とし穴
忘れられがちですが、文章題を解くときにはまず「文章で書かれている状況を正確に読み解く」という段階があります。
ここは完全に「国語」の問題。
「文章を読んで正しく情景を思い浮かべる」のとまったく同じ工程です。
それができたら、理解した状況を数式に落とし込むステップに入ります。
このとき、数字と数字の関係性を正しく読み解けていないと、冒頭の「なんでそんな計算しちゃうの!?」と言いたくなるような式が生まれてしまうわけです……。
まずは文章を理解する「国語の問題」を解いて、さらに数式に落とし込んで「算数の問題」を解く。
文章題を解くときの壁は、2段階あるんです。
そんな、ただ文章を読むよりも難しい算数の文章題をマスターするためには、一体どうすればいいのでしょうか……?

【保存版】文章題マスターになるための術
ワザ①:文章を音読する
「音読」はお子さんにとって最強の秘密兵器。
文章をただ目で追うよりも、格段に理解しやすくなる子が多いんです。
というのも、言葉を音で認識できるというのが大きいポイント。
まだ小さいお子さんは、目よりも「耳で読む」ようにした方が理解しやすいことが多いんです。
音読することによって文章の区切りも意識しやすくなり、強制的にゆっくり読めるようになります。
ワザ②:お子さんに問題を説明してもらう
問題文を一度読んでもらったあと、問題冊子を裏返します。
その状態で「どんな問題だった?」と聞いてみてください。
問題が読めない状態で内容を伝えようと思うと……
自分の言葉で、最初から組み立て直して説明する必要が出てきます。
このステップが、問題を正しく理解できているかの確認にぴったり!
始めたばかりの頃は反復練習になりますが、そのうちこのステップは不要になっていくはず。
小学校の算数の問題は「解き方のパターン」がそこまで多いわけではありません。
何度か取り組むうちに「あ、この書き方はあのパターンだな!」と、お子さん自身がわかるようになっていきます。

ワザ③:本を読もう
文章を正しく理解するための「読解力」をつけましょう。
しかし、ここで注意したいのは「読み解くテクニック」を身につけるのではないということ。
以下は、先日お届けしたnoteの一節です。
読解力を身に着けるのに必要なのは、「文章全体の文意をパッと掴む能力」です。
でも、国語の授業で扱うのは文章の抜粋となります。教わるのも「指示語の追い方」や「接続詞の役割」などのテクニックです。
テクニックを使って細かく読み込む力はつきますが、これは「読解力」を育てることにはなかなかつながりにくいんです。
そうすると、文章を丸々1冊を通して読み切る力はどこで身につくんでしょうか?
それが「読書」なんです!
(▽先日お届けしたnoteはこちら)
また、ここまで「算数の文章題が解けない」というエピソードに沿ってお話ししてきましたが……
「読解力」が足りずにつまずいてしまうのは算数にかぎったことではありません。
理科、社会、英語、調べ学習……どんな教科でも「読んで理解する」ことがハードルになってしまう可能性があるんです。
これは学年が上がればなおのこと。内容も文章のレベルも難しくなります。
読解力をつける工夫は、始めるのが早ければ早いほど、お子さんの「つまずき」を予防することができるんです。
魚を与えるより釣り方を教えてあげましょう。
短期的な解決策よりも、本来やるべきは長期的に役に立つ能力を身につけることです。
読書を通じて、どんな文章も自由に読みこなせる読解力を伸ばせたら、それはお子さんの強い味方になってくれるはずです。

「読解力」を武器に全教科に立ち向かおう
算数の文章題をはじめ、読解力はさまざまな場面で求められることをお話ししてきました。
でも、読書が読解力を育てるポイントになるとわかっていても……
実際に、お子さんにしっかり読書をしてもらうのって難しいですよね。
「ちょうど良い本がなかなかわからない……」「ずっと簡単な本ばかり読んでいる……」というお悩みもよくいただきます。
そもそも今お子さんは読書に対してモチベーションなんてない状態かもしれません。
読む気のない子に、無理やり難しい本を読ませても、ただ読書が嫌いになってしまい、逆効果になることも……。
そこで、読書を楽しく大好きになれるようサポートし、さらにどんどん読む力も鍛えていくのがヨンデミーオンラインです!
AIヨンデミー先生がお子さんの読む力をしっかり分析し、ぴったりな選書からスタート。
お子さんの読書のモチベーションを支える仕掛け満載のアプリで、楽しみながらレベルアップできます。
楽しくたくさん本を読んでいたら、いつの間にか、勉強が得意になっていることも……!
▽無料でまずは30日間お試し! ヨンデミーで楽しく「読解力」を鍛えよう!
▽「おうち読書のミカタライン」(無料公式LINE)で、保護者様向け資料をプレゼント!
プロによるおうち読書のノウハウをお届け!
この記事が面白かったら、ぜひスキ・シェア・フォローをしてみてください!
「スキ」を押すと、ヨンデミーの仲間たちが読書教育のヒントを教えてくれます📚✨
