
「桜」はなぜカミングアウトしたのか?映画『カランコエの花』から考えるアウティングとの向き合い方
/違和感ポイント/
短編映画『カランコエの花』の上映会に参加した後に、アウティングについて考え始めた。自分たちには遠い話に聞こえる一方、実は日常生活で起こりうる出来事でもある。筆者もLGBT当事者として、他の人にアウティングされたことが何回もある。複雑で難しい問題でありながら、私たちにできることはきっとある。

あの事件から7年。
2015年の一橋アウティング事件から、約7年が経った。この事件が起きて以来、、一橋大学の所在地である東京都・国立市では2018年4月にアウティングを禁止する条例が施行され、そして三重県でもLGBT差別やアウティングを禁止する「LGBT平等条例」が2020年4月から施行されるようになった。2020年11月25日のこの事件の東京高裁の判決では、被害者遺族の大学側に対する損害賠償請求は棄却されたが、裁判長は「アウティングが人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する許されない行為であるのは明らか」であると述べ、アウティングの違法性に言及した日本初の判決が出された。アウティングとは当事者の性的指向や性自認に関するプライベートの話を本人の許可なく第三者へ暴露する行為だ。この行為の深刻さは、条例や法律上の変化によって認識されるようになってきた(参考)。
ところが、条例や法律という制度面の変化は、必ずしも一般人の考え方まで変えるわけではない。「アウティングはダメだ」と漠然と知っていながら、なぜダメなのかを理解できず、そして具体的にどうすればいいのかもわからない人はまだ沢山いる。このようなケースは、特に学生の間でよく見られている。アウティングについて、私たちは当事者のために何ができるだろうか。本記事では、短編映画『カランコエの花』のストーリーと登場人物の分析を通して考えていきたい。
※この記事には一部ネタバレが含まれます。
『カランコエの花』のストーリー
『カランコエの花』では、とある高校2年生のクラスで起きた出来事が描かれている。同じ学校の他のクラスでは行われていない「LGBTについて学ぶ」授業が、このクラスだけで唐突に行われた。その授業を機に、「LGBTの人がうちのクラスにいるのでは?」と生徒たちは疑い始める。
犯人探しのように、当事者を探る者。当事者のカミングアウトを偶然聞いて、何か力になりたいがどうすればいいのか分からず胸を痛める者。そして事実を知っていながら、平然を装って取り繕う者。この作品では、LGBT当事者がその犯人捜しの雰囲気に耐えられず自分からカミングアウトした経緯を当事者視点だけではなく、様々な立場に立つ人の視点からとらえている。
『カランコエの花』というタイトルの映画だが、この作品にはカランコエの花は出てこない。その代わり、主人公の一ノ瀬月乃(以下:月乃)は母親からもらったカランコエの色をしている赤色のシュシュを持っている。母によると、カランコエの花言葉は「あなたを守る」だ。娘に贈ったこのシュシュには、母の娘を守りたいという気持ちが含まれている。また、カランコエ色のシュシュは月乃と月乃のことが好きな女子生徒であり、この作品が描いたアウティング事件の当事者である小牧桜(以下:桜)との関係性を象徴する物でもある。
母からもらったシュシュを付けて初めて登校した日に、月乃は桜から「すごく似合っている」と褒めてもらう。それを聞いて喜んでいた月乃だったが、桜がレズビアンであることを知った後は桜の再びの褒め言葉に対して「そう?ありがと」というそっけない返事しか返さない。そんなそっけない返事をした月乃だが、色々と考えた上で次の日もシュシュをつけて登校する。桜からの好きな気持ちを受け止めることはできないが、親友として桜を守りたい。しかし、月乃は桜を守ることはできない。月乃の「それは違うよ、桜はレズビアンじゃないよ」と言いながら、黒板に書かれた「小牧桜はレズビアン」の文字を消したその行為は親友を守るどころか、むしろ傷つけてしまう。
桜はなぜカミングアウトしたのか?
黙っていればいいのに、当事者の桜はなぜ自分からカミングアウトすることに決めたのだろうか?この質問に答えるために、性的マイノリティに対する差別の現状について言及する必要がある。
『カランコエの花』の冒頭では、月乃がオーケストラ部の稽古に参加するシーンがある。雑音が絶対に許されないオーケストラの合奏は、LGBTを異質の存在と見なして認めない社会の在り方と重なる。以前に比べれば改善していると捉えられるかもしれないが、性的マイノリティに対する差別は未だに存在している。

ヘイトスピーチのレベルを表す理論憎悪のピラミッドによると、ヘイトスピーチを5つのレベルに分けることができる。昔の性的マイノリティに対する差別はジェノサイド・暴力行為・差別行為のレベルだったが、現代社会においては偏見による行為や態度の方が多いのではないだろうか。しかし、このような行為や態度も別の形でマイノリティの心や身体を苦しめ、そして時には命を脅かすこともある。
マジョリティ側の何気ない言葉や行動にも、性的マイノリティを排除していることもよくある。例えば、月乃と桜が入っている4人の女子グループのメンバーが恋話をするシーンでは、そこにいる全員がヘテロセクシュアル(異性愛者)でアセクシャル(他者に対して性的欲求または恋愛感情を抱かないセクシュアリティ)当事者ではないということが前提にある。このようなマジョリティ側の「悪意のない」言動は表に出る明らかな差別行為とは少し違うが、マイノリティにとっては苦しいという点で同じだ。
LGBTについての授業を受けた日、月乃は家に帰ると、母に先生が今日休んでいたのではと聞かれる。母は「先生は生花店の息子で、お休みだったことを店主から教えてもらった」と答えた。それを聞いて、月乃は「隠し事できないね」とつぶやいた。どんな小さな出来事でも隠せない地方社会では、性的マイノリティと人に知られることはとても恐ろしいことだと想像できる。
桜が自らカミングアウトした理由も、このような偏見による行動や態度が耐えがたかったからだと考えられる。「いつか誰かに、他の人に自分の秘密を漏らされる前に、自分からした方がマシだ」と思っての決断だったのではないだろうか。しかし、これは桜のような立場に置かれている人にとっての最善策ではない。むしろ追い込まれた当事者が、やぶれかぶれになってやったことだけだとも捉えられる。
『カランコエの花』では、各エピソードの前に日付が書いてある。物語が始まる最初の日は7月4日で、最終の日は7月8日だ。わずか一週間弱の間にも、悲しくて恐ろしい事件は起きてしまう。偏見による態度や発言のように認識されにくい差別でも、日常生活の中には十分に起こりうる可能性があるということだ。
果たせなかった先生の役割
桜のカミングアウトが最後の悲しい結末に繋がってしまう前に、できることはあったはずだ。特に『カランコエの花』では先生たちが果たすべき役割を果たせていない。
桜からカミングアウトされて桜の秘密を知った保健室の先生、小島花絵(以下:花絵)。その告白の途中で、桜と同じクラスにいる葛城沙奈(以下:沙奈)が保健室に入ってきた。沙奈に「自分の秘密を知られてしまったのでは...」と不安に感じる桜のために、花絵は二人のいるクラスでLGBT理解増進のための授業を行う。しかし、あまりにも唐突なこの授業は桜を助けるどころか逆効果をもたらした。
好奇心に駆られて犯人捜しを始めた男子生徒の二人に対しても、花絵は二人が何をしようとしているのかを知っていながら、その場で二人を止めなかった。「うちのクラスにゲイいるんでしょう?もしくはレズとかそういうキモイやつが」と言ってくる男子生徒に対して、「『キモイやつ』なんて、そんなことは言ってはいけない」と返すべきだったのに、花絵はその場を適当に誤魔化しただけだった。
その後、花絵はクラスの担任の先生に事情を説明して、代わりに生徒たちの対応をしてもらう。担任の先生は厳しく生徒たちを叱ったが、「差別をしてはいけない」と教える代わりに、「(当事者が)いるから、そういう(LGBTに関する)授業をやったのではありません」と言った。問題を解決するために、一番に教えるべきだったことは差別行為の深刻さなのにも関わらず、「当事者がうちのクラスにいない」という言葉で問題を無理やり終わらせようとした。
先生のこのような中途半端な対応は当事者だけではなく、当事者以外の生徒たちまでをも困惑させた。桜の秘密を知り助けてあげたいが方法がわからない沙奈と月乃、犯人捜しの雰囲気は好きではないが前に出てそれを止めることができない他の生徒たち。先生が果たすべき役割を果たせなかったせいで、数人の生徒たちが頑張っても桜を助けることができなかった。
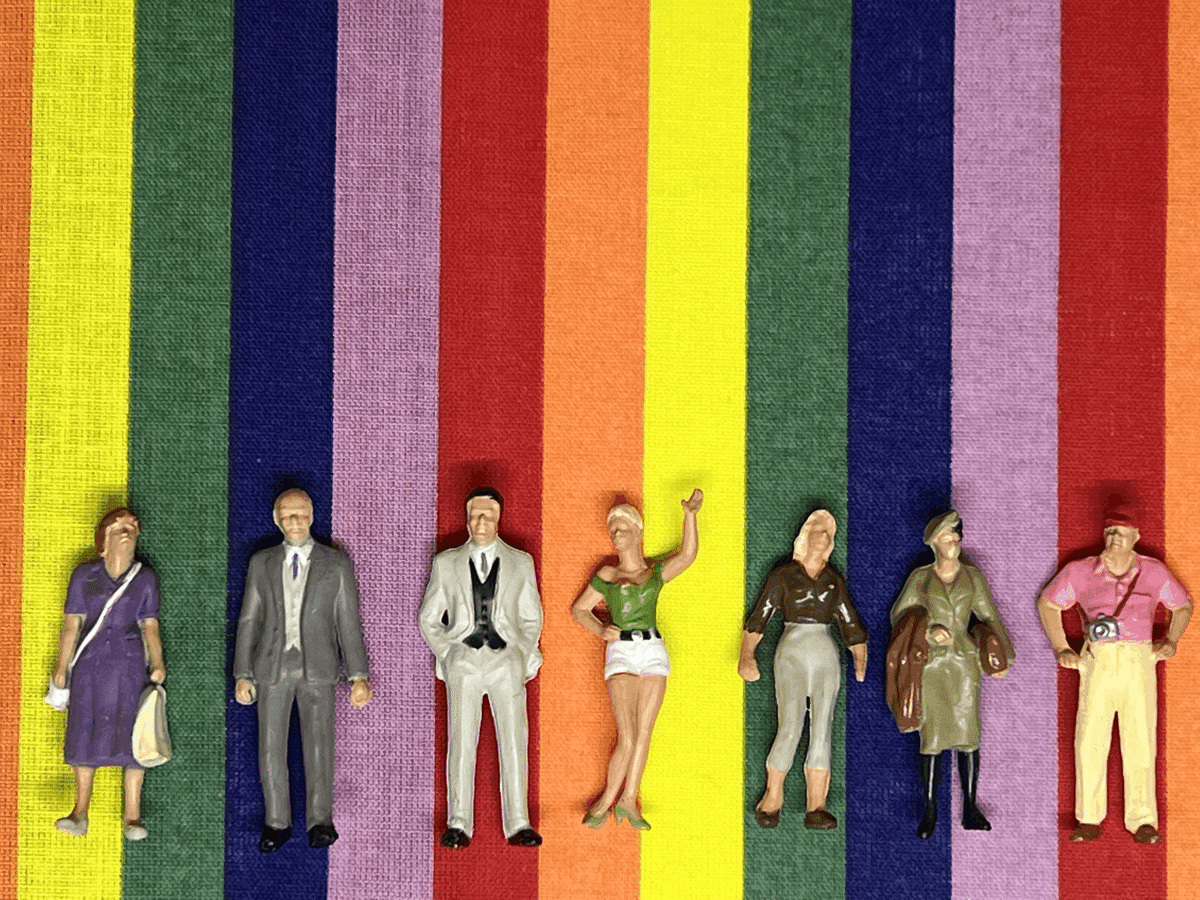
「桜」と同じ経験をする人がいなくなるように。
複雑な人間関係が含まれている問題として、アウティングの解決には専門家の介入と支援は欠かせないものだと考えられる。とはいえ、私たちにできることもなくはないと思う。一般人として、制度的な改革などのハード面での変化をもたらすことはなかなかできないが、周りの人の考え方を改めるというソフト面での試みを行うことができるはずだ。
性的マイノリティに対する理解を深める。他人のプライベートを尊重する。手に負えないと感じた時に素早く専門家のサポートや意見を求める。そして何より、差別行為を見かけた際にはそれを止めよう。このような形で、LGBT当事者に自分が一人ぼっちではない、自分を支えてくれる仲間がいるんだと感じさせることができる。これはその気持ちがあれば誰でもできるはずの、当事者に対する心理的サポートであるだろう。
映画の予告編はこちら
執筆者:袁盧林コン/Lulinkun Yuan
編集者:原野百々恵/Momoe Harano
