
手塚治虫は「火の鳥2772」をフルアニメーションで制作した
宮崎駿がアニメ界に入り、初めて携わった作品は東映「わんわん忠臣蔵」だとされているが、しかしここでは「中割り」を描く動画マンとしてであり、原画および一部の演出を手掛けて本格デビューとなった作品は「ガリバーの宇宙旅行」だとされている。

これ、「文芸」だか「エンタメ」だか結局どっちにつかずになってしまったSF作品なんだけど、内容はスペースオペラ、さらにいうとクライマックスには巨大ロボットとのバトルがあるというほどの野心作である。
で、この作品でヤバいのは、主人公たちが出会う宇宙人、まぁ、これが実質ヒロインということになるんだが、微妙な見た目なのよ↓↓

宮崎駿は、まだ当時ぺーぺーのくせに「こんなヒロインあかん!」と主張し、設定まで変えて強引に「実は彼女、美人だった」というシーンをラストで挿入したという(笑)。
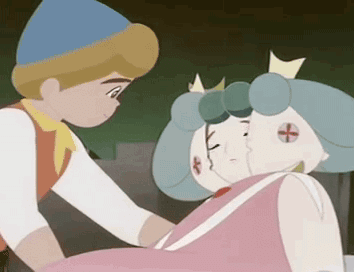

・・おぉ、めっちゃヒロインらしくなった(笑)
これが、宮崎駿の初ヒロインですね。
宮崎さん自身は「最悪の作品だった」と振り返るほどの黒歴史らしいんだが、彼の実質デビューがこういうスペースオペラ系活劇だったという事実はなかなか興味深いと思う。


でもね、この当時のスペースオペラはまだ子供だましの範疇ですわ。
「スペースオペラこそエンタメの金脈だ!」と決定付けたのは
【1977年】劇場版「宇宙戦艦ヤマト」興行収入21億の大ヒット
【1978年】映画「スターウォーズ」興行収入61億の大ヒット
【1979年】劇場版「銀河鉄道999」興行収入16.5億の大ヒット
という一連の流れである。
で、ここから「機動戦士ガンダム」がスタートしたわけだが、1980年、実は手塚治虫、石ノ森章太郎という漫画界の両巨匠が奇しくもスペースオペラの劇場版を作ってるんだよね。
「火の鳥2772愛のコスモゾーン」(1980年)

「サイボーグ009超銀河伝説」(1980年)

いかにも「時流に乗りました!」という印象の2作品である。
「サイボーグ009」に至っては、もう完璧にイメージビジュアルからして「宇宙戦艦ヤマト」スターシャのパクリじゃん?
ぶっちゃけ、真面目な「009」ファンはこの作品のことをあまり語りたがらないんだよね(笑)。
確かに、「009」にしてみれば世界征服を企むブラックゴーストこそが真の敵で、正直、宇宙は守備範囲外なのよ。
・・だけど、私はこの作品を嫌いじゃないよ。
だってこの作品のオチこそ、2012年神山版の「サイボーグ009Re:CYBORG」の原型だと思うし。
<セカイの書き換え>という、21世紀になってからようやく認知されてきた概念を、この1980年で既にやってたのは普通にスゴイって。

で、この脚本に協力したのが「スターウォーズ」の脚本を手掛けてたというジェフシーガルなる人物で、実際このジェフの名は大々的にプロモーションされたわけですよ。

ところが後日、「スターウォーズ」のスタッフに問い合わせてみると、誰ひとりジェフの名前を知らなかったという(笑)

・・ジェフ、結局お前は誰だったんだ?
結果、「超銀河伝説」の興行は大コケで終わったらしい。

さて、今回は「009超銀河伝説」のことより、「火の鳥2772」の方をメインとして書きたいんですわ。
これも興行的には大コケしたとはいえ、なかなかの野心作だからね。
総監督を務めたのは手塚先生ご本人であり、おそらく彼は並々ならぬ思いでこの作品に臨んだと思う。
なぜなら、「リミテッドアニメ」の象徴であるともいうべき手塚先生が
なぜか、この作品だけはフルアニメーション(1コマ打ち)で作ってるからだよ!


いやね、ホントこの映画の冒頭数分ぐらいはビビるよ。
セリフが一切なし、1コマ打ちの人物のモーションと音楽だけでストーリーが進んでいくんだから。
1カット長回しというのもあったり、アニメ好きからすると「おおっ!」という演出のオンパレードである。
当時は、これを「1940年代のディズニー映画みたいで古臭い」と捉える人が多かったと聞くが、いやいや、手塚先生はもともとが1940年代ディズニーに衝撃を受けてアニメを志した人なんだから、こういうのも全然ありでしょ。

でもまぁ、「火の鳥」も本来は日本の歴史に根差したサーガだったはずだし、宇宙を舞台にしたスペースオペラってのもどちらかというと守備範囲外なんだよね。
そこは、やっぱり「宇宙戦艦ヤマト」への強い対抗意識があったんじゃないだろうか?
先生と「ヤマト」プロデューサー西崎義展との間には過去に色々あり、正直いうと「ヤマト」を敵視してたと思う。
それがモチベとなり、ここにきてフルアニメーションへの挑戦という決断に至ったんだと思うが、他にもCGの一部導入、ロトスコープの一部導入など、先生はこの作品で実に様々な挑戦をしている。
・・ただね、手塚先生はこの作品を作った後、耳を疑うようなトンデモない発言をしてるのよ。
「もう、ディズニーみたいなバカバカしいことはやめました」

ええっ、アンタあれほど「バンビ」に感動して死ぬほど見たとか言ってたのに、ここにきて「バカバカしい」?
どうも、この頃(虫プロ倒産後)の手塚先生は、アニメというものにある種の迷いを抱えてた感じなんだよね。
それは、この時期のあるインタビューの中にそれが見てとれるわけですよ。
手塚「『ヤマト』や『あしたのジョー』なんかのアニメを見ている連中は、アニメに何を求めるかというと、物語性じゃないかと思います」
インタビュアー「動きじゃないですね」
手塚「動きじゃないですね。
動きが好きなのは、クロウトですね。
だから、今度の『火の鳥』の場合、凄く迷ったのは、これはいわゆるアニメにするか、そういう興行上の商品として完璧な、<今の観客に向く要素>を盛り込むか、そこらへんで物凄く悩んだですね。
その悩みがそのまま出ている」

この話を聞いて、なるほど、と思ったなぁ。
実際、「その悩みがそのまま出ている」要素のひとつとして、上の画の表現とか、これほとんどフルアニメーションになってないよね(笑)。
せっかく1秒24フレームの形で制作してるのに、画の表現としてはほとんど
リミテッドアニメに近いものなのよ。
というか、ほとんど「出崎演出」じゃん(笑)。
作品は後半にいけばいくほど、こういう傾向が強くなっていく・・。

「その悩みがそのまま出ている」と自ら言及してところから見て、先生自身この「火の鳥2772」を失敗作と見てるんだろうな。
中途半端になった、と。
・・で、実際この作品に携わったアニメーターが証言してるんだが、どうも手塚先生という人は完璧主義者というか、総監督という立場なら統轄として大局的な仕事をすりゃいいものを「全部をコントロールしたい」という悪い癖が出るらしく、どうも自分で原画を描いたりもしたがるらしいんだわ。
いや、それならそれで別にいいんだけど、やっぱ先生は本業もあって忙しい人ゆえ手をつけた原画を完成させられないってパターンが多かったらしく、ぶっちゃけ現場の原画マンとしてはそのフォローに追われてイイ迷惑だったらしい(笑)。
途中から画のクオリティが落ちてきたのも、率直にいえば手塚先生の責任という話も・・。
そのへんは先生自身も自覚があったのか、以降、彼は長編アニメ映画の監督を全くやらなくなったと思う。
私の知る限り、手塚先生は漫画家としては絶賛される一方、アニメーターとしての先生のことを絶賛した人は今まで1人もいないかも・・

残念ですけど、やっぱりそういうことだと思うんですよ。
アニメというのは漫画と違って、1人の才能で全部コントロールできるもんでもないでしょ?
もし、それを出来るとすれば「火の鳥」のような大作じゃなくて、小規模な自主制作アニメの範疇であるべき。
おそらく、先生自身もそういう結論に辿り着いたんだろう。
彼は「火の鳥2772」以降の80年代、あまり知られてないかもしれないけど、地道に短編アニメを制作するようになったんだよ。
そして驚くことに、80年代の短編手塚アニメは傑作が多い!
じゃ最後に、それらの傑作短編の幾つかを実際に見てもらいましょうか。
「JUMPING」(1984年)時間約6分
「おんぼろフィルム」(1985年)時間約5分
・・ね?
やっぱ手塚先生って天才でしょ?
お前、さっきと言うとること真逆やないか?と思うかもしれんが、違うのよ、先生は大所帯を仕切る演出家としては正直あれだけど、こうして1人でコツコツ漫画を描くみたいにしてアニメを作らせりゃ、十分に才能のあった人なんだわ。
この人は、正真正銘の<天才>だから、むしろ全部1人でやらせた方がいいってこと。
当然、本業の方があるから時間をたっぷりはとれないだろうし、だから必然短編アニメということになるんだけどね。
で、「JUMPING」にせよ、「おんぼろフィルム」にせよ、先生が作ったのはセリフなしのアニメなんだよな。
「JUMPING」は俗にいう「ワンカット長回し」、また「おんぼろフィルム」はレトロ調のサイレントムービー。
あぁ、結局手塚先生がホントにやりたかったのは、それこそ「火の鳥2772」でいうところの、冒頭数分のやつじゃん?
「火の鳥2772」オープニング
うむ、これは1940年代ディズニー、そのまんまである。
つまり先生は「もう、ディズニーみたいなバカバカしいことはやめました」と言いつつも、それは「商業作品において」という補足付きの話だったようで、その後の先生は明らかに<非商業作品>、<クロウト向け>の方に舵を切ってるんだ。
そのターニングポイントになったのがやはり「火の鳥2772」であって、これは手塚先生を語るにおいて絶対欠かせない一作だと思う。
未見の方はYouTubeでタイトルを検索すれば無料動画がありますので、是非一度ご覧になってください。


