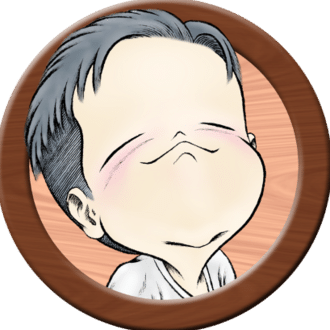宮本武蔵は素手でも最強?剣聖が極めた達人格闘スキルを史実から読み解く!
「宮本武蔵は素手でも最強?剣聖が極めた達人格闘スキルを史実から読み解く!」
「宮本武蔵」といえば、日本最強クラスの剣豪として語り継がれる存在ですよね。二刀流の使い手であり、生涯60回以上の真剣勝負で無敗を誇る伝説の剣士であることは、日本人なら誰もが知っていること。
でも、ちょっと待ってください。宮本武蔵は 「剣の達人」 というだけではなく、素手における格闘術でも、頭一つ図抜けた達人だったのではないか?
そんな説を、立ててみました。
もし、剣を持たない「素手の戦い」になったとしても、彼は普通に戦えるどころか、むしろ圧倒的に強かったのではないか?
そんな仮説を立ててみると、宮本武蔵の戦闘スタイルがより面白く見えてきます。
この記事では、 「宮本武蔵は素手でも強かったのではないか?」 という視点で、彼の戦闘能力を深掘りしていきます!
武蔵の戦いは武器だけに頼らない戦闘だった?
武蔵の最も有名な戦いといえば、やはり 「巌流島の決闘」 ですよね。
佐々木小次郎の長尺の刀「物干し竿」に対し、武蔵が選んだのは 木刀(しかも櫂=オールを削ったもの) でした。
この戦術には諸説ありますが、有力なのは、 小次郎の長剣に対抗するため、さらに長い武器を用意した という説。
つまり武蔵は、刀という武器の種類にこだわらず、「勝つための最適解」を考える戦闘者 だったのです。
ということで、この視点を広げて考えてみると。
「もし手にする武器すらなかったとしたら?」
武蔵は、剣を持たない状況でも「素手で戦うこと」という緊急事態を、常に想定していた可能性が高いのです。
武蔵の兵法には「体術(素手の戦い)」も含まれていた?
武蔵が創設した 「二天一流」 は、剣術だけでなく 「体の使い方」 を極める兵法であることがうかがえます。
その根拠として、彼の著書『五輪書』には、こんな記述があります。
「兵法の極意は、手の内、足の運び、体の置き方にあり」
この言葉、剣を持たない武術の柔術や合気術などでも、通じる極意だと思いませんか?
つまり武蔵にとっての戦いの極意とは、「剣だけではなく、体のあらゆる部分が武器である」という思考であり、身体の使い方が極意のようなもの だった可能性があるのです。
これは、現代の格闘技、たとえば 総合格闘技(MMA) や 護身術 にも通じる考え方ですよね。
また、武蔵の「二刀流」は、戦場では 「片手で刀を使う方がより実戦的」 であることに気づいた結果だとされています。
戦場では片手に刀を持ち、もう片手では槍を持つこともあれば、斜面を駆け上がるときに空いた手を地面についたり、支えになる木々を掴んだりすることが多く、両手の分担で敵を迎え撃ち、闘うという能力が重要でした。
つまり武蔵は抜きん出て「両手の使い方に優れた格闘家」 でもあった可能性が高いのですね。
素手でも強かったと考えられるエピソード!
武蔵の生涯には、「これは素手でも強かったのでは?」と思わせるエピソードがいくつかあります。
✅ 13歳での初決闘~木の棒で圧勝したこと
武蔵が13歳のとき、新当流の有馬喜兵衛と決闘をしました。
通常、武士同士の戦いなら「木刀」や「真剣」を使うものですが、武蔵が使ったのは 「木の棒」 でした。
それでも武蔵は圧勝し、喜兵衛を打ち倒しましたが、その当時の宮本武蔵は13歳という年齢が信じられないような、大人顔負けの体格をしていたようですね。
この時点で、すでに 「剣に頼らず、勝つために得意とする武器を使って戦っていた」 ことが伺えます。
✅「打ち込み」による一撃必殺の技
武蔵の戦闘スタイルは 「初太刀で決める」 ことにこだわっていました。もっと後の時代になって知られるようになる、薩摩示現流の極意でもある「一の太刀」と通じるものがありますよね。
この「打ち込み」の激しい鍛錬により、刀を使った剣術だけでなく、そのまま 素手での打ち込み(手刀などの打撃技) にも応用できるのです。
現代の格闘技でいうと、空手の追い突きや、形意拳(中国拳法)の崩拳のように、突き込むことができるわけですね。
もし武蔵が現代にいたら、MMAやボクシングでも 「一撃必殺の打ち込み」を得意とする選手 になっていたかもしれませんね!
✅武蔵、実は「寝技」も強かった?
江戸時代以前から、剣術に付随して 「組討ち(くみうち)」 という技術がありました。
これは、鎧武者同士が闘うときに、鎧で防いでいることから刀で敵を倒しにくいために、組討ちで敵をねじ伏せ、鎧通しで鎧の隙間から致命傷を与えて勝つための技術。
また、刀や槍が折れたときに素手で戦うための技術 としても伝わり、現代の 柔道やグラップリング(寝技) にも通じるものがありますよね。
武蔵は剣術での闘いも豊富ですが、島原の乱では戦場を経験しており、戦場での実戦に効果的な戦い方も、当然ながら知っていた可能性が高いのです。
つまり 「剣がなくても、組討ちで相手を制圧する力もあった」 と考えられるのです。
また、武蔵が二刀流を実戦で使いこなしていたことや、13歳で最初の真剣勝負に勝ったことを考えると、単純に 握力や腕力が異常に強かった 可能性が高いのですね。
現代のトップアスリートの握力は 60kg~80kg 程度ですが、江戸時代の武士は 100kg以上 あったとも言われています。もし武蔵がこのレベルだったとしたら・・・・相手の腕をつかんだ時点で勝負ありだったのでは!?
つまり、武蔵が「素手で組み合ったら、一瞬で極めてしまうほどの怪力だった」と仮定すると、よりリアルに「素手でも強かった説」が際立ちますね!
武蔵の「戦闘スタイル」を現代の鍛錬に活かすと?
もし武蔵の戦い方を、現代のトレーニング(ワークアウト)や武道に応用するとしたら、こんなことが考えられます。
「体の使い方」を意識したワークアウト(重心移動・体幹の強化)
「最小の動きで最大の効果を出す」訓練(打撃・投げ・防御の最適化)
「武器に頼らない身体操作」(どんな状況でも対応できるスキル)
これはまさに、現代の 護身術や実戦格闘技 の考え方そのものですよね。
さらに、武蔵は「剣術家特有の動体視力」も持っていたはず。
武蔵の剣術には、敵の「動きを見切る」技術が組み込まれています。
特に「観の目」「見の目」という概念は、現代の格闘技に通じる部分が多いのですね。
✅ 「観の目」= 相手の全体を見る(状況を読む)
✅ 「見の目」= 相手の武器や手足をピンポイントで観察する
この2つの目の使い方は、現代ボクシングや総合格闘技(MMA)で重視される 「ディフェンス能力」 に直結します。
武蔵は、相手の動きを見極めるスキルがずば抜けていたはずなので、素手で戦っても「攻撃をもらわない格闘家」になっていた可能性が高いですね!
武蔵に限らず昔の剣士は、電光石火の刃筋を見切る鍛錬を積むため、現代格闘技の打撃スピードでは 「スローに見える」 可能性が高いのです。
つまり、武蔵が現代にいたら 「剣士の目+柔術+打撃系+MMA」 という、超ハイブリッドな総合格闘家になっていたかもしれませんね!
まとめ:「武蔵は素手でも強かった」説はあり得る!
宮本武蔵は 「剣の達人」 というイメージが強いですが、宮本武蔵の残した二天一流の形や、60回に及ぶ戦い方、「五輪書」の記述内容から紐解く極意のエッセンスを考えると 「素手でも相当強かった」 という説には十分な根拠があります。
✅ 剣にこだわらず、どんな武器でも戦えただろう
✅ 二天一流は「両手使いの体の使い方」が特長である
✅ 実際に「打撃・組討ち」の技術も持っていた可能性が高い
ここから考えると、武蔵は 「剣術 × 打撃系格闘技 × 体術」 を総合的に習得した MMAの原型となる戦士 だったのかもしれません。
今回の話は「剣の達人は素手でも最強なのか?」 そんなロマンあふれる話でしたが、宮本武蔵に関しては、 単なる仮説ではなく、実際にあり得た話 のような気がしていま。
もし武蔵が現代にいたら、きっとUFCで 「史上最強のファイター」 になっていたかもしれませんよね!?🔥
ってことで、今回は
「宮本武蔵は素手でも最強?剣聖が極めた達人格闘スキルを史実から読み解く!」剣聖宮本武蔵がもし素手で闘ったらどのくらい強いのかの話。😄
※見出し画像のイラストは、メイプル楓さんからお借りしました。
では!
一撃に 魂のせて のほほんと
<最近投稿のスキの多かったサブアカの記事がこちら!>
いいなと思ったら応援しよう!