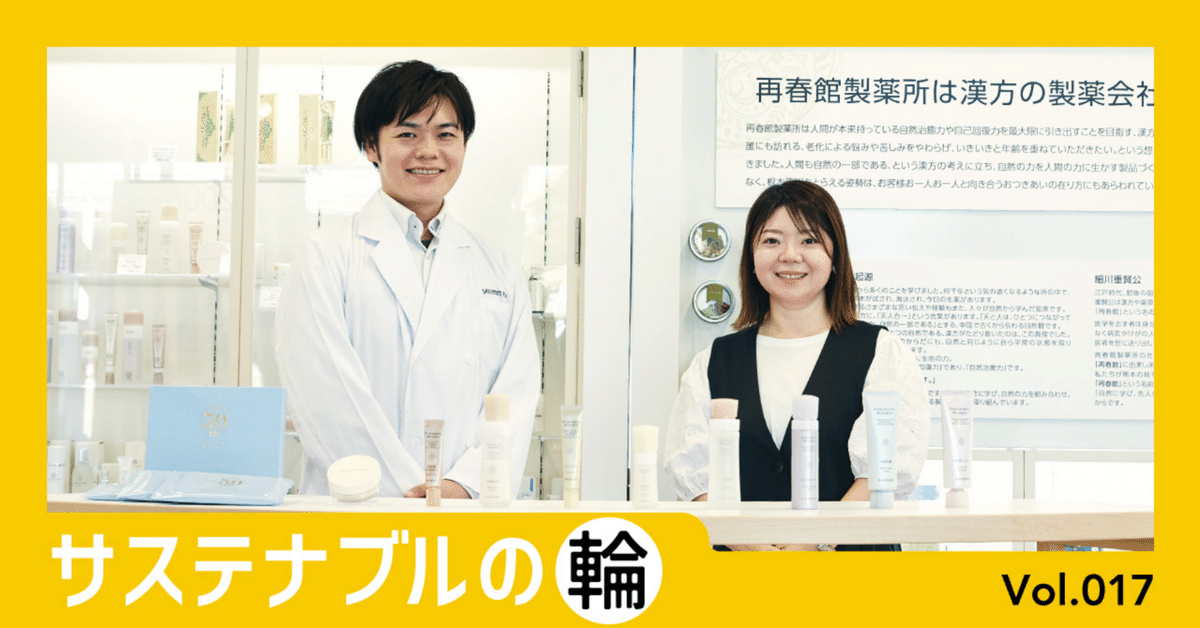
"人間も自然の一部”という漢方の考え方をベースに、自然からの恵みを人の力に活かしていく。サステナブルの輪Vol.017再春館製薬所
皆さまこんにちは。ヤマト運輸公式note編集部です。
ヤマト運輸公式noteがお届けしている「サステナブルの輪」では、ヤマトグループとともにサステナビリティへの取り組みを推進しているパートナーさまに、サステナビリティに関する活動や想い、狙いについて語っていただいています。
今回は、漢方の製薬会社として化粧品・医薬品・医薬部外品などの製造・販売を行い、通信販売で世界に展開する再春館製薬所さまのサステナビリティへの取り組みをご紹介します。
熊本に拠点を置く再春館製薬所は1932年創業。漢方の製薬会社として、神経痛やリウマチによる痛みに対する生薬製剤「痛散湯」を軸に販売。そして、同じ漢方発想にもとづき、1974年に年齢肌のための基礎化粧品として「ドモホルンリンクル」が誕生しました。「ドモホルンリンクル」は日本で初めてコラーゲンを配合したスキンケア製品として誕生し、今年50周年を迎えました。
ドモホルンリンクルをはじめとした製品は熊本の自社工場で製造。店舗での販売は行なわず、独自のテレマーケティングを展開しています。2011年より海外へも展開し、現在、アジアを中心に世界43カ国で愛用されています。
今回、研究開発部上席研究員の今吉裕隆さまと、ブランドコミュニケーション部の林基理さまにお話を伺いました。
漢方の考え方をベースに人と自然が共生できるものづくり

私たち再春館製薬所は、「人間も自然の一部」という漢方の考え方にもとづき、自然の恵みを人の力に活かしていくことが根本の理念です。ものづくりに関してもその想いは同じで、SDGsやサステナビリティという言葉が世に出てくるずっと前から、自然に負荷をかけない取り組みをおこなっています。
まずは本社と工場を置く「再春館ヒルトップ」をご覧いただくと、当社のサステナビリティへの取り組みについてご理解いただけるのではないかと思います。阿蘇山を望む自然豊かな高遊原(たかゆうばる)という場所に位置する「再春館ヒルトップ」は、2001年、約9万坪の敷地に「森の中の工場」をイメージしてつくられました。建物のネーミングにもこだわり、工場は人と自然が共生できるものづくりを行いたいという想いから、「薬彩工園(やくさいこうえん)」と名付けられました。

また、「ヒルトップ」という名称は、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポターが自然保護活動に尽力した場所である英国の丘陵地「ヒルトップ」にちなんだものです。「再春館ヒルトップ」は、総面積の約7割が緑地・草地になっており、生態系の調査などを行い、動物や植物の住み心地を損ねないことを一番に考え、もともとある木々をできるだけ残せるような設計がなされています。
樹木の一部は竣工時に、九州にお住まいのご家庭から移植した木々です。ご事情により切り倒さざるをえなくなった庭木を「木のふる里キャンペーン」として、新聞紙面などで呼びかけ引き取りました。それから20年を超えた樹齢200年のクスノキは、今では、この丘のシンボルとなっています。
「美花隊」という部署も設け、社員自らの手で管理も行なっています。2007年には本社機能やコールセンターも移転し、製販一体となった拠点として、動物や植物の生態系を保護しつつ、水源となる森や花畑、池や小川など自然環境の育成に努めています。「この自然を次世代につないでいきたい」という想いから、「再春館ヒルトップ」では自然との共生に向けた、さまざまな活動に取り組んでいます。
2001年には太陽光発電設備に着手し、13年の歳月をかけて、3万枚ものソーラーパネルを建物の屋上や敷地内の斜面に少しずつ増やしながら、張り巡らせました。そして、太陽光から電気を生み出すこの場所を「太陽の畑」と名付けました。敷地内で使用する電力は、年間自給率100%を達成し、年間3,356tのCO₂削減につながっています(2022年1月時点)。
また、生薬を煎じてエキスを抽出する際に出る原料のカスも決して無駄にせず、肥料として敷地内の畑で活用し、野菜や果物を栽培。採れた野菜は、社員食堂のメニューに取り入れられています。その他、資材のリサイクルはもちろん、オフィスから出る不要物も、可燃、プラスチック、金属、ビニール、古紙などの分別を徹底し、工場資材のリサイクル率は99%超の実績。
そして、豊富な地下水に恵まれた熊本だからできることとして、阿蘇の伏流水を地下200mから汲み上げ製品づくりに活用しています。さらに、容器洗浄などに使った工場排水は浄化槽を通し、魚が棲めるほどの状態にして、防火用水やトイレの水に再利用するほか、7割が緑地である再春館ヒルトップの敷地を生かして、雨水を地下浸透させて帯水層に水を供給する「涵養(かんよう)」を行い、使用量よりも多くの水を地下水として戻しています。その延長として、涵養対策を行う財団への長期的な支援も開始しています。
「もったいなかよ」から生まれたサステナブルな原料選び

ここからは再春館製薬所ならではの、原料に関わる取り組みについていくつか紹介させていただきます。1974年に誕生した「ドモホルンリンクル」は、今年で50周年を迎えました。「ドモホルンリンクル」もまた、「人間は自然の一部」という漢方の考え方から、その原料の多くは自然界の摂理に着目して見出されてきました。当社では、「自然界に無駄なものは、何一つない」という考えから、捨てられてしまう物の有効活用に取り組むことを通して、持続可能な社会の実現に寄与する原料の使用を積極的に進めています。

主力商品である「ドモホルンリンクル」は製品ごとにさまざまな植物のエキスを使用していますが、そこでもサステナビリティにつながる原料を採用しています。例えば、保温機能に優れ、水分を豊富に含む水茄子。「保温液」に欠かせない原料として使用していますが、水茄子栽培は大きく成長させるために間引きが行われます。当社ではその間引きされ、捨てられてしまう水茄子を有効活用しているのです。また、熊本名産で世界最大級の柑橘「晩白柚(ばんぺいゆ)」も、成長後の枝への負担を考え、摘果・廃棄されてしまう早摘みの「晩白柚」を使用。青い実こそ、生命力の塊ではないかという発想によるもので、実際、肌を元気にする効果や、うるおいを高める効果が見出されています。
最近の事例では、「パール柑」というブランドで販売されている熊本産の「文旦(ブンタン)」があります。その中で販売できないB級品だったり、ジュースの残り滓だったり、捨てられてしまうものを有効活用できないかと考え、結果ハリに効果があることが分かり、今年の12月にリニューアル発売する「クリーム20」に配合いたします。

その他、“百草の王”とも呼ばれる「長白参(ちょうはくじん)※1」という高麗人参がありますが、当社はその「長白参」のひげ根の部分のみを採用しています。なぜかというと、このひげ根には肥沃な大地の養分を吸い尽くすほどの力強さがあるために、栄養が非常に多く含まれているためです。「長白参」の中でもグレードの高いものはすぐに売れてしまうのですが、ひげ根を必要とするため、売れ残ってしまうものを有効的に活用することができます。
※1/中国東北部にそびえる長白山脈で育つ人参で、再春館製薬所ではその地名にちなんで「長白参」と呼んでいます。
熊本は焼酎でも有名ですが、焼酎を造る際に出る残りカスも有効活用しています。「ドモホルンリンクル」は、ずっと同じ素材を使い続けているというわけではなく、数年ごとに製品の処方や設計などを一からすべて見直す「リニューアル」を行っています。何らかの効果が期待できる、アップサイクル素材があれば優先的に採用し、さらに良いものが見つかれば切り替えていく、そういう考え方を軸として進化を続けています。コラーゲンを化粧品に初めて採用したパイオニアとして、コラーゲン研究にも50年の深い歴史があり、これまで様々な原料由来のコラーゲンを使用してきましたが、現在はタイのアンダマン海で採れる「鱧(はも)の皮」から採れるコラーゲンを採用しています。日本の鱧より2倍以上もの大きな鱧で、タイでは皮の部分は廃棄されていました。そこに着目したところがこの鱧コラーゲンとの出会いです。
最後に、地域とともに取り組んだ事例を一つご紹介します。熊本県不知火地方で健康茶として民間伝承されてきた「不知火菊(しらぬいぎく)」という菊があります。不知火地方だけでしか育たない珍しい菊で、”幻の花”とも呼ばれていました。発見当時はまだ学名もない事実上の新種でしたが、再春館製薬所では研究を重ねることで、「ドモホルンリンクル」の原料の一つとして採用することになりました。当初は特定地域のみでの栽培で300株ほどしか栽培されていなかったのですが、ドモホルンリンクルの原料として採用することで栽培エリアが広がり、今では地域活性化や雇用促進にもつながっています。
このようにさまざまな事例を紹介させていただきましたが、自然からの恵みを大切にし、それを人の力に活かしていくという想いから、捨てられてしまうものをであっても有効活用していく、あるいはアップサイクルしていく。こうしたサステナブルな原料選びは、再春館製薬所が長年にわたって続けてきたことです。結果として現在、サステナビリティにつながる取り組みになっていると思います。
サステナビリティは社員一人ひとりの当たり前の価値観

商品の容器や包装に関しても、少しでも資源の無駄をなくすために、環境に配慮した取り組みをおこなっています。例えば容器ですが、できるだけお客さまが分別・リサイクルしやすいよう、ガラスはガラス、キャップの樹脂は樹脂としてすべて外れるような作りにしています。ガラス製の容器は品質保持の観点から採用されていますが、輸送時の割れ防止のために、今治のタオル工場で出た残り糸を使った「残糸タオル」でボトルを包む取り組みも。これからもこのような資源の無駄をなくすことにつながる取り組みを継続していきたいと思っています。

私たち再春館製薬所では、毎日、そして永く使うものだからこそ、容器には安心感・安全性の追求、環境への配慮、そして使い勝手を大切にしています。三分の一ひねれば開くキャップや最後まで使い切れる設計のノズル、人間工学にもとづく、手にフィットする太さのボトルのストレスフリーな使用感なども、見た目以上に重要なことだと考えています。こうした容器や包装のデザインに関しては、お客様から意見を取り入れて、お客さまとの「共創」を重要視しています。例えば、私たちが見逃してしまった点をお客さまのご指摘により気づかされ、デザインを変えたこともあります。現在のデザインも、こうした教訓が活かされた、お客さまとの「共創」の一つです。
サステナブルな容器・包装の取り組みに関しても、お客さまからの声を積極的に取り入れていきたいと思っています。再春館製薬所では、こうした資源の無駄をなくす取り組みは、社員一人ひとりが身近な活動として日々、行われています。使わない場所の不要な電気は消す、紙一枚でもむやみに捨てない。毎日の仕事や生活の中で感じた「もったいない」の気持ちを行動に移す。私たちの環境への取り組みは、そんな身近なところから始まると考えています。
再春館製薬所には、サステナビリティを推進していく専門部署はありません。これまで紹介させていただいたように、私たちにとって、サステナビリティは当たり前であり、漢方の考え方にもとづく根本の理念にあるものです。ですので、あえてサステナビリティという言葉を使うこともなく、これまでも、これからも、当たり前のこととして取り組んでいくという共通の価値観は、社員一人ひとりに根付いています。
今回は、再春館製薬所さまのサステナビリティへの取り組みをご紹介させていただきました。次回からも引き続き、パートナーさまのサステナビリティへの取り組みをご紹介し、「サステナブルの輪」を広げていきたいと思います。
次回の配信もお楽しみに。
編集・著作:ヤマト運輸株式会社
