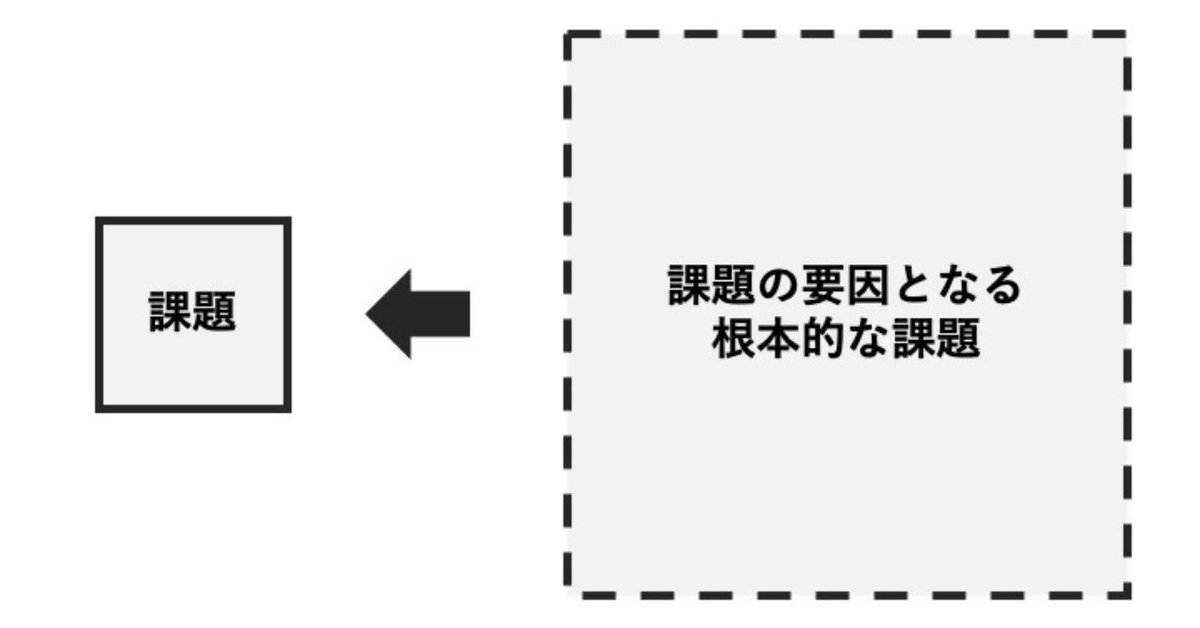
SaaSのプライシング戦略:コスト積み上げで算出しないSOB(Source Of Business)という考え方
プロダクトが提供する価値をどう定義するか、が事業の成長を決める大きな因子になります。
先日twitter上でHiCustomerの高橋さんとプロダクトのプライシングに関してこんな議論になりました。
上記の通り、SIerや、以前僕もやっていた広告代理業、等の従来のビジネスモデルでは、納品にどれくらいのコストがかかるのか、が提供価格のベースになることが多いです。
ただ、SaaSを始めとするプロダクトビジネスにおいて、コスト積み上げだけで価格を算出することには事業に対していくつかネガティブな点があります。
・顧客単価を引き上げる為に、より多くの機能を実装する/より多くの人員を投下する、というような"量"での勝負になってしまう
(顧客は必ずしも多機能/他人員を求めているわけではない)
・"どれだけ課題を解決したか"ではなく"どれだけリソースをかけたか"が事業全体の判断基準になり顧客ファーストの意識が薄れやすい
・利益率の改善が難しい
SaaSやプロダクトのビジネスにおいては、いかにLTVを高めるか、が最も重要なイシューになるので、コスト積み上げ算出による価格設定をしてしまうと、上記の状況からビジネスの拡大が難しくなってしまいます。
SOB(Source Of Business)を定義する
僕は、プロダクトの設計やマネタイズの計画を策定する際は、SOB(Source Of Business)という考え方を用いて進めます。
SOBは、プロダクトが解決する"根本的な課題"を如何に捉えるか、を定義することから始まります。"根本的な課題"とは、目の前の"課題"の本当の要因となっている、もしかしたら顧客も気がついていない真の課題要因を指します。
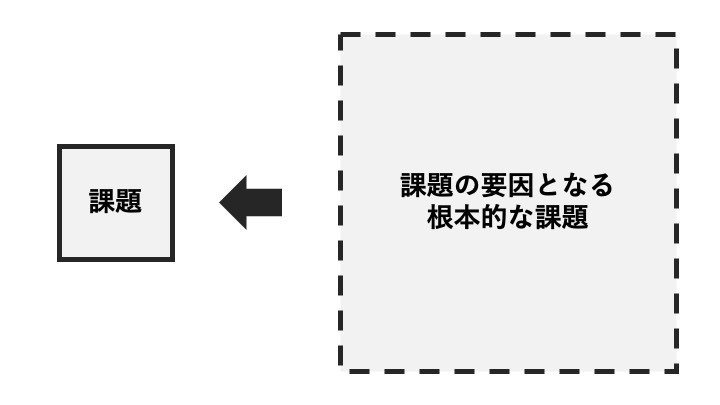
この"根本的な課題"の大きさに応じて、プロダクトの提供価値や価格が変動します。
例えば、以前に広告代理事業でお客様だったA社さんでは、
「広告運用の手間がかかりすぎて運用改善に手がまわらない」
という広告運用担当者の"課題"があり、人材派遣や広告運用ツールの導入を相談されたのですが、その課題をよくよく深掘ってみると、
「広告運用ノウハウが体系化されておらず、マーケティング人員の成長が鈍化している」
という"根本的な課題"が存在していることが分かりました。
このケースの場合、前者の課題をSOBの始点と捉えてしまうと、
・運用人材の派遣
・入稿業務の効率化機能実装
・自動最適化機能の実装
など、現場担当者の今の業務が楽になるプロダクトの価値提供が想定されます。
一方で、後者の課題をSOBの始点と捉える場合、
課題の核は"マーケティング人材がノウハウを体系化できないこと"と定義できるので、提供すべき価値は、
・広告指標の設計から伴走するコンサルティングサービスの提供
・媒体のアップデートや最新の運用Tipsコンテンツの提供
・社内関係者へ広告運用のプロセスや結果が簡易に共有できるレポーティング機能の充実化
など、マーケティング人材の底上げやノウハウ平準化まで視野を広げた価値の提供が必要になります。
2つとも、広告運用サービスであることは変わりませんが、
前者は、業務を効率化してくれる広告運用サービス
後者は、マーケティング人材の継続的な成長を実現広告運用サービス
と描写することができ、顧客からしたら全く異なるサービスとなります。
且つ、前者は現場の担当の方が対象になりますが、後者の場合は部門責任者や経営層が対象となる課題になり、予算規模も大きく変わります。
この認識の違いを生み出すことで、
①競合他社との強烈な差別化要因を作る
②より大きな予算にアプローチする
ということが可能になります。
SOBを策定する時のポイント
SOBを策定する際に有用なフレームワークがDIGIDAYさんの記事内に掲載されていたので転用させていただきます。

上記のフレームワークに沿って<・・・>内の単語を埋めていけば、自社プロダクトのSOB見直しが比較的カンタンに行えると思います。
ただ、その際に注意すべきが、
・<問題>や<根本課題>が顧客が使う言葉で定義されていること
自社内でしか使われない言葉や抽象的な概念を用いて<問題>を定義してしまうと、自社内では綺麗にまとまりますが、実際に顧客はピンと来ません。
定義する過程で「この<問題>ってお客様はピンと来る?」と何度も反芻することで、本当の<問題>にたどり着きます。
・<競合商品>が定義可能な<問題>を策定すること
<競合商品>が思いつかない=顧客が普段からお金を使っていない領域=自分たちの事業にもお金が入ってこない、ということになります。
<競合商品>が定義できない場合は、<問題>が正しいのか、から見直すことが必要になります。
の2点になります。
自社プロダクトへの思い入れが強ければ強いほど、自分たちの思考に囚われてしまいがちなので、SOBを策定する際は常に客観性を保ちながら行うことをオススメします。
SOBから逆算の価格を設定する
策定したSOBに対して、現状の価格が整合性を取れているか確認し、もし「低すぎる」「高すぎる」等があれば価格を改訂を検討すべきだと思います。
仮に価格が倍になったとしても、SOBで定義した"根本的な課題"を持つライトパーソンに当たれていれば、全く問題なく販売できるはずです。
今一度プロダクトが向き合う"根本的な課題"を見直し、言語化することで、事業拡大の一手が見えてくるかもしれません。
Twitterやってます。プロダクト事業のリアルな姿を毎日発信していますので、ご興味あれば是非ご覧ください。
参照:https://digiday.jp/brands/marketing-communication/
