
バイリンガル育児と、不安を煽る社会
アメリカ・カリフォルニアを拠点に活動している非営利団体ウィコラです。
ウィコラの活動詳細はHPからどうぞ
ウィコラが毎月開催している「妊娠産後サポートグループ」。
今回はその中のミニ講座準備における裏話をnoteで公開!
2022年初回のミニ講座のテーマは「バイリンガル教育」です。
裏話も最後はウィコラらしく!?意外な着地となりました。
バイリンガル育児中の方、これから予定されている方、ぜひ気付きやご感想があればコメントをお寄せくださいね!
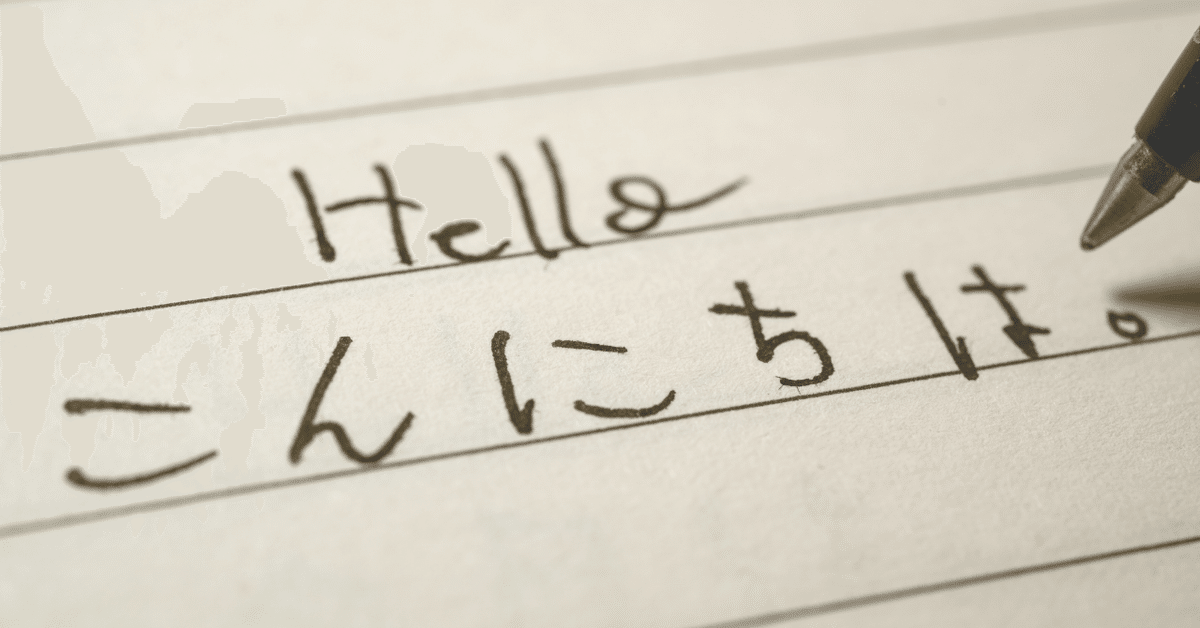
雪子:
以前皆さんに伺った意見も取り入れて、来月のミニ講座のアウトラインが出来あがりました〜。
10分にまとめるのでこの7割くらいはカットすると思いますが…
祥子:
いいですね!
親は自分の母国語を話した方がいいんですね。
うちは私もパートナー(日本語が第2言語)も日本語を話してます。
でも確かにそれで家族関係が難しいと感じる時もあるんですよね。
雪子:
悩む点だけど、悩んで出した答えはみんな正解だと思いますよ!
パートナーさんがこれまで頑張ってくれているおかげで、日本語の学校に行かずに日本語保持できているわけだし。
「親が複数言語を流暢に話す場合、弱くなりがちな言語で話す」に該当するんじゃないかな?
でも、今後何か問題があった時にまたベネフィットとリスクを考え直してもいいかもですね。

あかね:
講座が楽しみです!
私はまさに、なんとなくマルチリンガルだったらいいかな、でした。
なので、目標を設定することの大切さと、それを保育者全員で共有という点にはとても共感しました。
我が家はトリリンガル環境ですけど、パッションは本当に大切ですよね。
歌とかお話の重要性もひしひしと感じています。
子供って本当にそこから吸収している気がしていて。
そこから入らなかった言語に失敗してます、今。
雪子:
ふむふむ。
うちは北京語に少し挑戦してみたんですが、惨敗しました。
トリリンガルでインプットとアウトプットを必要量維持するのって難しいです…。

あかね:
特にトリリンガルを目指していたわけではないんですが、このままだとその言葉を好きじゃなくなってしまいそうで。
どう軌道修正すべきか悩んでいるところです。
片方の親の母国語のはずなのに!?でしたが、パッションや歌、読み聞かせのインプットが足りなかったのかなと思います。
アウトプットが重要というのも納得です。
祥子:
我が家は上の子だけトリリンガルうまく行ってます。
日本語と英語とスペイン語。
スペイン語は小学校がイマージョン(スペイン語で教科を習う学校)だったから。
雪子:
ぜひその話を次回してください!

みづき:
我が家は全員、日本生まれの日本人なので、子どもたちの第一言語も日本語であって欲しいと思っています。
でも、最近日本語が段々弱くなってきている気がして焦っていて。
日本語と英語が混ざることは良くあると思うのですが、兄妹で話すときは、遊び感覚でわざと混ぜて話すんですよね。
たまにそういう話し方をする程度なら良いんですが、何時間も延々とその言葉で話しているのを目にして、私は不安や苛立ちを感じてしまいます。
雪子:
分かります〜。
うちも混じりますけど、おばあちゃんとか日本語の先生と話す時には頑張って日本語で話しているのを見て、相手を見ているみたいとは思います。
やっぱり英語が楽なので、わざと私に英語をしゃべることもあるんですが、その度に「日本語って使わないとすぐ忘れちゃうらしいよ」とかいろいろ言い聞かせてます。
日本のバイリンガル教育では2言語の単語を混ぜることをタブー視しているとこもありますが、英語で見たリソースはほとんどが許容していいと言ってますね。
みづき:
国によって、バイリンガル教育への考え方も違うのですね。
「混ぜて喋っていても心配いらない」と聞いて、少し気が楽になりました。

みづき:
他には「子供の英語力が親の英語力を越えたとき、そのことで子供が親を見下すようになることがある」というのも、どこかで読んだ気がします。
すでにそういう兆候があるので、これも不安です。
雪子:
うちは既に長男の英語力が私を超えている部分がありますね。瞬殺されました(笑)。
「英語すぐ上手くなるからお母さんに教えてね」って昔からお願いしてます。
親を見下すのはプリティーンあたりに加速するらしいです。
されたらやだなぁ… 多分説教しそう(笑)。
みづき:
余談ですが、10年ほど前にポルトガルに行った際、付いてくれた通訳さんの日本語が素晴らしかったんです。
その方はブラジル育ちでしたが、おばあちゃんが日本人で日本語を教えてくれたそうで。
ご本人は日本には一度も行ったことがないそうですが、私よりも美しく流暢な日本語を話されていて大きな衝撃を受けました。
お聞きすると「とにかくたくさん日本語の本を読んだ」そうです。

雪子:
へぇー!すごいですね。
流暢さももちろんですが、「美しい日本語」に憧れます!
本を読むのが良いのは分かってはいるんですが、うちの子(7歳)は読み聞かせが好きすぎて。
自分で読ませるのを怠っていたら、読むことにもう苦手意識ついてるんですよね。
今必死で毎日自分で読ませてますがどうしたらいいもんだか… 。
先が思いやられます。
みづき:
我が家も6歳の娘には、毎日1冊音読させていますが、それでは全然足りてないようで。
会話は日本語が強いんですが、読み書きは英語が断然強いです。
英語はスラスラ読めるんですよね。
学校の力がないと、やはり難しいなと感じています。

雪子:
今アメリカに来て何年ですか?
みづき:
2年半です。
雪子:
2年半で!子供って本当すごい適応能力ですね〜。
1日1冊じゃ足りないんですね。
今5歳の娘、焦ってます。
みづき:
子供の適応能力、すごいですよね。
置かれている環境は、かなり大きく影響しますね。
雪子さんのミニ講座にあるように、「その言語「で」学ぶ」というのがかなり大きいと実感しています。

祥子:
うちは家ではほぼ完全に日本語。
時々子供2人が英語で話してたら、「日本語」と一言いうと日本語に戻します。
あ、もちろんルー大柴的な日本語は多いですよ〜。
結局のところ、各家庭のそれぞれのやり方で問題ないよ、というオチ?!
みほ:
それぞれのやり方が見つかってない方が、他の家庭の様子を聞きたくてミニ講座のリクエストをくださったんでしょうね、きっと。

もとえ:
リクエストして下さった方の中には、まだ子供が小さくて、これから何に気をつけたらいいのか分からない方もいらっしゃるかもしれませんね。
私がまさにそれです。
やはりアメリカにいるならバイリンガルになってほしいなと漠然と思うものの、何にどう気をつけるべきなのか?と気になってます。
我が家は夫も日本人なので息子にも日本語で話していますが、英語の絵本もあるのでそれは英語で読んでいて。
それっていいの?と、小さいことが気になったりしています。
なので皆さんのお話がすごく興味深いです!
祥子:
なるほど、そういうことかぁ。
みほ:
私も子供に英語の絵本も読んでます。
上の子なんか絶対私より上手に英語読めるのに、読んでって持ってきます。
でも、絵本に対するコメントや私への質問は日本語なんですよね。
海外在住で日本語の絵本にこだわるとお金持たないし、本当にそれぞれの環境でできることを細く長く続けることも大切ですよね。
日本語でも英語でも、子供を膝に乗せての絵本タイムはそう長くないので、私はかけがえのないその時間を楽しむことにしてます。

祥子:
ウィコラに来てくれる人は特に、妊娠、出産、睡眠、母乳、すべてにおいて、漠然とした不安を始まる前から持ってる人多い気がする。
私がそういう性格でないので、なかなか思い至らないことあるけど、そういう漠然とした不安を解消していけるとよいね。
ビジネスのために不安を煽る、という社会現象もあるから、それも問題なんだよね。
私たちも気をつけないと。
もとえ:
なるほど!だからかもしれません。
前にバイリンガル育児の難しさを強調するネット記事を妊娠中に読んでしまって、それで漠然とした不安があって。
内容はあまり覚えてませんが、私にはそんなこと出来ないと衝撃を受けた覚えがあります。
そういう親に何かを買わせたりしたかったのかもしれないですね…。
雪子:
不安を煽ってる人も不安があることもあるんですよね。
バイリンガルに失敗した人が他の人には同じ間違いをして欲しくなくてそういう言い方になってしまったり。
リスクについて知っているプロほど情報を共有したいと思うこともある…。
同じ情報でも不安を感じる人と感じない人もいますしね。
喋り方には気をつけないといけませんね。

雪子:
今度のミニ講座、継承語が失われるリスクなどは省いたほうがいいですか?
個人的には不安があったら情報集めれば集めるほどやるべきことが見えて好きなんですが、きっと知らぬが仏の人もいますよね。
祥子:
存在するリスクは、言い方だけ気をつけて話せば良いと思います。
雪子:
はい。大切なのは内容もだけど伝え方ですね〜。
= = = = = = = = = = = = =
次回(第135回)「妊娠産後サポートグループ」は1月9日(日)13:00〜Zoom にて開催予定です。
詳細のご確認・お申し込みはウィコラHPから。
※ 記載開催日時はアメリカ太平洋時間
最後までお読みくださりありがとうございました!
スキ、コメント、フォローなどで
応援いただけると嬉しいです!
▽ ▽ ▽
