
【*】"ある"ように"なる" 神話の論理と近代の論理、論理を息づかせるコミュニケーションの問題 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(68_『神話論理3 食卓作法の起源』-19)
(本記事は無料で最後まで立ち読みできます)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第68回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第四部「お手本のような少女たち」を読みます。これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
いま、目の前にボールペンがひとつ”ある”。
窓から空を見上げれば、大きな雲が”ある”。
もうすぐ雨が降るでしょう、という情報が”ある”。
そして、「雨が降ったら、蒸し暑くなるだろうなあ」などという言葉を思いつく私という存在者が”ある”。
ある/ない の区別は
”ある”でもなく”ない”でもないことから
『神話論理』は第三巻に至って、いよいよ佳境に入る。「神話」の「論理」とは一体何がどうなっているのか、ということを手っ取り早く知りたいという関心をお持ちの方であれば、まずはこの三巻を徹底精読なさるとよろしいかと存じます。
起源
神話は、しばしば、ある何らかの事柄の(例えば「夜」でも「月」でも、「人間」でも、「季節の交代」でも、「タバコ」でも)の”起源”を説明したところでその語りが閉じられる。
起源ということは、要するに「あるように、なる」ということである。
もともとなかったことが、”ある”ようになった。
*
例えば次のような”月の隈”の起源神話がある。
「カエルの娘が、義兄である人間の姿をした月の胸に飛びついて離れなくなった。以来、月には隈がみられるようになった」
これを”ある何らかの事柄(いまの場合は隈がある月)”に至るまでの、他の事柄たちが連なる直線的な因果関係の連鎖として読んでしまうと、「風が吹いたので桶屋が儲かりました」式の怪しげな展開に見えてしまう。
カエル?
月が人間の姿をしている??
カエルが月の兄弟と結婚???
自然科学的な実験と観察に基づく物事の成立の説明と比べると、この手の神話は分けのわからないものにみえる。そうであるからして「〇〇安全神話」のように、確かな根拠も理由もないことを、あたかもはっきりと定まっていることかのように主張するような語り口を「神話」と呼んで非難するということもできる。
+ +
神話の論理と科学の論理
ところで、「神話の思考」というのは、科学的な因果の論理とは、大きく異なる論理で動いている。神話の論理の「わからなさ」は、今日の私たちが教育において、マスメディアにおいて、あるいはその残響のような日常の会話において、科学の論理だけでなんとかしてやろうと頑張っていることの裏返しである、といえようか。
科学的な思考では、ある事柄xについて、その原因、元になる物事は、x-1であり、x-1の元はx-2であり、x-2の根拠はx-3であり、といった形で順番に項を遡るように説明がなされる。これをある謎の項を、最初の原因となる項に帰属させるということで「還元主義」と呼ぶ。
Δxは、じつはΔ1で・・・Δ1は・・結局、Δnだったんですよ!
Δx→Δx-1→Δx-2→Δx-3→Δ…→Δ…→Δ…→Δ…→Δn
という具合に「還元」していく。
そしてこの線形配列が一度定まれば、今度はΔnの方からΔxを作り出せるようになる。そうであるから、誰が作っても同じ商品を大量に生産できるという産業革命と自然科学は親和性が高い。
+
神話論理
一方、神話の思考は、xや、x-1や、x-2、x-3といった「項」たちが、「ある」ということを前提に"しない"ところから動き出す。
・・・
自然科学の論理
自然科学が、Δx→Δx-1→Δx-2→Δx-3→Δ…→Δ…→Δ…→Δ…→Δn のリニア配列を結んでいくとき、Δに収まることができるのは、感覚的、経験的、統計的に大多数の人間にとって”そう感じられるもの”である。例えば、飛行機が離陸できるのは、「風の精霊が人間には見えない神秘のロープを機体に結びつけて引っ張り上げてくれているから」ではなくて、「高速で地上を走行しながら翼の下の方に空気を押しつけるようにして、翼の上下で空気の密度に差をつくり・・」といったような説明になる。ここで密度とか圧力とか速度というのは、なにも霊感がなくとも、適切な測定装置を用いることができる人であれば、誰が測定しても同じように「ある」と言える。
+
測定器の規格化量産化
精霊の力は見える人にしか見えないが、密度や圧力や速度であれば、同じ測定器を使えば、誰がいつどこで測定しても(測定条件を統制することも測定器を使えるということの範疇に入る)「同じ」ように観測することができる。
近代以降の世界は、同じ(規格化された)測定器、あるいは同じ(規格化された)道具を大量生産できる、ということの上に成り立っている。
+ +
マスメディア式コミュニケーション
そしてつい数年前まで、いや、いまでも、と言った方が適切だろうが、「言葉」とその意味というものも、この同じ(規格化された)測定器、あるいは同じ(規格化された)道具の一種として、大量生産・大量複製・大量再生産されてきたのである。完成品としてパッケージ化された(意味を定められた)記号や象徴が、一度に大量に生産・複製され、一方通行で同時に同期を取りながら、国民国家規模にまとめられた人々(マス=大衆)の目や耳に注ぎ込まれる。
このようなマスメディア型コミュニケーションによって統一、平定された世界というものが、ここ最近、インターネットの急速な発展によって崩されはじめている。インターネットは少数対多数の一方通行ではなく、一対一にして多対多の双方向での言葉のやりとりを可能にし、そこではある記号や象徴の「意味」などということは、記号それ自体に付着して固まっているものではなく、、人によって、時と場合によって次々と変わっていくし、あっという間に真逆にひっくり返ったかと思えば、またくるりとひっくり返る。そういうことが日常茶飯事、常態である。
この状態は秩序の崩壊でも何でもなく、人類の言葉というのは、声による会話ということが始まって以来の数万年にわたって、そういう「意味が定まりようもないところを、あれこれ言い換えておもしろがる」という姿をしていたのである。
この辺りについて詳しく知りたいという方は、ウォルター・J・オングの『声の文化と文字の文化』、そしてティム・インゴルドの『ラインズ』あたりがおすすめである。オングがコンピュータネットワークによるコミュニケーションの世界を「二次的な声の文化」であると書いているところは特におもしろい。
いまこそ神話論理
さて、いまこのマスメデイア型の”一対多一方通行”により同期され規格化された固まった意味分節体系を理想とする世界に(ちなみに、生きた個々人の人生においてこの規格化がいつも必ず成功するわけではないことはいうまでもない)、近代以前にはるかに遡る意味分節がぐにゃぐにゃと動き続ける「声の文化」的な世界がハイブリッドに重畳するような状況にあって、言葉ということをもう一度、大量生産された観測装置ではない姿に組み直す必要がある。
個々人がつどつど遭遇する、端的に「謎」である他者たち(ここには人間以外の他者も含まれる。動物に、草木国土はもちろん、死者や、幽霊、天体なども含まれる)と繋がったり切れたりするための言葉へ。
その言葉は、あらかじめ完成させてパッケージ化して量産販売できるような言葉ではなく、わたしたちひとりひとりが現に生きたり苦しんだりしているところでたまたま拾い集めている(あるいは無理やり貸し付けられた)ことばたちを流用転用創造的に誤用しながら(これをレヴィ=ストロースの用語ではブリコラージュという)、分節体系として束の間、その姿をはっきりと現したかと思えば、いつの間にかバラバラになって転がっているような、そういいう残響たちの姿になるだろう。
* *
そしてそこでは、驚異的なことに(ごく当たり前のことだが)、「ある」などということ、「ある/ない」といったごく基本的な分節さえもが、対立する二極を際立たせたかと思えば、どちらか不可得に溶けてしまい、いやまたそうかと思えば、少しズレたところでまた二極を際立たせたりするという、そういう動きの痕跡として浮かんでくるようになる。
あるように、なる。
というのはこのことである。
+
起 滅 辺際 不可得
諸項が”あるでもなくないでもない”ところから、「ある」と「ない」の二項対立が分かれてくる。ここで「ある」というのはそれ自体として独立自存している事柄ではなく、「ない」との関係において「ない-ではない」ということに尽きる。

この「ある」ひとつの項Δが、非-Δと分かれつつも対立関係(ペア)にあるものとして結びついたままになるように、対立関係の対立関係の対立関係としての二重の四項関係(八項関係)を安定させるのが神話の論理である。
この「安定させる」ための奥義が、上の図でいえばβと書いたところの項あるいは領域にある。
このβは、対立することになるある二つのΔのあいだに広がっており、二つのΔの一方でもなく他方でもない、どちらのΔとも同じであるが、同時に異なっている。このβもまた単独で孤立自存して「ある」なにかではなくて、他のβとの分かれるような分かれないような関係を通じて、束の間、他ではないなにかとして区切り出されてくる。

四つのβを過度にくっつけたり、過度に分離したりしながら、振れ幅をえがきつつ、その振れ幅の最大値と最小値を繰り返し区切り出していく。そうした極値のあいだに、反復的に現れ続けるΔの収まる位置がひらかれる。
これが神話の論理である、と仮に考えておこう。
もちろん、他にももっとみずみずしい跳ねるような感じの言葉でいうこともできるはずである。
上の言い方は、これは私の、1970年代の最後に生まれ、大量生産された企画品の「正解」と過度に同期することを強いらる剥き出しの暴力による強制心温まる指導をつうけつつも、その同期すべき巨大な「正解」の世界がガラガラと崩れていくのを目の当たりにし(ベルリンの壁崩壊、昭和から平成へ、阪神淡路大震災、オウム事件、バブル崩壊、就職超氷河期。そして、モバイルでリアルタイムなインターネットの登場と「正しさ」なるものの清々しいほどの吹き飛び)、ただひたすら「なんだこれ(いい意味とわるい意味の両方で)」と思い続けて生きてきた「私」のための手作り日曜大工ブリコラージュのカヌーと櫂のようなものである。
レヴィ=ストロース氏は『神話論理3 食卓作法の起源』の中盤で、次のように書いている。
「本当のことを言えば、本巻の冒頭から、われわれはたったひとつの神話しか論じていなかった。つぎつぎに神話を紹介してきたのはすべて、すでに述べたように、出発点となった神話をよりよく確認しようという意図からだった。その神話とは、狩人モンマネキの結婚生活の災難を語るトゥクナ神話M354である。」
たったひとつの神話しか論じていなかった。
ここまで第三巻で分析されてきたあれこれの神話、カヌーに乗った月と太陽の旅の神話も、すべて第三巻の冒頭に掲げられた「狩人モンマネキの結婚生活の災難」の神話と、異なりながらも異なるものではない。
あれこれの神話では、登場人物の姿形は大きく異なるし、そのやることなすことも大きく異なる。表面的に見ると、あれこれの神話はたがいにまったく違う、別々の神話である。しかしいずれも全て、同じひとつのことを実行している。
その同じ一つのこととはすなわち、分離と結合の対立関係を分離しつつ結合し、結合しながらも過度にくっつきすぎないように分離しておく、という操作である。
ここで「結婚」というのが重要である。
結婚は、元々別の家族に属していた二者が「ひとつになる」「一緒になる」ということであるが、これは”分離と結合の対立関係を分離しつつ結合し、結合しながらも過度にくっつきすぎないように分離しておく”ことの経験的事例である。
結婚の神話
というわけで、「狩人モンマネキの結婚生活の災難」の神話をあらためて眺めてみよう。
結婚の神話は、「結婚」の話をしているのであるが、それはたぶん、結婚の話をしたいからそうしているのではなくて、分離と結合の分離と結合をバランスよく調停したところに見事な対立関係の対立関係(四項関係)が安定して、良い感じよね、ということを言いたいらしいのである。

分離と結合のリズミカルな分離と結合を感覚させることができるのであれば、なにも結婚にこだわる必要はなく、カヌーの両端に乗った二人の人物の川下りでもよい。
ということで、M354「狩人モンマネキとその妻たち」である。
この神話では、主人公であるモンマネキという神話的人物が(神話的人物というのはつまり人間であるが通常の私たちが経験的にこれだと思っているような人間ではないということである)、5回(4回+1)の結婚(と離別)を繰り返す。
神話的結婚は五回、反復される
結婚というのは要するに、分離し対立する二極を結合するということであり、結婚からの離別への転換とは、分離から結合に組み替えられたところが再び分離するということである。
五度の結婚と離別を反復することで、
分離 → 結合 → 分離
という具合に、最大の距離から最小の距離へ、そして最小の距離から最大の距離へ、振幅を描くように脈動している。
M354「狩人モンマネキとその妻たち」の要約を再掲しておこう。
第一の結婚:カエルとの結婚
世界が創造されたばかりのころ、モンマネキという名の人間が狩猟だけを生業として暮らしていた。
狩の道の途中、地面に穴が開いているところがあり、そこにはいつも一匹のカエルがいた。このカエルがある日、人間の娘の姿になってモンマネキのもとに現れ、二人は結婚する。
二人は結婚したが、食事は別々だった。カエルである妻は「黒い甲虫」以外のものを食べようとしなかったからである。モンマネキは狩った肉を食べ、妻は黒い甲虫を食べた。
ある日、モンマネキの母親が、息子夫婦の食事に「黒い甲虫」が供せされているのを発見した。息子が黒い甲虫を食べさせられていると思った母親は憤慨し、甲虫を捨て、代わりに甲虫が入っていた容器に唐辛子を入れた。
それを知らずにモンマネキの妻=カエルは容器の中身の唐辛子を、いつもの甲虫だと思って食べてしまった。あまりにの辛さにおどろいたカエル娘は逃げ出し、カエルの姿に戻って水中に飛び込んだ。
水中に戻ったカエル娘は息子を夫のもとに残したままだとネズミに咎められる。カエル娘は一度義母のもとに戻り、息子を奪い返すと、水中に帰っていった。第一の結婚はこれで終わりである。
++
第二の結婚:アラパソ鳥との結婚
カエルの妻を失ったモンマネキは、また狩をしていた。
ある日、林の中で、高い枝にとまる一羽のアラパソ鳥に出会う。
モンマネキは鳥アラパソ鳥に対し「あなたが作った飲み物を、ひょうたんにいれて、わたしにおくれ」と話しかけた。
モンマネキが狩からの帰りに同じ場所を通りかかると、可愛らしい顔の娘がいて、ひょうたんに満たされたヤシ酒をくれた。モンマネキはこの娘と結婚した。アラパソ鳥の娘は可愛らしい顔をしていたが、モンマネキの母親は、彼女の足が不恰好であるとなじった。
気を悪くしたアラパソ鳥の娘は去っていった。
第二の結婚はこれで終わりである。
++
第三の結婚:雌ミミズとの結婚
モンマネキが狩をしていると、地面の穴からミミズが変身した美しい娘が声をかけてきた。二人はすぐに結ばれ、人間の村で一緒に暮らすようになった。ミミズ娘はすぐに男の子を産んだ。
モンマネキはミミズの妻に子供を義母に預けて、畑の草刈りをしておくように頼んだ。妻はミミズの姿に戻って、畑の土の中に潜って、雑草の根を切った。そこへ義母が赤ん坊を連れてやってくる。
赤ん坊が泣き止まないので、母親=ミミズに帰そうとしたのである。
義母は畑一面にまだ草が立っているのを見て、嫁が草刈り仕事をサボっているものと勘違いした(本当は根が切ってあるのに)
義母は嫁を「怠け者だ」と詰り、自ら草刈りをしようと、貝殻でできた鋭利な鎌を使って草の根元を切って回った。その途中、地中にいるミミズ嫁に気づかず、その唇を鎌で切ってしまった。
負傷して家に戻ったミミズ娘は家を出ることにし、息子を自分に渡すように夫に言おうとしたが、口を切られて喋れなくなっていた。仕方なく、息子を夫のもとに残したまま、ミミズの娘は森へ帰っていった。
第三の結婚はこれで終わりである。
++
第四の結婚:コンゴウインコとの結婚
モンマネキは、狩の途中、コンゴウインコの群れに向かって「とうもろこしのビールをおくれ」と声をかけた。帰りがけ、ひとりのコンゴウインコの娘がとうもろこしビールをもってモンマネキを待っていた。二人は結婚した。
ある日、モンマネキの母はコンゴウインコの嫁に、自分が畑に出かけている間に、梁に干してあるとうもろこしの穂を下ろしてビールを作る準備をするよう命じた。
コンゴウインコ娘は、わずか一本だけの穂から、五つの大壺を満たすほどのビールを作った。
義母が帰ってくると、嫁はおらず、穂がたくさん残っている。
五つの大壺に気づかない義母は嫁のことを怠け者だと言った。
コンゴウインコ娘は家から離れた川で水浴びをしていたが、この義母の声を聞いていた。
家に戻ったコンゴウインコ娘は、屋根藁に隠した櫛が見つからないと夫にいい、屋根に登った。そして屋根の上で、「すでに大量のビールが出来上がっている」ことを歌った。義母は嫁に謝ったが、嫁は許さず、コンゴウインコの姿に戻って、梁にとまった。
夜明けになると、コンゴウインコ娘はモンマネキに向かって
「私を愛しているなら、私と一緒にいきましょう。削ったおがくずを水にいれると魚に変身する特別な月桂樹があるから、その幹でカヌーを作って、下流へ下ってください。その先で会いましょう」
というと、飛び去った。
モンマネキは妻を追いかけるべく特別な月桂樹を探しまわった。
さんざん迷った挙句、ようやく、根元が水に浸かっていて、削ったおがくずを水に落とすと魚に変身する月桂樹を見つけると、一日中これを削ってカヌー作りに精を出した。
モンマネキの親族の年下の男が、このカヌー作りの様子をこっそり覗き見た。そのせいで、おがくずは魚に変身しなくなった。モンマネキは魚を無尽蔵に手にいれることはできなくなった。
モンマネキはこの年下の男を呼び寄せると、一緒にカヌー作りを手伝うようにいった。男がカヌーにふれるやいなや、モンマネキはカヌーをひっくり返して、男を水中に落とし、カヌーで蓋をして、一晩閉じ込めて懲らしめた。
翌朝、モンマネキは男を許し、一緒に川下りの旅に出るよう誘った。
カヌーの後部にはモンマネキが、カヌーの前部には親族の年下の男が乗った。ふたりは櫂をこぐまでもなく、水のながれにのって川下へと進んだ。
そしてとうとう、コンゴウインコの娘が隠れ住む里の近くにやってきた。
里の人々がカヌーを迎えに出てきたが、コンゴウインコ娘はまだ姿を表さず、隠れていた。親族の男がモナン鳥に変身して飛び立ち、コンゴウインコ娘の肩に止まった。
その時、突然、カヌーが垂直に立ち、モンマネキは川に放り出された。
モンマネキはアイチャ鳥に変身して飛び立ち、妻のもう片方の肩に止まった。
無人のカヌーは流され、大きな湖にたどり着き、そこで川の魚の主である怪獣に変身した。
++
第五の結婚:同郷の人間の娘との結婚
コンゴウインコの村からもどったモンマネキは、同郷の人間の娘と結婚した。
この妻は魚を獲る時、家から遠く離れた船着場まで行って、そこで胴体の中程で体を半分に割り、腹から足までを岸辺に残して、胸と腕と頭だけで水中に入っていた。そして身体の切断面から漂う肉の匂いに惹かれて集まって来る魚たちをつぎつぎと捕まえて蔓に通していった。
漁が終わると、上半身は這って土手まであがり、下半身と合体した。
下半身にはこの合体のための取っ掛かりとなる「脊髄の端」が突き出していて、これが”ほぞ”の役割を果たした。
モンマネキの母は新しい嫁が漁りの天才であることに驚いていた。
ある朝、義母は嫁に川で水を汲んでくるよう頼んだ。
しかし、嫁がなかなか戻ってこないので、義母は苛立って川に様子を見に行った。すると、土手に下半身だけがある。義母は、残された下半身から突き出している脊椎の端をもぎ取った。
嫁が川から戻ると、もう下半身と合体することができなかった。
仕方なく、嫁は腕の力だけで木によじ登り、そこで待った。
夜になっても妻が戻らないことを心配したモンマネキは松明をともして捜索に向かった。そして妻が上に隠れている木の下まできた。
上半身だけの妻はモンマネキの背中めがけて木から飛び降り、しがみついた。その時以来、上半身だけになった妻はいつもずっとモンマネキにしがみついて、モンマネキが何かを食べようとすれば、すべて口から奪い取って貪るようになった。
モンマネキは痩せ衰えていった。
モンマネキは背中の妻から自由になろうと画策し、「魚取りの堰に行くが、そこには恐ろしいピラニアがいて、おまえの目玉を食べようと狙うだろう」と脅かした。妻は土手で待つといい、モンマネキから離れた。ここぞとばかりモンマネキは川に飛び込み、泳いで逃げ去った。
上半身だけの妻は夫が戻らないので、堰の杭に行って、そこにとまった。
数日後、彼女はオウムに変身しており、飼い慣らされたオウムのようにおしゃべりになっていた。そしてしきりに鳴きながら、川の下流の鳥たちが住む山地へと飛び去った。モンマネキは藪に隠れて、その様子を見ていた。
(おわり)
引用が長すぎだろう、と思われるだろうが、驚いてはいけない。
この神話をもっと細かく精読したものを上記の記事に掲載しているので、ご興味ある方はご参考にどうぞ。
* *
この神話を無理を承知でごく煎じ詰めると、時間軸上に写像するならば、減衰していく振幅を描く脈動を示している。
最初の結婚から最後の結婚へと移行する過程で、徐々に、人間から「遠い」動物から人間に近い動物へ、最後は人間同士の結婚へと、結婚によって結びつけられることになる所与の距離が狭まっていく。

分離と結合の分離と結合を調停するために、過度な分離状態と過度な結合状態を最大値と最小値にとるある振幅を、一定の幅に収めることが課題となる。さらにはこの一定の幅の間を同じ速度で、一定の周期で周期で回転する正弦波の波形を描けるようになるかどうかが、最重要課題になる。
この第三巻の神話は、いや、この神話に限らず、極めて抽象度の高い「神話論理」は、すべてここと目指している、と仮に言っておいてもよいだろう。
分別の起源、
二項対立の一方の項としての
あらゆる存在者の起源
神話というのは、私たち人間が物心ついたときはすでに書き込まれ刷り込まれてしまっている分別について(物心がつくということは、この分別の刷り込みが完了したということである)、「あれっ?この分別、どこから起源したのだろう??」と疑問を持ち、この疑問に言葉でもって答えてみる、という営みである。
神話は、生死の区別の起源を考えたり、人間と動物の区別の起源を考えたり、火を使うことと火を使わないことの区別の起源を考えたり、天地の区別の起源を考えたりする。
生 / 死
人間 / 動物
天 / 地
何と何でも構わない。
Aと、Aではない(非A)
この二つの区別=分別〜分節を、「もともとあるものだから」と言って特に疑問に思わないという生き方ではなくて、「どうして、分離したんだろう」と問い、その分離に至る経緯を考える。
ここに、区別があること・分離されていることに対して、区別がないこと・分離されていないこと、が突如浮かび上がってくる。
区別・分離を所与のことと考えないということが、区別・分離の起源、始まり、ということを考えざるを得なくする。そして区別・分離が「起源する=始まる」ということはつまり、それが始まる前、区別される前、分離される前ということを考えざるを得ない、ということになる。
分離 / 未分離
(分節 / 無分節)
ここで経験的な区別の起源を、区別の手前(区別が”まだない”)ことと対比して考えるという神話的思考は、分離と未分離と分離と未分離、分離と結合の分離と結合、といったことをどうしても思考せざるを得なくなる。
そして神話は、この思考を、抽象的な言葉ではなく、あくまでも経験的で感覚的な区別を概念の道具にして論理(分離と結合のシステム)を組む。
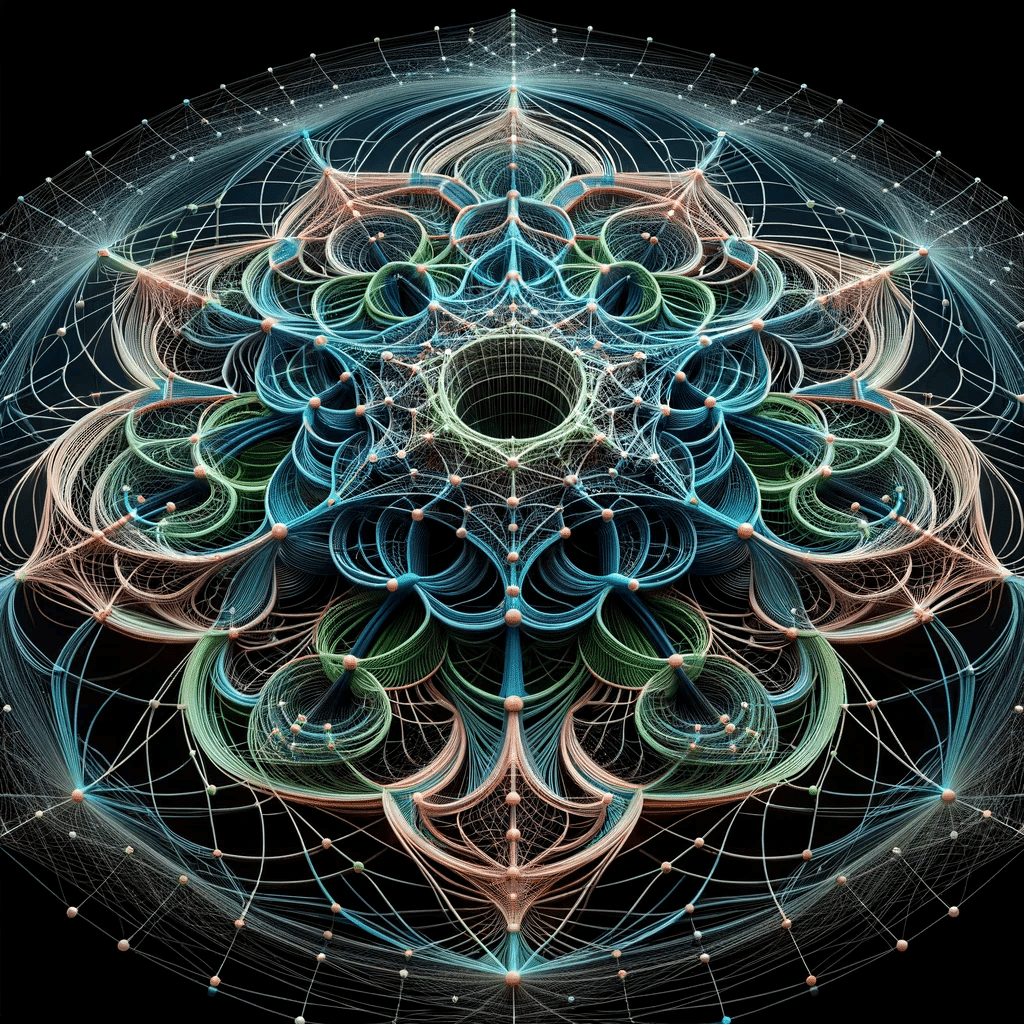
「結婚」は、抽象的な「分離と結合の分離と結合」を経験的に思考するためにうってつけのイベントなのである。
しかもM354「狩人モンマネキとその妻たち」の場合、結婚と離別が5回繰り返されながら、対立二極の間の振幅が徐々に狭まっていく。分離と未分離が分離しているでもなく未分離であるわけでもない、という分離しているのか結合しているのか、どちらか不可得というところから始まって、適度な分離が画定した均衡状態に至る。

この四極が適度な分離が画定した均衡状態をなすように見える
八項関係を分節する
抽象と具体の両極の間も、振幅を描くように思考してみよう。
最長距離の分離が突如ショートして結合したかと思えばすぐに分離し、続けて別の方向で同じような長距離を短絡する結合が生じるもまた分離して、ということを繰り返しているうちに徐々に結合される分離の距離が狭まっていき、最終的に、過度な結合と過度な分離のどちらでもない適度な分離に落ち着く。
意味分節理論の観点からのこの神話の細かく詳しい分析は下記の二つの記事に掲載しているので、ぜひ参考になさってください。
レヴィ=ストロース氏はこのモンマネキの神話から「四つ」の「根本的な性格」が引き出されるという(pp.225-226)。
動物の妻たちと、人間の妻を対立させる。
最初の動物妻は「カエル」であり、最後の妻(人間の妻)も比喩的な意味で「カエル」である。
比喩的なカエルとは「しがみつく」(過度な結合)ということである。
性格が対照的なふたりが乗ったカヌーの旅
そしてこの四つの性格が組み合わさって「周期性という角度から見た太陽と月に関わる」神話群を発生させている。
*
カヌーに乗った月と太陽
対立する二項が、はっきりと別々に分かれつつ、しかし完全にバラバラに分離してしまうことなく、適度な距離を保ったまま「付かず離れず」になっている状態。これが神話の語りが仮に目指す地点である。
太陽と月が、はっきりと区別され対立した二つの事柄でありながら、付かず離れずに規則的に、ペアになって動いていること(太陽と月が一つのカヌーの前後の端に乗って旅するように)は、この神話が目指す調和の姿の一つの理想的な形態の、経験的な形である。この調和し均衡した分離と結合・二項の関係を安定させるために、上の1.〜4.が必要になる。
「動物」と「人間」は、経験的に遠く分離した二項の関係である。
この遠距離の分離が、結婚によって短絡、ショートする。この経験的に遠く分離した二極をショートさせるには、ある種の結合力のようなものが必要であり、この結合力の経験的な姿が「しがみつくカエル」である。
この「しがみつき」は分離を結合へと変換することはできるが、しかし「くっつきすぎ」になる。神話は、分離を結合に転換したいのではなく、分離と結合を分離しつつ結合したい、つまり二項関係の付かず離れずのバランスを目指している。
この付かず離れずのバランスの経験的な姿こそ、カヌーの両端に乗った二人の人物である。二人の人物は一緒になって、一方が漕ぎ、他方が舵を取ることで「カヌーが進む」ということが実現される。この二人がどちらか一方の端によってしまうと、カヌーはひっくり返ってしまう。
カヌーに乗った月と太陽の旅については、上記の記事で詳しく書いているので、参考にどうぞ。
何千キロという距離をへだてて同じ構造が
さて、このような分離と結合の両極の間での、過度な分離から過度な結合への急転換から始まって、安定的に調和した付かず離れずの二項対立関係が形をなすという神話の構造は、南米の神話に限らず、北米の神話にも見られる。
そこに「何千キロという距離をへだてて見つけ出された[…]ひそかな類似」があることに、レヴィ=ストロース氏は注目する(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理3 食卓作法の起源』 p.227)。
レヴィ=ストロース氏は次のようなパターンの北米神話に注目する。
「太陽と月の兄弟ふたりが、人間妻と動物妻それぞれの美点に関して口論をする。その動物というのはまさにカエルである。意見は一致せず、兄弟おのおのは、自分の思い通りの選択をする。夫の家族はカエル妻を嫌う[…]その食べ方のせいである。[…]カエルは浴びせられた非難に怒って、義理の兄弟である月に飛びつき、放してやるまいとする[…]」
北米の太陽と月は、カヌーにのっているのではなく、一緒に暮らしており、そして一方が人間と、他方がカエルと、結婚する。
ところがこのカエルの嫁が太陽と月の兄弟の実家で疎まれ(食べ物の食べ方=食卓作法がなっていないことを非難される)、結婚している状態から分離されそうになる。天地(水)という遠距離に分離した天体と動物の間の結婚という、過度な分離を過度な結合に転じた状態は、ここでバラバラに分離する。
ここで一転!カエルの嫁は夫の兄弟(義理の兄弟)に飛びついて、へばりついて(過度な分離からの過度な結合)離れなくなる。
>>>太陽 / 月>>>>
|| || || ||
カエル/人間 → 人間/カエル
これは例えば、次のような神話になる。
ひとりかふたりの人間の娘が、星を夫にしたいと願う。
天体たちは彼女らを歓迎し、天に連れていき、星の息子と結婚させる。
星たちは、空の庭にある食用作物の根を決して掘らないように人間の娘に命じる。しかし、娘は暇を持て余し、根を抜いてしまう。
すると、天空に穴が空き、そこから地上にある娘の故郷の村が見える。
ホームシックにかかった娘は、根菜の蔓を結び合わせてロープを作り、この穴からおろし、これを伝って地上に帰ろうとした。
しかし、綱は短すぎて、娘は宙吊りになった。
そして娘は手を離してしまい、地上に落下する。
娘は、天体との間に生まれた息子を背負っていた。
娘は地上に落下して死んでしまうが、赤ん坊は助かり、
すぐに成長して旅に出た。
そして。ある老女の畑から食べ物を盗んだところを見つかり、
この老女に捕らえられる。
やがて、天体の息子は怪物退治に出かけることになり、戦ったり交渉したりして怪物を追い払う。この過程で養母である老女が怪物に食われる。
人間と天体、経験的に遠く分離された二者の登場から話が始まる。
この分離が、結婚という形で、一挙に短絡される。
人間と天体の結婚である。
ふたり?ひとり?
この際、人間の娘の方が「ふたり」であると強調される場合がある。
神話では、過度な分離から過度な結合へと急転換するような、最大スケールの振幅を描いて動き回る項は、しばしば”一即二二即一”の姿をしている。
それは経験的で感覚的な「一(他と無関係にそれ自体である)」であるような項のままでは、かっちりと地上界に据え付けられてしまっており、天空に飛び上がったりすることはできないからである。一であるような非一であるような、経験的感覚的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもないような、どちらか不可得な状態に励起されることで、初めて経験的な諸項たちは分離と結合を自在に分離したり結合したりする媒介者の役割を演じることができるようになる。
つまり、ひとりなのか、ふたりなのか、一体どちらなのかよくわからない、というのが良いのである。

月と太陽の兄弟
この二人の人間の娘と結婚する天体とは、太陽と月である場合が多いという。
ここに日本を含む東アジアの神話にもしばしば登場する、”人間の娘が太陽と結婚して息子を産む”というモチーフがつながる。太陽の子を産む女神の話は中沢新一氏が『アースダイバー神社編』で詳しく解かれているので、ぜひご参考に。
ここで神話M425「アラパホ 天体の妻たち(1)」を見てみよう。
地上の人間の娘たちは、各々結婚したい天体を思っていた。
天界では月と太陽が、下界の女性たちについて長所を比較しあっていた。
月は、人間の女性が何よりも美しいといった。それは人間が月を見るときに、とても美しい魅力的な目をするからである。
太陽は、人間の娘はしかめ面で醜いといった。太陽見るとき、人は顔をしかめる。むしろ水に棲むカエルの方が、目がぱっちりして、太陽を見ても顔をしかめない、と。
*
ある朝、四人の娘が森で仕事をしていて、一人の娘が一本のポプラの木に近づいてきた。
月は、天からこの木に降りてきて、枝にとまってヤマアラシに変身した。
娘は裁縫に使えるヤマアラシの針が欲しくなり、木によじ登った。
ヤマアラシ(月)は逃げ回り、娘はなかなかこれを捕えることができない。そうして追いかけっこに夢中になっている間に、木がぐんぐんと伸びていった。地上から呼ぶ残り3人の娘たちの声も聞こえなくなるほど、高いところに登っていった。
木が天まで届くと、月はヤマアラシの姿から人間の美しい若者の姿に変身し、自分は月であると名乗った。この娘はちょうど月と結婚したがっていた娘であった。娘はすぐに結婚に同意し、月は、人間の嫁を親たちに紹介した。天体の親たちも嫁になった人間の娘を歓迎した。
*
同じとき、太陽もまた嫁を連れてきた。
太陽の嫁はカエルであり、家の外を飛び跳ねていた。
月は、自分の妻である人間の娘と、兄弟の妻であるカエルに。それぞれ臓物の料理を与えて、「どちらが耳に快い音を立てて食べるか」勝負させた。
人間は、コリコリという音を立てて臓物料理を食べた。
一方カエルは、音を立てて噛むことができず、誤魔化すために木炭を口に含んで、擦り合わせて音を立てたが、口から炭を含んだ黒い唾液が流れた。
月は、その様子を見苦しいと揶揄った。
先に食べ終わった人間の娘が壺を持って水汲みに出ていったとき、まだ口の中に臓物と炭が残っていたカエルは、水汲み用の壺を抱えてくずくずするしかなかった。
怒ったカエルは、「あんたから離れるものか」と月の胸に飛びついた。
それ以来、月には、壺を手にしたカエルの姿がずっと見られるようになった。
この神話は、私たち人間が感覚的・経験的に知っている”隈があり、満ち欠けしながら周期的に天に現れるあの月”が起源したところで閉じられる。
月が起源するということは、すなわち天体たちが起源するということであり、天体たちといえば経験的には天空に静止しているものではなくて、長い周期や短い周期で規則正しく天を駆け巡るよう動く。
この最終的に起源する「Δ月」は、「β1カエルの娘」と「β3人間やヤマアラシに変身自在な月」とが、違いに怒り憎しみ合うという”過度に分離”した状態のまま、それでいて”過度に結合”することで生まれている。
過度な分離と、過度な結合とが、はっきりと分離しつつひとつに結合しているのが、経験的なこの「月(Δ月)」である。
月に限らず、私たちの経験的で感覚的な日常に溢れるあれこれの項は、じつは、論理的にはすべて、このような過度な結合と過度な分離が分離するでもなく分離しないでもない、という緊張状態から析出されている。
+ +

ここで、βカエル娘とβ月が分離したまま結合する直前に何が起こっていたかをみてみよう。それはすなわち、月の正妻であるβ人間の娘(天に昇っていると言う点で、経験的なΔ人間の娘ではない)が、「壺を持って水汲みに出ていった」ということ、β月のもとから、β月と安定的に結合しているはずの正妻β人間の娘が、束の間「離れた=分離した」隙をみて、βカエルはβ月にへばりついた(罵りながら)。
ここで、
β人間の娘 / βカエルの娘
が、
テキパキと家事をこなす嫁 / モタモタしている嫁
という二項対立関係に重ね合わされて分離し対立している。β人間の娘とβカエル娘は臓物料理を食べる時の音という点でも対立している。
β人間の娘は、コリコリとリズミカルないい音を立てながらよい作法で食べる。
一方、βカエル娘は、噛み音を立てることができず、木炭同士がぶつかる音で誤魔化しつつ、黒い唾液を垂らすという無作法をはたらく。
*
ここでふと思うのは、カエルの「ケロケロ」と鳴く音は、人間がモツ煮込みのある部位を食べる時の「コリコリ」という音と、よく似ているが、異なるもの、として非同非異の関係にありそうだ、ということである。
人間は、臓物煮込みという異物を口の中に入れた時に、コリコリと言う音をたてることができるが、何も噛んでいないとそういう音は立てにくい。
一方カエルは、口に何も含まなくても、ケロケロ、コロコロという良い音を立てることができるが、口に石炭を含んでしまうとそういう素敵な音は出なくなる。
じつに細かいところで、カエルが立てる音と人間が立てる音とが異なりながらもよく似ていて、よく似ているが異なっている、という関係を織りなおしている(β二項の関係)。
+ +
さてこの臓物料理の食べ方比べに至る前の、分離と結合の動きもみてみよう。
神話のはじめ、天/地の両極の前者の方にβ太陽とβ月が、後者の方にβカエルとβ人間の娘とが、遠く分離していた。
β太陽/β月
|
|
|
|
|
βカエル/β人間
ここで気をつけてほしいのは、この語りはじめの段階では月や太陽は、私たちが経験的に感覚しているあのΔ太陽、Δ月ではなく、どうやら人間の姿をして言葉を交わし合うような神話的な登場人物の姿をしている。
ここで月と太陽は、他の神話では「兄弟」として描かれるほど近しい関係にある。
一方、β人間の娘とβカエルの娘は、前者は目を細めて眩しがり、他方は目を開けたまま眩しがらない、という点で真逆に対立する=差異が際立つ。
ここからまず、月が人間の娘にアプローチする。
ここで人間の娘は、人間の娘というだけですでに経験的で感覚的なΔ人間の娘のことだと誤解されやすい項であるため、すかさず「四人でワンセット」であったことが強調される。「四即一」であるということは、すなわちβ四項が一点に凝集したり四方に広がったりする動き方に対応できる、ということであろう。
四人セット、あるいは二人セットで出てくる人間は、神話では、両義的媒介項であって、分離された二極の間を結合したり、結合しすぎた二項を切り離したりする役割をはたすのだろうな、というつもりで読むといい。
* *
ここから月が天/地の両極の間を移動して、地上に降りてくる。
そして「ヤマアラシ」に変身することで、その針を裁縫道具として欲する人間の娘たちを誘き寄せる(分離から結合への転換)。月=ヤマアラシは、人間の娘を自分の方に引き寄せつつ、同時に人間の娘を地上から引き剥がして、上へ上へと誘き出していく。
こうして人間の娘は、元々いたところから分離され、元々いたところとは対極に位置する天界へと移動する。そこで月と娘の結婚=β二項の過度な結合が成就する。
そしてそこから転じて、月と人間の娘は分離して、代わりに月がへばりつく、という急転換へと物語はすすむのである。
そしてそして、ここにきて突如「それ以来、月には、壺を手にしたカエルの姿がずっと見られるようになった」とあるように、二つのβ項の、どちらでもあってどちらでもないところに、「隈のある月」という、経験的感覚的に「ある」ものが、その収まりうる位置・領域として、起源するわけである。
神話の論理はこのようにして「ある」ように「なる」プロセスを、経験的に対立する二極のどちらか不可得であるβ項たちを、過度にくっつけたり、過度に分離したり、縦にながーくのばしたり、横にながーく、伸ばしたりしながら、四方にぐーっと引っ張り出しつつ、その極のあいだに、四つの「辺」を開く。この辺が、経験的な事物たちが「他ではないそれ」として「ある」ように「なる」ことができる場になる。

関連記事
ここから先は
¥ 710
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
