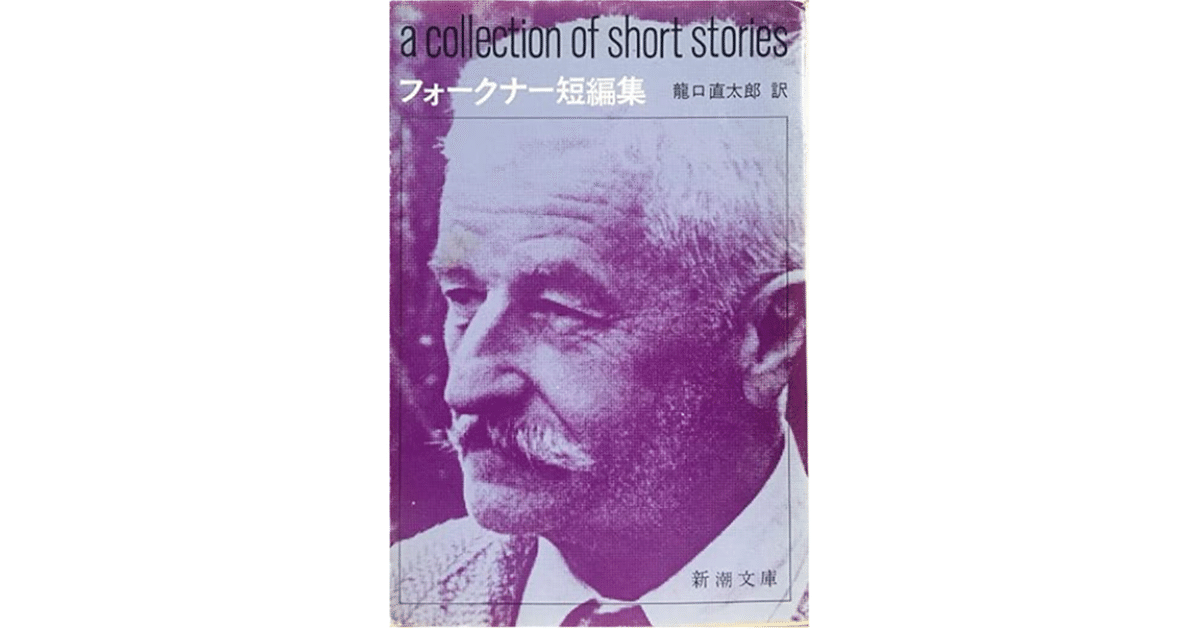
『フォークナー短編集 』(新潮文庫) フォークナー (著), 龍口 直太郎 (翻訳) 40年前に買った文庫を初めて読みながら、バイデンvsトランプのテレビ討論についてまで思いをはせたという話。
フォークナー短編集 (新潮文庫) 文庫 – 1955/12/19
フォークナー (著), 龍口 直太郎 (翻訳)
Amazon内容紹介
アメリカ南部の退廃した生活や暴力的犯罪の現実を、斬新な独特の手法で捉えたノーベル賞受賞作家フォークナーの代表作を収める。
ここから僕の感想
この本を手に取った経緯
フォークナーの長編『アブサロム、アブサロム!』『響きと怒り』を続けて読んで、かつ『アブサロム、アブサロム!』の池澤夏樹氏の親切な解説で、フォークナーの主要作品が彼の生まれ育った故郷の南部ミシシッピ州の町をモデルにした、ヨクナパートファ郡ジェファソンという架空の町を舞台にした、そこに住む多くの家族一族の、南北戦争をまたぐ数十年にわたる、膨大な作品群を書いた作家であると知ることができ、そう分かってみると、次々に読んでみたいという気持ちになった。
https://note.com/waterplanet/n/n4d42887f36da
とはいえ今(2024年6月後半)、サッカーの欧州選手権EURO2024と南米選手権コパアメリカが開催されていて、私はサッカーの国際大会はここ何十年もの間、どんなに仕事が忙しくても全試合を生中継で見るという趣味を続けてきたので、1日多い時は12時間くらいサッカーを観ないといけない。その隙間に細切れで読書するなら短篇集だなということで、本棚にあった、学生時代に買ったらしきこの新潮文庫の短篇集、奥付を見ると昭和57年1月30日38刷とあるので、大学生の時に買って読まずに置いておいたものだろう。いままで読んだ記憶はない。初読である。
池澤夏樹氏に伝授された知識と翻訳者龍口直太郎氏のあとがきから判断して、ヨクナパートファ連作の一部であるのは「エミリーに薔薇を」「あの夕陽」「乾燥の九月」「孫むすめ」「クマツヅラの匂い」「納屋は燃える」の六編のようである。「孫むすめ」に至っては、これは『アブサロム、アブサロム!』の一部としてこの前読んだままである。あの小説主人公サトペンが殺される場面であった。「あの夕陽」は、『響きと怒り』のコンプソン家の兄弟妹が子どもの時の話である。あと4篇の家族・登場人物は、初めましてである。別の主要長編に登場するのであろう。
そして、どうもこのヨクナパートファ連作に属さないようなのが、若い時の習作「嫉妬」と、インディアン(という用語で書かれているのでそのまま使う)と黒人しか出てこない「赤い葉」である。特にびっくりしていろいろ考えさせられてのが「赤い葉」なので、それについて論じながら、フォークナーの小説になぜ私が今、夢中になっているか、はまってしまっているかについて、まずは書いていこうと思う。
「赤い葉」インディアンが黒人奴隷を持っているという話から考えたこと
解説によると「フォークナーの作品に登場するインディアンはすべてチカノー種族であり」「そしてここでは、この種族が伝統ないしは習慣として受け継いでいる殉死をテーマに選んでいる」なのであるが、酋長が死ぬと、その家畜と従者は殺して一緒に埋葬されるのだな。死後の世界で酋長が困らいように。まあ、そういう習俗はエジプトから古代中国からアステカとかで皇帝が死ぬとものすごくたくさんの従者が生きたまんまだったり殺されたりして埋葬されたりしたから、インディアンのある種の種族にそういう習慣があっても別に不思議ではない。そして従者というか、近隣部族との戦争で捕虜にしたのを奴隷として使うという習慣も、全部ではないが一部インディアンは持っていたのは文化人類学の研究で分かっているから、おそらくこのチカノー族というのはそういう、奴隷を持ち、酋長が死んだら奴隷は殉死させるという部族だったんだろう。
ところがだなあ、この小説でびっくりするのはいくつかあって、まずこの部族の酋長、死んだのが二代目、埋葬するのが三代目という話なのだが、その一代目というのが、フランス人のミシシッピ川流域は、はじめフランス植民地だったのと、フランス人はイギリス人やイギリスから独立した東部のアメリカ人に対抗するために、インディアンを迫害せずに、懐柔して取り込んで、対イギリスや対アメリカの戦いに協力させたらしいのだな。で、そういうフランス人の将軍と親友になって、フランスにも連れて行ってもらったり、そのお土産としての靴をもらったり、汽船の古いのを譲り受けてそれを陸の上にあげて家にして住んだり、何より、黒人奴隷を譲り受けて、黒人奴隷を持っていたのである。白人がするようには、うまくは農園を開墾したり荘園を経営したりはできず、あんまり豊かにはなっていないのだが。インディアンの価値観にはあくせく働いて富を増やすみたいなのは無いわけだ。自然の恵みを適度に頂いてあとはのんびり暮らすのが人間の理想のあり方だから、自分たちもあくせく農園を経営したりしたくないし、黒人を働かせるのも気乗りがしないのである。
何はともあれ船を陸に上げたお屋敷に住んで、黒人奴隷を使って、酋長一族は暮らしているのである。その二代目酋長が死んだわけだ。なので、馬と犬と、黒人従者を殺して、酋長の遺体と一緒に埋葬しないといけなくなったわけだな、三代目は。しかしこの三代目、太りすぎでほとんど歩けず、祖父から代々譲り受けた酋長のしるしの靴も足がむくんで入らず、輿というか担架に乗らないと移動できないという退廃ぶりなのである。
そして、黒人従者は殺されたくないから、逃げちゃったのである。
そこで一族の長老と言うかご意見番みたいな二人(がはじめこの小説の語り手である)が、三代目に「とにかく黒人従者をつかまえてこないことには、葬式も埋葬もできないよ、あんたが人間狩りを指揮するんだよ」とご注進にいくわけだ。
その途中の会話でこの二人、恐ろしいことを話していて、
「(中略)人間は汗を流すように造られているわけじゃないからね」
「そのとおりさ。汗ばかり流したおかげで、やつらの肉体がどうなったか見てみるがいい」
「そうだ、真っ黒けになってさ、それに、にがい味もするんだな」
「おめえさん、食べたことがあるのかい?」
「一度はね。そのころ、わしは若くって、いまより食欲が旺盛だったからな。(中略)」
「そうよ、この節じゃ、やつらもたいへんに貴重で、かんたんに食べるわけにはいかんしな」
というわけで、殉死の習慣だけでなく人食いの習慣もちょっと前まで有していたインディアンが、逃げた黒人奴隷を殉死させるため、それまでは元気じゃないと死後の世界で酋長が困るから、生け捕りにしようと人間狩りをする話。黒人の従者の方はミシシッピ川流域の沼地を、泥を塗りたくって沼に隠れたり、木の上に隠れたりしながら逃げるのであるが。そういう、白人フランス人と仲良くなって土地と奴隷を持ったインディアン一族の酋長の葬式のために、殉死用の黒人従者を狩る話なんだわな、これが。
フォークナーの小説をここまでいろいろ読んできて、ユーモアは無い代わりに、荒唐無稽な嘘を書くような、ガルシア・マルケスみたいな作家ではない。フォークナー自身が体験したか家族や知人から聞いた、ありのままの南部の生活や社会のありようを、小説にしていく作家のように思われる。なので、そういう、フランス植民地時代にフランス人と友好関係を築いて、黒人奴隷を持ち、屋敷に住んでという生活をしたインディアンがいたというのは、きっと事実としてあったんではないかと思う。そしてその種族が、もともと近隣部族間での戦争で奴隷を持ち、その奴隷を殉死させ、またなんらかの宗教的祝祭的意味からか人肉食の習慣もあるということも嘘ではなくあったんではないかなあと思う。
現代のポリコレ全盛時代のアメリカ文学では、ネイティブアメリカンと黒人というのは、どちらも白人に迫害された存在で、現代にいたるまで、差別迫害される弱者として、黒人、ネイティブアメリカンの間で混血もいろいろな事情で進んでいる、という描かれ方、登場の仕方をすることが多い。ちょいと前に読んだ小説で言えばジェスミン・ウォードの『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』では、主人公の父親が黒人とネイティブアメリカンの血を引く、どちらかというばネイティブアメリカンが濃い感じで描かれていた。黒人収容所で働かされた過去、というものが描かれる。
下のnoteで、僕は登場人物について、それはどういう混血でどういう肌の色かがこの小説では極めて重要だからということで整理したのだな、ちょっと引用する。
この小説の主人公家族、何人かの話者が入れ替わりながら話は進むのだが、13歳の少年ジョジョから見た関係で人種を説明していく。母方の父祖、リヴァーはほぼネイティブアメリカン。黒人の血も入っているのかもしれないが、肌の色は「赤い」と表現され、自然の様々な物や動物を神として捉える文化的背景もネイティブアメリカンのようである。顔立ちや立つ姿の描写も、誇り高いネイティブアメリカンの末裔、という雰囲気が漂っている。その妻、ジョジョの祖母はアフリカ系。ブードゥー的な巫女的資質を受け継いでいる。この二人の娘、レオニが、ジョジョの母。黒人とネイティブアメリカンの混血ということである。レオニには兄ギヴンがいた。高校のアメフトのスター選手だったのだが、白人に撃ち殺された。その撃ち殺した白人のいとこ、マイケルというのが、レオニの夫、ジョジョの父である。純粋な白人。マイケルの父、ジョジョの父方祖父のビッグ・ジョセフは白人で元・保安官。ひどい人種差別主義者だ。妻、ジョジョの祖母マギーも白人。つまりマイケルは100%白人。白人のマイケルと、黒人とネイティブアメリカンが濃い黒人の混血の母レオニの間に生まれたのが、主人公のジョジョ。彼は自分の肌の色を「中間色」という。肌の色は中間色だが、全体にネイティブアメリカンの祖父の遺伝が強く出ているように描写される。ジョジョには妹、ケイラがいる。父マイケルと母レオニの子供、それはジョジョと一緒なのだが、目の色は緑、髪の色はブロンド、白人の父の遺伝が濃く出ている。しかし肌は茶色い。
タナハシ・コーツの『ウォーター・ダンサー』の中にも、主人公黒人男性(白人農園主の、父と黒人奴隷の母を持つ)が、様々な迫害を受けている人たちが集まって集会を開いているイベントのようなところに行って、そこでネイティブアメリカンの人たちもいるなあ、というようなことを体験するシーンがある。(現代作家のポリコレ意識表出シーン、黒人差別だけではなく、ネイティブアメリカンのことも、女性差別のことも、ちゃんと意識していますよということが表現される。作品内時代は南北戦争前だが、作者は2020年代のいかにも現代人が書いた小説らしいシーンだなと思いながら、僕は読んだのである。)
そういう現代の文学での「迫害されてきたものとして連帯するネイティブアメリカンとアフリカ系アメリカ人」(インディアンと黒人)、というのが当たり前だと思っていたのに、このフォークナーの小説、そういう「ポリコレ以前」の(これは善悪価値判断ではなく)、だってそうであったんだから、というアメリカ南部の、社会の在り方をあったまんま、まるまんま描いてしまう小説として、なんと、インディアンがフランス人と親友になってお屋敷と奴隷を持って、黒人奴隷を殉死させるために人間狩りしちゃう小説、というのを、書くわけである。
これがどこまでそういう事実があったのかは、これは専門家の研究、意見をまたねば、私には正確なところは判断できないのだけれどね、もちろん。しかし、つまり20世紀前半を生きた(1897~1962)フォークナーの、南部に生まれ南部に生きた白人の意識・価値観を通して認識している南部の歴史とありようというのは、こういうことだったんだろうなと知ることができる。フォークナーの小説を、今、私がものすごく熱心に読んでいるのはなぜかというと、アメリカという国の持つわからなさについて、実はこの、南北戦争をまたぐ時期の、アメリカ南部の人たちの価値観とか、南北戦争によっておきた心の傷とか、そういうことを理解しないと、実はよくわからないんじゃないかなあ、と思い始めたからなのだな。
という中で、ちょうどこの本を読み終わろうとしていたそのときに、6月28日、アメリカで、バイデンとトランプのテレビ討論会第一回というのがあった、バイデンが老化によるボロボロの醜態をさらして、CNN調査でもこの討論会トランプの勝ちが67%、民主党びいきのCNNでさえ、バイデン最低だったとお通夜みたいにキャスターたちが落ち込むという事件が起きたのだな。でね。これを読みながら考えたことをFacebookに投稿したので、引用するね。
やっぱりバイデンだめだと今日の討論会で民主党も判断せざるを得なくなったぽい。民主党びいきCNNもお通夜状態である。もう2年前くらいから認知症がかなり進んでいたのをなんとか誤魔化してきたが、今日の討論会でいくらなんでも無理と白日のもとに晒された。
バイデンに代わる大統領候補としてカリフォルニア州知事の名前があがったりしている。間に合うかな。
世界は(もちろん日本も)トランプが大統領になったときに備えていろいろ準備しておかないと。
今ね、というかここ最近、フォークナーの小説を続けて読んでいるのだけれど。南北戦争前後の南部ミシシッピ州の架空の街ジェファソンの複数の家族一族の数十年にわたる膨大な連作群、というのを。
南北戦争で負けた南部の人たちの鬱屈って、というかまず戦争の生活全体を巻き込んで破壊したその傷の深さというのが、日本の太平洋戦争というか大東亜戦争というか、先の大戦で負けて心まで砕かれてアメリカに占領されてというのに匹敵する深い傷を南部の人は負ったというのが、まず分かる。アメリカって実は全然ひとつの国ではなくて、戦勝国北部が敗戦国南部に屈辱を与えて国体(価値観や生活基盤まで)を根こそぎ否定して併合した、そういう国なんだということが分かる、フォークナーを読むと。
さらにいうと、北部南部の対立という以前に、アメリカって17世紀くらいに、カナダから五大湖地域からミシシッピ川流域からメキシコ湾岸まで、フランス領ルイジアナという形でフランスが広大な地域を植民地にしていて、その後段階的にイギリスやスペインに割譲していったのだけれど、そのフランス植民地時代の領域っていうのが、なんとなく今のトランプの支持基盤と重なっているように思われるんだよな。
イギリス植民地から独立した北東部(ミシシッピより東)13州と、フランス植民地だったフランス領ルイジアナとでは、本当になにもかもが違う国だったのが、紆余曲折あってアメリカ合衆国になったいるけれど、実は全然別の価値観の国を内包しているようだな。
バイデンとトランプの対決を、フォークナーの小説を読みながら見ていると、そんなことを(合っているのかどうかは自信がない、ただの私の感想に過ぎないが)考えてしまうのである。
フォークナーの小説に色濃く表れる南部人、白人の、南北戦争後の鬱屈、怨み、復讐心、そういうものというのが、深くそのまま現代に持ち越されて、そういうものを上手に刺激したのがトランプなんじゃあないかしらと思うのだな。それは上の投稿でも書いたけれど「南部」というそのさらに下に、五大湖沿岸からメキシコ湾に至るミシシッピ川流域の、旧フランス領ルイジアナみたいな「ニューヨークやボストンとカリフォルニアの東部西部のインテリリベラル」とは異なる起源のアメリカというのが横たわっているんじゃないかと思ったわけ。そこでは、実はリベラル価値観、現代のポリコレ価値観の中では同じ「弱者・被害者」として連帯しあっている黒人とインディアンでさえ、(あえてこの言葉を使っているよ、だってフォークナーの小説ではそうなんだから。)、お互いに支配被支配、暴力をふるいふるわれ、喰い喰われという関係も(あくまでも、「も」だからね。連帯していた場合も多かっただろうけれど、それだけではなかっただろうということ)、そういう古い何層にも積み重なり、現代文学では語られなくなってしまったような物語が語られているのだな。
「クマツヅラの匂い」にみる「仇討ち」と「男らしさ」
蛇足なんだけれど、リベラル、ポリコレ的にはNGワードで、トランプが体現している価値のひとつに「男らしさ(女らしさ)」というものがあるように思われるのだよな。でね。
「クマツヅラの匂い」という小説、サートリス家という、ヨクナパートファ連作の始まりになったらしき家の、いかにも暴力的権威的父親が(決闘で)死に、その大学生の息子がミシシッピ大学の下宿から実家に呼び戻される話なんだけれど。この父親というのが、街に鉄道を引く事業を起こして財を成すのだけれど、その過程でずいぶん人殺しもした。北部からきた山師たちを何人も殺したりもした。そして、事業のパートナーと仲たがいをして対立するようになり、父親は州の議員になっていた。そのかつてのパートナーのトラブルになって決闘になり、殺されちゃったわけだ。
で、ここからが解説を読んでまあ事情がよく分かったのだが「南部における従来のモラルでいえば、父親か殺されたなら、息子が親の仇を討つのが正義だとされていた。」のだな。でも主人公の大学生は、もう南北戦争後の新しい時代の子なので、仇討ちはしたくない。のだけれど、下宿させてあげている大学教授もその夫人も、実家に返ってきて出迎える義母も父親の仕事上の子分仲間たちも、みんな主人公が仇討ちするものだと、銃をくれたり、「明日がんばれ」みたいな感じで、ああ、南部ってそういう価値観、土地柄なのね、江戸自体の武士の時代小説みたいだなあ、と思って読んでいたわけだ。なんというか、そういう暴力的で古風な男らしさ女らしさみたいなことががっつりあって、今も、ちょっと何枚か皮をめくれば、そういう価値観が顔を出す。そういうところが、少なくともアメリカ南部にはあるんだろうなあ。もちろんこの主人公がそういうことに抵抗したように、おばさんが、「そんなことはしないで隠れても逃げてもいい」と言ってくれたように、その方向に南部人だって価値観は現代に向けて変化進化はしているのだろうけれど。でも根っこにあるそういう、人類普遍の古くさい価値観というものが、南北戦争敗戦の屈辱、奴隷制は廃止されたけれど、そのまま黒人を使用人として生活を自分たちも黒人もなりたたせていかなければいけなくなった鬱屈、そういうものが相まって、アメリカ南部というか、ミシシッピ川流域には残っているんだろうなあ。
そんなことを、この小説を読みながら、バイデンとトランプの討論会後のごたごたニュースを眺めていたのでありました。
