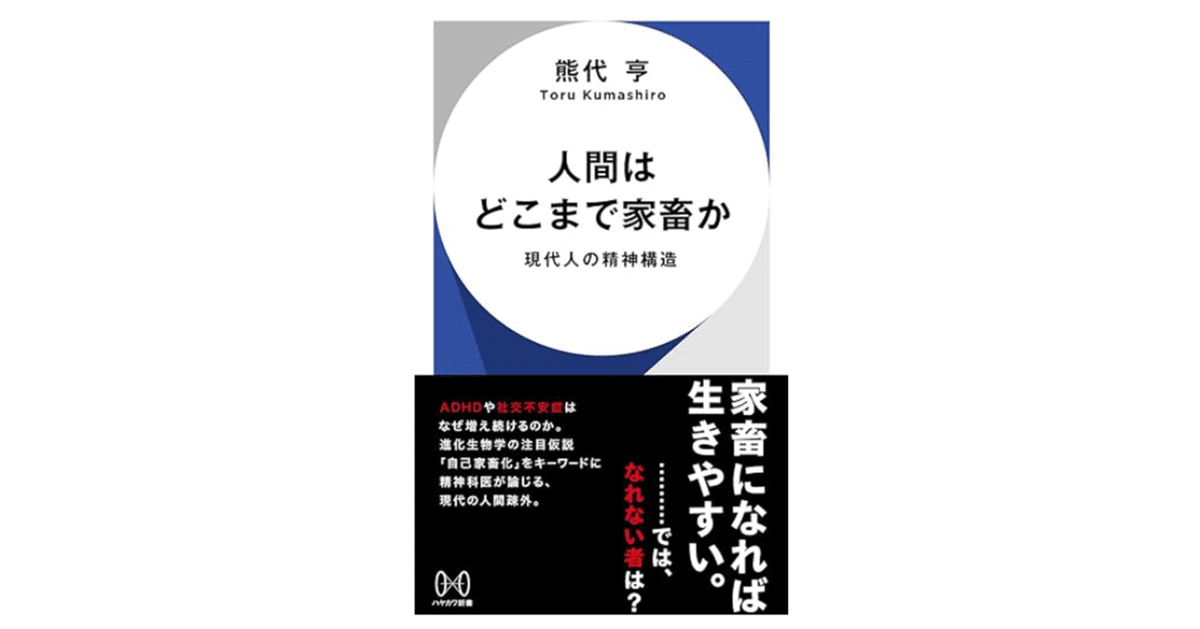
『人間はどこまで家畜か: 現代人の精神構造』熊代 亨 (著) いや、薄いんだけど新書なんだけど『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』合わせたくらいの全人類ビッグヒストリー+未来予測提言の書です。
『人間はどこまで家畜か: 現代人の精神構造』 (ハヤカワ新書) 新書 – 2024/2/21 熊代 亨 (著)
普段ならここでAmazon内容紹介なのだが。この本、タイトルも副題も帯のコピーも、Amazon内容紹介も、どれも本の内容の凄さを全然、表していない。まあ、キャッチーで売れるにはこうだ、と編集者の人が決めたのかな。だから引用しません。なんか、現代の、自分探しの、生きにくさを感じている人向けの、いまどき人間論みたいな薄っぺらい話な感じがしてしまうのだよな。タイトル・帯・Amazon内容紹介が。
全然そんな本じゃない。これ、「序章」で著者も書いているから引用しよう。
本書は「自己家畜化」というキーワードから出発して、これまでの文明を振り返り、これからの文明を見据えるものです。と同時に、進化生物学、精神医学、人文社会学の視点から人間と社会について再考するきっかけを提供するものであります。お読みになった上で、私たちの未来について考えていただけたらと筆者として願っています。
そう、この本、薄い新書ではあるのだけれど、扱っている射程とテーマは、例えばユバル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』(これまでの人類史)と『ホモ・デウス』(未来の人類の行く先)全部を合わせたくらいのスケールの本なんだわね。
本の売り方として編集者は「身近な社会的話題と自分探しみたいなことに悩んでいる人向けの本、みたいなアプローチが売れる」と考えたのだと思うし、売るためには正しいのかもしれないが、著者の志は「人類全体史を生物学と社会人文科学の両面から俯瞰して人類の未来を考える」というビッグヒストリーものの気合で書いたと思うのだよな。そしてその気合、成功していると思う。
目次をそのまま引用しながら、本書について僕なりにまとめながら感想を書いていくことにします。
序章 動物としての人間
第一章 自己家畜化とは何か
進化生物学の最前線
第二章 私たちはいつまで野蛮で、いつから文明的なのか
自己家畜化の歴史
第三章 内面化される家畜精神
人生はコスパか?
第四章 「家畜」になれない者たち
第五章 これからの生、これからの家畜人
あとがき 人間の未来を思う、未来を取り戻す
それから、著者経歴を引用しようかな。
■著者略歴:熊代 亨(くましろ・とおる)
1975年生まれ、精神科医。信州大学医学部卒業。ブログ『シロクマの屑籠』にて現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信し続けている。
でね、精神科医という仕事は、生物学的・動物としての人間(内分泌物質とかの影響下にある生き物)、そこで生じる問題、不都合を解決するという側面と、今の社会の在り方、働き方とか家族とか学校とか、そういうことに適応できずに生じる不具合に向き合う、という両方のアプローチで具体的な患者さんを診ているわけで、そういう両面から人間を、人類を見つめようという本なのだな。
だから、「第一章 自己家畜化とは何か 進化生物学の最前線」はまず、生物学的な視点から、動物における家畜化、自己家畜化が起きるとどういう変化をするか、それは内分泌系のどういう変化なのかを解説するのだ。野生のギンギツネのうち、人間に対して攻撃的でないものを選別してそういう個体だけを掛け合わせて交配を続けると、当然そういう性格のものだけになっていくのだけれど、性格行動がそうなるだけじゃなく、身体の特徴も、顔が平らで横に長くて縦に短くて、耳が垂れてたりしっぽが巻尾になっていたり、ぶちや斑点が出たり、全体に小さくなったり、牙も小さくなったり、ぬいぐるみっぽくかわいくなってしまうんだそうだ。
これは、ストレスに対して攻撃性を高めるコルチゾンとかのノルアドレナリンなどのホルモン反応が低下し、その代わりに家族仲良くおとなしくなるセロトニンが増えるという変化が、身体の特徴形成にも効いてしまうということなんだそうだ。で、こうした「家畜化」を、この実験では人為的に作り出したわけだけれど、猫や犬なんかは、ヤマネコや狼なんかのうち、人間の近くで暮らしているのが、自らそういう方向に進化して家畜していったということがあるらしく、そういう自分から家畜化方向に進化しちゃうことを「自己家畜化」というのだな。
で、人類も、類人猿から原人からホモサピエンスへという進化の中で、HPA系の攻撃性が低下し、セロトニン系が優位になっていくという「自己家畜化」をしてきた、ということなんだ。
この章の最後で、それでも人間はどうして戦争はするし殺人もなくならないの、という疑問が呈されるのだけれど、HPA系は「カッとして殺す」みたいな「反応的攻撃性」を増やすが、冷静に計画して復讐するみたいな「能動的攻撃性」はHPA系が減ってもセロトニンが増えても、減らすことはできない、ということなんだそうだ。
と、生物学的知見から語る一章だったわけ。じゃあ、「第二章 私たちはいつまで野蛮で、いつから文明的なのか 自己家畜化の歴史」はというと、アナール学派という歴史学、スティーブ・ピンカーの『暴力の人類史』なんかの社会科学のアプローチで、暴力や攻撃性がどのように社会の中で、人の行動の文化、どの様な感情や感性、それにもとづく行動がその時代社会で主流、普通のこととして受け入れられ、どの様な行動は社会的に認められなかったかというようなことを考えていくのね。身近なトピックが例に出されていてちょっと引用します。
昭和生まれの方なら、数十年前を思い出せばピントくるでしょう。20世紀後半の日本社会とその文化は現在よりも暴力や迷惑に鈍感で、テレビに映る芸能人たちもどついたりどつかれたりと「身体を張った演技」をしていました。体罰やDVに対する意識も低く、取っ組み合いの喧嘩も今よりずっと多かったと記憶しています。未成年者の飲酒や喫煙も当時は珍しくないものでした。たかだか数十年でもこんなに違うのですから、数百年前の日本社会や文化は今とはまったく別物、と想定すべきでしょう。国や地域によっても文化は異なります。2023には埼玉県川口市でクルド人が100人以上の徒党を組んで病院に押し掛けるトラブルが発生しました。現在の日本社会では非常識な行為ですが、人類史全体でみれば彼らの解決法のほうがメジャーです。先進国同士でも違いはあります。たとえば現在の欧米ではデモやストライキが頻繁に行われますが、日本ではそうでもありません。
アナール学派は欧州の中世から現代までの変化を主な研究対象領域にしていますが、15~16世紀くらいまでの騎士の文化では、HPA系優位の行動が、むしろ賞賛される文化だったと分析します。それらは近代まで残っていたといいます。
掠奪、戦闘、人間狩り、狩猟、それらすべてが中世社会では、社会構造に応じて公然と認められた生活必需物の一部を占めていた。したがってそれらは権力者や強者にとって人生の喜びに欠かせぬ要素であった。(ノルベルト・エリアス「文明化の過程 ヨーロッパ上流階級の風俗の変遷 上」法政大学出版局 1977 374頁)
軽蔑されたら猛然とやり返す文化、名誉のために決闘する文化は、アンガーマネジメントが勧められる今日の文化と比較して、中世の騎士たちの文化に近いと言えます。そこではカっとなる能力、HPA系を介して反応的攻撃性を発揮する能力はまだまだ必要です。『男らしさの歴史』によれば、そうした決闘に終止符が打たれたのはイギリスで19世紀半ば、フランスやイタリアでは第一次世界大戦の頃だったそうです。
そういうHPA系の生物学的特質が幅を利かす中世までの状態から、近代の社会契約説に基づく近代国家の成立(つまりは人間の暴力性を国家にゆだねて個人から取り上げる方向の社会進化)、そして現代社会に至る道筋というのを、歴史学視点でまとめたのが二章だったわけだ。生物学的な家畜化に、文化や社会制度的な人間の家畜化が加わって、そちらの文化的自己家畜化の方が加速していくという状況を解説するのがこの二章。
次の「第三章 内面化される家畜精神 人生はコスパか?」は、現代の社会の在り方を「生物学的自己家畜化を、文化的自己家畜化が上書きしている状況」、HPA系が優勢になって衝動的にふるまうということを、徹底的に抑圧する、その抑圧を内面化していかねばならない状況について、いくつかの切り口で検証していく。
「健康が義務化され」「子どもの誕生と死が個人から専門家に任せ」、そのことを、ルソーなどの社会契約論からミッシェル・フーコーの生権力・生政治の流れで、社会システム(暴力のコントロールと生命健康の管理)、ベンサムの功利主義、そして徹底した個人主義など、こうしたものを「文化的遺伝子」として内面化し、生物的自己家畜化よりもさらに急激に文化的自己家畜化が進んでいることをデータと例証を併用して論じていく。二章が「歴史」であるならば、三章は現在についての社会科学的考察の章である。
で、「第四章 「家畜」になれない者たち」
これは精神科医としての立場からの章。生物学的家畜化を追い越して文化的家畜化が急速に進むと、それに適応できない人、子どもも大人も、が急激に増えている。かつては正常の範囲だった人が、不適応者として病名が付き、精神科の治療対象になる。
大人でもうつ病、双極性障害、各種不安症、ストレス性障害が増加し、HPA系を抑制し、セロトニンを人工的に増やすSSRI薬の投薬が激増している。著者は書く。
治療に携わりながらアナール学派の書籍を読んでいると、「あの入退院を繰り返している患者さんは、中世の戦場では英雄だったのではないか」と連想したくなります。数百年前なら良い仕事に就き、尊敬され、結婚し、子を遺していただろう人が、現代においては精神疾患に該当し、なかなか良い仕事も見つからず、生きていくことに疲弊していることがしばしばあるように思わるのです。
子供で言えば「ジャイアン・のび太い症候群」、昭和の時代にはどの小学校にもいた、ジャイアンのようにHPA系優位で自己中心的に粗暴にふるまう子、のび太のように注意力が継続せずなにをしてもうまくいかないぼんやりした子、どちらもまあ普通にいた。のが今やそういう子はADHDやASDと診断されて、治療の対象になっている。
こうした、過剰に文化的自己家畜化を、人生の早い時期から厳しく求められる社会の在り方が本当に良いことなのか、ということについて、後戻りはできないが、ここは精神科医として働く中での、例えば社会の安全を優先して家族が患者を入院させられる「医療保護入院制度」(海外からは批判も多い)が、自己家畜化への社会的要請が極めて強い日本では必要とされ、批判にもかかわらず今も運用されていることについて、その葛藤を吐露する形でこの章は終わる。精神科医としての具体的問題について語る章である。
さて、この本でいちばんびっくりしたのが「第五章 これからの生、これからの家畜人」
この章の未来予測シナリオふたつを読むだけでも、この本を買う価値がある。絶対。
ひとつめ未来Aは、2060年、今から36年後。今生きている50歳以下の人はそこを生きて迎える可能性は高い。今の価値観とここからの科学の進歩が合わさった先の、まあそうなるしかないなあという悲惨だが現実的な日本の姿が描かれる。ここは書いちゃうと営業妨害になるので、書かないけれど、悲しくなるけれどすごく納得。
さらにすごい、こっちは、こういうことを考えるのが割と大好きな僕でも相当驚いた西暦2160、136年後の未来。生殖技術の進化と、価値観変化「文化的自己家畜化」の100年以上の大変化で、もうこれは悶絶するような未来が描かれる。前に、それよりはるか先の未来を描いたフランスの大ベストセラー作家(フランスの村上春樹と村上龍を合わせたような存在)ミシェル・ウェルベックの『ある島の可能性』を読んだときもびっくりしたが、それより過激な未来予測である。もうほとんど人間じゃあないじゃん。しかし、肉体性は失っていない。なんかもう、これも、お金払って読んでね。すごいから。
そうして、こうした未来に進む過程で、生物学と医学がやっていいことまずいことのテーマとして、「エンハンスメント」=疾病障害の治療ではなく、能力を伸ばす方に薬や技術を使うことの是非と、もうひとつは生命次世代の再生産、生殖と子育てについての変化について、こまかく論じていきます。
これは「少子化」問題と直結する話で、たまたま僕が読み終わった日に、2023年の合計特殊出生率が1.20というニュースが出たので、本当にここまでの深さで考えないと、少子化は論じられないよなあとこころから思った次第。
これ、僕のnote他のものを読んでくれている人はご存じの通り、僕ら夫婦は子どもを六人持った、かなり今どきの価値観から外れた夫婦であり、少子化についてはずっと怒りながらいろんなことを考えたり書いたりしてきたので、ここの部分はものすごく納得しながら読んだのでした。いくつか引用します。
最終的には、配偶や子育ては個人のものから社会のものになるしかないのではないでしょうか。
そもそも、世代再生産を個人のインセンティブに頼っているから少子化が進むのです。資本主義が浸透し、誰もが家族や子育てにまつわるリスクを合理的に考えるようになれば、ホモ・エコノミクスとしての私たちが子育てを躊躇し、配偶すらリスクとして回避するのは当然でしょう。なぜならそれらは投資事業としてはあまりに長期的にベネフィットが不確かだからです。今後、私たちが真・家畜人として思想に一層忠実になっていくとしたら、配偶や子育てが納税のように義務化されない限り、それらをわざわざ選ぶのは異端者とみなされるように思います。事実、すでに私たちは衝動的に性行為をし妊娠し出産する人を異端者のように眺めていませんか。
あのね、僕や妻のことを、そういうふうに異端者のように眺める、その視線に人生ずっとさらされて生きてきたのだよね。で、そういうとき、僕ら夫婦は(もちろんこの本を読む何十年も前から)、人間は人間である以前に動物であり、僕ら夫婦はまず動物として最も自然な性行為をすれば妊娠し、妊娠したら出産するというそのことに素直に、そのことを最優先して生きて来て、そのことを幸せだとおもっているよね、と。人間はまず動物だよねと、何十年も二人で確認しあってきたのだな。そして、この著者も、この章の終わりで、同じようなことを言っています。
大事なことなので繰り返しますが、進歩そのものは否定すべきではありません。地球温暖化や人口問題やパンデミックへの対処は進歩なしには成し遂げられませんし、私たち自身も変わっていかなければなりません。しかしこれまで、その進歩のスピードと内容は、動物としての人間を勘案し、動物としての人間に配慮して来たでしょうか。
過去、思想のイノベーターたちは、当時最新の自然科学の知識を借用しながら世界や未来を展望してきました。今日でもそうあるべきです。倫理学や哲学や政治学、歴史学や社会学といった人文社会科学の未来を担う人々には、生物学にも関心を持っていただき、たとえば自己家畜化というトピックや動物としての人間の性質についてのアップトゥデイトな知識に触れ、それらを視野に入れつつ、動物としての人間にやさしい未来の社会について議論していただきたいと願います。と同時に、自然科学を研究する人々にも人文社会科学に関心を持っていただけだらと思います。
「動物としての人間にやさしい未来社会を」とは言っても、昔に返れとか、現状に踏みとどまれと言いたいわけではありません。たとえば今日の社会は男性、それもブルジョワ男性のようなキャリアを暗黙の前提にできていて、およそ、出産する女性を前提にできているとはいえません。動物としての人間にやさしい社会、ひいては本当に女性にやさしい社会とは、女性の会社役員の輩出率のような、、いわゆる男性ブルジョワのようなキャリアを生きる女性の数を誇るばかりのそれとは思えません。もちろん男性ブルジョワのように生きながら身を粉にして出産や子育てを両立させている、ごく一握りのスーパーウーマンをロールモデルにするような論説にも、動物としての人間にまったくやさしくありません。
本当の意味で女性にやさしい社会とは、男性ブルジョワのように生きたい女性がそのように生きられるばかりでなく、女性の生物学的特徴を踏まえた就学・就職・配偶・挙児・社会参加ができるものであるべきで、女性の生物学的特徴を踏まえたキャリアもしかるべき尊敬と社会的地位が伴う社会であるべきでしょう。この点において、現代社会は動物としての女性の生物学的特徴を顧慮した進歩をほとんどみせていません。というより男性ブルジョワの模倣こそが正しいと思い込むあまり、そうした顧慮を忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか。
過剰に「文化的」自己家畜化を進めすぎるな。いまのままの生物学的動物である人間を、そのまま尊重できるような、社会システムの未来をみんなで考えよう。と著者は主張している。引用しておしまい。当然、僕は大賛成である。
進歩を否定せず、しかして動物としての人間を取り戻すこと。加速する文化や環境と生物学的な人間とを折り合いつけられる、そんな未来を創造すること___それが本書をしめくくるにあたっての、私のメッセージになります。
※ 僕が、大河ドラマ「光る君へ」について「平安時代のセックス&バイオレンス」性と愛と生殖がストレートにつながった状態という反時代的テーマを脚本家・大石静氏が追求することを、毎回、肯定的に論評するnoteを書いているのも、文学というのは性と暴力と愛についての各時代、各社会の中のありようを描くことが常に中心にあるという視点で小説感想文を書いていることも、こういう「動物としての人間」回復を最重要な人生のテーマとして生きてきたことと、当然、直結しているのである。というわけで、とても読んで興奮したので、すごく長い感想文になりました。
※あと、合計特殊出生率1.20が発表された日に読み終えたのも奇遇、少子化問題について、これまで読んだ本でいちぱん納得のいく深い洞察が書かれている。具体的対策施策ではなく、少子化が起きている最も深いレベルでの原因、理由について。
