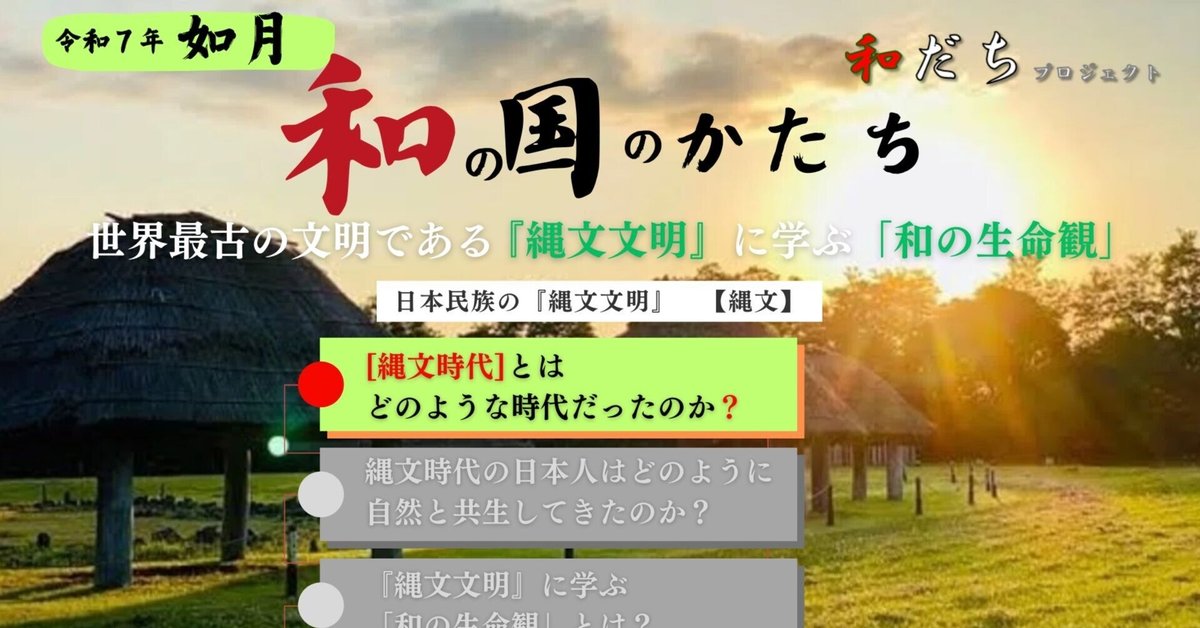
世界最古の文明である『縄文文明』に学ぶ「和の生命観」~「縄文時代」とはどのような時代だったのか?~ー『和の国のかたち』7ー
こんにちは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
小学校の教員としても働かせていただいております。
今週は、
「建国記念の日」があり、
我が国も今年で建国2685年目を迎えました。
毎年、橿原神宮にお金を奉納しているのですが、
先日、境内特別整備事業への感謝状を拝受いたしました。
大変、身が引き締まる思いが致しました。
今後もより一層
歴史教育を通じて日本の子供が自信と誇りを持つことができるように
精進してまいりたいと思います。
また、
我が国の歴史から
先人たちが大切にしてきて、
昔も現代においても普遍的な「和」という考え方の様相を
明らかにしていきたいと思います。
今回は、
「縄文時代」とはどのような時代であったのか?を
一緒に学んでいきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

1)「縄文時代」の概観

我が国では、
「土器」がつくられるようになった時期を
「縄文時代」の始まりと捉えています。
土器の出現された約16000年前から、
水田稲作が開始される紀元前10世紀ごろまでを「縄文時代」と呼びます。
前回の記事でもお話させていただいたように、
平成10(1998)年、青森県の「大平山元I遺跡」という
縄文時代草創期の遺跡で、世界最古級の土器が出土されました。
時代は、
今から約16300年前。
その後も、
長崎県の「福井洞窟」の土器は、約16000年前。
東京都の「御殿山遺跡」の土器は、約16300年前。
神奈川県の「宮ケ瀬北原」の土器は、15500年前。
などなど。
日本全国で世界最古級の土器が広く発見されているのです。

日本では、
世界的に見てもかなり早い段階で素焼きの土器に縄の模様をあしらった
「縄文土器」がつくられるようになりました。
青森県の「大平山元I遺跡」で出土された土器には、
縄の模様はありませんが、
この土器の出土によって、
「縄文時代」の始まりが相当遡ることになりました。
ヨーロッパなどでは、
だいたい10000年前くらいの時期を
旧石器時代(人類が自然石をそのままの状態で使っていた時代)。
10000~3000年くらい前の時代を
新石器時代(人類が自然石を加工して用いた時代)などと呼びます。
その当時、
日本列島ではすでに「土器」を使用していたことになります。
我が国の「縄文時代」という時代は、
ヨーロッパや支那における旧石器時代後半から新石器時代にかけて栄えたまったく日本独自の文化の時代なのです。
ひとくちに「縄文時代」と言っても、
年代的にはものすごく長い期間です。
【草創期】
今から16300~9000年くらい前。
【早期】
今から9000~6000年くらい前。
【前期から晩期】
今から6000~3000年くらい前。
と分けられています。
「縄文時代」は、
総年約13000年というとてつもなく長い時代なのです。
文化の芽生え(磨製石器の出現)を
我が国の民族の歴史の始まりと考えるのであれば、
歴史の約9割以上が、
「先土器時代」と「縄文時代」だったことになります。

「縄文土器」の名称は、
アメリカ人の動物学者エドワード・モースが、
明治10(1877)年に「大森貝塚」で発見した土器に
縄の模様がついていたことに由来しています。
「大森貝塚」は、
縄文時代後期から末期ころの貝塚です。
貝塚とは、
食べ残しやごみなどを捨てた遺跡を意味しています。
「大森貝塚」からは、
貝殻や土器の破片、土偶、石斧、石鏃、骨角器、人骨片などが発見されました。
このモースの発掘は、
我が国の考古学の発祥とされています。
2)気候の変化は日本列島にどのような恩恵をもたらしたのか?

まだ「日本国」が建国される前の今から約11000年前。
地球は、
氷河期が終わり、温暖期に移行していきました。
それに伴い、
日本地域は支那大陸と分離されて日本列島が形成されていきました。
気候の変化によって、
日本列島は現在と同じような四季のある温暖湿潤な気候になり、
植物の生育速度を速め、人々は木の実などの食料を確保しやすく、
多種多様な植物が育ちました。
また、
海面が上昇によって日本列島の至るところで
多くの入り江が形成されました。
これを
「縄文海進」と言います。
日本近海は暖流と寒流がぶつかり、
さらに縄文海進によって森の養分が直接入り江に流れ込み、
多くの魚が住み着くようになり、豊かな漁場となりました。
現代においても、
・北東大西洋海域(寒流:東グリーンランド西洋海流)
アイスランド・イギリス・ノルウェー近海
・北西大西洋海域(寒流:ラブラドル海流、暖流:メキシコ湾流)
アメリカ・カナダ東海岸(グランドバンク)
に並ぶ、
『北西太平洋海域』(寒流:親潮、暖流:黒潮)
釧路沖、 三陸沖、常磐沖、オホーツク海
という「世界三大漁場」を我が国は有しています。

このようにして、
日本列島では、植物資源だけではなく
海洋資源もより豊富に利用できるようになり、
世界でも有数の豊かな土地になりました。
現在でも日本食の文化は「魚」を中心としていますが、
その起源は「縄文時代」にあったのです。
この時代になると、
日本列島からはナウマンゾウなどの大型動物が姿を消し、
イノシシやシカ、ウサギなどの中小動物が増えました。
このような動物たちを捕えるために、
弓矢が発明され、犬を猟犬として使うようになったとされています。
落とし穴もつくられるようになりました。
カツオ、タイ、貝類、昆布などの豊かな海の幸やクリや豆などの山の幸など日本列島は豊かな環境御恵まれたため、人々は定住するようになりました。
豊か過ぎたがゆえに、
農耕や牧畜はあまり発達しませんでした。
そのため、
北部九州での水田稲作の開始は、
ずっと先の縄文時代晩期となったのでした。
3)縄文時代を生きた先人たちはどのような暮らしをしていたのか?

「土器」の製作には、
粘土の堀削(くっさく)から焼き上げまで、多くの手間暇がかかります。
この製作活動は、
移動して住むような生活では到底不可能であることから、
この当時から定住的な生活が営まれていたことが分かります。
「土器」が使われるようになると、
煮る、蒸す、炊くといった調理法が加わって、
汁物の調理もできるようになります。
ほかにも、
木の実などのあく抜きもできるようになり、
効率よく栄養を摂取できるようになりました。
土器で飲食物を貯蔵することもできるようになり、
世界で初めての酒造りが行われた形跡も確認されています。

人々は地面に掘った穴に柱を立てて、
葦で屋根をふいた「竪穴住居」に住み、集落をつくるようになりました。
丸太をくり抜いた丸太舟で沖に出て漁をして、
遠方へ航海することもあったと考えられています。
男性は、
動物の狩りと漁に出かけ、
女性は、
植物の採集と栽培に精を出し、
年寄りは、
火のそばで煮炊きの番をしていたのではないかと考えられています。

縄文時代の人々の人物像を大きく変えた近年の発掘は、
平成4(1992)年から発掘が始まった青森県の「三内丸山遺跡」です。
「三内丸山遺跡」は、
今から約5900年前から約4300年前まで、
およそ1600年間営まれた広さ約35万ヘクタールにも及ぶ
縄文時代中期の巨大遺跡です。
しかも、
多くの住居のほか、
35棟の「高床式倉庫」や
10棟以上の大型建造物跡が見つかっており、
全体で3000棟以上もあったと推定されています。
他にも、
道路、貯蔵穴、墓、盛り土、ゴミ捨て場なども計画的に配置されていたのです。
15mもの大型掘立柱の建物があったことも分かっています。
これは、
夏至の太陽が正面から登るような神殿設計がされていることから、
秋田県の大湯ストーンサークルと同じように、
縄文の人々が太陽を崇拝していた証ともいえるのです。
ただ一か所に多くの人が住んでいたわけではありません。
遠方との交易にも盛んで、
糸魚川(新潟県)のヒスイ、
岩手の琥珀、
秋田のアスファルトなども出土しています。
遠方の集落との交流網がすでに構築されていたことを示しています。

縄文時代を生きた先人たちの食料調達に関する最大の特徴は、
多種多様な食べ物をまんべんなく利用することにありました。
狩猟・採集を基本として、
山菜、魚、木の実、動物など、
様々な食べ物を組み合わせて生活していたと考えられています。
新潟が誇る我が国の考古学者で
新潟県立歴史博物館名誉館長である小林達雄先生の原画による
『縄文カレンダー』を参照すると、
縄文時代を生きた先人たちの食の豊かさが見て取ることができます。
実際、
貝塚から出土した魚介類や動物遺存体においても、
食の多様性という特徴が共通して確認されています。

このように、
縄文時代を生きた先人たちは、
採集経済を基盤とする社会としては稀に見る平和で
高度で安定した社会を構築していたことが明らかになってきています。
日本列島の豊かさが人の心の豊かさを育み、
大自然との調和を重んじる独特の世界観を作り上げてきたのです。
縄文時代の世界観こそ、
日本人がもつ世界観の土台となるものではないでしょうか。
次回は、
縄文時代を生きた日本人はどのように自然と共存してきたのか?
についてさらに詳しくお話をしていきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「和」とは、
周りに流されることのない主体性と信念を持ちながらも、周りの人々や自然と調和することを実践する道であり、我が国が建国されてからも2000年以上、受け継がれてきた価値観である。
日本が疲弊している。
日本人が疲弊している。
でも、日本を諦めたらいけません。
僕は諦めません。
日本人はまだまだやれる。
なぜなら、
僕たちが歩む道の後ろには先人たちが繋いでくれた
「我が国を遺したいという思い」がたしかにあったからです。
私たちが今できることは、
何よりもまず自分の国の神話、歴史、文化、そして精神性を学ぶこと。自分と先祖の歴史と生き方を学ぶことだと思うのです。
令和時代に、
「和の精神」を発揮して日本国を再び
よろこびあふれる感動する国へと取り戻す。
そのために、
皆様とともに学んで参りたいと存じます。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
