
先人たちが大切に受け継いできた「和の国のかたち」を現代に体現する~今の日本は「和の国」といえるか?~ー『和の国のかたち』1ー
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
謹賀新年
皆様、本年もよろしくお願いいたします。
令和7年は『和だちプロジェクト』が本格始動して4年目を迎えます。
昨年も大変お世話になりました。
皆々様のお陰で活動を進めることができています。
本年も、さらに飛躍した一年になればと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年で、7年目を迎える『和だちプロジェクト』。
『和だちプロジェクト』の活動としましては、
令和元年には、『和』の学級経営。
令和2年には、『和の国』日本国講座。
令和3年には、先人たちの『神語』。
令和4年には、『新・日本文明』。
令和5年には、『日本再興戦略』。
令和6年には、『日本人のこころ』。
国体、伝統文化、国史、経済、政治、修身というさまざまな視点で「日本」という国を見詰めなおして参りました。
そして、
令和7年は、
『和の国のかたち』という主題で研究を進めていきたいと考えております。

1)あなたは「日本」を語ることができますか?

このまま行つたら「日本」はなくなって、
その代わりに、無機的な、からつぽな、
ニュートラルな、中間色の、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう。
日本の小説家であり政治活動家であった三島由紀夫さんは、
昭和45年に次のように国民に対してこのような言葉を残しました。
あなたは、
三島さんが語った「日本」をどのように考えますか?

日常生活の中で「日本」とはどのような国なのか?
「日本人」とはどのような人の集まりなのか?
ということを考える人はどのくらいいるでしょうか?
現代は、
訪日観光客の増加とともに、
街で外国人とすれ違う機会は増え、
その時にふと「あの外国人観光客はどこの国から来たのだろうか?」と思うのと同時に、自分が日本人であることを感じることはあるかもしれません。
しかし、
それもほんの些細な一瞬のことでしょう。
そもそも、
国際化が進み、
アメリカやEU、シンガポールなどのように世界中から多様な人々が集まっている諸外国に比べると、
日本における生活において、
「日本人であること」をわざわざ意識する機会など、
ほとんどない人が大半でしょう。

しかし、
日本から出ていざ海外に行って友人たちと国際政治について語るときに
聞かれることは、
「日本は、どう思う?」
「日本はどうなっているの?」
「どうして日本はそのように考えるの?」
…などなど聞かれることは、「日本」についてのことばかりです。
そして、私たちは気づくのです。
「自分はこれまでたくさん勉強をしてきたけど、
日本について何も知らない…。」
と。
このように思うのと同時に、
「自分が日本人である」ことを強く意識し、
「日本とは?」「日本人とは?」と考えるきっかけにもなるのです。
2)「和」とは?

日本はよく「和の国」である。
また、
日本人は、争いごとを避け、
何か問題があれば極力話し合いで物事を解決しようとする傾向がある。
個人では難しいこともみんなで力を合わせて協力した時に大きな力を発揮することができる。
何よりも「和」を大切にする。
このように言われることがあります。
では、
「和」とはどのようなものでしょうか?
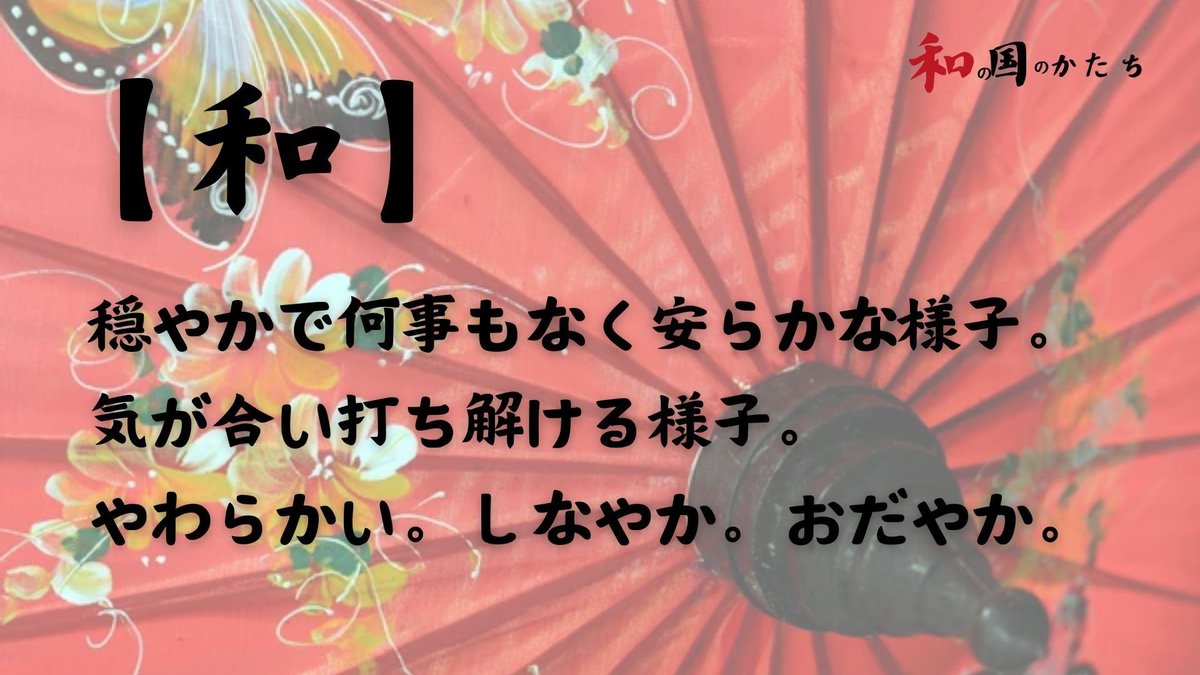
「和」という漢字を辞書で調べてみると、
穏やかで何事もなく安らかな様子。
気が合い打ち解ける様子。
やわらかい。しなやか。おだやか。
などを表すものと書かれています。

日本人が抱く「和」の概念の形成に最も影響を及ぼしたと思われるのが、
604年に成立したとされている厩戸皇子(聖徳太子)が示した
『十七条憲法』の第一条「和を以て貴しとなす」の一文でしょう。
『十七条憲法』とは、
国のリーダーに対して日本国をどのような国にしていくのか?
という国家の枠組みを初めて成文化したものであり、
国の在り方を示し、日本という国の理想像を語ったものです。

「和」という精神性は、
神話の時代、
すなわち「日本」という国家が誕生する前から人々の間で育まれてきたものであり、
日本人の生活や作法、そして森羅万象たいして捧げる祈りの中で実践され続けてきたものです。
日本国は、
その島国という地理的要因によってもたらされた言語、文化、外国からの侵略を受けたことがほとんどないという恵まれた歴史によって「和の精神」という価値観が育まれてきました。
「和」とは、
周りに流されることのない主体性と信念を持ちながらも、周りの人々や自然と調和することを実践する道であり、我が国が建国されてからも2000年以上、受け継がれてきた価値観である
と考えています。
3)今の日本は「和の国」といえるのか?

では、
今の私たちの国は「和の国」ということができるのでしょうか?
戦後の日本は、
日本に対する猛烈な反省と否定など反国家的文脈の中で語られる義務教育が行われてきました。
日本人の政治に対する無関心。
選挙における投票率の低さ。
防衛に対する関心の薄さ。
その結果、個人が日本という国家共同体に貢献してよりよいものにしようとする姿勢が否定され、国家観が完全に欠如した行き過ぎた個人主義が出来上がりました。
ネットを中心とする誹謗中傷。
大人の世界にも起こっているいじめ。
本来は家庭や地域で育むべき道徳教育の崩壊。
我が国の教育では個人主義が大切だということを教えても、
実際に個人が主体となって物事を考える真の個人主義的な思考を養うことをしてこなかったがために、
共同体から切り離された個人主義であるばかりではなく、
主体性と客観性と論理的思考に欠けた「同町圧力」という空気の支配に屈服し、他者の意見に依存する他者本位の個人主義が蔓延るようになってしまっています。
憲法において、
手厚く個人の尊重が保護されている国にもかかわらず、
個人の自己肯定感は他国と比べても極端に低い結果になってしまっています。
人と人との「和」が失われようとしています。

さらに、
先人たちが築いた緑豊かな国土は、
年々増え続ける我が国における食品廃棄物の発生量。
乱獲による海における水産資源の減少。
放置林による荒廃した森。
過度な自然破壊による人的災害発生。
などなど、多くの課題を抱え、
人と自然との「和」も失われようとしています。

日本が疲弊している。
日本人が疲弊している。
でも、日本を諦めたらいけません。
僕は諦めません。
日本人はまだまだやれる。
なぜなら、
僕たちが歩む道の後ろには先人たちが繋いでくれた
「我が国を遺したいという思い」がたしかにあったからです。
私たちが今できることは、
何よりもまず自分の国の神話、歴史、文化、そして精神性を学ぶこと。自分と先祖の歴史と生き方を学ぶことだと思うのです。
そのため、
令和7年度は、
「和の精神」という視点で
我が国の歴史や文化を見つめなおす
『和の国のかたち』
と題して
先人たちのお姿や遺してくださったお言葉・書物から学び、
我が国をどのように形づくるのか?に重点を置いて
研究したことをお伝えをしてまいります。
今年もどうぞ、
「和だちプロジェクト」をよろしくお願いいたします。
