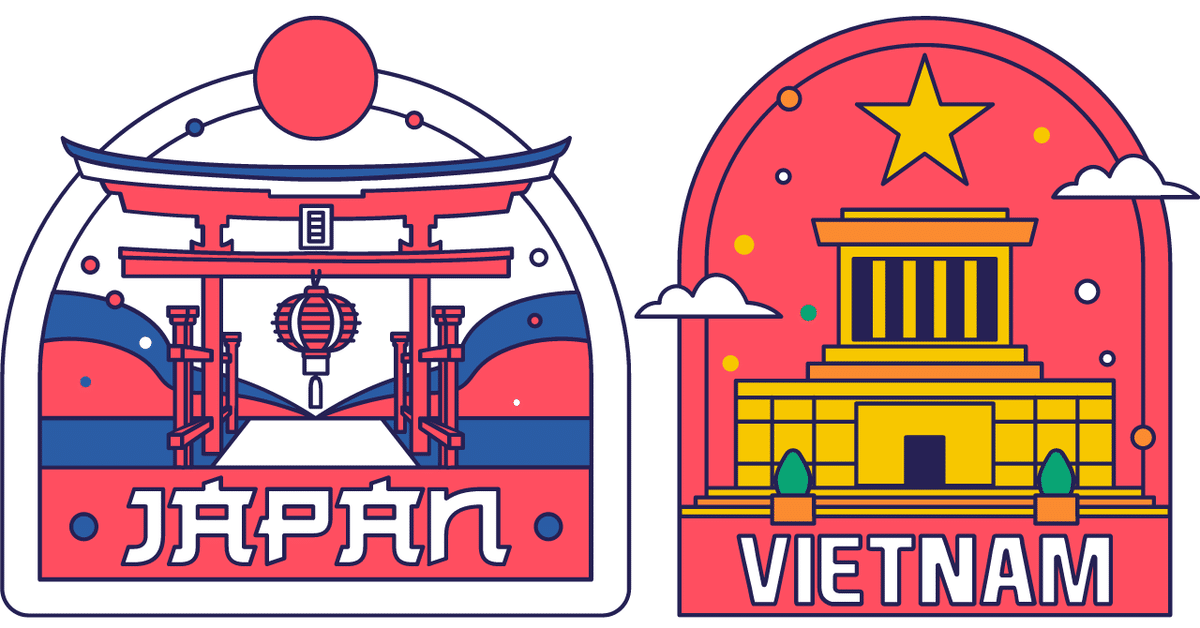
『虹へ向かって飛ぼう』の書評
1 挨拶
皆さん今晩は。今回は、浅野夕雪先生の著作『虹へ向かって飛ぼう』の書評を、哲学者として、様々な文献と見解と共にご紹介と書評します。
2 教育と人間関係
思うに、ほとんどの教育機関において、本質的には人間関係の学習が最も重要であり、そして根本義ではないでしょうか?今現在、日本は衰退の一途にありますが、教育の衰退もまた、その中、いや、その要因の一つではないでしょうか?
『106時間』という数字は公立学校の教員の1か月の残業の平均時間です。過労死ラインとされる1か月80時間を大きく超えています。過酷な労働の背景には、時代遅れの法律があります。教員たちの“ブラックな”勤務問題に迫りました。
小学生の「ランドセルが重すぎる」ことが問題になっている。重すぎるランドセルが、子供の健康や集中力にも影響を及ぼすと指摘する専門家もいる。なぜランドセルは重くなったのか。
新しい学習指導要領の登場、教育委員会制度の改革、保護者・地域の学校参加制度、教員の資質・能力向上政策…。それで結局どうなったのか、どうなるのか?「改革疲れ」が指摘される現場にむけて、理想と現実のギャップと「副作用」、「立ちどまって問い直すための視点」を提示。教育分野を牽引する、頼りになる研究者による、四年ぶりの単著。
無駄な宿題・無意味な集団行動・無益な役割…人生の基本・基盤・基礎を形成する幼児期・児童期・青春期を、一個人から社会に至るまでは、もっと真摯に向き合うべきでしょう。
多くの子ども達が勉強しない・勉強したがらない・勉強できない・勉強の意味や目的を持たない・勉強の喜楽や幸福が無い…いや、それは、多くの大人達に教師達や親達も同様でしょう。
親達よ、学校教育に放任すること勿れ!家庭教育の確保とその不断の実践と改善をしましょう!
教師達よ、学校教育に自閉すること勿れ!社会教育の確保とその持続的な応用をしましょうよ!
経営者達よ、営利主義に偏重すること勿れ!労働者達の時間に休養遊楽と自学自習への顧慮も!
親達の年中に亘る多忙に激務、そして帰宅後は寡黙や爆睡…子供達は寂しさや苦しみばかりを…
教師達の年中に亘る多忙に激務、そして形式や利潤に隷属する教育…青少年達は厭悪や鬱憤を…
情報技術に報道倫理、知識経済に経済倫理、成人教育に生涯学習、これらが徳治国家の宝。
家族の愛は実に偉力でしょう。ですが、逆に言えば、家族の禍は実に猛毒でしょう。
「愛」の一語が秘めた深遠な思想史の扉を開く。よりアクチュアルに、より哲学的に、なにより身近なテーマを問う。
個人や家族の抱えるさまざまな心理的・行動的な困難や問題を,家族という文脈の中で理解し,解決に向けた援助を行っていこうとする対人援助方法論の総称が「家族療法」である。
本書は広範な臨床領域と多様な理論的背景を持つ家族療法の全体像を把握し,理解できるよう,黎明期から現在にいたる理論・実践史をまとめた「理論編」と医療・教育・福祉・司法など多領域からのアプローチを網羅した「臨床編」で構成されている。
事例を交えたわかりやい記述,用語解説・コラムを収載した本書は,家族療法を学ぶための最適な入門書であり,より詳しい探索のためのガイドブックでもある。家族療法が日本に本格導入さて以来30年の理論と実践を集大成した,本邦の家族療法家たちによる初の家族療法の教科書。
本書は、家族心理学領域で開発されてきた革新的な主要技法を収録し解説した初めてのハンドブックである。臨床的に有効な59の技法を取り上げ詳しく解説している。
そして残念ながら、家族を見棄てて逃げ去ることが最善の道である人もまたいます。『虹へ向かって飛ぼう』の主人公の一人「河原椿」ちゃんもまたその一人です。
しかし、問題はその後です。誰かの助けに依りつつも、自力で確りと着実に自己治癒と自助努力して行かなければなりません。
先進国である日本は、確かにインフラストラクチャー(社会的経済基盤と社会的生産基盤とを形成するものの総称)が、極めて豊富で良質・高品質でしょう。ですが、ソーシャルキャピタル(社会・地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念)が極めて不足しており、今後、この充実化と向上等が、日本の再興と新興の一つの重要な鍵となるのではないでしょうか?
社会の格差はどこからくるのか? それを克服する展望は? 人々の関係性に着目してこの問題に接近する「社会関係資本」概念。この概念を起源から紐解き、人脈や信頼が持つ正と負の影響力、デジタル時代の新たな動向も踏まえ、この概念の全体像を描き出す入門書。
「国家」「社会」「個人」「自由」…こう言った言葉も、突き詰めて行けば、結局のところ、私達人類は、群居本能を持った社交性の動物であるということを知ると同時に、所詮は、孤独な存在であることを知ることになるでしょう。
教育は、こう言った私達の人間の生物学な本能と社会学的な本性に確りと向き合っては、洗練して、人類の成長と進歩に貢献していくことにも取り組んでいくべきではないでしょうか?
3 自殺・自死・生命倫理
自殺は自分の意志に由るものか?自死に正しさや善さはあるのか?生き続けること自体は正しいか?善いか?もし原始時代であれば、答えるのは着火や稲作よりも容易いことでしょう。ですが、現代では、そう簡単ではないでしょう。
今自分が確かに言えることは、「個人の意志」と「環境の影響」、この二者の因果関係や相関関係に相互作用を確りと精察や分析に洞察しては、改善や新規に努め励んでいくことが大切ではないでしょうか?
自殺をしてはいけない。この言葉は、どのように根拠づけられるのだろうか?この問いへの答えを求めて、古代ローマの歴史的資料や古代ギリシャの哲学者たちの思索をはじめ、戯曲や芸術、キリスト教やイスラム教といった宗教思想、宗教から距離を置いた哲学、社会学的な取り扱いまでをも含んだ広い視野で「自殺」がどう考えられてきたのかをまとめ上げる。古くは宗教的な罪とされていた自殺は、精神医学の発展に伴って倫理的に中立なものになり、現代では選択肢や権利として肯定する立場さえある。このような思想の変遷の中にも、自殺を肯定しない考え方が確かに生き残ってきた。誰もが納得する答えを出すことがむずかしい問いである。それでも、生きることをやめないでほしい、という切実な思いに向き合い、生きることをやめるべきではない理由とその論理をたどることが、この生に踏みとどまる助けになりうるし、切実な悩みに応えるためのヒントになりうるだろう。
「生き続けるべきだという主張と証拠について考え、それを選ぶことがはじめの一歩になる。そのあとはどんなことも起こりうる。まず、生き続けることを選んでほしい」(本文より)
環境社会学は、人間社会とその周辺の自然環境との相互作用を社会や人々の側から検討する学問である。日本の環境社会学は、公害や大規模開発の問題等の解決を目指す「環境問題の社会学」と、人間と自然環境の多様な関係性や生活世界の理解を目指す「環境共存の社会学」として展開されてきた研究がベースとなっている。ともに被害者、被災者、生活者、居住者の視点とフィールドワークを重視しながら、時には隣接する学問分野と協働し研究することが特長といえる。
新型コロナウイルス感染症、豪雨による洪水被害、猛暑・台風・豪雪の激甚化など、私たちの日常生活は多くのリスクに直面している。このようなリスクの根源には人間社会と自然環境との関係性の歪みが潜んでいる。
本事典は、こうした時代だからこそ社会にとって重要な意味を持つ、環境社会学の視座やアプローチ、これまでの研究蓄積、そして今後の展開を収載している。
生き続けることは、生命の本能であり、そして天命ですが、私達人類は、学び知ることで、今度は、自ら選択することが出来ます。その選択肢には、自殺と存続があり、思うに私達は、後者を選択できるようにしていくべきでしょう。
4 人生の虚しさと愛
生きては、色々と学び知って、本当に達観した時、いかに自分が孤独で無力あり、いかに世が非情で無常であり、いかに天が無情で合理であるのかを悟ることでしょう。
なんという空しさ、なんという空しさ、すべては空しい。
太陽の下、人は労苦するがすべての労苦も何になろう。
一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。
日は昇り、日は沈み、あえぎ戻り、また昇る。
風は南に向かい北へ巡り、めぐり巡って吹き風はただ巡りつつ、吹き続ける。
川はみな海に注ぐが海は満ちることなくどの川も、繰り返しその道程を流れる。
何もかも、もの憂い。語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、
耳は聞いても満たされない。
かつてあったことは、これからもあり、かつて起こったことは、これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない。
見よ、これこそ新しい、と言ってみても、それもまた、永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。
昔のことに心を留めるものはない。これから先にあることもその後の世にはだれも心に留めはしまい。
愛もまた虚しくて空しいことでしょう。
自分の愛する大切な人が自分を愛してくれるなんて、どうして言い切れるでしょうか?
自分の愛する大切な人が自分を愛してくれるという幸運も、どうして続くと言い切れるでしょうか?
自分の愛する大切な人が自分を愛し続けてくれるという幸甚も、必ずや死という終着点と永遠の別れに辿り着きます。
自分の愛する大切な子供達…その子孫が、被害者になったり加害者になったりする可能性は十分にあります。何故に種の保存をし続けるのでしょうか?
他の生き物を損なうことも傷付けることも害することも殺すことも無く生き続けることは不可能です。何故にそこまでしてでも生き続けるのでしょうか?
自分が生涯を掛けて育て成した愛する物・事・者…自分の死後、壊されたり、棄てられたり、廃らされたり、害されたり、殺されたりすることが多々あります。ああ、ならば、最初から何も存在しない方が幸いでは?
それでも…私達人類は、生き続けては、種を保存し続けて、闘争しながら創造と破壊を繰り返し続けるのです。何の意味も目的も無いこの世界で…それでも、脳に精神、本能に欲求、心に意識、知識に学習、言語に概念等を有した私達「人類」という生命体は、意味や目的等を創造しては仮定して、多様な生命活動を行うでしょう。
その多様な生命活動は正に「虹」の如く、美しくも儚いものであり、「虹へ向かう」のは、勇ましくも愚かなものであり、そして「虹へ向かって飛ぶ」のは、徒労に終わるものの、確かな幸せを自ら創っては得られるものでしょう。

何もない自分も、それが私なんだと思えるようになった。少しずつでいい、今の自分を愛せるようになった。
『高く飛べば、あの虹に届くと思っていた』憧れていたその場所は、願って届く場所ではないと気づいた。それでも、頑張って、頑張って、がむしゃらに生きて、生き抜いて。きっとその先には、今まで目指した場所よりも輝く場所が待っている。だからもう、うつむかないで、生きるんだ。
5 結語
以上が、浅野夕雪先生の最新作『虹へ向かって飛ぼう』への個人的な書評です。先生への深謝と今後の無事健康とますますの新たなご活躍を願いつつ、ここに声援の意を示します。
自分も現在、『根性』という平和と戦争の哲学小説を執筆中で、内容が戦争で、その結末が余りにも悲惨であるということから、今現在、大変精神的にも心理的にも極めて多大なストレスを克服しつつ、完成に向けて奮励努力しております。死ぬと分かっていても、それでも必死に生き延び続けては、戦い続けて、愛する大切な人々を想う…それが、次回に出版する拙作の哲学小説のメッセージです。


最後に、以下の天野先生の御言葉を皆さんにご紹介します。
自然の中から学ぶということは、実戦と理論との調和の立場に立って、人生の慧智を得ることであって、そこには未来の道を開拓する限りない可能性がある。(中略)明日への道を、再び自然の中から学び取らなければならない。
明日から、上記の拙作の執筆を再開します。
いいなと思ったら応援しよう!

