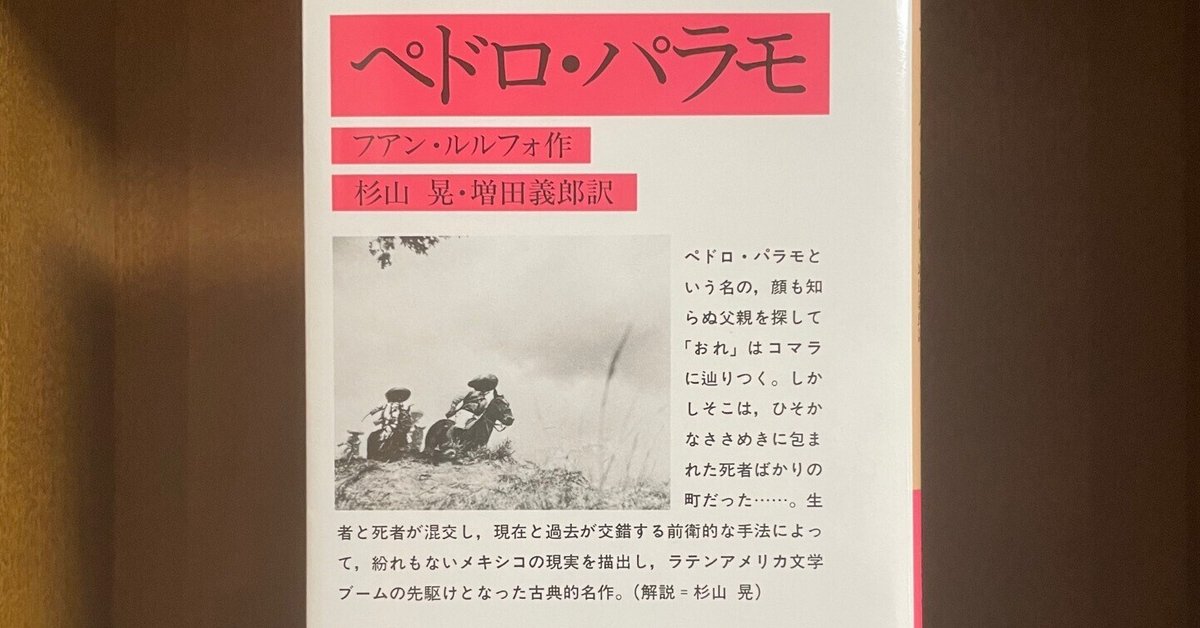
『ペドロ・パラモ』を紹介したい!(書評って感じではないです)
今から三年ほど前。
まだ大学生だった頃に、本を紹介し合うコミュニティの中で、メキシコの作家、フアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』について紹介文を書いたことがあります。
今回は、その時の文章をnote用に再編集して投稿することにしました。
なので、感想文・書評…というよりは、純粋に「紹介文」として読んでもらえたら嬉しいです。
※もうすでに『ペドロ・パラモ』を読み終わっている人(改めて紹介されるまでもない人)にとっては、ちょっと退屈な文章かも知れません。あらかじめご了承あれ。
『ペドロ・パラモ』 フアン・ルルフォ(訳:杉山晃、増田義郎)
いきなり個人的な話になってしまい恐縮ですが、僕が「短篇」以外の小説の中で、これほど再読を繰り返した作品は他にありません。
多分これから先も、何度も何度も読み返すだろうなあ…と思っています。
それくらい味のある作品です。
実は『ペドロ・パラモ』は、僕が初めて読んだラテンアメリカ文学でもあります。
しかしながら、今の自分が誰かに勧めるとしたら、ラテンアメリカ文学の一冊目、としてはお勧めしないだろうな…とも思っています。
特に、これまでに「ストーリー自体が面白いタイプの小説」を沢山読んできたという人は余計、ラテンアメリカ文学一冊目としては、『ペドロ・パラモ』以外の作品をとっかかりにした方が良いかも知れません。
(例えば、同じくルルフォの小説ではありますが、短篇集の『燃える平原』や、コロンビアの作家ガルシア=マルケスの中篇『予告された殺人の記録』など。それらは何となくストーリーを追っていても楽しいですし、ラテンアメリカ文学特有の「魔術的な雰囲気」への耐性もできると思います。)
そもそもストーリー自体がどこか朧気な『ペドロ・パラモ』をきっかけに「ラテンアメリカ文学って、分からなくてつまらない」という印象を持ってしまうのは勿体無い。
(その点では意外と、それまでの読書経験があまり無い人のほうが、案外「文学ってこんな感じなのかあ…」と入りこめたりするかも知れません!)
すくなくとも僕自身は、初読時、この小説が何を言わんとしているのか、あまり理解できませんでした。
…にも関わらず、やっぱりどうしても勧めたい。
特に、ラテンアメリカ文学の2冊目、3冊目を探している人には声を大にしてお勧めしたい!!
メキシコ的な風土や死生観について、予備知識(現地の神話など)が無くても入りこめますし、現実感が保たれたまま、非現実的な感覚も混ざり合ってくる「魔術的リアリズム」の原型を探るような形でも楽しめるはずです。
「いわゆるファンタジー」の幻想性とはまったく違う、現実の中での「あちら側」が存在している感じ。
時間や空間が入れ替わりながら、最終的にはひとつの流れがしっかり描き出されます。
(あとで言いますが、実はそれが難しいポイントだったりもします。難しいポイントが、そのまま「面白いポイント」でもあるのです。)
**
とは言うものの、いきなり「お勧めだから難しいけど読んでみろ」と言って放り投げるのも不親切なので…。
僕なりに『ペドロ・パラモ』が読みにくい理由、つまり「挫折ポイント」を2つほど挙げることにします。
※そのポイントさえあらかじめ分かっておけば(覚悟が出来ていれば)、滅多なことでは投げ出さなくなるはず…!
①…70もの断片を複合することでひとつの物語として成り立っていること。
②…死者が平気でおしゃべりしているので、生きてるのか死んでいるのかもよく分からない登場人物がいること。
では、それぞれ詳しく。
**
まず①について。
この小説はなんだかジグソーパズルみたいなんです。ジグソーパズルというのは、一つの画像(絵や写真)がいくつかのピースに分解されていますよね。
それを一片ずつ「あ、ここは繋がっているな」という風に組み立てていって、いずれひとまとまりの画像全体が完成する…。
この小説をよむ人も、まるでジグソーパズルのピースひとつひとつを組み合わせるようにして、物語の全体像を、自分のなかで構築していく作業が必要になります。
ひとつひとつの断片を組み合わせることによって、全体の話がイメージできるようになるのです。
恐らく多くの人は、一回読んだだけで全てのピースを上手くはめこんで完成…というわけにはいかないでしょう。
試行錯誤して読んだわりには、結局ちんぷんかんぷんだったな、、、となっても全くおかしくありません。
ただ、この「ちんぷんかんぷん」が印象に残るか残らないかでかなり違うと思うのです。
まったく印象に残らなかったのであれば、それはまた別の本を探した方が良いかと思いますが、「なんだこれ、どうなってんだ...?」という風に、ワケは分からないけど印象に残った、、、という人には、是非再読していただきたいものです。
一回目に読んだときよりもはるかに理解しやすくなっているはず。
ただそれでも、「どうもこのピースはどこにも合わない気がするだけど...」という断片もあるかも知れません。
僕自身、いまだに上手くはめどころが見つかっていない断片があります。しかし、読み返せば読み返すだけ新しい発見、驚きを得るのです。
(文庫本で約200頁。なんとか読み返そう、と思えるくらいの長さではあります。)
最初は「分かろう」とか「理解しよう」と躍起にならなくても良いと思います。
「具体的ななにか」を得ようとするのではなく、もっと抽象的な、「印象」や「雰囲気」のようなものを楽しんでみてはいかがでしょうか。
**
次に、挫折ポイントの②について。
これはもうどうしようも無いんですけど、死者がしゃべります。しゃべるどころか動き回ります。そういう小説が生理的に無理、、という人にはお勧めしません。
ただ、慣れてしまえばこれもまた面白い。というか、これこそがラテンアメリカ文学の醍醐味だろうという気もします。
「死」というものが、とてつもなく恐ろしいもの…として描かれるのではなく、どこかユーモラスに「死んでも喋っちゃうんだぜ」くらいの感じで描かれているように思います。
(もちろん、お笑い的なユーモラスさとは違いますが)
「恐怖」というよりは、どこか「悲哀」とか「諦め」とかそういうニュアンスが強い感じです。
**
…と、こんな感じ。
ラテンアメリカ文学、そして「魔術的リアリズム」の完成者、とも称されるガブリエル・ガルシア=マルケスも、この『ペドロ・パラモ』のことは大絶賛しています。
(…なんて、最終的に権威を借りてきちゃったりして 笑)
ここまで、この投稿を読んで下さった方は、きっと読み切ることが出来ると思います!
是非是非、読んで、戸惑って、それでもハマって、結局再読まで辿り着いてもらえたら幸いです。
