
余分がなく、鮮明。-志賀直哉 著 『和解』
植物や生き物の声、大切なひとの身に明日起こること、残された時間。「聞こえたらいい」「見えたらいい」と思うものは、この世にごまんとある。
「愛情」もまた、目に見えないもののひとつだ。
愛情は「目に見えない物質 世界代表」のようなもので、渡すほう、受け取るほうによって捉え方がまるで違う。なかでも「家族の愛」は、人によって地盤がまったく違ってくるように思う。
育ってきた環境や、受けてきた影響によるものなのだろうか。本当は、それだけではないかもしれない。
◇
「心情の移り変わりが緻密」
あるとき、先輩のライターさんからこの「和解」という本について、そう教えていただいた。
そのときの私は、作者である志賀直哉さんの作品をしっかりと読んだことがなく、おすすめの本を尋ねたところ、この本を挙げてくださったのだった。
「霧中にいる感覚」「静の中の激しさ」
先輩ライターさんのそんな魅力的な表現で、私の“読みたい欲”はじりりと刺激される。
志賀直哉さんの小説にはじめて触れる、これからも触れつづけたくなる、印象的なきっかけになった。
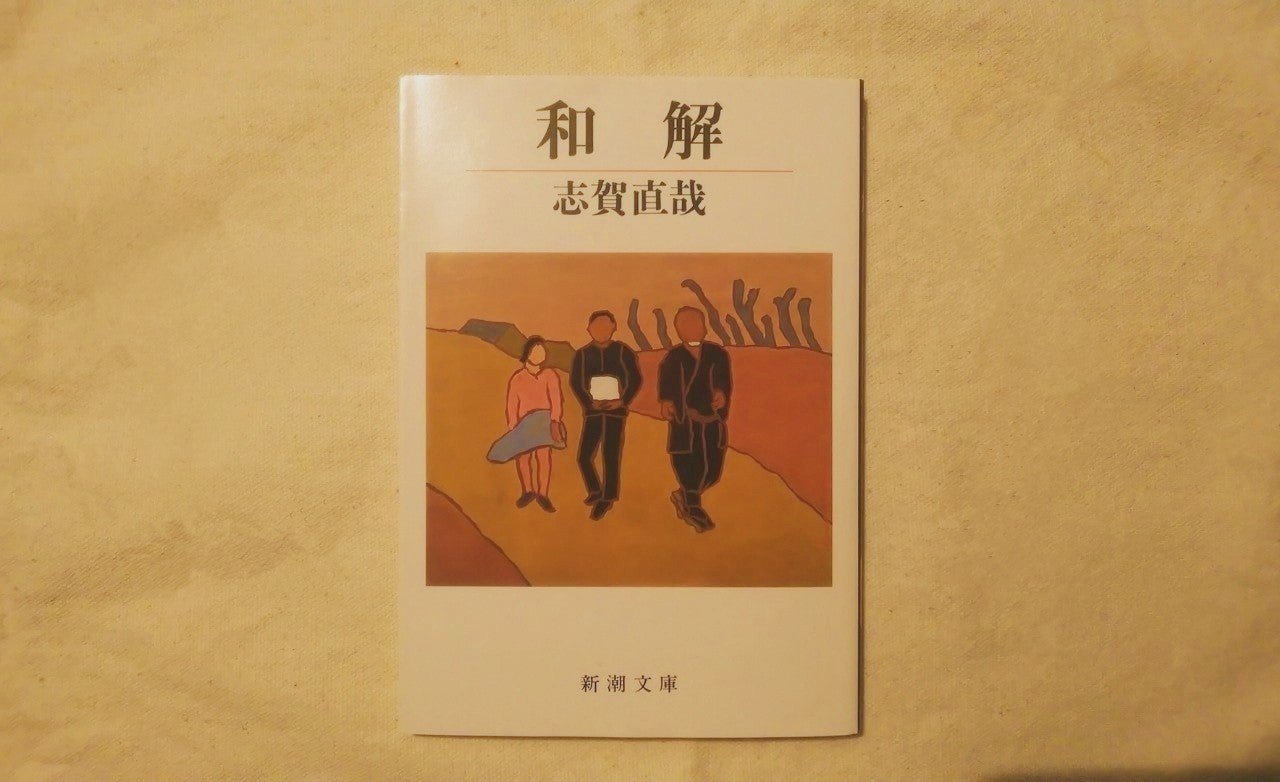
読んで冒頭から、その淡々とした話の切り口に、ずしんと引き込まれる感覚に襲われた。
この七月三十一日は昨年生れて五十六日目に死んだ最初の児の一周忌に当たっていた。
衝撃的な一文からはじまる物語には、主人公である順吉が長女の誕生や早すぎるその死を経るなかで、複雑に絡む父との不和に葛藤するさまが書かれている。
とりまく環境の変化や、時代の移りかわりが描かれる節々に織りこまれているのが、「実の父親への反抗心」だ。
文中で順吉は、父親との面会を拒絶するなど、憎しみをわかりやすく露わにしている。しかし、次女が生まれたのちに命名で祖母の名前をかりた頃から、徐々に父親への気持ちがほぐれていき、長年の溝が埋まっていく。
そしてついに、ふたりは和解をとげる。
この物語に触れているとき、目の前の文章を読むしか余地がないような、選択肢が与えられていないような、不思議な感覚になった。
感情をあらわしている内面の描写は必要最低限。観察描写は簡潔、それでいて、的確。
「余分がない」と思った。蓄積した憎しみややり場のない悲しみ、素直になれないもどかしさ、和解へ行きついたときの喜び。そのどれもが、ときに目を背けたくなるほど正直で、生々しく、人間くさくって、鮮明。
とくに、長女が息を引き取るまでの描写は凄まじい。「悲しい」などの内面的な感情は、易々と語られていない。ただただ、観察したままの情景が明け透けに描かれている。悲痛だった。
「追われるように読むしかない」というより、「必然的に追うように読んでしまう」。そんな魅力がある。
◇
父親に反抗心を持ってから和解するまでの経緯が、くっきりとかたどられるように書かれているものの、では、それほどのわだかまりを持つまでに至らせたできごとって何だったのだろう。
その部分は、この本では明らかにされていない。「その疑問にだれもが気づかないように、巧みな技法でぼやぼやと守っている」のではなく、最初からきっぱり触れられていない。
ピントをあてるつもりさえ、はなから無いように思えた。
作者がこの物語でもっとも熱を帯びさせたかったのは、確執の原因や父親への反感ではなく、家族からの愛情をしっかりと自覚できたこと、「和解できたことの喜び」なのではないか。
複雑な感情を持ちながら立っていた凍てつくつめたい世界に、ひとすじの光が差し、長年かけて無理やり作りあげた氷が、しずかに、ゆっくりと溶け出していく。
次女に祖母の名前をかりたのを皮切りに、父親との溝がじりじりと埋まっていく描写からは、そのようなものを感じた。
ところどころ、注釈を読みながらすすめるのもまた良い。

読んでいる最中、何度も「私小説」という単語が頭をかすめた。
私小説とは、作者自身の経験や心理を素材にしてほぼそのまま書かれた小説をさす。「和解」は志賀直哉の私小説で、この作品を発表した年の8月に父との和解が成立しているのだそう。
だとするとこの本は、どこか“日記帳”のように思えた。
「本のかたちをしたものを拾ったので興味本位でめくってみると、持ち主と家族との確執が興奮ぎみに書きあげられていた」ような。作者が自らを投影した順吉の日記を、「勝手に覗いてしまった」ような。
そんな、ちょっと罪悪感にも似た感情は、読みすすめていくなかで小刻みに衝撃を受けつづける理由のひとつに、間違いなくなっていると思う。

「月日が経ったら再読したい」と思う本に、ときおり出会うことがある。同じ本でも読む時期が違えば、別の視点や気づきが見つかる気がする。
この「和解」もまさにそうで、すこし年を重ねてからもう一度触れてみたい。今は、ぴんとまっすぐで頑固な順吉のほうに気持ちを引っ張られるようにして読んだけれど、再読したころには、もっと父親側の立場にいる自分がいるかもしれない。
交錯していて、儚い。おぼろげに見えて、しっかり強い。言い知れない悲しみのなかに、そんな家族の愛情とやさしさを感じた。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
