
『アメリカン・フィクション』バズらなきゃいけない創作業界
インテリ黒人作家が「リベラル白人が喜ぶ軽薄な貧困黒人小説」の真似ごとを書いてみたらそのまま大ヒットしてしまう……Amazon Prime配信映画『アメリカン・フィクション』は、あらすじから想像されるより皮肉な風刺ではない。むしろビタースイートに「バズる企画じゃないと通らない」クリエイティブ職のつらい現実をとらえている。
「ポリコレ」嫌いの主人公
ステレオタイプをネタにしたこの映画はステレオタイプではじまる。黒人教員が授業で差別用語を使っていったことで白人学生にクレームを入れられて休職に追い込まれる……これはイーライ・ロス『ヒューマン・ステイン』と同じ導入だ。「ナイーブで世間知らずなリベラル白人大学生」というのは叩かれ材料になりがちで、最近も『TAR/ター』や『ホワイト・ロータス』に登場している。「偉大なる芸術を侵すポリコレ風潮」に嫌気がさしているアートファンから快哉を呼ぶお決まりの戯画なのだ。
「ポリコレ風潮」を憎む者の筆頭が主人公モンクである。高尚そうな文学を書いてるものの売れておらず「人種は関係ない」と断言して売れやすい「白人が喜ぶステレオタイプな貧困黒人小説」企画を拒絶している。そもそも裕福な医者一族の出身だからステレオタイプにあてはまらない。ただ、なにかとまわりを見下す嫌な奴でもある。そんな男が妹を亡くし、放置していた実家でアルツハイマーとなった母を支えなければいけなくなり、自暴自棄になって「ステレオタイプな貧困黒人小説」を別名で書いたら、出版社を大喜びさせてしまう。
【以下ネタバレ】
バズるコンテンツ論
もちろんモンクは出版を嫌がるが、介護のための大金が必要でもある。エージェントは、アート論というより経済的なコンテンツ論で説得をはかる。

ジョニーウォーカー赤24ドル ジョニーウォーカー黒50ドル ジョニーウォーカー青160ドル
分かるか? どれも製造会社は同じだ
赤と黒はイマイチだが青はうまい だが青は高価で手が出ない
結局は酔えればいいんだ
君の本は青だった 上質で複雑な味わい
だが売れるのは気軽に楽しめる本だ
これまでの高尚な作品とちがって、指名手配中の貧困出身黒人による半自叙伝として売り出した『ファック』は「リアルな社会派」として白人に大ウケしていった。要するにバズったのだ。エージェントが言うとおり、わかりやすく「真実ではなく免罪符を求めるリベラル白人」需要にかなっていたのだろう。ちなみに、現実のアメリカでブラック・ライヴズ・マター運動が広まったときベストセラーになったのは「白人向けQ&A」要素を打ち出す本だった。『白き脆さ:なぜ白人が人種差別を語るのが難しいのか』『アンチ人種差別主義者になる方法』『あなたは人種について話したいのね』。よく言われるのは、こうした書籍にお金を払う消費者には高学歴白人が多いから、その層に訴求する企画やパッケージングが多くなる説。市場には、倫理や信念ではなかなか変えられない需要と供給の問題が立ちふさがっている。
「世間知らず」のアート論
リベラル白人用の快感装置として文学賞の白人審査員たちまで舞い上がらせたのだからコンテンツ論的には大したものだが、アート論として重要なのはシンタラとの討論だろう。
「『ファック』のどこが迎合的だと思った?」
「うまく言えないけど……世の中に出回ってる作品と違いはないんだけど……魂がない。あえて言うなら。あなたも同意したでしょ?」
「そうだね。罪悪感を抱える白人の嗜好を満たすために書かれた感じだ」
「そう。批評家が『(社会的に)重要/必要』とは言うけど『よくできている』とは評さない類」
相変わらず失礼なモンクは「君の本とはどこがちがうのか」と斬り込む。相手の作品を読んでもいないのにだ。彼からしたら、彼女だって「ステレオタイプな貧困黒人」ではないのにそういった物語を売っている。しかし、二人のちがいは、関心のある題材だったか、真面目にリサーチと取材を行ったかである。モンクなら、文芸趣味の合う公選弁護人の恋人に話を聞くことだってできたはずだ。
「白人の奴隷としての黒人」作家と侮辱されたシンタラは反論していく。市場の需要に応じてビジネスを行っている実態だけで駄目なのか。「白人弱者の物語なら無徴となるが黒人だと偏見を呼ぶ」議題は黒人作家ではなく白人たちの問題ではないのか。彼女のジャブは強烈だ。「長く大学にいて忘れちゃった? 人生はハードなの」。キャンパス政治に不満を抱きつづけていたモンクこそアカデミアの論理に引きこもる世間知らずだと糾弾されるのである。

退出したモンクの前にあらわれる写真は、1940年代に行われた「ドール実験」。当時、黒人の子どもたちに肌の色以外は同じ黒人と白人の人形を見せてどちらが好きか聞くと、ほとんどが白を選んだ。幼い黒人の自尊心がどれだけ損なわれているかを示す結果とされた。この演出から導きだされるのは、中年のモンクが「黒人ではなく白人の問題」にとらわれつづける黒人であることだろう。
現実を受け容れる
『アメリカン・フィクション』とは、妹の死を発端として、持論に固執していた主人公に「ハードな現実」が襲いかかるドラマである。信念が悪いわけではないが、恵まれた立場で実家も放置して傲慢な態度をとりつづけた彼は、実社会や他者の複雑さを学んでこなかった。文学賞と破局によって打ちのめされたモンクにとって最後の藁となったのは、母親との会話だろう。ついに不倫について聞くと「天才は人と交われないから孤独、あなたも天才だ」と語られたから「そう感じられないよ、半々は(I certainly don’t feel like one, half the time.)」とこぼす。つまりこの男は自分をわりと天才と思っているわけだが……次の瞬間、母は話し相手をクリフと呼んだ。
「ハードな現実」を味わったモンクはハリウッドに飛び、映画の仕事をすることに決めた。最後、軽薄な白人監督がつくる映画に出演する「黒人奴隷の悪霊」役者にピースサインを送られ、嫌味なく挨拶を返す。コード・ジェファーソン監督いわく、主人公がシンタラの意見を理解したのはこのときだ。
「モンクもあの俳優も、クリエイティブ職として自活するために必要なことを行っている。求められることをやっている事実は、その人の尊厳を毀損しないし、能力を低下させることでもない。モンクのお辞儀は『わかってるよ』ということだ。ついに彼は世界とつながったのだ」。
持論に折り合いをつけたことで、モンクは「ある意味、傲慢ではなくなった」と主演のジェフリー・ライトは語る。「彼は自分の欠点、外部の欠点、そして黒人コミュニティの巨大な不均質と複雑さも受け容れようとしている。ある面、理解というより、もともと批判していた存在に近くなった。あの瞬間、そのことにちょっと気づいたんだろうね」
ヒューマンドラマとしての『アメリカン・フィクション』とは主人公の成長譚である。ご高説を振りまいていた男が、クリエイティブ職の現実を受け容れたのだ。もちろんビターエンドではある。社会批評として見ると、アメリカのストーリーテリング業界は「マジョリティの白人に売れる黒人の物語」商売に寄ったままである。本作を人種差別構造に屈服した芸術家のバッドエンドと視る人もいるだろう。ただ、映画のメッセージは「同胞」の共感性に向けられている。社会や産業に問題があるからといって、需要に応える物語を懸命に売っている黒人クリエイターを「白人の奴隷」だなんて断罪していいのだろうか? 結局のところ、資産家でもないのなら、妥協もしながら商業的成果を見込まなくてはいけない現実がある。
さらに踏み込めば、世知辛い制約のなか「魂」を込める努力だって、その「魂」が誰かに届くことだってあるはずなのだ。「本は人生を変える」。妹の言葉は冗談だったかもしれない。でも、本当にもなるかもしれない。少なくとも、モンクの人生は変わり、映画監督の横暴に耐えながら「ステレオタイプを演じた黒人作家の物語」をどうにか届けようとするようになった。
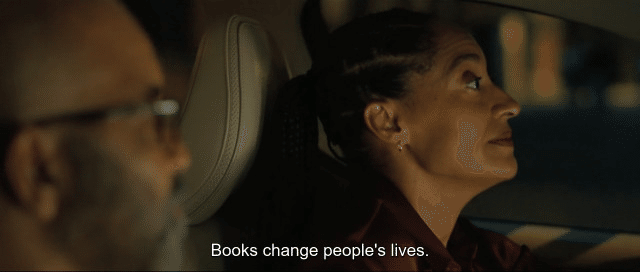
この記事が参加している募集
よろこびます
