
やさしい物理講座ⅴ135「等価原理では説明しきれない『力・F』の本質と相対性理論の矛盾」
物体(物質)に内在する力・Fは相対的に見ないと判断が難しい。その力は慣性力が働いたか否かは「止まっている物質」と「運動している物質」の見分けが一見して出来ないのである。
空間において、その物質の位置だけでは両者の力F違いは区別できない。そこである基準点との位置の変化によって「運動している物質」であるかの認識ができるのである。
「止まっている物質」に「動いている物質」に力Fが加わった場合はどうなるのであろうか。これが力Fの本質(衝突)である。
そして、この実験装置は地球の自転を伴う重力下における(慣性系)環境にあることも忘れてはならない。
動かない玉にも重力が下向きに働いている。そして、地球の自転による力を受けている。つまり、重力以外に遠心力が各緯度に働くのである。太陽系で考えた場合、太陽の重力の影響から逃れることができないのである。
そしてもっと範囲を広げると銀河系の重力などの影響から逃れられない一種の慣性系の渦に巻き込まれているのである。 平穏な環境と思っていても大変な慣性系の環境にいるのである。そして、その慣性系にある物質はその環境の中では「慣性力」を感じさせないのが、「慣性力」であろうか。
そして、運動する物質と運動しない物質の衝突のときに初めて力Fの存在を認識させることになるのである。運動する物質の衝突によって力Fを知ることになる実験例を次に掲載する。なお、運動する物質の力は重力と遠心力が作り出した現象であることに留意が必要である。
皇紀2684年10月5日
さいたま市桜区
理論物理研究者 田村 司
ニュートンの振り子
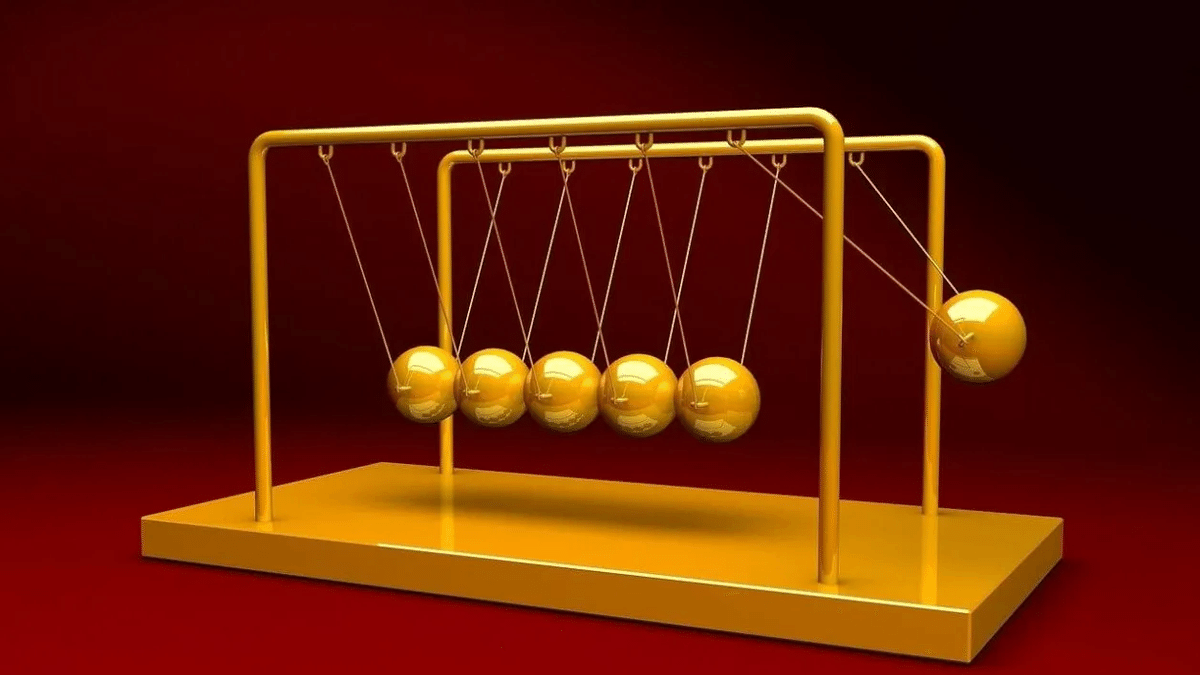



ニュートンのゆりかごの動きの球の数による違い
中間の金属球は静止したままのように見える。実際に、中間の球を指で挟んで持っていても、この装置は動き続ける。これも、直感に反しているように見える。止まったままで動きを伝えているからである。
実際には、最初の球の衝突が衝撃を生みだし、その衝撃が中間の球を伝わっていくのである。バスに並んだ人の列と違って、鉄のような固い物質は、衝撃力の伝達に優れているのである。
この衝撃波は、物質の中を音速で伝わっていく。鉄の中での音速(約4699 m/s)は空気中(約343 m/s)よりずっと速く、数センチメートルほどの短い距離を伝わる時間は人間には捉えられないほど短い。これは、金属球の中を物理的な歪みとして伝わっていく衝撃波についても言える。
理想的な世界では、この動きは永遠に続くが、現実には撃力を100パーセント伝達できない。そのため、金属球のエネルギーは、吊るされた紐、空気抵抗あるいは音といった形で失われる(金属球のカチカチという音は、運動エネルギーが音のエネルギーとして失われている証拠)。振動が終わりに近付くと、中間の球も少しだけ揺れる。
もっと興味深いことが、複数の球を最初に衝突させたときに起きる。5つの球を持つゆりかごで考える。2つの球で始めたときには、反対側の2つの球が対称に飛び上がって往復する。運動量保存則を満たしていても、反対側の1つの球が倍の速度で飛び上がるとか、4つの球が半分の速度で上がるといったことは起きない。これは、対称な動きだけが運動量と運動エネルギーの両方を同一にするからである。
もっと多くの、半分以上の球を最初に衝突させたとき(たとえば5つ中の3つをぶつけたとき)には、真ん中の球は、振動の中断や再開なしにそのまま動きつづける。
遠心力という慣性系

地球を舞台とする緯度と遠心力

地球の緯度とrsinθ

等価原理(とうかげんり、英語: equivalence principle)は、物理学における概念の一つで、重力を論じる一般相対性理論の構築原理として用いられる他に、異なる座標系での物理量測定の一致性についての議論でも登場する。
重力質量と慣性質量
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
