
【防災#02】冬に大地震発生!もしもの時のために備えていますか?!
今年もあと残り2ヶ月ですね。
日増しに寒さも厳しくなってきましたが、皆さんはもし冬の寒い時期に大地震が発生した場合、備えは十分に出来てますか?
厳しい寒さで地域によっては積雪もあり、暖房器具の使用など、夏とはまた別の問題が伴います。
過去、日本でもいくつかの大きな冬の地震が発生しており、そこから多くの教訓を学んでいます。
今回は冬の地震にフォーカスをおいて、そこから学んだこと、
そしてこれから個人ができる減災対策を考えていきましょう。
その後に、冬に備えておくと良い『食料備蓄品』もあわせて提案していきます。
--------
--------
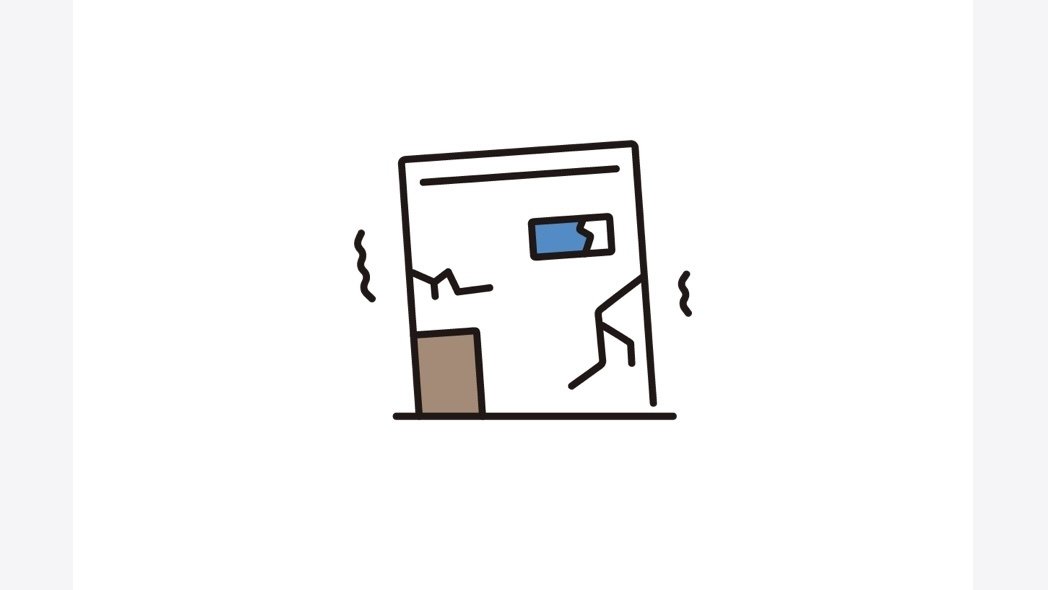
冬の地震の歴史
1. 1891年 濃尾地震(12月)
冬の寒さに加え、家屋の倒壊や火災で多くの被害が発生。
2. 1943年 鳥取地震(12月)
冬の寒さの中、避難生活が長引き、寒さ対策が十分でないため、健康被害が増えました。
3. 2004年 十勝沖地震(2月)
雪に覆われた地域で発生した地震のため、道路が寸断され、救助活動に支障が出ました。
4. 2018年 北海道胆振東部地震(9月ではあるが、雪の多い地域)
冬に向けての復旧が困難で、停電が続く地域では寒さ対策に苦労しました。
.
.
.
そして、2024年 能登半島地震。
--------

冬の地震から学ぶこと
• 寒さと停電:寒冷地では暖房が生命線となるため、電源に頼らない暖房器具の備えが重要です。
• 避難生活の防寒対策:地震後の避難生活で低体温症や凍傷のリスクが高まるため、防寒具や毛布が必需品とされます。
• 火災リスク:地震による火災は冬の乾燥した空気や暖房器具の使用で燃え広がりやすいことから、火の元の確認や初期消火が求められます。
--------

個人でできる冬の地震対策・減災
1. 防寒対策をした備蓄品の準備
寒い冬に備え、非常用リュックに毛布やホッカイロ、断熱シート、厚手の衣類を入れておきます。停電やガス停止時の暖房代替として、カセットコンロや小型ストーブなども備えます。
2. 避難時の寒さを想定した服装確認
避難時は厚手のコートや手袋、帽子を身につけて体温を保ち、避難場所での冷え込みに備えます。また、スニーカーなど動きやすい靴も手元に用意しておくと安心です。
3. 火災対策
暖房器具の転倒防止対策を施し、揺れに耐えるように工夫します。また、初期消火のために消火器を準備し、家族で使い方を確認しておきます。
4. 停電時の照明と電源確保
冬の長い夜に備えて、LEDライトや懐中電灯、モバイルバッテリーなどを準備しておきます。ラジオ付きの手回し発電機があれば、情報収集と同時に携帯の充電も可能です。
5. 定期的な地域の避難所確認
冬に利用できる地域の避難所を事前に確認し、暖房設備が整っているかやアクセス方法を把握しておくと安心です。また、雪が多い地域では除雪対策について自治体と連携しておくとスムーズです。
冬の地震は寒さや火災など独特のリスクが伴います。
日頃からの防災意識を高め、家族や地域と協力して備えることで、いざという時の被害を最小限に抑えることができます。
--------

冬に備えたい食料備蓄
また、それ以外での冬の備えとして、
防災用の食料品は、寒さに対応できるよう、温かく食べられて体温を維持できるものや、栄養価が高く保存性のあるものが理想的です。
調理が簡単でカロリーが高めのなものを備蓄することで、寒冷時のエネルギー消費にも対応しやすくなります。
以下に冬におすすめの防災用食料品を理由をつけて紹介します!
1. インスタントスープ・味噌汁
理由:お湯を注ぐだけで温かいスープが飲め、体が温まります。味噌汁やスープには塩分が含まれているため、発汗による塩分不足にも効果的です。
備蓄方法:カップタイプやフリーズドライタイプが保存しやすく、場所も取らないので便利です。
2. カップ麺・インスタントラーメン
理由:お湯を注ぐだけで簡単に温かい食事が取れ、炭水化物でエネルギー補給がしやすいです。また、種類も豊富で飽きにくいです。
備蓄方法:長期保存が可能なものを選び、ローリングストックで定期的に消費・買い足しを行うと新鮮な状態を保てます。
3. レトルトのお粥や雑炊
理由:消化が良く、体調が悪いときにも食べやすいです。温めて食べると特に寒い冬に適しており、体を温めてくれます。
備蓄方法:加熱せずにそのまま食べられるタイプや、温めて食べられるレトルトのお粥や雑炊を用意しておくと便利です。
4. カロリーメイトやエナジーバー
理由:手軽に栄養補給ができ、高カロリーで小腹が空いた時にも便利です。ビタミンやミネラルも含まれているものが多く、栄養バランスが取りやすいです。
備蓄方法:保存期間が長いものが多く、備蓄に適しています。個別包装で携帯しやすいのもポイントです。
5. 缶詰(スープ缶、おでん缶)
理由:缶詰は保存性が高く、スープやシチュー、おでんなどの温かい料理が楽しめます。缶ごと加熱できるタイプなら、寒い冬でも温かく食べられます。
備蓄方法:コンビーフやサバ缶なども高タンパクで、エネルギー補給に役立ちます。フルーツ缶はビタミン補給に最適です。
6. ホットドリンク用の粉末・ココア・甘酒・インスタントコーヒー
理由:体を温めるホットドリンクは、寒い季節に気持ちもリフレッシュさせてくれます。ココアや甘酒はエネルギー補給にもなり、甘酒にはビタミンも含まれています。
備蓄方法:粉末状で保存性が高いものを選び、お湯を注ぐだけで簡単に飲めるタイプが便利です。
冬は停電や断水のリスクも考えられるため、お湯を簡単に沸かせるようにカセットコンロと予備のガスボンベを備えておくと便利です。
また、食品の賞味期限を定期的に確認し、ローリングストックで入れ替えながら備蓄を整えましょう!
--------
自分を守る備えを!
いつ何が起きても良いように日頃から考え、備えていきましょう。
この発信が皆さんの防災を見直すきっかけになると嬉しいです。
それではまた(*^o^*)/
