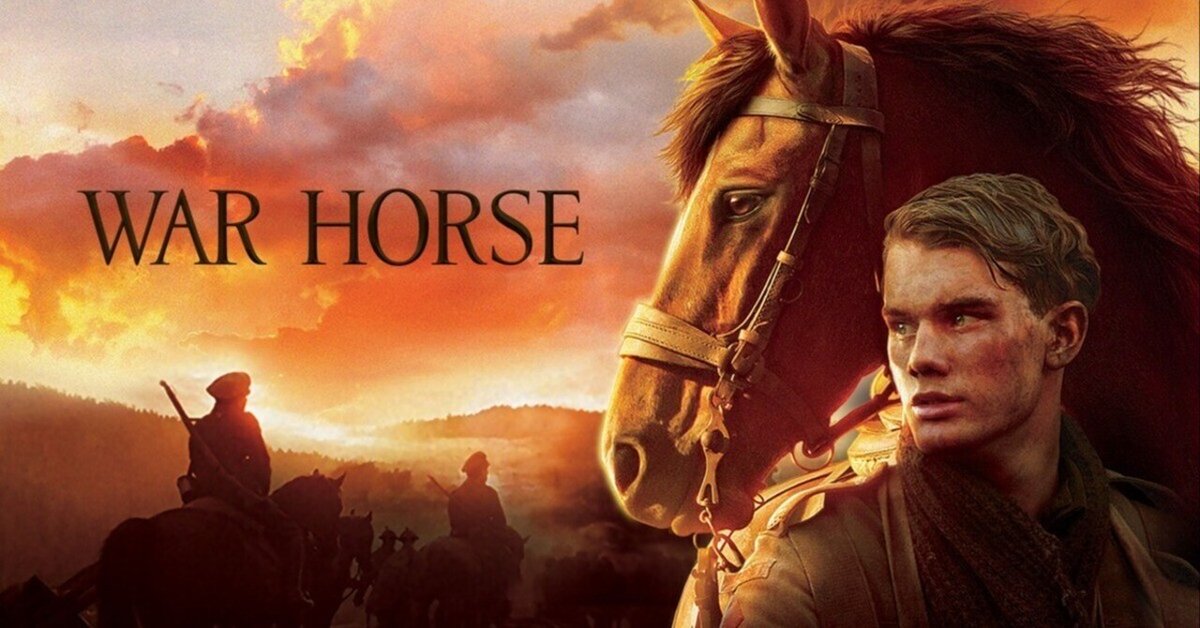
映画感想 戦火の馬
馬と少年と戦争の物語。
今回はスピルバーグの名作映画。2011年12月公開『戦火の馬』。すでに名匠と呼ばれるようになった65歳のスティーブン・スピルバーグが監督する。同じ年にはスティーブン・スピルバーグ監督のアニメ映画『タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密』が公開され、翌年にはやはり大作映画『リンカーン』。その後も現在に至るまでハイペースで旺盛に作品を発表し続けている。衰えを知らぬ名監督だ。
原作のマイケル・モーパーゴの小説『戦火の馬』は1982年に出版。
映画化の直接の切っ掛けになったのは、2009年に映画プロデューサーのキャスリーン・ケネディとフランク・マーシャル夫妻が舞台版『軍馬ジョーイ』を観劇したことに始まる。キャスリン・ケネディとフランク・マーシャルはこの舞台に感激を受け、まだ誰も映画化権を取得していないことに驚き、ただちに押さえる。
そこから二人の古くからの友人であり、仕事仲間であるスティーブン・スピルバーグに話が行き、ドリームワークスで映画化することが発表される。
その後は2010年5月にスピルバーグ自身が監督することが発表され、6月にはキャスティング発表、9月に撮影が始まり、10月完了。社内試写にかけると、「この映画はホリデーシーズンがよかろう」ということが決まり、2011年の末である12月に公開された。プロデューサーが舞台を観劇してわずか2年。相変わらずスピルバーグの映画制作はやたらと早い。
映画批評集積サイトRotten tomatoでは245件の批評家によるレビューがあり、肯定評価75%、一般レビューも74%と高評価。セントラルオハイオ映画批評家協会賞で作品賞、撮影賞受賞。アカデミー賞をはじめ、様々なアワードでノミネートはされるものの、受賞には至っていない。いい作品なのになぜかアワードに恵まれない……スピルバーグの不遇はいつまでも続く。
では前半のあらすじを見ていきましょう。
イギリス南西部の田舎デヴォン。その牧場で、一頭の馬が出産の時を迎えていた。その様子を、近くに住んでいた少年アルバートが見ていた。
間もなく母馬の腹から小さな子馬が生まれる。額に白いダイヤの模様、足には白の靴下の子馬だった。アルバートはそれからは時々牧場を訪ねては、子馬と交流するのだった。
ある日、父親のテッドは街の競売へと出かける。農耕馬を買うことが目的だったが……テッドはそこで立派なサラブレッドに一目惚れをしてしまう。
競売が始まり、テッドはそのサラブレッドを手に入れようとするが、大地主ライオンズと競い合いになってしまう。とうとう30ギニーという大金を出すことになり、サラブレッドを落札した。
サラブレッドを連れて自宅に帰ると、妻のローズはあきれるが、息子のアルバートは馬を見て大喜び。近所で生まれたあの子馬じゃないか! まさか自分の家に来るなんて……。しかし30ギニーという大金を出してしまい、母親のローズは「家を追い出されるんじゃないか」と危惧する。
アルバートは馬にジョーイという名前を与えて、日々交流を深めていく。アルバートにとっては楽しい日々であったが、大人達の様子は深刻だった。地主のライオンズが小作料の徴収にやってくる。しかしジョーイを買うために大金を支払ったために、テッドにはお金がない。
「下の畑を耕す。秋まで待ってくれ。利息を付けて全額を払う」
テッドは地主にそう約束するのだった。
しかし馬のジョーイはいまだ人も乗せたこともない。農具を着けて働かせることもできなかった。アルバートはジョーイを静かに諭して、農具を着けることを納得させる。
ようやく農具を着けて荒れ地へと出てきたが、ジョーイはなかなかいうことを聞かない。一歩も動かなかったり、かと思ったらアルバートを引きずって走ったり……なかなか思うようにはならなかった。
やがて雨が降り始める。地面が雨でぬかるみはじめる。むしろ都合がいい。
「ジョーイ、わからないだろうけど、僕たち一家のためなんだ。ありったけの力でまっすぐ引っ張ってくれ。いけ、ジョーイ! 前に進め!」
ようやくジョーイが農具を引っ張って歩き始めた。荒れた土地がめくれて、柔らかな土へ耕されていく。雨が降り終える頃には荒れた土地は農地へと変わっていた。
ここまでで前半35分。かなりゆったりペースで、馬と少年の交流物語がじっくり描かれる。
画面を見てみましょう。

撮影のほとんどはイギリス。前半シーンは原作小説の舞台となっているデヴォンで撮影された。風景は見ての通り、抜けがいい。水平線の奥の奥まで見えて、ピントもそこまでぼやけておらず、隅々まで見えるように撮っている。風景がいいものだから、どこにカメラを向けても絵になる。ロケーションをこの地に決めた時点で、色んな意味で「勝ち確定」の映画になっている。

カメラが寄ったところ。カメラが寄ると、さすがに人物にフォーカスがいく。
最初の農場のシーンは、あえてクローズアップ控えめ、風景を中心に描かれていく。風景があまりにもいいので、人物ばかり撮るのはもったいない……という感覚があったかも知れない。

街のシーンはカースル・クームで撮影されている。映画の中では「最寄りの街」となっているが、実際はかなり東の方へいったところにある。人口350人の小さく、美しい町並みであるため、たびたび作品の舞台にされる。アニメ『きんいろモザイク』に出てくるアリスの実家もこの周辺。
この場面では、画面右手、このシーンの主役である人物にだけ強めの照明が当たっている。照明は自然光中心ではなく、意外に作り物っぽい光で作られている。

屋内撮影になると、照明のやや不自然なところが目立つ。最近の映画では、ナチュラルぎみの照明で撮るのだが、本作ではくっきり照明で人物を浮かび上がらせる。もしかすると、これも「時代観」の表現かも知れない。昔の映画は今よりくっきり照明だったから……。

主人公一家の家として使われたのは、重要文化財建築物であるディッツワージー・ウォーレン・ハウス。小作人の家にしては、立派すぎる気が……。3人家族だと部屋があまりそうだし。
見栄えを優先しすぎた結果、「小作人の住宅としてはどうなんだ?」という住居になってしまっている(美しい家だが……)。

前半はかなりゆったりと、「少年と馬」の物語が描かれる。平和な時代を長めに描いているからこそ、後半のドラマが際立っていく。

しかし1914年、第一次世界大戦が始まってしまう。馬のジョーイは「軍馬」として連れて行かれることに。
スティーブン・スピルバーグはこれまで戦争を題材にした映画を撮ってきた(『太陽の帝国』『シンドラーのリスト』『プライベートライアン』)が、いずれも第2次世界大戦。第1次世界大戦時代を描いたのは本作が初めて。

連れて行かれたのはここ。なんだよ、この城は?
ここはウェリントン公爵の邸宅ストラトフィールド・セイ・ハウス。第1次世界大戦は人類史的に始めて近代戦が始まった戦争で、開戦当初はその以前の「古い時代の戦争」を引きずっていた。

この馬に乗って剣をふりかざす人々は、おそらく一般階級ではなく、エリート階級。もしかすると貴族の出身。第一次世界大戦初期は、一般からも徴兵されて戦場へ行く者も多かったが、基本的にはまだ「貴族階級のもの」だった。戦争とは貴族が「名誉のため」に戦いに行くもの、「貴族の義務」で、一般大衆のものではなかった。
(戦争が貴族階級のものだったから、軍馬が集められるのもお屋敷)
貴族階級だから身なりがきちんとしているし、文字の読み書きもできて、絵も描けるし、情緒も豊か。馬を大事にして、馬の飼い主である少年と「男と男の約束だ。必ず馬を返す」と誠実に約束するのも、貴族階級ゆえの性格。そういう性格だから、本当は奇襲作戦なんて卑怯な戦法も採りたくない。こういう時代だから、まだ彼らは「ガトリンクガン」なんて存在すら知らなかったのでは?

騎馬の攻撃を一掃するガトリンクガン。戦争の形が一瞬にして変わる瞬間だった。
この戦いで、イギリス軍は壊滅。ほとんどが戦死、生き残った者は捕虜。ドイツ軍はすでに車移動がメインだったので、馬は不要。「馬は処分してしまえ」と命令されるが「負傷者を運ぶのに使える」と説得されて、ジョーイはかろうじて生き延びる。

ここから画面のトーンが一気に暗くなる。
ドイツ軍の軍馬となってしまうジョーイ。このあたりで映画が始まって1時間。だいたい30分間隔で所有者が変わっていく。ここから後半に向けて、ジョーイの「過酷な旅」が始まる。
ハリウッドでは今でも「ドイツ軍人は悪役として描いてもいい」……という空気があるが、スピルバーグは『シンドラーのリスト』『プライベートライアン』の2作を描いて以降、ドイツ軍人を悪役として描けなくなっていた。この映画における馬好きはすべて善人として描かれるわけだが、ドイツ軍兵士でも馬に関わる人は、特に情緒ある人間として掘り下げられる。

一つ引っ掛かったのは、ドイツ人もフランス人も、みんな英語を喋ること。ハリウッド映画だからみんな英語というのは普通で、こういう指摘も今さらだけど……。
(日本のアニメだって、あらゆる国籍の人が流暢に日本語喋りますし)

戦争の最中だが、フランスに入ってからは故郷を思わせる農家に引き取られる瞬間がある。
『戦火の馬』は「冒険物語」として語ることができる。冒険物語は過酷な旅が続き、後半に向けてトーンが重くなっていくのだが、必ず途中で「休憩所」と呼ばれるような場所が出てきて、主人公達はそこでしばしの安らぎを得る。『指輪物語』でいうところの「裂け谷」がそれ。フランスのこのシーンは、そういう休憩エリアと解釈できる。
ただ故郷のデヴォンほど抜けのいい画面は出てこない。飽くまでもここは戦場の最中にある休憩エリアであるから、スケールは小さい。ただ、映像のポイントというべきか、どの構図を見ても、フランス人一家のこの家が背景に見えるように描いている。

しかしジョーイは再びドイツ軍に発見され、砲台を引く仕事をやらされることに。ここから映画のトーンはずっとこのまま。とにかく画面が暗い。色もモノトーンに近い。場面によってはシルエットのみで描いていて、兵士達の顔がまったく見えない。戦争の非人間性がどんどん進行していく様子が描かれていく。

お話しは最終盤へ。「1918年」と出ているから、第1次世界大戦も最終盤に入っている。戦争の始まりと終わりとで、様子はぜんぜん変わってしまっている。戦争の初期は貴族が中心に立ち、騎兵を突撃させていた。その頃はまだ貴族による「名誉と誇り」の戦争だった。それが次第に一般人による、泥臭い戦争へと変わっていく。
前にも書いたように、第1次世界大戦は「戦争の形」ががらっと変わった戦争だった。まず黒色火薬の発明により、飛距離が伸び、連発が可能になった。その以前の銃は、一発撃つごとに銃身を磨き、一発だけ込めて撃つ……という感じで、早くても数分かかっていた。だからまだ騎兵に優位性があったが、連発可能な銃が出てきてしまって「銃中心」の戦争になっていった。すると戦争は「数頼み」になっていくから、一般人から即席の兵士が作られ、次々に戦場で死んでいく……という地獄が作られていく。
他にも初めての無線通信、初めての毒ガス、初めての航空機爆撃に初めての戦車……。戦争のステージが一つ上がった戦争だった。大量徴兵に大量殺戮、自然破壊も深刻になっていった。この戦争によって、田舎から徴兵された若者達は最新の科学文明に触れ、戦争が終わって故郷に戻ってもカルチャーギャップに悩むようにもなった。
第1次世界大戦の最終盤とともに、馬と少年の物語も収束していく。
はい、まとめです。
原作者であるマイケル・モーパーゴは、どうして戦時中の馬をテーマにした作品を描こうとしたのか? Wikipediaの情報をそのまま書くと、マイケル・モーパーゴはイギリスの田舎であるデヴォンで自営農家の生活を営んでいたのだが、地元のパブには多くの退役軍人たちが通っていた。そのなかで第一次世界大戦の退役軍人と出会い、そこで当時の軍馬の話を聞くことになる。
マイケル・モーパーゴ自身も調査を始めるが、この時代、多くの馬も犠牲になっていた。イギリスからは大陸へ100万頭の馬が送られたが、帰ってきたのは6万2000頭。第1次世界大戦でのイギリス人の死亡者は88万6000人と、こちらもたいへんな犠牲だが、それ以上に犠牲になっていたのが馬だった。
戦争の犠牲になる人間の物語はたくさんあるのに、それ以上に犠牲になった馬たちの物語がないのはなぜか? ……そういう疑問があったか定かではないが、おそらくはそういう経緯で物語が創作された。

感想文の途中にも書いたが、第1次世界大戦は「戦争の形」がガッと変わった戦争でもあった。第1次世界大戦の初期はまだ「ナポレオン時代の戦争」だった。教養豊かな貴族達が馬に乗り、名誉と誇りのために、国家の代表として国と国民を守る――そういう昔ながらの大義のための戦争……というのがまだちょっとだけ残っていた。馬たちはまず、そういう貴族達が乗る馬として徴兵されていた。この時代をわざわざ描いたのは、「馬が戦士として輝いた時代」だったからだろう。
ところが、近代戦争がここから始まる。馬みたいな燃費の悪いものより、トラックに兵士と兵器を乗せて運んだ方が、効率が上。当時からドイツは近代兵器を多く採り入れていたから、馬みたいな旧時代の産物は無用になりかけていた。せいぜい、車両で運びきれないものの補助……のような扱いだった。
余談ながら、ドイツは近代兵器に盲信するあまり、“ぬかるみ”にはまることになる。第2次世界大戦、世界征服を目指すナチスドイツはフランスに勝利し、次はソ連を狙っていた。ところが、そこへ行くための“道”がなかった。ソ連へ繋がる道路などはなく、荒れた土地を進むしかなかったわけだが、そういった土地を車両で進もうとすると、タイヤが“ぬかるみ”にはまりこみ、1日かけても数メートルしか進めない。燃料は無駄に消費するし、兵士は疲労困憊になるし、おまけに寒いしで……。こういう場合、実は車両よりも馬で運搬した方が有意だった。
近代兵器も万能というわけではないのだ。ナチス・ドイツはまず「道路」を作るべきだったが当時の人にローマ人のような発想力はなかった。

話を戻すと、近代戦争が始まろうという最中、馬は無用の長物になろうとしていた。第一、塹壕戦に馬は不要。人間と同じように100万頭の馬が“徴兵”されていったが、その馬たちの多くは戦場で死んだというより、“処分”されてしまった。そんな過酷ななか、生き延びた馬にはどんなドラマがあったのか……。それが本作の大きなテーマとなる。
物語にはその社会におけるどんな問題があるか、人に知らしめる効果がある。人知れず差別を受けていた……そういう人に光を当てるのが物語の効果であるといえる(逆に、「嘘の物語」を世に広める力もあるが……それは別の話)。戦争の物語はたくさん描かれてきたが、その中で「馬」という視点で語られた物語はなかった。
だからこそ「馬の物語」が描かれた。実は人間より過酷な境遇にさらされていた馬たち。その馬たちに向けた謝罪と愛情を向けたのが、本作。馬を愛する人間のために描かれた作品だ。

その劇場版。原作版と舞台版は私は見ていないのだが、どうやらこちらのバージョンには「馬のモノローグ」があったらしい。しかしスティーブン・スピルバーグの映画は、「馬視点のモノローグ」を徹底的に排除。人間的に考える馬ではなく、あくまでも馬は馬らしく描かれた。それでいて、映画の観客に馬がどういう情緒でいるのか、わかるように描く。
そこを徹底しているのは凄いのだが、場面によってはやりすぎで、「馬はそういう仕草はしないんじゃないか?」と疑問に感じる場面もあるにはある。伝わるけれども、過剰にやっているところはある。演出の意図はわかるけれども、さじ加減が難しいところだ。
そういう引っ掛かりは小さなものとして、だいたい無視できる。やはり本作の大テーマは、馬の物語をいかに構築するか。その一点において、見事と言うしかないクオリティ。「馬映画に駄作なし」……これは私の個人的な持論だが、本作の存在を持って、また「馬映画に駄作なし」が証明された。しかも馬映画の中でも名作と呼べる傑作。馬を愛するものはぜひ押さえておくべき作品だ。
いいなと思ったら応援しよう!

