
追悼 佐藤忠男
2022年3月17日に映画評論の第一人者、佐藤忠男氏が亡くなった。享年91歳。
高校生の頃、金沢で観たジム・ジャームッシュ監督『ダウン・バイ・ロー』に感激して以降、フランス映画社のバウシリーズをはじめ、ロッセリーニ、フェリーニ、ゴダール、小津安二郎や溝口健二、川島雄三等々、古今東西の文芸映画を探しては観るようになった。
そして、当時から、多くの映画のパンフレットで目にしていたのは「佐藤忠男」という名前だった。
以降、忠男先生と呼ばせてただくが、忠男先生は、映画評論家としてだけでなく、若手の映画映像振興事業をご一緒させていただき、大変お世話になった方だった。
忠男先生とご一緒した日々は本当に貴重だったし、どれだけの出会いや学びをいただいたかわからない。忠男先生なくして、私たちの今はないとはっきり断言できる。
この場を借りて改めてお礼申し上げるとともに、忠男先生とご一緒した事業について、noteに書き残しておこうと思う。
ただの個人の記録なので、正直、読まれる方にとってはあまり面白くないと思う。しかも、5000字超えてしまったし。すみません…。
アートイベントプロデュース
2001年4月。
私たち夫婦は、ひょんなことから横浜でアートイベントをプロデュースする羽目になった。
長女が2歳の頃で、何をして生きていけばいいのか模索している最中だった。
「横浜市開港記念会館という国の重要文化財(通称:ジャックの塔)で、芸術プログラムを組んでほしい」と、同館を管理している横浜市中区役所地域振興課の課長から依頼されたのだ。
「予算はありません。でも会館は無料で使えます。」
という条件だった。
夫は頼まれると断れない性格なので、色々な人に相談し、一流の音楽家やパフォーマーを招聘した非営利コンサートシリーズを開催することに。
未就学児や障害のある方も一同に介して、色々な人が場を共有することで新しい文化が創出されると確信して、中学生以下無料、障害のある方と介助者無料、一般の入場料も1,980円〜2,500円という破格の料金を設定した。
このシリーズは7年間72回まで続けられた。
ジャズ、日本舞踊、前衛舞踏、即興、邦楽から現代音楽に至るまで様々なジャンルの一流の方々が趣旨に賛同してパフォーマンスしてくれた。
その間に2歳の長女は9歳に、2人目、3人目と生まれて、主催者自身、背中に末っ子をおんぶし、未就学児の長女、長男がコンサートを手伝っているという混沌とした中で実施した。
横濱学生映画祭開催(2002〜2009年)
シリーズを始めて2年目。
夫に日本映画学校(現:日本映画大学)の卒業制作の音楽をつけてほしいという依頼がきた。
ボランティア仕事ではあるけれど、夫は、若者たちが一つの映画制作の中で激論を交わし、作り上げる姿に感動し、引き受けたのだ。
制作した卒業制作の発表が終わった時、夫は当時日本映画学校の校長だった忠男先生にこう言われた。
「学生映画には、学生の頃しか描けない貴重なものがある。うまい下手以上に、その感性で、その時期でしか伝えられないものがある。しかしそれらは、商業ベースには乗らないから、なかなか上映される機会がない。」
日本映画学校の卒業制作に参加して、忠男先生の教育方針にすっかり惚れ込んでいた夫は、横浜市開港記念会館で主催している芸術プログラムの一環として、映画祭を開催できるんじゃないか、と思いつく。
そんな経緯で映画ド素人、映画祭未経験の私たちは、2002年から学生映画祭を始めることになった。
題して「横濱学生映画祭」。


忠男先生とのおつきあいはここから始まった。
日本には相当数の映画映像の専門学校・大学がある。
学生映画祭を始めるにあたり、「せっかくだから、学生映画を一堂に会したらいいんじゃないか。」ということになった。
何もわからず始めた超手作り・手弁当の学生映画祭。
折しも横浜市は、中田宏市長の元、映像文化都市宣言をし、映像文化に注力し始めたところ。翌年には映画祭を共催したいと申し出があった。
中国日本学生映画交流シンポジウム(2003年)
転機は2003年年末。
第2回の学生映画祭を終えた私たちに、あるメディア系の知り合いからこんな話が舞い込んだ。
「中国共産党が、文化政策方針を変換した。中国最高峰の北京電影学院の院長が、日本の各映像教育機関と連携したいと言っている。学生映画祭をやっているんなら、各学校の先生を集めてくれないか?電影学院の先生方を招聘してシンポジウムを開催してほしい。」
当時横浜では、歴史的建造物を文化施設として活用できないかという話がもちあがったばかりで、のちにBank ARTになる、旧第一銀行のホールを使えると横浜市の関係者に言われた。2004年の本格始動の準備ということで、実験事業をしたいという同市のニーズにマッチしたのだ。
今思えばこれもドンピシャのタイミングだった。
*奇しくも、Bank ART1929の運営をされていた池田修氏も3月16日に亡くなった。心よりご冥福を申し上げる。
シンポジウムには当時北京電影学院の学院長であった張会軍氏、副学院長の謝小晶氏はじめ、関係者が初来浜。
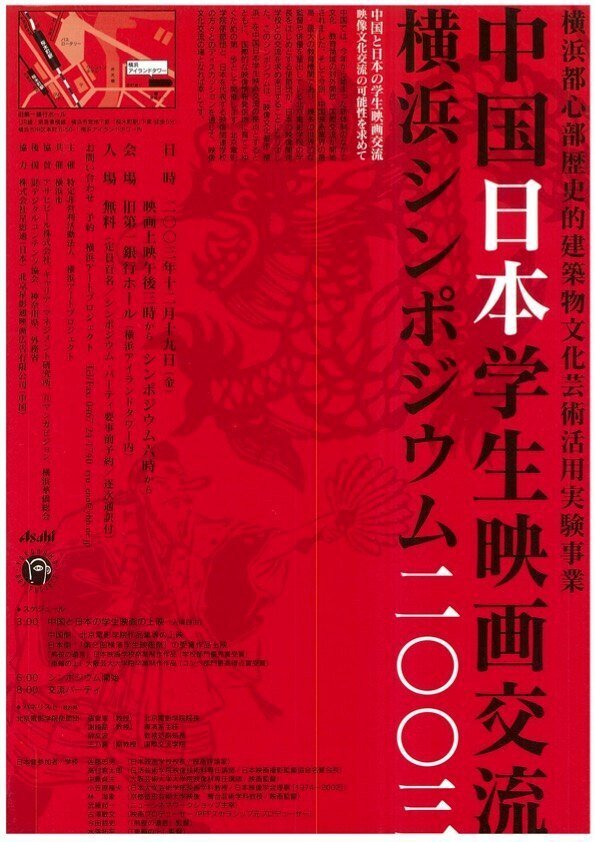
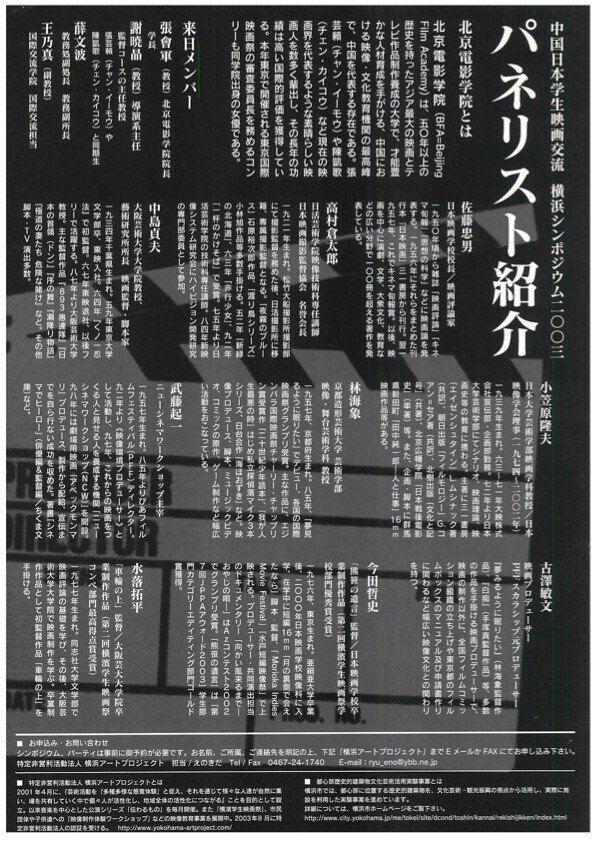
張元学院長は、いわゆる第五世代。チェン・カイコーやチャン・イーモウらと同期である。彼らをはじめ、中国のメディア教育機関では、忠男先生の著作物が教科書として長く読まれてきた。彼らの間で、忠男先生はまさに神。
日本の映画をアジアの諸地域に紹介し、また、アジアの映画を日本に紹介した大恩人なのだ。
当時の学院長はじめ、来日した中国の先生方がどれだけ感激したかは、我々のような無名の人間がプロデュースする小さな映画祭に、翌年から参加したいと申し出たところでも十分理解できる。
そこから、中国の北京電影学院との付き合いが始まった。
2012年、中国中央電視台(CCTV)に東日本大震災の特別番組を組んでもらったり、2016年の熊本地震や2018年の北海道地震の後の中国インバウンド拡大のため、SNSでの拡散コンテンツを制作してもらったり、と色々な形でコラボしている。
また、シンポジウムには、日本からも各映画映像教育機関から、錚々たる関係者(佐藤忠男氏、撮影監督の高村倉太郎氏、中島貞夫監督、小笠原隆夫氏、林海象監督、古澤敏文プロデューサーほか)が、手弁当で集まってくださった。
今思えば、震えがくるほどの強者揃いである。そういった方々が快諾してくださったのも、忠男先生の吸引力だとしか思えない。
*同映画祭は、場所を東京都墨田区に移し、2010年、2012年にTokyo Downtown Cool Media Festivalとして開催
日中韓共同・横浜開港150周年記念映画製作事業(2006~2009年)
映像文化都市宣言下の横浜は、2009年に開港150周年を迎えるということで、当映画祭にも「記念になるものを何か作ってほしい」という打診があった。
2005年から韓流を仕掛けた国立韓国フィルムアカデミーも参加し、日中韓で開催してきた同映画祭。
是非とも3国の若者で共同製作映画を作ろうということになった。
日中韓共同の映画製作。
それは、映画関係者にとっては悲願だった。
日本、中国、韓国という東アジア3国は、戦争により近くて遠い国になってしまい、歴史認識の違いで、とても共同製作は難しいと言われてきたのだ。
しかし、当映画祭は次世代の担い手を育成する映画祭である。
若手を育てるという名目なら、3国での製作も可能だろう、と。
なんと言っても、忠男先生を旗印とした信頼関係ががっちりできてきている。
そこで、まず準備として、2006年に日本に韓国と中国の若者を招聘し、ドキュメンタリー映画を製作、同映画祭にて発表し、シンポジウムを行った。
実際の映画の製作は2008年なのだから、異例の長丁場である。
通常の現場なら、こんな無駄なことはしないだろう。
しかし、若手育成の目的だから、そういったこともできた。
忠男先生も炎天下の撮影現場に来てくださったりして、いつも気にかけてくださった。

とはいえ、3国で一つの映画を製作するのは現実的に無理がある。
そこで「三つの港の物語」というタイトルとして横浜、青島、仁川という三つの港を舞台とした物語のオムニバス映画として製作した。
途中、韓国作品の監督が行方知れずになるなど、想定外だらけとなり、困難を極めたけれど、なんとか2009年春に完成した。
忠男先生も、奥様の久子さん(映画プロデューサー)も大変喜んでくださった。
早速忠男先生から原稿をお預かりして、以下にも掲載させていただいた。
ウルトラマン事件
実はこの映画の青島編に、ウルトラマンの人形が出てくるシーンがある。
横浜の開港記念ということで、中国の監督が気を遣って入れてくれたシーンだった。
完成間近になって、これは円谷プロに許可が必要だ、となり、慌ててお伺いを立てるも、なんと、中国で購入したというウルトラマン人形が偽物だった。(中国あるあるですね笑)
円谷プロに相談したら「本編に出てくる人形はウルトラマンとは無関係です」というテロップを入れてほしいというリクエスト。
せっかくの友情に水を差すようで、申し訳ないやら興醒めやら。
一連のやり取りをするために、忠男先生と円谷プロ(権利関係は全てTYO管理)に挨拶に伺った。
上記のような次第で、まぁ、なんとか事なきを得たのだが、
印象的だったのは、久子夫人に携帯で電話し、その都度状況を報告する忠男先生のお姿。
失礼だけど、なんとも可愛らしく、微笑ましいものだった。
フィルム芸術としての映画
そんなこんなで、横浜を中心に2002年から2012年までの約10年間、忠男先生とご一緒させていただいた。
今思えば、その10年間は、映画がフィルム芸術として、最後の煌めきを持っていた頃だったかも知れない。
例えば、日本映画学校では、卒業制作は16ミリで撮影されていたし、北京電影学院も韓国フィルムアカデミーも35ミリだった。
そして奇しくも、その時期に当映画祭に出品してくれた学生たちは、
いまや正に日本映画の中枢を担う映画人に育っている。
渡辺紘文監督(『8月の軽い豚』で出品/ 『三つの港の物語』の日本編を監督)、石井裕也監督(『剥き出しにっぽん』で出品)、そして、深田晃司監督(『椅子』で出品)など。
最後にお目にかかった時のこと
最後にお目にかかったのは、2018年に引き受けた仕事、「橋本忍生誕100周年記念事業」だった。
どんな事業が、巨人・橋本忍の生誕を祝うに相応しいか、相談に伺ったのだ。
2度ほど、お邪魔してお話ししたけれど、淡々とした話しぶりは相変わらずで、ありがたい気持ちになったものだった。
実は私は、その時、忠男先生に言葉遣いを注意された。
忠男先生に対してではなく、他の方のことを話していた時にふと出てきた言葉の意味が、先生に引っかかったのだ。
「君、それはちょっと違うんじゃないか。そういう言い方をしたら別の意味に取られちゃうよ。」
そんなふうに諭してくださった。
後日、お詫びに伺った時にはご不在だった。
その場で便箋3枚くらいのお詫びの手紙を書いて、置いていった。
もちろん、先生からはお返事はなかった。私も気になりながらも、その後連絡することはなかった。
最初の最後で先生に諭されたことは、後悔とも申し訳ないともつかないような、なんとも言えない気持ちになって、今腹の中に蟠っている。
映画人生
2009年の共同製作映画が完成した頃、当時事務所にしていた横浜の共同オフィスで、忠男先生を前に「ポルトガルのオリヴェイラ監督にしても、新藤兼人監督にしても、映画人はみんな長生き。先生もまだまだ頑張ってくださいよ。」と、日本映画学校のIさんと一緒に話したのを覚えている。
忠男先生は、私たちの期待通り、最後まで映画評論への情熱を失わなかった。
忠男先生、長い間本当にお疲れ様でした。
私たちのようなズブの素人が、忠男先生と同じことを目指し、同じ世界を描く、という大変な光栄を預かりました。
またお目にかかれる日には、もうちょっとマシな人間になれるよう、言葉遣いに気をつけて、日々精進します。
本当に、本当にありがとうございました。
<関連note>
横浜でアートイベントを主催していた頃の話↓
その他、映画祭のチラシなどです↓
チラシやパンフレットの多くは、本の装丁や本文組のデザイナーとして活躍されている細野綾子さんにデザインしていただきました。(今思えばなんて贅沢な。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
