
小学生・中学生からの50の質問
日本トイレ研究所では、トイレや排泄の大切さを伝える活動として、11月10日(いいトイレの日)~11月19日(国連・世界トイレの日)に、「トイレweek」という活動を実施しています。
その一環として小学生・中学生から質問を募集したところ、たくさんの質問をいただきました。
そこで、重要な問いや質問数の多かったものなど、50問をピックアップして回答を作成しました。医学的なことについては排便・排尿が専門の医師に監修いただきました。
学校の先生や保護者の皆さまには、ぜひ子どもたちに伝えていただけると嬉しいです。大人にもためになる質問がたくさんありますので、これをきっかけにトイレや排泄について一緒に学んでいただければ幸いです。
いいうんちをする方法について(6問)
Q.1 いいうんちをするにはどうしたらいいですか?
いいうんちというのは、するっと楽に出せるうんちです。うんちをしたあとに、すっきり!と感じられることが大事です。形は、バナナのような形が多いです。色は黄色っぽい茶色で、においはほとんどくさくありません。
このようないいうんちをするには、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんをよくかんでたくさん食べること、昼間は元気よく体を動かして遊ぶこと、夜はぐっすりねむることです。とくに朝ごはんのあとは、うんちをしたくなりやすい大事なタイミングです。あせったり、あわてていたりすると、うんちが出にくくなる、また緊張している時も腸の動きが悪くなるので、リラックスすることが大切です。

Q.2 便秘のときに食べると良い食べ物は何ですか?
いろいろな食べ物をバランスよく食べることが大切です。食物繊維(しょくもつせんい)が含まれている食べ物(ごはん、そば、いも、きのこ、野菜、海藻など)はうんちのもとになるので、いいと言われています。
一番大切なのは、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんをよくかんでたくさん食べることです。毎日、だいたい同じ時間に食べることも大事です。そうすることで、からだがリズムをおぼえるので、それにあわせてうんちが出やすくなるからです。

Q3. 健康なうんちを出すためにはどんな食べ物がいいですか?
健康的な、なめらかバナナうんちをするには、いろいろな食べものを好ききらいせずにバランスよく食べることが大切です。なかでも、食物繊維(しょくもつせんい)がたくさん入っている食べもの(ごはん、そば、いも、きのこ、野菜、海藻など)がおすすめです。よくかんで食べるようにしましょう。食べものはとても大事ですが、ぐっすりねむること、からだを動かすことも大事です。たとえば、バランスよく食べても、ねぶそくだといいうんちが出ないことがあります。
Q4. 便秘を解消する方法を教えてください。
便秘を解消する方法はたくさんあります。まずは、いろいろな食べものをバランスよく食べることが大事です。よくかむこと、水分をとること、ぐっすりねむること、元気よくあそぶこと、毎朝トイレに行くことなども大事です。また、毎日決まった時間に起きる・寝る、同じ時間に食事をするなど、生活リズムをたもつことで、うんちをするリズムもととのってきます。便秘はほうっておくとひどくなりますので、よくならないときは、おうちの人に相談しましょう。

Q5. 1日にどのくらい水を飲めばうんちがスムーズに出るようになりますか?
たくさん水分をとったからといって、うんちがスムーズに出るようになるわけではありません。からだが求める以上にたくさん飲んだ場合、それはおしっこになって出ていってしまいます。
食事のときや、水分がほしいなぁと感じたとき、汗をかいたとき、運動のあとなどに、しっかり水分をとっていれば大丈夫です。ただし、からだの水分が足りなくなると具合が悪くなるし、うんちも出にくくなるので注意してください。

Q6. うんちは毎日出た方がいいのですか?
食事をするたびにうんちが出る人もいれば、毎日1回の人もいます。2~3日に1回出る人もいます。もっとも大切なのは、うんちをしたあとにすっきりすることです。2~3日に1回だとしても、とてもすっきりする感じがすればよいです。逆に、毎日うんちが出たとしても、おなかがはっていたり、残っている感じがしたりするのは、よくありません。このように回数は人によってことなりますが、4日に1回とか、5日に1回しか出ないのは心配ですので、おうちの人に相談してみてください。
うんち・おしっこの仕組み(13問)
Q7. おしっことうんちはどのように作られるのか教えてください。
おしっこは、人間の体の中を流れている血液から作られます。体の中を移動している血液は腎臓(じんぞう)で、いらないなものと余分な水分が取りのぞかれます。これらのいらないものを膀胱(ぼうこう)にためていきます。膀胱はおへその下あたりにあるおしっこをためる風船のような入れものです。膀胱が満杯になると、脳に「おしっこしたい!」という連絡をします。膀胱にためられた尿は、尿道というおしっこの通り道を通って体の外に出ます。

うんちも、体にとっていらなくなったものです。食べたものを胃でドロドロにした後、小腸に送って栄養を吸収し、大腸に移動させて水分を吸収します。体に取り込まれなかった食べ物の残りと腸の中にいる目に見えないぐらいの小さな菌、そして大腸で吸収されなかった水分が混ざったものがうんちです。大腸の中を運ばれてちょうどいい形、量になったら、おしりの穴(肛門)から体の外に出します。

Q8. うんちとおしっこってどうして出るところが違うのですか?
うんちとおしっこは、体にとっていらないものであることは同じですが、体の中の別のところを通って、作られ、出てきます。
おしっこは、体の中を移動している血液が、腎臓(じんぞう)で不要なものと余分な水分を取り除かれたものです。これらのいらないものを膀胱(ぼうこう)にためていきます。膀胱はおへその下あたりにあるおしっこをためる風船のような入れものです。膀胱が満杯になると、尿道というおしっこの通り道を通って体の外に出ます。
うんちは、食べたものが胃でドロドロになった後、小腸に送られて栄養が吸収され、大腸に移動して水分が吸収された後に残ったもので、ちょうどいい形になったら、おしりの穴(肛門)から体の外に出します。

Q9. トイレに行きたくなるしくみを知りたいです
トイレに行きたくなるのは、うんちをしたいときと、おしっこをしたいときです。まずはうんちから説明します。うんちは大腸というところでつくられます。うんちが出来上がったら、肛門の近くにある直腸という場所に運ばれます。すると「うんちしたい!」という信号が脳に送られるので、みんなはトイレに行きたいと感じます。
つぎに、おしっこについて説明します。おしっこは、膀胱(ぼうこう)という、おへその下あたりにある風船のような入れものにためられます。この風船はおしっこがたまっていくとふくらんでいき、ある程度いっぱいになると「おしっこしたい!」という信号を脳に送ります。このとき、トイレに行きたくなります。どちらもがまんしすぎるとからだに良くないので、信号が来たらあまりがまんをしすぎないようにトイレに行ってくださいね。

Q10. うんちの出る時と出ない時の違いがあるのはどうして?
おなかの中にある大腸というところでうんちはつくられます。うんちがたまっていなかったり、うんちとして外に出す準備ができていないと、がんばっても出ません。
それとは別に、うんちをしたいときにがまんばかりしたり、野菜ぶそく、ねぶそく、運動ぶそくだったりすると、便秘になります。便秘というのは大腸にうんちがたまって出にくい状態です。かたいうんちやコロコロのうんちが目印です。便秘になると、がんばって力をいれてもうんちは出にくいですし、おしりも痛くなってしまいます。こうならないように、朝ごはんをしっかりたべる、外で元気よく遊ぶ、ぐっすり眠ることを気にしてくださいね。
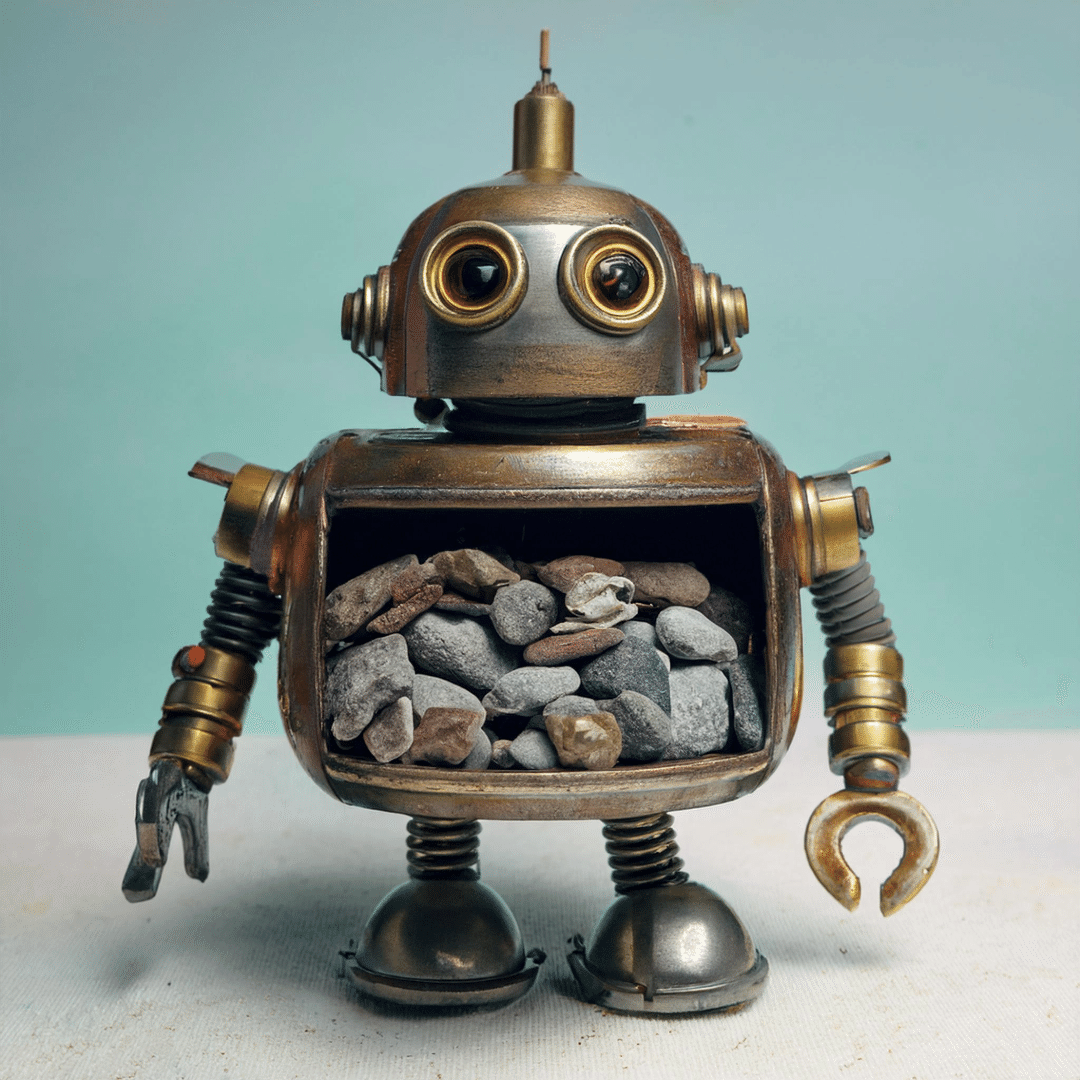
Q11. うんちはなぜ臭いのか知りたいです
いいうんちは、そんなにくさくありません。たとえば、赤ちゃんの腸にはビフィズス菌といういい菌がたくさんいるので、いいうんちがつくられてにおいもくさくありません。大きくなるにつれて、腸の中にいろいろ菌がふえていきます。いろいろな菌がバランスよくいることが大切なのですが、肉やあぶらっこいもの、お菓子ばかりを食べていると、わるい菌がふえてしまいます。このわるい菌に肉やあぶらっこいものの食べかすを与えてしまうと、くさいガスが出るので、うんちもくさくなってしまうのです。
でも、肉やあぶらっこいものが悪いわけではありません。大切なのはバランスです。野菜や魚、くだものなど、いろいろなものを食べることで、腸の中にいる菌のバランスもよくなり、うんちがあまりくさくなくなっていきます。もし、うんちがくさいなと感じたら、食物せんいがたくさんふくまれている食べものをたべてみてください。
また、うんちがたまり過ぎると腸の中の菌のバランスが悪くなり、臭くなります。溜めすぎないようにしましょう。

Q12. ドロドロうんちが出る時におなかがグーッとなるのはなんでですか?
水分やガスがいっしょになって胃や腸の中を移動するときに、グーっとなったり、音がなったりするといわれています。ドロドロうんちのときは、栄養や水分をからだにうまく取り入れられていないことが考えられます。いいうんちのときは腸の中をゆっくり移動するのですが、ドロドロうんちやしゃばしゃばうんちのときは、ふつうより速めに移動します。そのときに、腸が大きく動いておなかがグーっとなるのです。

Q13. 食べたものによってうんちが変わるのはなぜですか?
うんちは食べたものから栄養や水分をからだに取り込んで、そのあと残ったものなどでできていますので、食べたものによってうんちは変わります。ちなみに、うんちの大部分は水分で、食べかす、腸の中にすんでいる菌、はがれた腸の壁などでできています。
たとえば、食物繊維(しょくもつせんい)が多くふくまれるを食べものをたべると、そういうものは固すぎて身体に取り込まれませんので、食べかすが増え、うんちの量が増えてやわらかくなります。食物繊維は腸の中にいるいい菌のエサになるのでおなかの調子がよくなります。
また、からだのなかのいらないなものをうんちとして取りまとめる役割もあります。うんちはかたすぎてもダメだし、やわらかすぎてもダメです。ちょうどよい感じにするには、いろいろなものをよくかんで食べることも大事です。においの強い食べものを食べると、うんちのにおいが強くなることもありますよ。

Q14. 胃や腸の役割について詳しく知りたいです
胃や腸は、からだに栄養や水分を取り込むための大切な役割をもっています。胃は、食べたものをためて、小さくほぐして、ドロドロにして栄養を取り込みやすい形に変えます。このとき、胃液(いえき)というものが出て、ドロドロにしやすくするとともに、この中にいる菌などをやっつけます。
次に小腸です。ここではドロドロになった食べものを運びながら、消化酵素(こうそ)と呼ばれるものをまぜて、栄養をより取り入れやすいように変えます。そして、栄養をからだに取り入れます。大人の小腸はおよそ6mぐらいあります。
次に1.5mぐらいの長さの大腸に運ばれてからだに水分やミネラルを取り入れながら、いらないなものをこねてうんちをつくり、からだの外に出しやすくします。
ちなみに小腸と大腸には、目に見えないくらい小さな生きものである腸内細菌(ちょうないさいきん)が100種類・1000兆個ぐらいいるといわれています。これらの生きものは、ドロドロにできなかったものをエサにしてエネルギーをつくりだしたり、病気にならないようにする力をつよくしたりするなど、いろいろな働きをしています。とても大切なのですが、どのように役立っているのかまだまだわかっていないことがたくさんあります。
私たちが栄養や水分を取り入れて元気に過ごし、うんちをすることで健康でいられるのは、胃や腸のおかげなのです。

Q15. どうやって腸内細菌が働いているのですか?
腸のなかには数百種類、約40兆個の目に見えないくらい小さな生きもの(腸内細菌)がいます。どんな菌がどれくらいいるかは、1人1人ことなります。腸内細菌は腸の中で食べものを人のためになるものへと変えたり、からだによいものをつくったりします。食物繊維は腸のなかで腸内細菌のエサになって、免疫力(悪い細菌から体を守る力)を高めてくれるといわれています。
Q16. 1週間うんちが出なかったらどうなりますか?
1週間もうんちが出ないと、おなかがはって痛くなったり、心や体がつらくなったりしてしまいます。ごはんも食べる気にならなくなったり、吐き気が出ることもあります。うんちは大腸のなかにたまっているあいだに、水分がどんどん吸収されて、かたいうんちになってしまいます。また、とても太いうんちになることもあります。こういううんちを出すのはとても苦しく、うんちを出すときにすごく痛くて、血が出ることもあります。
いいうんちをするには、たくさん食べること、元気よく体を動かして遊ぶこと、夜はぐっすりねむることが大切です。うんちをしたくなったら、がまんせずにトイレに行くようにしましょう。

Q17. トイレに行かない場合、体にどのような影響がありますか?
うんちやおしっこは体にとっていらないものなので、トイレで出すことが必要です。体の中にうんちがたまっていると、おなかがはって痛くなったり、腸内細菌のバランスがくずれたりします。おしっこをためすぎると、膀胱(おしっこをためる風船のような入れもの)で悪い細菌がふえて、病気になることがあります。また、おしっこを作って膀胱に送っている腎臓(じんぞう)の具合が悪くなって病気になることもあります。
そのほかにも、気持ち悪さやストレスが大きくなり、生活がうまくいかなくなります。がまんせずにトイレに行きましょう。

Q18. なぜ人はうんちやおしっこをするのか知りたいです
うんちとおしっこは、食べたり飲んだりした後に残った体にとっていらないものです。いらないものを体の中に留めておくと、体にとって良くないことが起きます。健康に過ごすために、うんちやおしっこをすることは大切なことです。

Q19. おなかが鳴るのはなぜですか
水分やガスがいっしょになって胃や腸の中を移動するときに、グルグル、ギュルギュル、ボコボコというような音が鳴ります。とくに胃や腸が大きく動くときに鳴りやすいです。たとえば、胃が空っぽでおなかがすいているときは大きく動くので鳴りやすいです。また、食事のあとは、胃や腸が元気に動こうとするので鳴りやすいです。人によっては、牛乳やヨーグルトを食べたときや、からい物を食べたときに鳴りやすい人もいます。炭酸の飲みものも鳴りやすいと思います。あとは、おならをがまんしている状態は、腸にガスがたまっていることになるので、おなかが鳴りやすいです。
おなかが鳴ることは悪いことではないので、心配する必要はありません。ただ、おなかが鳴るときにゲリになったり、はきけがしたり、気持ち悪くなる場合は、良くないときですので、おうちの人に伝えてください。

うんちと体調(6問)
Q20. うんちが出るとどうしてすっきりするの?体調とどう関係するの?
体の中のいらないなものが外に出ていくので、うんちが出るとすっきりします。詳しく説明すると、うんちは大腸の中を移動して、おなかの左下あたりの大腸で体の外に出る準備をしています。それがご飯を食べるなどの何かのタイミングで、もともとはぺちゃんこの直腸(肛門のすぐ近くの腸)に移動すると私たちは「うんちをしたい!」と感じます。そしてトイレでうんちをすると、直腸の中がまたぺちゃんこになるので、その合図としてすっきり!と感じるようになっています。
ごはんをしっかり食べなかったり、寝不足だったり、体調が悪いときなどは、うんちが出にくくなることがあります。また、うんちをがまんして体の中にずっとためてしまうと、体調が悪くなってしまうこともあります。うんちと体調は深く関係しています。
Q21. うんちを見て体の健康状態や調子が分かるのですか?
うんちを見ればからだの健康状態や調子がわかります。やわらかくてするっと出るバナナのようなうんちは健康でからだの調子がいいサインです。
コロコロだったり、ゴツゴツだったりで、たくさん力を入れないとでないようなかたいうんちは便秘です。おしりもいたくなります。お肉やお菓子ばかりたべて、野菜やかいそうなどが足りていないときになりやすいです。ねぶそくのときもなります。
ドロドロやしゃばしゃばのうんちはゲリです。栄養や水分をからだにうまく取り入れられないときやよくないものを急いでからだの外に出さなきゃいけないときになります。こういうときは、おなかをあたため休ませてあげてください。あぶらっぽいものや冷たいものはよくありません。ごはんをたべるときはいつもよりよくかんでたべることでおなかを助けてあげてください。もしも、うんちに血が混じっていたり、色がいつもと違ったりしているときは、からだの中に何か問題があるかもしれません。うんちをよく見ることが大事です。
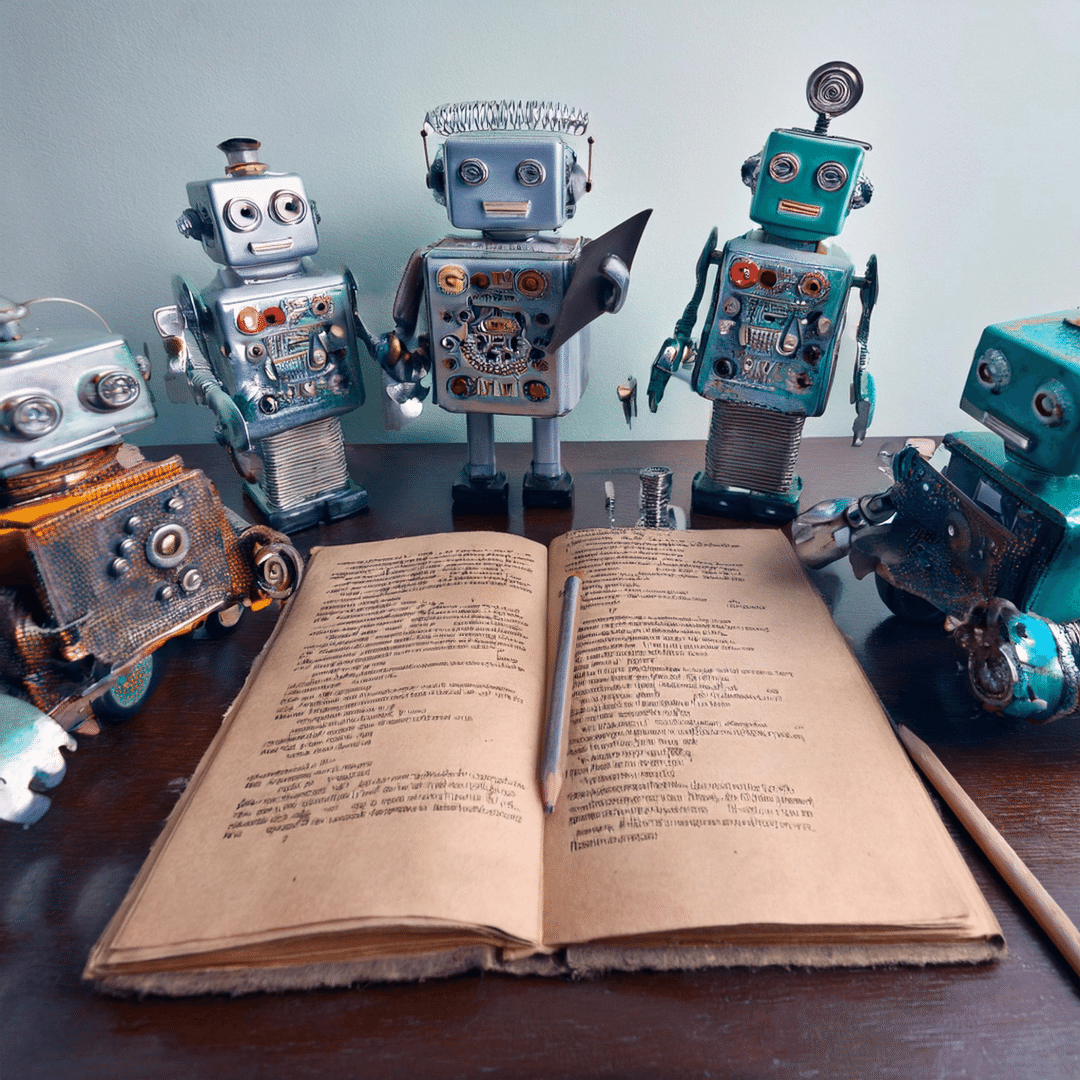
Q22. うんちチェックシートなどを使用して何を調査しているのか気になります。

食べるものは、栄養やアレルギーなどいろいろと気にしますが、うんちを気にする人は多くありません。ですが、うんちを見ることでからだの健康や調子がわかります。うんちを見ることの大切さと、どういううんちがよくて、どういううんちがよくないのかをおぼえてもらうために、うんちチェックをしてもらっています。
また、一人ひとりがきろくしてくれたチェックシートを集めることで、日本の子どもたちが1週間に何回くらいうんちが出るのか、そのうんちはかたいのか、やわらかいのかなどが分かります。これは子どもたちが健康なのか、そうでないのかを知るのに役立ちます。子どもたちの生活をよくするためにとても大切な調査です。

Q23. 朝早くトイレに行ってうんちが出ることは重要ですか?
朝、トイレでうんちが出ることは重要です。朝起きて水を飲んだりごはんを食べたりすると、胃や腸が目を覚まして大きく動きます。この動きで「うんちをしたい!」と感じるのです。このときにトイレに行くと、スムーズにうんちを出すことができます。朝うんちが出ると、一日を気持ちよく過ごすことができます。うんちを出しておなかがスッキリすると、気分がよくなり、集中力も高くなります。
ですが、一番重要なのは毎日うんちを出すことですから、朝にこだわらなくてもいいですよ。

Q24. 朝食後にトイレに行きたくなるのはどうして?
朝、しっかり水分をとり、よくかんでたくさん食べると、胃や腸が目を覚まします。そして胃も腸も元気よく動きます。この動きにより、栄養や水分がからだに取り込まれ、いらないものをうんちとして外に出す準備をします。うんちが肛門(こうもん)の近くまで運ばれると「うんちしたい!」という信号が脳に届くのです。この信号をむししてがまんすると便秘になってしまうことがあります。朝、トイレに行くという習慣をつくるのは大切なことですが、「うんちをしたい!」という信号が来ていないときにおなかに力をいれてもうんちは出ないので、そういうときは無理せず、しんこきゅうをするなどリラックスをしてうんちをしたくなるのを待ちましょう。
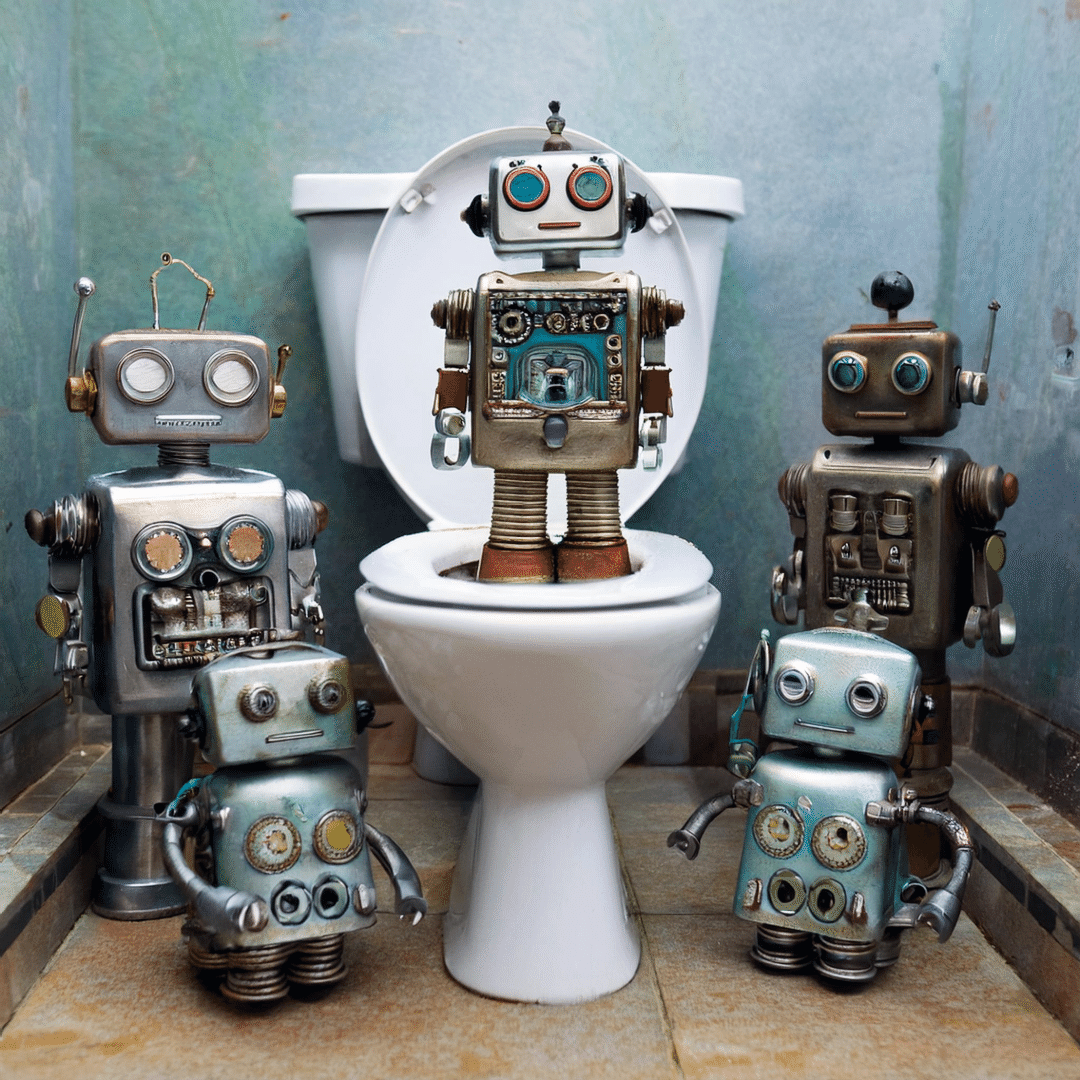
うんちの色・形・成分(3問)
Q25. うんちのかたさや柔らかさがなぜ変わるのか、健康状態との関係について教えてほしいです
健康状態は、食べ物、水分、運動、睡眠、心など、あらゆることが関係します。そしてこれらはすべてうんちのかたさに関係します。健康の状態によって、胃、小腸、大腸の活動が変わるので、うんちのかたさも変わるのです。一つ分かりやすい例を言うと、大腸の動きが弱くなるとうんちが大腸の中に長い時間とどまることになります。そうすると大腸に水分をたくさん吸い取られてしまうので、うんちはかたくなっていきます。そして、うんちがかたい状態が続くと出しにくくなってしまいます。
うんちがかたくなって出しにくくなり、それで健康状態が悪くなることもあります。

うんちの色・形・成分(2問)
Q26. うんちが茶色なのはどうしてですか?
おなかの中では、食べたものをドロドロにして、栄養として体にとりこむ作業が行われます。この作業のときに必要なものの一つが胆汁(たんじゅう)と呼ばれる液体で、肝臓でつくられます。胆汁がまざると、栄養をからだに取り入れやすくなります。エネルギーのもとになる脂肪も取り入れやすくなります。また胆汁には体にとっていらないなものをうんちと一緒に出す役割もあります。この胆汁の色が茶色なので、うんちの色も茶色っぽくなるのです。
ここからちょっとむずかしいですが、胆汁についてもう少しくわしく説明します。胆汁は緑色ですが、腸の中にいる目に見えないくらい小さな菌(腸内細菌)が胆汁の中の成分をいろいろと変化(ビリルビン→ウロビリノーゲン→ステルコビリノーゲン)させ、最後に便と一緒になってからだの外に出します。ステルコビリンの色が、うんちを黄土色~茶色くします。

Q27. うんちの成分や中身は何か気になります
うんちは食べ物から栄養を体に取り込んだ後にのこったものや、腸の中にいる目に見えないぐ小らいさな菌(細菌)、腸のかべがはがれたもの、そして水分です。からだにとっていらないなものをうんちという形にしてからだの外に出してくれているのです。
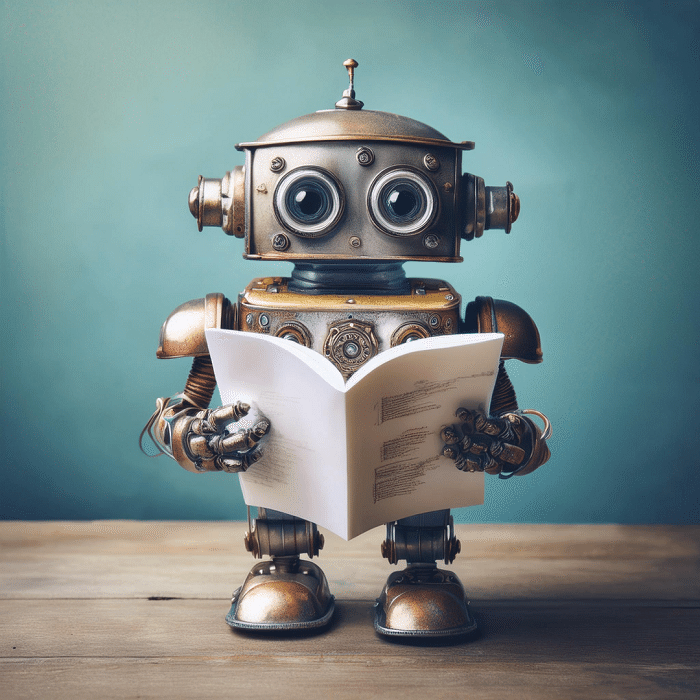
おなかが痛くなることについて(7問)
Q28. どうしておなかが痛くなるんですか?
おなかが痛くなる原因はいくつかあります。食べすぎたり、ばい菌がついているものを食べたり、くさったものを食べたりすると痛くなります。
また、ストレスや緊張などによる痛みもあります。さらに、胃や腸の病気、感染症などの病気による痛みもあります。うんちをがまんしてしてしまい、体の中にずっとためてしまうと、うんちはどんどん硬くなって出にくくなり、おなかが痛くなることもあります。
Q29. おなかが痛い時にはどうすればいいですか?
おなかが痛くなる原因によって、どうすればよいかは異なります。
食中毒、病気、感染症などによる痛みの場合は、病院で治療してもらうことが必要です。ストレス、緊張や、うんちが出にくいときの場合は、おうちでできることもあります。おなかをあたため、からだを休めてリラックスすることが大事です。少し休んでいてもよくならない場合は、そのままにせず、おうちの人や学校の先生に伝えてください。

Q30. おなかが痛くなるのを予防する方法はありますか?
食事をする前に必ず手洗いをしてください。そうすれば、食中毒や感染症を防ぐことができます。
うんちがしたくなったらがまんしてはダメです。がまんするとうんちが出にくくなるからです。また、毎日、朝ごはんを食べること、好き嫌いせずにいろいろな食べ物をバランスよく食べること、よく運動すること、寝不足にならないようにすることなど、生活リズムを整えることも大切です。生活リズムを整えると、うんちが楽に出るし、だいたい決まった時間にでるようになりやすいと思います。でも、怖い病気の中には予防できないものもありますから、痛い時は、Q28. のようにしてください。

Q31. おなかが痛くなってトイレをした後またおなかが痛くなります。どうすればいいですか?
便秘やゲリなどでおなかの調子が悪くなっていることが考えられます。一度トイレに行ってもまた痛いのならそれだけひどい便秘、下痢かもしれません。また、何か腸の病気かもしれません。
便秘の場合は、うんちがかたかったり、小さいうんちがコロコロと出ます。ゲリの場合は、ドロドロや水みたいなうんちが出ます。どちらなのかを確認して、おうちの人に伝えてください。
自分でできることとしては、便秘の場合は、いろいろな食べ物を好き嫌いせずに食べることが必要で、なかでも、毎日朝ごはんを食べることが大切です。
ゲリの場合は、おなかを冷やさないようにして、からだを休めてください。胃や腸が疲れているからです。ごはんを食べるときは胃や腸を助けるためによくかんで食べてください。あぶらっこいものや冷たいものはひかえめにしたほうがいいです。あとは、ゲリになるとからだの水分が出ていってしまうので、こまめに水分をとることも大切です。
どちらもぐっすり眠ることも必要です。腸の病気のこともありますから、おなかの痛みが続いたり、とても痛かったりしたら、おうちの人に相談しましょう。
Q32. ゲリになったときはどうすればいいですか?
ゲリになったときは、おなかを冷やさないようにして、からだを休めてください。胃や腸が疲れているからです。ごはんを食べるときは胃や腸のはたらきを助けるためによくかんで食べてください。あぶらっこいものや冷たいものはひかえめにしたほうがいいです。あとは、ゲリになるとからだの水分がどろどろ・びしゃびしゃうんちといっしょに出ていってしまうので、こまめに水分をとることが大事です。
ゲリがつづく場合は、おうちの人に伝えてください。病院でみてもらうと安心ですよ。

Q33. うんちが出ない日があるとおなかが痛くなるのはなぜですか?がまんしても良いですか?
うんちが出なくておなかが痛くなるのは、うんちのかたまりが腸の一部をふさいでいるからです。うんちで行き止まりになっているところに、腸が動いてうんちをむりやり動かそうとするので、痛くなってしまいます。
うんちがたくさんたまっていたり、おならも出ないと、おなかがはり、ますます痛くなります。うんちがしたくなる、ということはうんちが肛門のそばまでおりてきているということですから、がまんするのはよくありません。がまんしてうんちをためていると、たまっていることがふつうになってしまい、にぶい腸になりますので、ますますためるようになります。

Q34. 悪いうんちが出る原因やどうしたらよくなるかを知りたいです
悪いうんちには、大きく2つあります。1つ目は「どろどろ・しゃばしゃばうんち」です。食べすぎたり、飲みすぎたりしたときなどになります。下痢(ゲリ)とも呼ばれています。悪い菌、ウィルスに感染したときも下痢になります。この場合は、おなかが弱っているので助けてあげることが必要です。ごはんはいつもよりしっかりかんで食べてください。水分をとるときも、いつもより少しづつにしてください。
2つ目は「ころころ・ごつごつうんち」です。このうんちは便秘のうんちです。ごはんをちゃんと食べなかったり、野菜が足りなかったり、運動していなかったり、しっかり眠れていないときなどになります。便秘のうんちの場合にどうしたらよくなるのかは、Q.2に書きましたので読んでください。

おならについて(2問)
Q35. おならとうんちの関係について知りたいです
おならの大部分は食べるときにのみ込んだ空気です。少しはゲップで出ます。食べたものがおなかの中でドロドロになり、栄養と水分をからだにとりこんだ後、残ったものがうんちとして体の外に出されますが、腸の中にはたくさんの小さな生きもの(菌)がいて、栄養を取り入れる手伝いや、からだの抵抗力を強めたりと、いろいろな働きをしています。そのときにガスが出ることがあり、このガスもおならになります。
肉やあぶらっこいもの、お菓子ばかりを食べていると、腸の中のわるい菌がふえてしまい、わるい菌は臭いガスを作るので、うんちもおならもくさくなってしまうのです。
Q36. おならをがまんするとどうなるのか知りたいです
おならはが何でできているかはQ34.を読んでください。
おならをがまんすると、おならがたまり、おなかがはって腸が動きにくくなります、便もうまく運べなくなり便秘になりやすくなります。おなかが痛くなったり、気持ちが悪くなったりすることもあります。ほんとうはおならもゲップもがまんしないほうがいいのです。

おしっこについて(4問)
Q37. おしっこの成分や色の理由について知りたいです
おしっこは、血液の中にあるいらないなものと余分な水分ですが、血液のように赤くない透明な色をしています。成分としては、塩分や尿素などが含まれています。色は、うすい黄色から水に近い色です。からだの水分が足りているとうすい黄色から水のような色になりますが、水分が不足していると濃い黄色や、茶色に近い色になります。濃い色のときは注意してください。また、薬や食べ物の影響で色が変わることもあります。
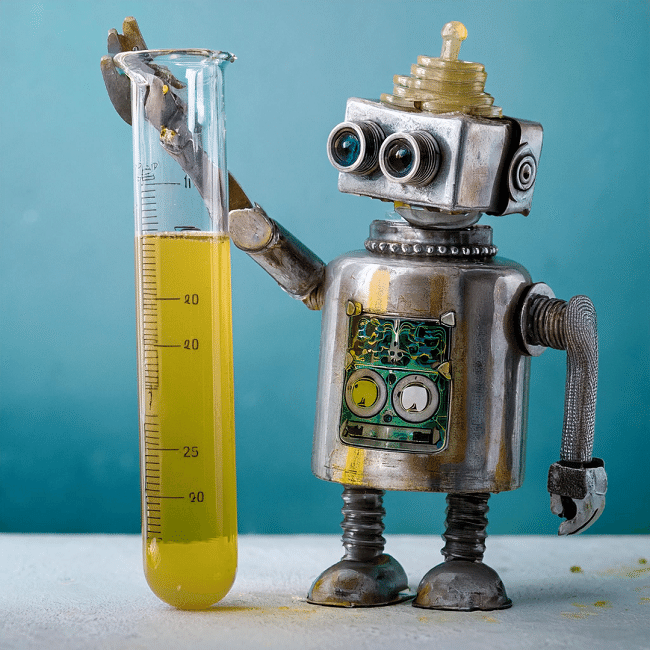
Q38. おしっこが出た後股間が痛くなるんですけどどうすればいいですか?
おしっこを出すときに痛かったり、おしっこをしたのに、まだ残っているように感じたりするときは、菌が入って悪さをしているかもしれません。なかなか直らないときは、おうちの人に相談しましょう。
Q39. おねしょはどうやったらしなくなりますか?
まずは、早寝早起きの規則正しい生活を心がけるようにしましょう。明るいうちに十分に水分をとることや、寝る前の2時間前にごはんや飲み物を済ませること、眠る前の飲みものは控えること、寝る前におしっこに行くこと、眠っているときは体が冷えないようにすることなどが効果的とされています。ただ、無理して飲みものをがまんすることは体に良くないので、のどがかわいたら水分はとりましょう。なかなか治らないときは、おうちの人に相談してみましょう。

Q40. 寝る前にトイレに行ったのにまたおしっこが残っているように感じて気持ち悪いです、どうしたら治りますか?
おへその下あたりには、おしっこをためる風船のような入れものがあり、その入れものが、まんぱいちかくなると「おしっこをしたい!」という信号が脳におくられます。この信号をうけとったらトイレにいき、ふくろの中のおしっこを出し切ります。そうすることで「すっきり!」と感じられるのがからだの調子がよいときです。おしっこをしたのに、まだ残っているように感じたり、おしっこを出すときに痛かったりするときは、病気かもしれないので、おうちの人に相談しましょう。

トイレの歴史・仕組み(4問)
Q41. トイレの起源や形について教えてください
日本では縄文時代のトイレのあとが見つかっています。そのトイレは、陸地から川の上に木の板を渡してしゃがむところを作り、うんちやおしっこが川の中に落ちる仕組みになっていたと考えられています。もう少し後の時代になると、みぞを掘って川から水をひいてきて、そこにまたがってしたり、木でできた箱のようなものにためて、決まった場所に捨てに行くようにしていました。
鎌倉時代になると、ためておいたうんちやおしっこを肥料にして、お米や野菜などを育てるために使うようになったといわれています。
便器が木から陶器に変わったのは明治時代ぐらいです。このときは和便器でくみとり式(おしっこやうんちをトイレの下にためてから、運んでいくもの)でした。
いまのトイレと同じ、水洗式の洋便器が増えてきたのは1960年代ごろからです。

Q42. トイレの仕組みや流れる仕組みについて知りたいです
水洗トイレは、水でうんちやおしっこ、トイレットペーパーを流します。便器から流れ出たら建物内の排水管をとおって下水道や浄化槽(じょうかそう)に行きます。
便器には、後ろにタンクがあるタイプとないタイプがあります。タンクがあるタイプはそこに水をためておき、タンクの水を便器に流すことでうんちやおしっこを水と一緒に便器から押し出します。このときにできるだけ便器に汚れが残らないようにあらいながら流します。
タンクがないタイプは、決められた水の量を電気でコントールしながら流します。
ちなみに、どちらのタイプも便器の中に水がたまっています。この水は次の3つのやくわりがある大切な水です。
1.便器に汚れがつかないようにする
2.排水管から虫やにおいが上がって来ないように水でふたをしている
3.うんちを水の中にしずめることでにおいをおさえる
水洗トイレのおかげで、安心してうんちやおしっこをすることができ、家の中をせいけつにたもつことができます。うんちやおしっこ、トイレットペーパー以外を流すとつまるので、気をつけてください。

Q43. ウォシュレットの水はきれいなんですか?
ウォシュレットやシャワートイレなど、メーカーによって名称がことなりますが、これらのことを温水洗浄便座(おんすいせんじょうべんざ)といいます。温水洗浄便座の水は、水道水などの水をつかっているためきれいです。
ですが、使っているうちに水が出るノズル部分に汚れがついたり、ほこりなどがついたりすることが考えられます。その場合はお掃除が必要です。お掃除のポイントは、定期的におそうじする、汚れに気づいたらすぐにふき取ることです。

Q44. トイレで流した後のうんちやおしっこはどこに行くのでしょうか?
水洗トイレで流したうんちやおしっこの行先は、大きく分けると3つあります。1つめの行先は「下水処理場」です。うんちやおしっこは便器につながっている管の中をとおって運ばれます。この管は、便器から道路の下にある下水道という管につながっています。この下水道はかなり長くて、街じゅうの汚れた水を下水処理場まで運びます。そこできれいな水にして、海や川に流します。
2つめの行先は「浄化槽(じょうかそう)」です。便器から管をとおって建物の外に運ばれていき、お庭などの地面の下につくられた浄化槽の中できれいな水にして、海や川などに流します。
3つめの行先は「し尿処理施設」です。「し尿処理施設」です。し尿というのは「うんちとおしっこ」という意味です。トイレの下にうんちやおしっこをためる場所があり、そこにためられたものをバキュームカーという車でし尿処理施設に運び、きれいな水にして、海や川などに流します。
汚れた水をそのまま海や川に流してしまったら自然や生きものに悪い変化を与えてしまうので、このようにきれいしてからもどすようにしているのです。

その他(6問)
Q45. 「うんち」という名前の由来や意味について知りたいです
「うんち」は古くから使われている言葉で、名前の由来はいろいろな意見があります。たとえば、昔の中国では大小便のことを「うん(吽)」といい、それをおく場所「うん・ち(置)」というので、それが語源であるという説があります。これ以外にも、うんちをするときに「うーん」といきむ声から「うんち」という名前になったという説もあります。

Q46. 動物がうんちを出す仕組みについて知りたいです
食べたものから栄養をからだにとりこんで最後にいらないなものをうんちとして外に出すのは人間と同じですが、その仕組みは動物の種類によって違います。ゾウ、ウシ、カバ、ライオン、ウサギ、キリンなど、それぞれのとくちょうがあるので、ぜひ調べてみてください。ほにゅうるいといわれる動物は、からだが大きくても小さくても、うんちをするときの時間はだいたい12秒ぐらいという研究結果もあります。ふしぎですね。

Q47. アニメのようなぐるぐるうんちは出ますか どうやって出すのですか?
長めのなめらかバナナうんちであれば、おしりから出たうんちが便器に落ちるときにソフトクリームのようにぐるぐるとなれば出来るかもしれません。ですが、かなりむずかしいと思います。とくに洋式便器は、便器にたまっている水の中に落ちていってしまいます。和式便器は、うんちが落ちる場所がほぼ平らになっているので、もしかしたらできるかもしれませんが、うんちをしながらおしりを動かすとうんちがはみ出るかもしれないので、それはやめてくださいね。

Q48. うんちをした後何回拭けばいいですか?
おしりをふく回数はよいうんちとわるいうんちによってことなります。するっと出るバナナうんちのときは、おしりがほとんどよごれないので、トイレットペーパーでふいても、ほとんど汚れがつきません。わるいうんちの中でもドロドロうんちやしゃばしゃばうんちのときは、トイレットペーパーで何回もふかないときれいになりません。しゃばしゃばうんちのときは、おしりのあちこちに汚れがとびちっていると思いますので、気をつけてふいてください。ただし、どんなうんちのときでも、つよくゴシゴシふくと、はだがあれてしまうので、やさしくふくようにしてください、ぬれているタイプのペーパーのほうがいいかもしれませんね。
女の子は、おしりの方から手をまわして、前から後ろにむかってふくようにしてください。また、おしっこをしたあとは、トイレットペーパーはこすってふくのではなく、やさしくペーパーをおしつけるようにしてふいてください。

Q49. トイレでうんちをする時どんな姿勢がいいですか?
洋式トイレでは、おなかを太ももに近づける前かがみの姿勢になると、うんちが出やすくなります。こうすることで腸の出口に近い部分と、肛門(うんちの出口)がまっすぐになるのでうんちが出やすいのです。足が床にしっかりついていることも大事です。足が床に届かない人は、台をおくとしっかりふんばれるのでいいです。

Q50. 生理によって便秘になるのはどうしてですか?
女性はおとなになる変化の途中でからだが成長していき、女性ホルモンなどのホルモンが出て、生理が起こるようになります。そのホルモンの影響で生理に関係して、こころやからだの調子が悪くなることがあるのです。調子が悪くなることのひとつに便秘がありますが、腸にまったく影響が出ない人もいるし、なかには便がゆるくなる人もいます。
生理の前に増えるホルモンは腸の動きをおさえる作用があるので便秘になりやすいのですが、生理の最中に調子がわるいという人もいるし、さまざまです。からだの他のところにも影響が出ることで、活動量が減ったり、食生活が変化することも、便秘になりやすくしているかもしれません。
生理前に便秘なることが多いなら、ふだんから便通をよくしておくことが大事で、生活調整や食事に気を付けるだけでなく、場合によっては便を出やすくする薬を内服することも考えたほうが良いのです。保健室の先生や、ご家族に相談しましょう。
【監修】
排便について:中野 美和子先生(神戸学園理事・校長、さいたま市立病院小児外科/非常勤・元部長)
排尿について:吉川 羊子先生(小牧市民病院 泌尿器科排尿ケアセンター部長)
*いずれもNPO法人日本トイレ研究所アドバイザー
※本記事の画像は生成AIを使用して作成しています。文章の内容を表すものではありません。
