
現代のタンパク質摂取量は1950年代と同じ ! その理由をわかってないとヤバいかも
「現代のタンパク質摂取量は1950年代と同水準」には驚かれた方も多いのではないでしょうか。
実際に1995年以降、急激に減少しているのがわかります。

この飽食時代になぜタンパク質が不足してしまうのか、その原因と対策について解説します。
(記事の文末に動画を添付しています)
1995年以降、何が起こったのか
日本人のタンパク質摂取量は、1970年頃から30年前後は好ましい水準にありました。
ところが、1995年あたりから急激な下降線を辿って、驚くことに現在では1950年代と同レベルになってしまいました。
1950年代といえば、まだ戦後の食糧難を引きづっていた時代です。
その時代と、現在のタンパク質摂取量が同じ水準というのには驚かされます。
では、今の飽食の時代にどうしてタンパク質不足になってしまうのか、考えられる原因を4点、列挙していきます。
1.ダイエットブーム
ダイエット自体を否定しているわけではありませんが、やり方が重要です。
摂取カロリー全体を減らすのに合わせて、タンパク質まで減らしてはいけません。
減らすのはおもに炭水化物(糖質)です。
そういう意味では、糖質制限ダイエットの考え方は理解できます。
けれども糖質制限ダイエットは、見よう見まねで自己流でやってしまうと、健康を害して危険なこともありますので、注意が必要です。
まずは、緩やかに糖質を減らす(従来の7割〜8割)ことから始めてください。
タンパク質は極力減らさないでください。
2.朝食抜き
ダイエットと一部重なりますが、朝食を抜く人って結構多いようです。
その理由は、いくつかのパターンに分かれます。
・ダイエットの一環として行う
・朝食抜きの方が健康に良いという考えに基づいて行う
・単に朝の時間がなくて抜いてしまう
などです。
朝食は食べた方がよいのかどうかという議論は、長い記事になってしまうので、ここではしません。
そもそも、簡単に結論は出ません。
ただ一つ言えることは、どんな理由の朝食抜きであっても、3食のうち1食を抜いてしまうと、タンパク質を十分に満たすことは、それだけで難しくなります。

また、朝食を3分とか5分とか超短時間で済ませてしまう場合は、タンパク質はほとんど摂れていないような気がします。
牛乳やヨーグルトを除いて、タンパク食品を食べるのは、それなりに時間がかかるからです。

結局、解決策は早起きして朝食の時間をしっかり確保して、お魚や豆腐、納豆、卵などを食べることです。
3.魚を食べなくなった
下は、魚の消費量のグラフです。

著しく減少しているのが一目瞭然でわかります。
その理由はよくわかりません。
骨を取るのが面倒くさい?
骨が刺さったのがトラウマになった?
ただ最近は、骨を取り除いた魚もスーパーに並んでいます。
魚は、比較的消化がよい良質なタンパク源なので、ぜひ食卓に並べてください。
「魚の消費量は減っているけど、肉の消費量は増えている。だから、タンパク質の摂取量は減っていないのではないか」
という疑問が浮かぶかもしれません。
確かに、肉の消費量は増えています。

問題は、肉に含まれるタンパク質の量です。
肉といえばタンパク質の固まりのようなイメージがありますが、部位によって相当違います。

牛肉の場合、モモ肉であれば比較的タンパク質が多いですが、牛丼などで使うバラ肉はグッと少なくなります。
ほとんどが油と言っても言い過ぎではありません。
しかも、ここに書いてあるのはバラ肉は和牛であって、アメリカ産バラ肉はもっとタンパク質が少ないはずです。
同じく豚肉もバラ肉の場合、タンパク質はそれほど多くありません。
豚肉であれば、やはりモモ肉、または(少し値段が上がりますが)ロース肉がお薦めです。
鳥肉ではササミのタンパク質が多く、しかも安いのでお薦めです。
我が家は愛犬がいるので、ササミをよく購入します。

もっとも、レシピによって使う部位はある程度決まりますが、多少は意識してタンパク質が多い部位(レシピ)を選んでください
4.炭水化物食が多すぎる
私は、これがタンパク質が不足する最大の原因だと思っています。
何と言っても、炭水化物食は美味しいものばかりです。

まずは麺類。
うどん、そば、ラーメン、パスタ etc.
私も沖縄に住んでいるので沖縄そばを時々食べます。
沖縄の前は福岡に住んでいたので、豚骨ラーメンをしばしば食べていました。
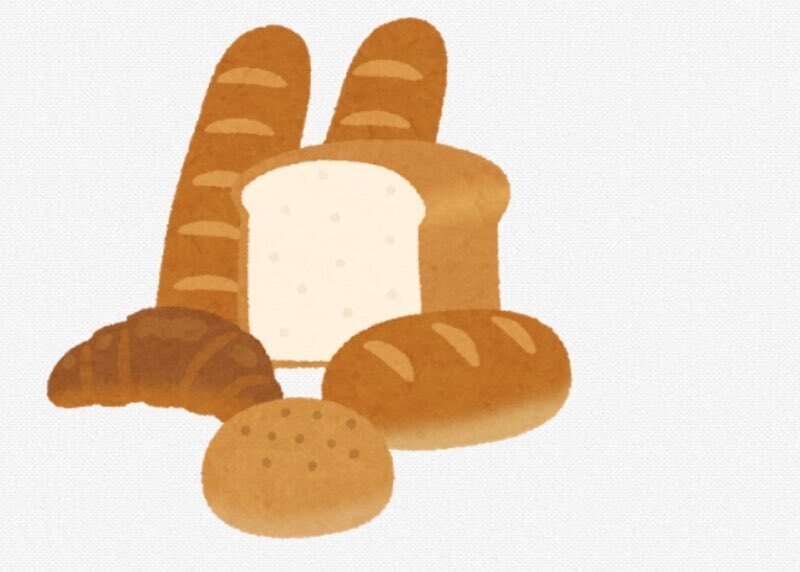
次にパン。香ばしい匂いが漂ってくる焼き立てパン。
どれも本当に美味しいですね。

そして、ご飯レシピ。
チャーハン、チキンライス、タコライス、ハヤシライス etc.
少しは肉が入っているかもしれませんが、ほとんど炭水化物です。
カレーライスも、意識して具を入れないと炭水化物ばかりになってしまいます。
世の中おいしい炭水化物食で溢れています。
カロリーはしっかり取れるし、お腹いっぱいにもなります。
けれども、そこにタンパク質はほとんど含まれません。
まず、そこに気がつきましょう。
タンパク質が多く含まれる5大食品

肉、魚、卵、大豆食品、(牛乳)乳製品。
ご飯、パン、麺類にも多少ははタンパク質は含まれますが、やはり多くは炭水化物です。
炭水化物食に走ってタンパク質が不足するというのは、飽食美食時代の負の部分かもしれません。
まとめ
日本人のタンパク質摂取量は、1995年あたりから急激な下降線を辿って、現在では1950年代の食糧難の時代と同レベルになっています。
その理由として考えられるのは、
①ダイエットブーム
ダイエット自体を否定してはいないが、減らすのは炭水化物、糖質です。
タンパク質を減らしてはいけません。
②朝食抜き
3食のうち1食を抜いてしまうと、タンパク質を十分に満たすことは、それだけで難しくなります。
解決策は、早起きして朝食の時間をしっかり確保することに限ります。
③魚を食べなくなった
魚は、肉と比較しても、消化がよい良質なタンパク源です。
骨を取るのを面倒くさがらずに、もちろん骨を取り除いた魚でもいいので、ぜひ食卓に加えてください。
④炭水化物食が多すぎる
麺類、パン、ご飯もの、たしかに美味しいですね。
けれども、そこにタンパク質はほとんど含まれません。
まず、タンパク質が多く含まれる5大食品、肉、魚、卵、大豆食品、(牛乳)乳製品を意識して食べることから始めてください。
お肉を食べる場合には、できる限りタンパク質が多い部位を選んでください。
この記事の内容は動画もアップしています。合わせてご覧ください。
