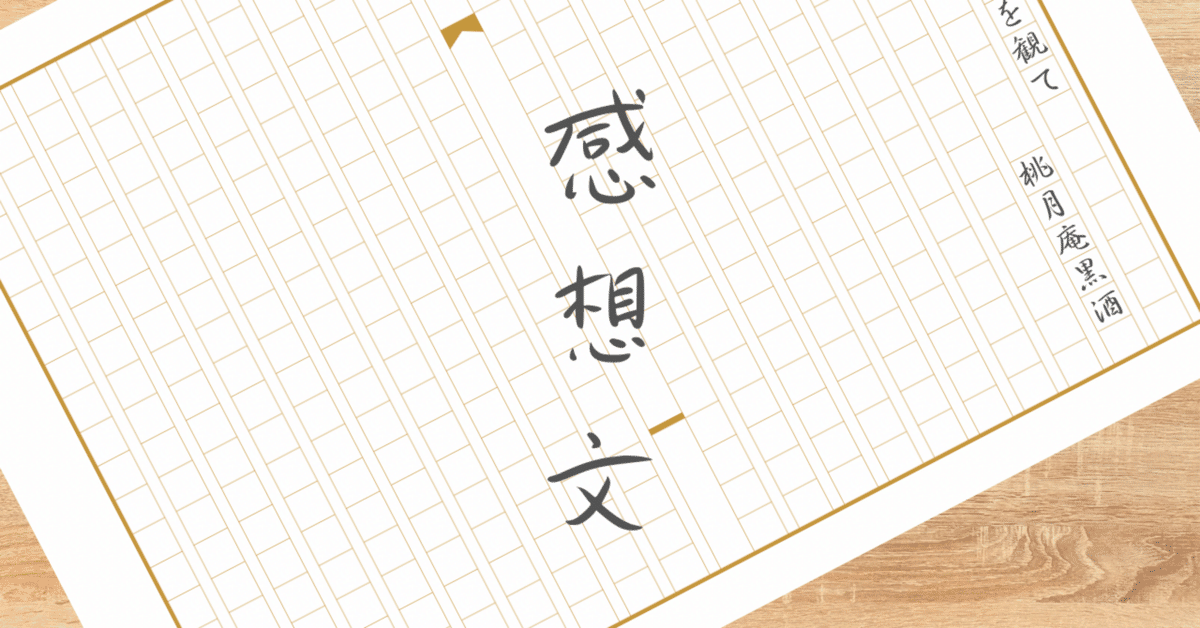
高比良くるま『漫才過剰考察』を読んで
今でこそ、毎年のM−1グランプリを一回戦のYouTubeから全部観て、手を叩いて笑っている私だけれども、
お笑いをやっていた頃は『分析』というフィルターを通して難しい顔で漫才を観ていて、
「このボケはこうだから面白い」「このスタイルの漫才は、これこれこうだから新しい」
と、素直に楽しめていなかった。
理屈の理解に必死。
で、こういった分析は割と得意な方だと思っていたけれども、この本を読んで「ああ、あの頃の自分は全然足りてなかったんだなぁ」と、悔しいとか残念とかではないんだけど、じんわりと心に来るものがあった。

『漫才過剰考察』は言わずと知れたM-1グランプリ2023、2024チャンピオンの高比良くるま氏のインタビューやWEB掲載されていたものを書籍化──と言っても9割書き直しと書き足し──したもので、
Mー1グランプリの歴史や当時の時代背景、漫才師のスタイル、ひいては当日の空気や流れを過剰に考察し、果ては寄席演芸から地域の笑い、そして世界までをも分析し尽くして言語化している。
チャンピオンだから結果論で好き勝手言っているんでしょ?
いや、本書は2024年で連覇する前に刊行されたものなので、
「私の考えはこうです」と発表してから優勝し、「ね? 言ったとおりでしょ」という、
実績に裏付けされた圧倒的な説得力が反論を許さない。
勢いで語っている部分もあるが、どんどん辻褄が合っていく感覚はミステリー小説ぽい面白さがある。
ネタ作りに根を詰め過ぎて、視野が狭くなって、「ネタさえ頑張れば売れる」と思考停止していたあの頃の自分に、羽交い締めにしてでも読ませてやりたい。
ネタの外にも、ネタを面白くできる活動がたくさんあったらしいぞ!
さてさて、M-1二連覇の凄さがよくわからない人もいるだろう。
落語で例えると……なんだろうか?
結構考えたけど規模感や、得られる富や名声や先の仕事が違い過ぎてどれも当てはまらない。
んー、出場人数だけで言えば、一番大きいNHKの落語のコンクールで出場者130人。
それに対してM-1が10000組、二年で20000組だから、
M-1二連覇はNHKで150回優勝する感じだろうか?
んなアホな。
勿論本書は、あの頃の自分ばかりじゃなく、今の自分にもグサリと刺さるところはあった。
『寄席』の章。
これはもう、そのまんま漫才師→落語家に置き換えても意味が通じるように思った。
寄席においては『ネタのクオリティ』より『お客さんとのマッチ度』が重視されるとか、
落語という複雑な物を初見にどう理解させるかとか、
笑っていい空間を作るためのツカミ、顔芸の大事さ、変なことを言いそうな空気感──これらが大事なのはそりゃわかるけど、意識してできるほど明確に認識ができていなかったと思う。
自分の当たり前がお客さんの当たり前になっていた部分もあったかも。
それが筆者の得意とする言語化によってハッとした。
口調だとか発音だとか間とか仕草とか、噺の技術にばかり気を取られていたんじゃないか?
対お客さんの技術は?
芸は芸で磨いていくことも大事だけれど、やっぱり客商売なんだから「付いてきてくれ」ばかりじゃなく歩み寄ることもしないといけないな。
今後できるかは分からないが努力はしたい。
一昔前に流行った動物占いみたいで面白かったのが、
日本のお笑いを東西南北に分けた『笑いの地域性』についての話。
確かに、私は江戸落語をやっているが大阪出身なので、フリを重視して、フリに対してのボケを考える、ツッコミ主導の西の笑いの取り方を無意識にやっていた。
噺の筋が知られ過ぎてる落語においては、フリもなくいきなりボケる東の笑いの方が現代では合っている気がする。
また、今漫才で一番強いとされている北の笑い──ボケが主導でふざけているが、どこか戯れ合っている──は、売れている人の滑稽噺に共通する要素。
うん、感心する。
どうすればここまで視野が広くなるのか。
物事を多角的なんてレベルじゃない、全方位から捉えて考える。
くるま氏は、M-1グランプリ2023も『勝てなくていいから良い大会にしたい』『盛り上げたい』その選択をしていたら優勝してしまったと言う。
戦略的に自分を一つの駒のように扱う──そんなことできるのかね?
と思ったけど……いや、これは寄席で師匠方がよく言う「自分の出番を理解して役割を全うする」というのと似てないか?
トリで1番盛り上がるように、程よく温め、前のネタと付かないようにする……寄席で当たり前のようにやっている事が、ベストキッドよろしくいつの間にか生き抜く為の広い視野を育んで……いる?
さすが寄席だ。
数百年の歴史を持つだけのことはある。
と思うと同時に、単独でその境地に行き着いている本書の説得力がまた増した。
