
【事例紹介】多言語サイト構築
この記事の作成担当:株式会社テンタス 代表取締役 小泉智洋
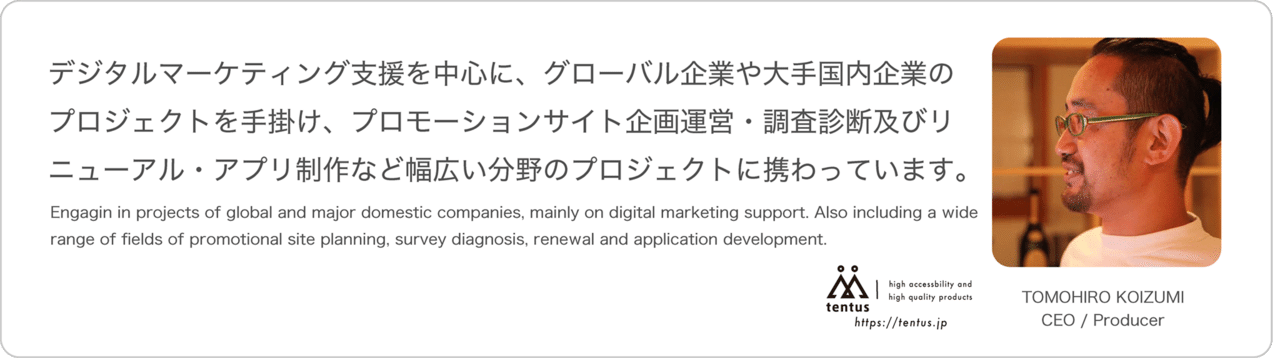
元々はグローバルカンパニーさんからのご依頼が殆どでしたが、海外からのインバウンド需要や、日本オリジナルを海外に発信するアウトバウンド需要などで、最近は本当に様々な企業さんが多言語サイトに取り組んでいます。
翻訳ツールなどが進化してきているので、昔ほどの難易度ではなくなりつつある多言語サイトですが、まだまだ気を付けるべきポイントがいくつかあります。
今回は事例をベースに気を付けるべきポイントをいくつかご紹介させていただきます。
英語を基本にした制作進行
とあるメーカーさんのグローバルキャンペーンで、日本語・英語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語・中国語(簡体字)の6か国語でサイト作成をいたしました。
プランナーはアメリカの代理店と日本の代理店、デザイナーはアメリカのデザイン会社、制作進行は日本人である私、制作は日本の制作会社という多国籍チームでの制作で、アメリカ西海岸の営業時間内ギリギリの7時台にテレカンをするのが本当に大変でした。
ちなみにこのテレカンで聞き取れない言葉が多くて、RIZAP ENGLISHに通う決心をしたのは秘密です。
当初はアメリカのデザイン会社から英語のドキュメントが下りてきて、それをベースに日本語の構成書を作成し、日本側のクライアントに確認を取り、問題なければ英語に翻訳をして、アメリカのデザイン会社に投げるといった非常に非効率な進行をしていました。
この非効率な進行を打破するために、クライアントや制作チーム内で英語が不得意な人が確認できなくなってしまうというデメリットに目を瞑り、すべてのドキュメントを英語で作成することにいたしました。
これにより非効率な手戻りがなくなった上に、翻訳ツールが最も得意な「英語×日本語」「英語×フランス語」といった英語を中心とした翻訳を行うことが可能になったため、制作コストが大幅に圧縮出来ました。
このように多言語サイトを多言語メンバーで制作する場合は、中心になる言語を英語にすることで非常に大きなメリットが生まれます。
翻訳の確認に関しては後ほど記載させていただきます。
言語だけではない多言語サイトの落とし穴
多言語サイトの作成は翻訳だけすればよいというわけではありません、その言語特有の文化にも考慮する必要があります。
一例をあげるとこんな感じです
・アラブ圏の場合は、イスラム教に配慮して女性が肌を露出している表現は避ける
・中国本土の場合は、パラアスリートの方などの四肢が欠損している人の画像に検閲が入る可能性があることを考慮する
・色に意味を持たせる場合に、文化によって色から受けるイメージが大きく違うことを考慮する。
(そもそもアクセシビリティの観点から色に意味を持たせるのは良くないんですけどね)
これらはもちろん必ずしも対応しなければいけない項目ではないのですが、知っておくことで各国での展開時に不必要な軋轢を避けることが出来るため、知識として持っておくと良いと思います。
先にあげたグローバルキャンペーンはIPでデザインの出し分けを行うことで対応を可能にしたうえで、まずは出し分けをせず表示して問題が起きそうならすぐに差し替えるといった対応を準備して、リスクコントロールを行いました。
完璧な翻訳を求めない
化粧品メーカーさんのサイトの事例なのですが、商品サイトリニューアルのオリエン時に対象言語が20以上あると聞いて危うく椅子からずっこけそうになりました。
先に挙げた翻訳ツールや頼みやすい価格帯の翻訳会社さんなどが多くあるので、英語から他の言語に翻訳することで原稿自体は簡単にあがってきますが、翻訳の確認をするためにはそれぞれの言語に精通したディレクターが必要になります。
じゃあイタリア語はイタリア人がいれば問題ないかと言うとそうでもなくて、言い回しなどが北イタリアと南イタリアで異なっていたり、年代によって表現が変化するため、10人のイタリア人が確認するとみんなが自分の主観でバラバラのフィードバックをしてくるのでとても混乱してしまいます。
このため、我々は基本的に【英語と日本語】のみを作成し、その他の言語はサイト自体は作成した上で、クライアント含めた【その言語のネイティブスピーカー】にお願いをして内容の齟齬がないことを最低限確認した上で、その原稿が【ニュアンスが間違えている可能性】を認識してリリースを行います。
絶対に間違えてはいけない【情報】と、表現に幅が出る【ニュアンス】を切り分けて確認をしたうえで、その境界線が曖昧なものはニュアンス部分を切り離して作成し、ニュアンス部分はリリース後に指摘があればいつでも修正可能にすることで、多言語化の落とし穴を回避いたしました。
忘れちゃいけないGDPR
まだまだ各社で対応が揺れているGDPR(EU一般データ保護規制)ですが、簡単に言えば「EU圏の人間の個人情報は絶対守れよ。守らなかったらめちゃめちゃ凄い罰則与えるからな」といった内容です。
このEU圏の人間というのが曲者で、スペインにいるスペイン人にはもちろん適用されますが、スペイン語を話すメキシコ系アメリカ人には適用されません。
ですのでどうやったらその人がEU圏の人間かを把握するのか?という問題が発生しますが、現状では「IPで判断」か「言語でみなし判断」の2パターンで対応している会社が殆どです。
GDPRに関しては非常に難しいので別途まとめさせていただくとして、少なくともヨーロッパ系の言語を使ったサイトを構築する際はGDPRを意識する必要があることだけ覚えておいてください。
最後に
このように多言語サイトを構築する場合は色々な落とし穴がたくさんあります。
これらの殆どが知識として知っておくことで回避が可能なことですので、多言語サイトを構築する場合は経験豊富な会社さんにご相談をしていただければ問題ないと思います。
