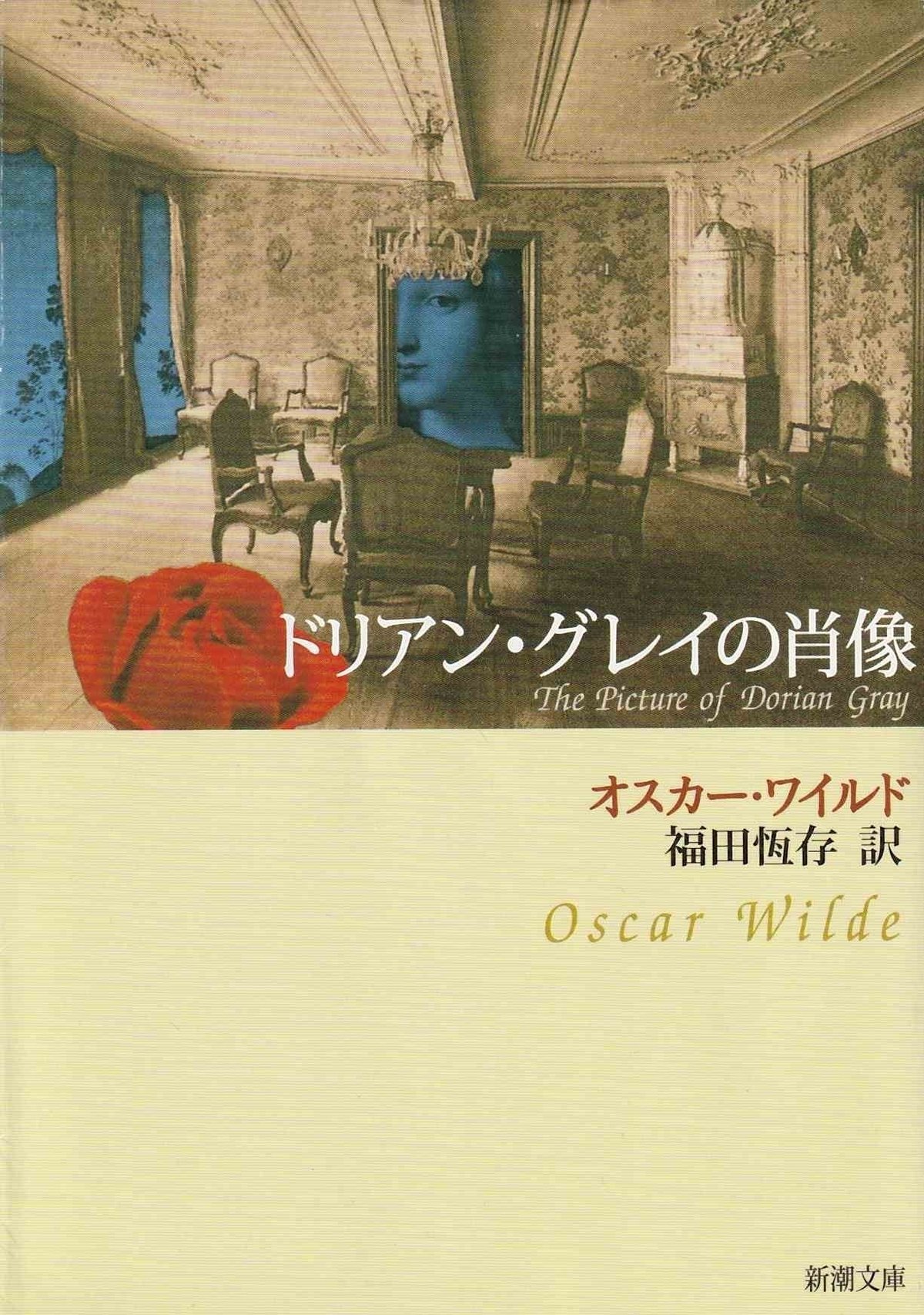#7日間ブックカバーチャレンジ
Facebookで好きな本を7冊紹介するというチャレンジが回ってきたのでやってみたんだけど、Facebookは友達のみ公開にしているのでアーカイブとしてこっちにもまとめておくことにした。
元のルールではカバーだけを貼り付けるということらしいんだけど、当然カバーでは気が済まないのでくどいレビューも付けることにした。あと、友達がいないので結局誰にも引き継がなかったのは内緒。
日本文学も含め他にも紹介したい本はたくさんあったけど、結果として海外文学だけになった。
ドリアン・グレイの肖像 / オスカー・ワイルド
自分の似姿に老いや罪を全部背負わせ、自身は永遠の若さと美を手に入れた青年ドリアン・グレイの破滅の物語ですが、その寓意もさることながら、小説としてのしっかりとした骨格、巧みに伏線を張り、それを回収しながら物語を一点に収斂させて行く手管、挿話も含め100年以上後の読者にもその世界を鮮やかに想像させる描写など、作家としての基礎体力がハンパない。さすが古典だと思います。
とはいえ、そこはワイルドなので底意地の悪い露悪趣味、質の高いキモさみたいなものはきちんと通奏低音としてあるので安心できます。こうでなくちゃね。ザ・スミスのモリッシーはワイルド直系のアーティストだと再認識しました。
今となっては筋立てそのものは読んでるうちにある程度予想もつきますが、それでも今日においてなお読まれるべき「怪作」であることに間違いはないです。芸術とかいうのが決して明朗闊達で品行方正なものでなく、こういう何ともいえない後味の悪いもの、見たいけど見たくないもの、自分の中のどこかにも埋もれているかもしれないヤバいものを暴き立てる営為でもあることを思い起こさせる作品です。
あと、訳が福田恆存っていうのがスゴい。
ジャズ・カントリー / ナット・ヘントフ

ジャズ・トランぺッターになりたい白人の少年が、黒人社会であるジャズ・ミュージシャンの仲間に入ろうとして、その軋轢に悩みながらも、その中で、自分を表現するとはどういうことか、自分の生を生きるとはどういうことかを理解しようとする、いわば青春小説です。
筋立てとしてはシンプルな成長譚ですが、そこにジャズという鋭敏な感受性が要求される音楽を介在させることによって、また黒人社会と白人社会の厳しい緊張関係という社会的な背景をしっかり描きこむことによって、主人公であるトムの心情の動きがとてもリアルに伝わってくる。
著者のナット・ヘントフはアメリカの高名なジャズ評論家。それだけにジャズに関する描写には妥協がなく、また優れたジャズと取るに足りないジャズに関する辛辣な描写などジャズ小説としても読めます。一線のジャズ評論家だからこそ書けたということは言えると思いますが、別にジャズに何の造詣もなくても普通に楽しめます。
大学生の時に買った講談社文庫版が友達に貸したままになってて、社会人になってからどうしても読み返したくなったけど既に絶版になってたので古本で何とか手に入れました。今は晶文社から装丁変えて出直してると思います。
フラニーとゾーイー / J.D.サリンジャー
この本には『フラニー』という短編と『ゾーイー』という中編が収められています。フラニーはグラス家の7人兄弟の末っ子、ゾーイーはその上の兄で、2つの物語はつながっています。グラス家の子供たちの物語は、「ナイン・ストーリーズ」に収録されている『バナナフィッシュにうってつけの日』を初めとして他にもいくつか書かれています。
『ゾーイー』では、ボーイフレンドの俗物性に我慢ができず、宗教書に助けを求めるフラニーに、ゾーイーが示唆を与えようと考えを述べる、物語はほぼ家の中の会話劇として進行します。ほぼこれだけの舞台装置で中編をひとつドライブして行くサリンジャーの筆致は、そこに差し挿まれる小さな描写も含め誠に巧みかつ確かなもので、自我と世界との相克という普遍的かつ答えのないテーマに悩む登場人物の心情を実に生き生きと活写しています。
「それから――よく聴いてくれよ――この『太っちょのオバサマ』といのは本当は誰なのか、そいつが君に分らんだろうか?……ああ、きみ、フラニーよ、それはキリストなんだ。キリストその人にほかならないんだよ、きみ」。
これはサリンジャーが神性の顕現について書いた重要な箇所です。神は、ベランダですさまじい籐椅子に座ってハエを追いながら一日中大音量でラジオを聴いている病気持ちの太ったおばさんなんだと、サリンジャーは看破する訳です。それは救いであり赦しです。ここは何回読んでも泣くところ。
村上春樹の新訳(タイトルは「フラニーとズーイ」に変更)もあって、こっちも悪くないけど、ここはトラディショナルな野崎訳で読みたい。
暗闇のスキャナー / フィリップ・K・ディック
これはリドリー・スコット監督の名作「ブレードランナー」の原作となった「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」の作者フィリップ・キンドレッド・ディックが書いたドラッグ小説です。
自身も重度のジャンキーであり、多くの友人をドラッグで失ったアメリカのSF作家ディックは、その悔恨ややり場のない怒り、絶望にさいなまれつつ、その先にかすかに見える希望の光を求めるようにしてこの作品を上梓します。バッド・トリップや禁断症状の書き込みがハンパなくリアルなのは、もちろんディック自身の経験に基づいてるからです。
SFという舞台装置に依拠した作品が多い中にあって、自らの傷をえぐるような硬質な描写をダイナモにして物語を進めて行く本作は異色で、彼の作品の中でも他に類のないもの。ディック得意の「現実崩壊感覚」の源流はここにあるのか。ディック本人は「最高傑作」と自賛して憚らないし、僕もそう思います。
これだけを読んでディックを読んだことにはできないが、これを読まないでディックを読んだことにもできない重要な作品です。今手に入るのはハヤカワ文庫から「スキャナー・ダークリー」のタイトルで出ている新訳(浅倉久志)ですが、創元推理文庫から出ていた山形訳を推したい。
あ、忘れてたけどこの作品もリチャード・リンクレイター監督(「スクール・オブ・ロック」!!)で映画化されています。
日々の泡 / ボリス・ヴィアン
この人といい、セルジュ・ゲンズブルといい、ジャン・コクトーといい、フランスからは時折ヘンな人が出てきます。これは僕の完全な偏見だと思いますが、フランス人には何か敢えて不品行なこと、不道徳なことをして見せたいという偽悪趣味というか妙な自意識みたいなものがありますよね。そういうのが文化だと思ってるフシがある。
ボリス・ヴィアンもたぶんにそういうところはあると思うんですが、こうやって出来上がってきた作品を読めば、その偽悪趣味、露悪趣味の後ろに、作家として、芸術家としての豊かな才能があることが分かります。夭逝の天才と言っていい人です。
この作品は彼が書いた恋愛小説で、「うたかたの日々」というタイトルでも知られているもの。しかし、カクテルを作るピアノがあったり、ヒロインの肺に水蓮の花が咲いたり、空想小説的というか散文詩的というか、リアリズムには一片の敬意も払われてないところがいい。
けったいな人の書いたけったいな小説なんですけど、第二次世界大戦直後に書かれいまだに世界中で読まれている作品です。何がそんなにすごいのか試しに読んでみる価値ありです。これが気に入ったら次はコクトーの「恐るべき子供たち」をお勧めします。
路上 / ジャック・ケルアック
何度挑戦しても最後まで読み切れない本というのがあって、J.G.バラードの「奇跡の大河」とかトマス・ピンチョンの「ヴァインランド」とかそうなんだけど、この「路上」も長い間そういう本のひとつでした。
学生の時に初めて手に取り読み始めたけどあまりの悪文と意味があるとは思えない内容に挫折、その後何度か読んでみたけどあかんかったヤツ。
さすがにビートニクス(ビート・ジェネレーション)の必読書を未読のままではあかんやろと思って、10年ほど前に一念発起して読み始めたところあっさり読めたのみならず面白かった。全然悪文でもなかったです。オレが成長したのか?!
内容的には主人公がガラの悪い不良の友達とクルマであっちこっち行ったり来たりしながらいろいろやらかすという小説。ビートニクとは何かを知りたい人(そんな人がいれば、ですが)は頑張って読み通してください。
僕は次は未読になっているバロウズの「裸のランチ」に挑戦するつもりです。
何かが道をやってくる / レイ・ブラッドベリ
原題は「Something Wicked This Way Comes」。サーカスが街へやってくるところから物語は始まります。逆回転させると1周ごとに1歳若返る回転木馬、鏡の迷路に潜む何か、団長の身体じゅうに彫られた不気味な刺青、フリークス、盲いた魔女。
ウィルとジムという二人の少年はサーカスの秘密を知り団長から追われる身となります。サーカス団が運んでくる非日常の空気を背景にしたファンタジー活劇ですが、ブラッドベリが描いて見せるのはその奥にあるもの。
何十年かに一回町にやってくるサーカス団が携えているものは確かに「何か邪悪なもの」ですが、それはもともとウィルやジムの心の中にもまた潜んでいるものでもあります。
サーカス団はただそれを呼び覚まそうとしているのに過ぎず、その誘惑に負けた者はサーカスに囚われ、永遠に町から町へと彷徨うことになる訳です。
誰もが心の奥に抱える薄暗い小部屋のことをブラッドベリはよく知っています。ファンタジーでこそ描ける成長期の心に兆す不安やきしみを表現した名作。