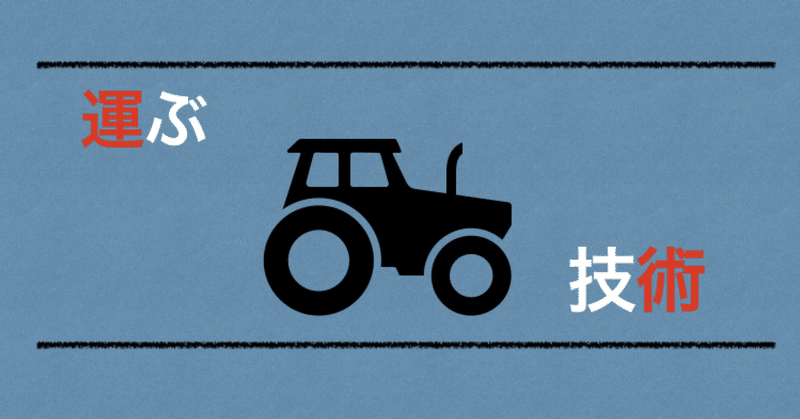記事一覧
新幹線の車内を静かにする工夫
スピードが速くなれば車内で聞こえる騒音も当然大きくなります。でも、JRや私鉄などの通勤電車の車内騒音は約70~80dBで、新幹線の車内は約60~70dBと、車内騒音がかなり軽減されています。
新幹線の車内には、プラスチック製の吸音材が天井・壁・床にたくさん貼り付けられ、車外の音が車内に伝わらないようになっています。窓は3枚のガラスに空気の層をはさんだつくりにし、外の音が伝わりにくくしています。
ま
新幹線の自動消雪装置
東海道新幹線は例年、岐阜県や滋賀県の区間で降雪に見舞われる。雪は高速で走る新幹線の台車に付着して大きな氷塊になり、落ちると線路に敷き詰めた石に激しい勢いで衝突する。石が吹き飛んで車体を傷つける恐れがあり、台車の除雪が欠かせない。
雪の日に最大40人の作業員を配置し、高圧洗浄機で除去している。天気予報を基に待機する場合があるなど人的負担が重い。名古屋と新大阪の両駅で実施しておりコストもかさむ。
鳥の隊列飛行を飛行機に応用
空を見上げた時に、渡り鳥が“V”の字や“へ”の字ともいえる、形で飛んでいるのを見たことがあるだろう。隊列を組んで飛ぶことで、前を飛ぶ鳥の後ろに生じる上昇気流を、後ろの鳥が自身を浮かすのに利用しているのである。渡り鳥の中には数万キロという長い距離を飛んで移動する種もおり、飛んでいるときのエネルギー節約はとても重要なことなのだ。
この鳥の隊列を飛行機で活かそうと、エアバス社が検証しているのが『fe
車の補器類の進歩 ラジオ
昔の車はAMラジオだった。ラジオ受信機は、トランジスタになる前には真空管式だから、スイッチを入れてから少し経ってラジオが鳴り出した。
その頃のカーラジオのアンテナは、ロッド式で、大体はフロントフェンダーに埋め込まれていて、アンテナ先端のリング状の窪みに簡単な鍵を差し込んで引っ張り出していた。
その後、ラジオのスイッチを入れると、1段分が飛び出す方式が普及した。そして上級機種には、モーターで上