
2024年に読んだ本ベスト15 → ◯
2024年に読んだ本がbooklogによると90冊くらいでしたが、星4つ以上つけた印象深い本をまとめてみました。どちらかと言えばドキュメンタリーとかノンフィクションが好きなのですが、意外にも小説が多かったような気がします。
名前のチカラ (たくさんのふしぎ2022年12月号)
クリハラタカシ

弊社で読むこと必須になっていたので、あわてて図書館で借りて読みました。名前をつけることの哲学的意味がわかります。三土たつおさんに弟子入りしたいと思いました。
サラゴサ手稿
ヤン・ポトツキ 畑浩一郎

ヤン・ポトツキの怪作。ようやく上中下3巻を読み終えました。語彙が足りないので、凄いとしか言いようがなく、不思議でとても面白い。フィクションとはこういうものかという驚きです。この入れ子になった物語構造をちゃんと設計して執筆しているのは、人間業とは思えません。
薔薇の名前
ウンベルト・エーコ 河島英昭

名作を読むと圧倒され、沈黙せざるを得ない時がある。今回も正にそんな感じです。映画化もされているようですが、この作品をどのように映像化しているのかあらためて観てみたいと思いました。
神と黒蟹県
絲山秋子
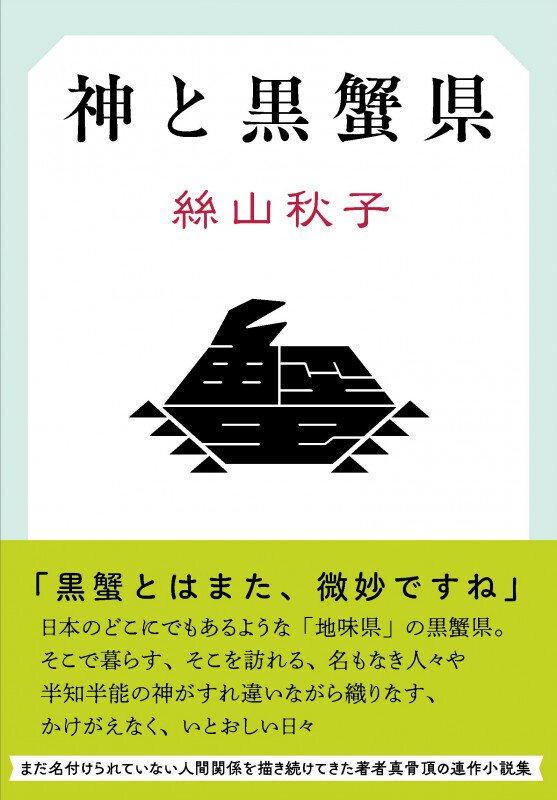
絲山秋子さん好きにはたまらない魅力が詰まった作品です。ファンタジーですが、細部の地方都市のリアリティが抜群にうまい。黒蟹辞典と地図で何時間でも妄想が掻き立てられます。
ミニマル料理
稲田俊輔

これまでのレシピ本とは一線を画すシンプル料理のマニュアル。合理的というか理系的というか、記載に無駄がない。料理に関心が薄かったり、ほとんどやったことがない人に向いているのかもしれません。
逆に料理が好きで趣味にしているような方が、この本をどう感じるかについても聞いてみたい。
一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書
ネオ高等遊民
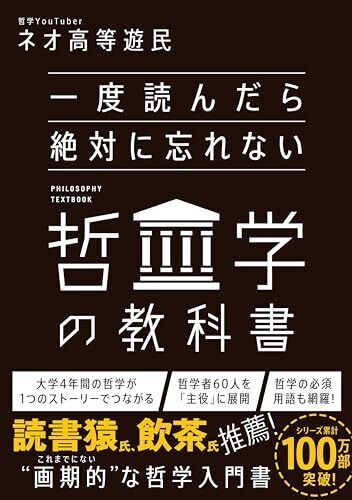
みんな大好き哲学系YouTuberのネオ高等遊民さんによる古代から現代までを網羅した哲学の通史。
取り上げられている哲学者にもよりますが、通史なので流れがあって概ね読みやすいと思います。本書を読んでから千葉雅也さんの『現代思想入門』を読むと良いと感じました。
哲学にちょっと興味はあるけど硬派な本は苦手な人にお勧めです。
波止場日記 労働と思索 (始まりの本)
エリック・ホッファー 田中淳 森達也

とても良い読後感。薄っぺらい文字シンボルのみを操る知識人への反感、自由とは何か、働くことと思索すること、いろいろと改めて考えさせられる。他の著作も読んでみよう。
科学がきらわれる理由
ロビン・ダンバー 松浦俊輔

科学についての方法論、マインドセットやそれにまつわる諸々がていねいに書かれている。サイエンスとはどういう態度なのか、なぜ私たちはその態度が分かりにくいと感じてしまうのか。人文系の一部の研究者への憤りも含めて、大変面白く興味深い。
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下
アンディ・ウィアー 小野田和子

普段SFはあまり読まないのだけど、こういう緻密な構成を荒唐無稽にならないように上手く読ませるのは素晴らしい。小松左京っぽさもあるように感じる。「火星の人」も読みたくなってきました。
関心領域
マーティン・エイミス 北田絵里子 田野大輔

とてもひとことでは表現できない読後感。映画もぜひ観たいと思います。
万物の黎明 人類史を根本からくつがえす
デヴィッド・グレーバー デヴィッド・ウェングロウ 酒井隆史
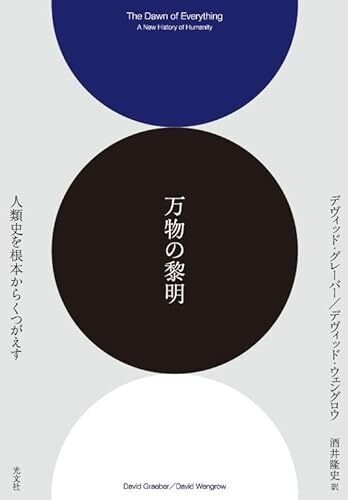
ひとことで言えば「ビッグ・ヒストリー」への疑問、アンチの超大作だが、ハラリやダイアモンド、ピンカーなどをポップ人類史と徹底的に批判しているのが興味深い。
遊戯農耕とシリアス農耕というコンセプトも大変面白い。わかりやすく直線的に語ることの弊害にも気付かされる。
膨大で熱のこもった訳者あとがきもあるので、先にここから読んで全体の見取り図とするのも良いと感じた。
まだ、うまく眠れない
石田月美

エッセイでありドキュメンタリーでもあるのに、どこか散文ではなく詩を読んでいるように感じます。
著者の生き方・人生観がストレートにほとばしる表現。人によってはあざとく感じてしまう人もいるかも知れません。うまく言語化できないけれど、言葉の使い方がとても新鮮で格好いいです。
老いぼれを燃やせ
マーガレット・アトウッド 鴻巣友季子

おっさんおばさんはみんな読むと良いと思う。単なる懐古趣味や昔は良かったではなく、痛快で小気味良いのにしみじみと時の流れの恐ろしさを感じてしまう不思議な読後感を味わえる。
かなり好き嫌いが出る作品がほとんどだと思うが、おっさんである私は十分楽しめた。
周恩来キッシンジャー機密会談録 (岩波オンデマンドブックス)
毛里和子 増田弘

本物の史実の面白さ。米国での機密が解除され公開された公式記録なので、大変興味深かった。
ニュースでは数行で済まされる会見の裏にはどんなやりとりがあったのか。対話から緊張感が伝わってくる。大国の外交とはどんなものかの一端がわかるような気持ちになった。
50年前の記録にもかかわらず、当事者のひとりキッシンジャー氏などつい最近まで存命であったのも深みを増している。
侍女の物語
マーガレット・アトウッド 斎藤英治

恥ずかしながら初めて読んだが、ディストピア小説の古典と称されるのも納得。なんとも言えない閉じ込められた閉塞感がじわっとまとわりついてくる。
それでもちゃんとエンタテインメントになっているのが素晴らしい。
いいなと思ったら応援しよう!

