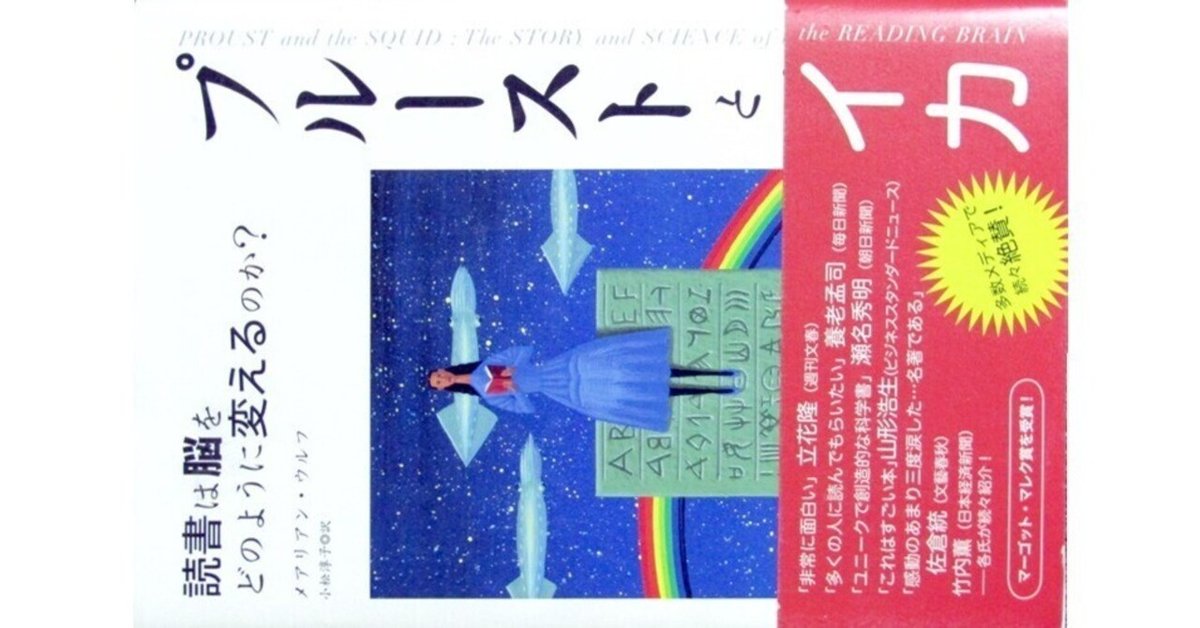
『プルーストとイカ』(メアリアン・ウルフ:小松淳子訳・インターシフト)
今井むつみ教授の推薦の本である。早速読みたくなった。
タイトルが普通ではない。一般向けの書であるために、ユニークなものとしたのだろうとは思うが、分野としては脳科学に属する。テーマは、読書である。さらに言えば、文字が人間の脳に与えた影響を探るというものである。
人間の能力については、しばしばそれの欠陥や障害の実例を探ることによって、健常者の能力や性質が明らかになる場合がある。本書においても、大きな軸として、「ディスレクシア(読字障害)」について調べることで、文字を読解するということはどういうことなのかを探ろうとしている。
サブタイトルは「読書は脳をどのように変えるのか?」というものだ。
ずっと言われていたことではあるが、スマートフォンが行き渡るにつれ、ますます「読書」についての大人の懸念は進んでいる。いまや、1か月に一冊も本を読まないとアンケートで答えた人が、3分の2に迫ろうとしている。これは様々な意味で、人間の能力に対してもそうだが、その社会生活、それから社会の構成にまで影響を与えるのではないか、と心配されているのである。
塾で子どもたちに勉強を教えるのが私の仕事だが、算数の能力の劣化を時が経つにつれ顕著に見ているのはずっと気になっていたが、読解力の劣化も著しいことを実感もしている。そもそも語彙が少ないというのも悲痛に感じているが、それも年々減少しているような気がしてならない。ごく当たり前の日常語や、少々小説でも読んでいれば知らないはずのない言葉が、まったく外国語のように聞こえるというぽかんとした顔を授業で日常的に感じているのである。人間は言語により思考する。言語の貧困は、思考の劣化をも示す。さらにれは、想像力の欠如をも意味し、感性も悟性も理性も、うまくつながって機能しない事態を招いていると推測される。
ただ、それはそう「感じる」ということであるだけで、事実データとしてはどうなのか、という点では、迂闊なことは言えないというのが自戒であった。
ただ、本書のようなものに触れて改めてじっくり話を聞いていくと、人間が文字を解読するということは、実に大変なことなのだ、ということに思い当たった。そう、考えてみれば、文明国と言われる国々であっても、つい百年あるいは二百年前には、文字が読める人というのは、ごく一部に過ぎなかったのであり、多くは文字が読めなくても生活していけたのである。『ハイジ』でも、字が読めるようになったハイジが、アルムじいさんに放蕩息子のたとえを読んで聞かせることによって、じいさんは回心するという設定になっていたし、ペーターもまたついに文字は読めないままだった。19世紀、それが村人の普通の姿なのだった。
古代エジプトでは、書記という役職は、超エリートだった。聖書の歴史を考えても、聖書は代表が読んで聞かせるものであって、聖書という書物を人々が読むという信仰生活は、ずっと後の世代でしか実現しなかった。日本では寺子屋の発達があり、世界的に見ても文字の読み書きは進んでいる方だったという推測があるが、明治期にも比較的多くの人が本を読むことができたのではないか、と考えられている。それでも、読書というのは朗読するというのが常態であり、黙読という読み方は、非常に新しいものだと聞いたことがある。
プルーストとくれば、『失われた時を求めて』という超大作で知られるが、彼は「読書」というものを、「人間が本来ならば遭遇することも理解することもなく終わってしまう幾千もの現実に触れることのできる、一種の地域"聖域"と考えていた」そうである。知的生活を一変させる力を秘めているものとして、読書を捉えていたというのである。著者は、この言葉に限らず、プルーストの読書観に刺激され、この研究に進んでいるようだ。
また、イカには長い中枢軸索があり、ニューロンの発火の解明によく用いられたらしい。それは、「人間の脳が読むために行わなければならないことと、それがうまくいかなかった場合に適用する巧みな方法に関する研究と相通じるところがある」のだそうだ。
長い旅が始まる。古代文字の歴史を辿る試みは、聖書について考える場合にも大いに参考になりそうだ。それはやがて「アルファベット」という、画期的な文字のあり方に到達する。この表音文字が、文字というものを人間が用いるにあたり、決定的な役割を果たすのである。さしあたり、それはギリシア文字として生まれ、これが人類史上のエポックとなるのだ、というように著者は捉える。
但し、そのギリシア文字について、ソクラテスという哲学の象徴にあたる人物が、たいへんな警告を与えている。ソクラテスは書き言葉を嫌い、それは人間に害を及ぼすことを警告していたのだ。皮肉なことに、そのソクラテスの考え方を後世に伝えたのは、弟子プラトンによる書物であったわけだが、確かにソクラテス自身は自らは何も書いたことがなく、対話により思索したことだけが伝えられている。この件は、最後の結論でも大きな論点となる。
字を読むとはどういうことか。それは、人類が身に着けた特別な能力であるのだという。少なくとも、遺伝子の中に、読字能力がセットされているのではない、というのが本書の大きな主張の一つである。それを含めて、脳科学の実験や研究を丹念に辿ることで、確実なデータとして説明することを怠らない。そして、子どもが読むということについて、特にその発達について、細かく丁寧に解説が加えられてゆく。結論としては、子どもが親の膝の上で、同じ絵本を幾度も幾度も繰り返し読み聞かせてもらうことが、子どもの文字の認識や言語生活、読書に至る道を形成する、というものであった。これには私は大賛成であり、共感できる。経験的に、納得できる。著者は、そのような仕方で言語を授けられなかった子どもの場合、語彙としても読字能力としても、格段の差が実際についてしまうことを指摘している。
このことを、先ほど挙げたディスレクシア(読字障害)を題材に論じてゆく。単純に右脳と左脳と分けてよいのか分からないが、おおまかに言うと、文字を図像として認識する仕方と、その概念や意味を把握する仕方とが、脳の別の箇所で行われ、それらを一種の訓練によって瞬時に回線で結ぶことが素早くできるようになってこそ、読書というものが成り立つのだそうだ。
細かな議論が苦手な、それこそ読書が苦痛であるような方は、最後の「結論」だけをお読みになっても、概略は伝わるのではないかと思う。そして、著者自身、家族にディスレクシアがいることによって、この研究を実践的に生きているということも告白されるため、身につまされるような感覚を与えられるのではないかと思う。
遺伝子の中に、本を読む能力はない。読書そのものは、遺伝子により決定されるものではないという。いまの子どもたちは、人類が2000年にわたって身に着け発展させてきたこの能力を、2000日で獲得するような教育を受けている。そのときに、先の絵本のように、快い環境で、素早く文字から意味へと結びつくことが繰り返されてゆくことによって、その能力を得てゆくのである。
読書が簡単でない、という当たり前のことに、今さらながら気づかされた。万人が同じように読書をすべきだ、という前提で考えることが間違っているのだ。読書をしない人が3分の2いるというのは、人類の歴史の上では、極めて当然のことであるのかもしれない。
なお、時折中国語や日本語についても、気にした叙述がある。著者はアメリカでこの研究をしているわけだから、英語という背景で文字認識と読書の理屈を捉えている。本書は基本的にそれで貫かれている。だが、漢字というものの妙を知らないのではない。漢字は、アルファベットの認識とは、かなり異なる背景をもち、構造を有しているはずである。時折そのことに軽く触れながらも、本書でそれに深入りすることはできていない。これについて日本人研究者が、漢字の認識ということについて、より詳しく、明確なことを教えてくれると私はうれしく思う。
すでに始まっていた、デジタル機器による読書というものが、従来の読書とどう違うのか、そこに一定の違いがあることを、著者は幾らか臭わせている。だが将来的にデジタル主体へ移ることがあるにしても、本質的な部分では比較的楽観的に構えているように見えた。ところが、その後10年、その「違い」の部分が際立ってきたのではないかと思われる。まだ本書の時期には、そこまで立ち入ってはいなかったのだ。そこで、デジタルで読むことと、紙の本で読むこととについての比較研究が必要となり、本書にはその続編が発行されている。私は早速それも取り寄せた。
