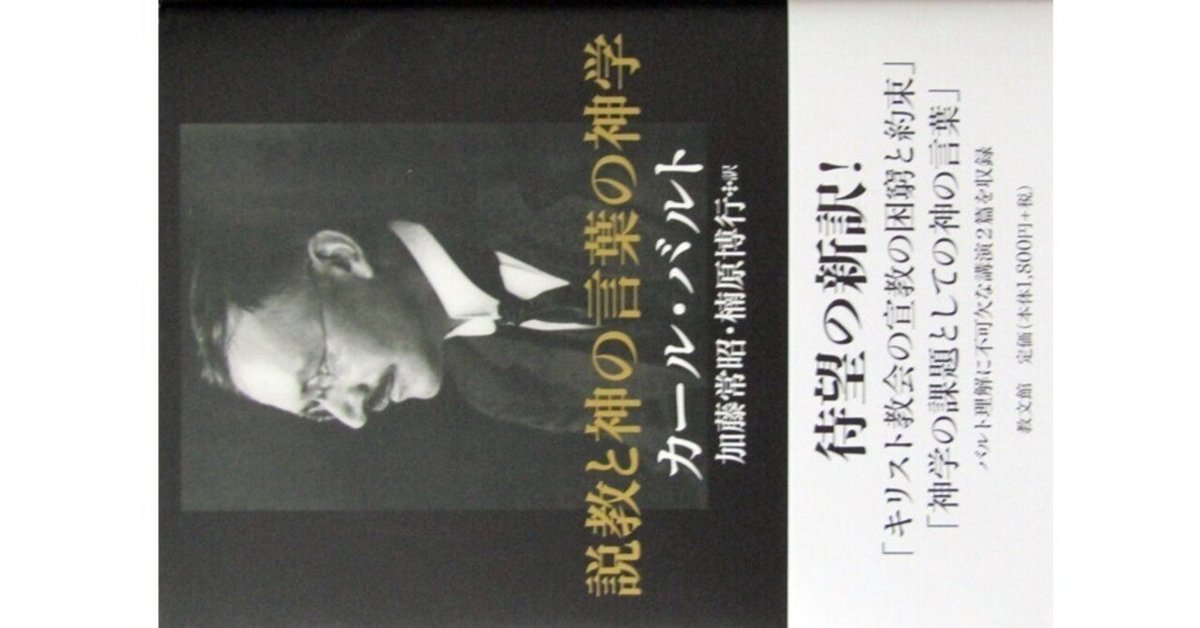
『説教と神の言葉の神学』(カール・バルト:加藤常昭・楠原博行訳・教文館)
以下は、カール・バルトのよく知られている、1922年に語られた講演「キリスト教会の宣教の困窮と約束」の新しい翻訳である。――ここから「はじめに」が始まる。訳者のひとり、加藤常昭氏の手によるものである。本書の発行後、一か月を待たずして、召されることとなった。
主宰する説教塾で必要があって翻訳したものである。それが出版に値するということで、「新訳」として世に問われることとなった。これは、百年後の現在、説教者たちがこぞって心して読まねばならないものである、という切実な思いからである。それが、こうして遺言となって、私の手許に届いたことになる。あの最後の説教を聴いた礼拝の感動から半年、なんとも感慨深いものがある。
同じ「はじめに」は、次のような内容で結ばれている。「私は、今もなお、私ども説教者にとって必読の文章と考える。」「教会の立つべき原典に立ち戻ることができればと願う。」
本書には、二つの講演の新訳が収められている。「キリスト教会の宣教の困窮と約束」並びに「神学の課題としての神の言葉」である。後者は榊原氏の訳である。
百年前は、第一次大戦後の厳しいドイツ情況があった。人々の信仰への具体的な詳細は知らないが、教会が信用されていたかどうかという点は疑わしい。実際、人々の心が教会から離れていることが、この講演の危機感に現れているように見える。
バルト自身、このころ新進気鋭のオピニオンリーダーとして光を浴びると共に、キリスト教世界からは異端視され、非難も受けていた。二つの講演のうち、前者は1922年7月、牧師会に招かれて話したもの、後者は同年10月、キリスト教の会議において、ためらいつつ列車の中で書き終えた原稿に基づく講演であったという。これらのエピソードが、前者は始まって間もなくの「注」の中で、後者は後半の訳者による「はじめに」の中で明かされている。それぞれ別個の訳出原稿であったためであろう。この辺り、読者のためにはひとつにまとめて提示できなかったか、とも思う。というのは、確か由来がどこかに書いてあった、と私が思い返したとき、どこにあるのかしばらく探したからである。しかし、本書の訳の由来を知る限り、それはやむを得ないことのようにも思われる。
いま触れた「注」だが、これが非常に見やすくてよい。開いたその頁の左端が、その「注」の場所として確保されている。しかも、ありがちなことだが、えらく小さな文字で書かれてあることが多い中で、本文とあまり変わらないポイントで、読みやすく整えられている。尤も、「注」を入れてもそれほど長い分量とならなかったために、書物の体裁を調えるために、あまり小さな文字や詰めた行間であってはならなかった、という事情もあるだろう。全部で170頁、今どきの書物としては相応の価格となったが、文面そのものの量はさほど多くはない。
否、そんなことを気にしている場合ではない。これはバルトである。まだ36歳、世を注目させた『ローマ書』から3年、若々しい勢いがここにあるが、その著書同様、非常にもってまわった表現と文体が犇めいており、流して読むことを許さない魅力、あるいは困難がある。一読しても分かりづらいのは、語る方が、できるだけ正確に説いてゆこうとする気持ちから、一つの文の中に何もかも注ぎ込んでゆくからであるが、これを実際人々は、耳で聞いたのである。耳で聞くと、これは呑み込みやすいのだろうか。
従って、これが文章として見える形になったのは、やはり幸運であった。それだから、何度も辿り直し、行きつ戻りつその真意を掴もうと努めるしかない。分量に価値があるのではないわけだ。
そのためにも、これらの「注」は、並の本のそれとは違い、この講演の背景にあることや、ゲーテやギリシア古典にある言い回しを含んでいることなど、理解のために必要と思しき多くの素材に満ちている。当時のドイツの教会の立場や習慣など、読むにあたり必要な知識であるだろうにも拘らず、通常あまり意識されずに出版されてしまうようなことも、そこには多く盛り込まれている。こうした「注」に、非常に価値のあるものがある、と考えたい。
それは、講演のタイトルの「キリスト教会」あるいは「困窮」という訳語についても、細かく検討されていることを説明する場にもなっている。そのドイツ語が何であるか、それはバルトにとってどのような意味を含んでいるのか、他の著作でどう説明されているか、そこまでこれらの「注」には書かれている。説教塾での学びのテクストとして使われただけのことはある。本当に、これは勉強会のための資料ではなかろうか。
内容については、お読み戴くしかない。困窮の中でこそ神学が存立すること、しかしそこには約束があり、希望があること、それを期待する人々に説教が応えるべきことを目論むが、二つ目の講演では、人間にはそもそもそうしたことが不可能である、という苦悩を示さなければならなかった。確かに、時代における危機がある。十字架に立ち帰るべきことは分かっているが、それにしても教会の置かれた情況は厳しい。その上で、神について語らねばならないと共に、神について語ることなどできないのだ、というところから出発しなければならないのが説教者なのである。それでも、バルトは問う。問いと答えとの一種の同一性を明かしつつ、私たちは神が人となられるところに焦点を当てていくように向きを定めることになる。それを高い所に掲げて信仰を迫るようなやり方であってはならない。人々は問うてよいのだ。二つ目の講演では、やはり「教会」はどうあるべきか、を背景に置きながら、説教することに向き合っている。人が、教会が、権威を以て教えるようなことは、もうできないだろう。神に語って戴こう。但し、イエス・キリストを証ししよう。
中にちょろっと出てきただけの言い回しだが、私の心に強く残ったものがある。聖書を語り説教をする者にとってできるのは、「ひとかけらの真理」を示すことと、そこに「ひとかけらの永遠」があることを確信することなのだ。ああ、確かに、自分にできることは、「ひとかけらの」ものであるに過ぎない。だが、それは間違いなく、「真理」と「永遠」の一部なのだ。この信仰と共に、何度も読み返してみたい本である。日本のキリスト教会が、死なないために。
なお、本書は「カール・バルト著作集」に既にある訳を新たに訳出したものである。本の帯にも「新訳」の文字が強調されている。私はどうしても、そこに「新約」の文字を重ねて見てしまうのだったが、書店側に、隠れたその意図は、なかったのだろうか。
