
電気信号論争 篇
1. 唯物論者たちとの死闘の始まり
現在、林田が主催っぽくやっている勉強会に、論語講座@東京(月1回)、論語講座@大宰府(月1回)、経済学講座(どこかで再開予定)、中国語研究会(麻雀ではない方)と、まさに学びを遊びと化して小銭を稼ごうというチノアソビを体現しているわけですけれども、2024年、最も壮絶な論争を巻き起こしたのが荘子講座(月2回/隔週木曜日開催)での電気信号論争です。
論争相手は、林田の宿敵、高木ランラン。自称物理学者。48歳、独身(未婚)です。

電気信号論争がどんなものであるかというと、市井の物理学者にして、量子力学の申し子らんらんがいう「この世の全ては電気信号である」と主張するのに対して、林田が「心も電気信号なのか?」という疑義を問いかけたことに始まります。
らんらん子、曰く、
「心も電気信号である」
と断言されてしまったので、林田は続けて問いました。では、心はどこにあるのかと。らんらん子、答えて曰く、
「脳が体に電気信号を送って、それを体が受け取って動いている。つまり、心は脳である」
とさらに断言するんですね。
「ならば、人は恋をしたとき、もしくは悲しいことがあったり、嬉しいことがあったとき、心躍る、もしくは心が締め付けられる、胸が痛い、という表現をするのだが、脳が喜んだり、痛くなったりはしない」
と反論すると、
「馬鹿かテメェは、それも全部、脳がそうなるように電気信号を送っとるんじゃ」
などとヌかすので、
「何かい、ええっ?嬉しいことがあった時に、脳が、あっ、うれしい、胸よドキドキしろー、とかって信号を出すのかい?それに何の生物学的合理性があるんじゃボケェー!!」
と激昂して大論争に発展しているのです(ちなみに、チノアソビの競馬担当、こゆちゃんには、人生で胸が痛くなったことなんかない、と返されて討ち死にしそうになりました)。
これを一度、チノアソビ本編にて、理系担当のすーさんにぶつけてみたことがありました。
「すーさん、心というものの物理的存在は確認できないけれども、心はある、ということには同意するよね?」
と、本当は、その後、心の本義について話を進めたかったのですが、すーさんは、しばし考えたあと、
「それは定義による」
と呟いて、時間やらメートルやらキログラムやらを片っ端から定義しまくるという明後日の方向に進んでしまいました(現在進行中)。
何というんでしょう。『星の王子さま』の中で「本当に大事なものは目に見えないんだよ」といわしめたサン=テグジュペリのロマンチシズムを根底から覆す物理学者どもの無骨さ。
歴史派経済学をルーツとする(そこそこ理系的思考も入っているはずの)文系代表、林田も、だんだんとこういう気分になってきました。

2. アリストテレスの形而上学
しかしながら、向こうは最新の物理学の理論らしきもので武装しているので、文系としての反論体系を整えていないぼくとしては『神学大全』も書かずにイスラム教徒と論争するトマス=アクィナスの様相を呈してきました。
そこで、まず存在論についての整理をしておこうと思い立ちました。ギリシャの哲学者の中で、最初に存在論に言及したのはパルメニデスです。パルメニデスは、
「そこに物が存在しているから、物がそこに"ある"」
と言いました。これはまぁ、当たり前の話なのですが、これを受けてプラトンは、では物がない状態というのはどういうことなのか(非存在)について考えました。
プラトンは、存在と非存在とは対立するものではなく、存在は、非存在によって我々の前に現れる、と考えました。

つまり、ここに飲み物(存在)がある。この飲み物は、水ではなく(非存在)、コーラでもなく(非存在)、ビールでもない(非存在)。これはコーヒーである(存在)と言ったわけですね。
プラトンの弟子のアリストテレスは、このことを「存在本質」と呼びました。すなわち、すべての「ある物(上の例では飲み物)」は「何か(ここではコーヒー)」であり、この「何か」が存在本質だというわけです。アリストテレスは、どのような原理に基づいて「ある」のかを問う学問を「第一哲学」と呼びました。今日では、我々はこの哲学のことを「形而上学」と呼んでいます。
3. 心は自然界にどう収まるのか?
実は、林田-らんらん論争を待つまでもなく、この「心は我々の世界のどこに存在しているのか?」という主題は、哲学において古典的な課題でした。
やはり古の物理学者の中にもらんらんのような人がいて、彼らが唱えたのが「心脳同一説」でした。

仮に、自然科学、ここでは物理学と置き換えておきましょうか、の中において、非物質的な心や魂といったものの存在を否定したとき、意識(これまた自然科学界で存在を証明するのが難しい)を伴う主観的な経験はどう説明されるのでしょうか。
唯物論者にとって、バスケットボールの試合をしていて、選手Aが選手Bにパスを出し、選手Bがゴールを決めて勝利しました、という事実は、それ以上もそれ以下もないのです。
ですが、それまで人間関係として歪みあっていた流川 楓が、山王戦に勝つために桜木 花道にパスを出し、桜木の左手は添えるだけシュートによって逆転勝ちを収める、というシーンには主観的経験に伴う意識が存在しているのです。

4. 決定不全性テーゼ
意識、とか心、魂といったものを考えるときに、物理学者たちが用いたのが「還元論」でした。還元論とは、複雑なことでも、それを構成する要素に分解して、個別の要素だけを理解すれば全体を理解できる、という考え方です(要素還元主義)。
「心とは脳から発せられる電気信号に過ぎない」
という考え方が、まさに要素還元主義の穴に陥っている考え方です(ちなみに、現代社会のあらゆる事象が還元論的に取り扱われいて、その弊害が大きくなってきたのが、メタ認知教が拡大している要因でもあります)。
しかし、この還元論的な思考には「決定不全性テーゼ」と言われる弱点があります。決定不全性テーゼとは「結局、物理現象を説明するだけでは十分な理解に到達できない」ことを意味します。
例えば、ある人が、マラソンを走っていて、太ももにピキーンと痛みを覚えたとしましょう。同じ人が別のときに、都営新宿線の満員電車に乗っていて、太ももにピキーンと痛みを覚えたとしましょう。
計れるものではありませんが、この痛みは同じレベルの痛みだったと仮定します。脳が太ももからの電気信号を受け取って、痛みを発する。全く同じ構造で。でも、心のもち様は異なります。前者は、
「ああ、マラソン走ってて太もも痛めたわぁ」
と原因がハッキリしていますが、後者は、
「え?なに?なんで太もも痛くなった?」
と原因が分からずに心は不安になっていきます。このように、意識は物理学では還元できないのです。
5. 心は脳に還元できないんだよ
ここまで書いたことを総括して考えると、存在論は大きく二つに分かれます。
どこまで行っても唯物論
存在するのは宇宙だけ。全てが物質とエネルギーからなる存在
どこまで行っても観念論
存在するのは心的なものだけ。物質やエネルギーも全て心的
どこまで行っても唯物論は、らんらん派と言って良いでしょう。ですが、ぼくがどこまで行っても観念論派というわけではありません。こうした一元論(一つの考え方を元にして世界が構成されている)の考え方では、説明できないことが多すぎるからです。
今のところ、ぼくとしては物質的存在と心的存在の両方を認めたい(形而上学的二元論)。でも、この二つには大きな溝があリます。サイクリングをするために自転車が必要です(物質的存在論)。でも、サイクリングに行きたくなる理由は自転車があるからではありません(心的存在論)。
何が言いたいかというと、やはり心の問題は脳の機能に還元できないのです。
と、いったん今のぼくの立ち位置をまとめつつ、孫子曰く、敵を知り己を知らば百戦危うからず、ということで、今年はらんらんの主戦場である物理学も勉強していきたいと思います。
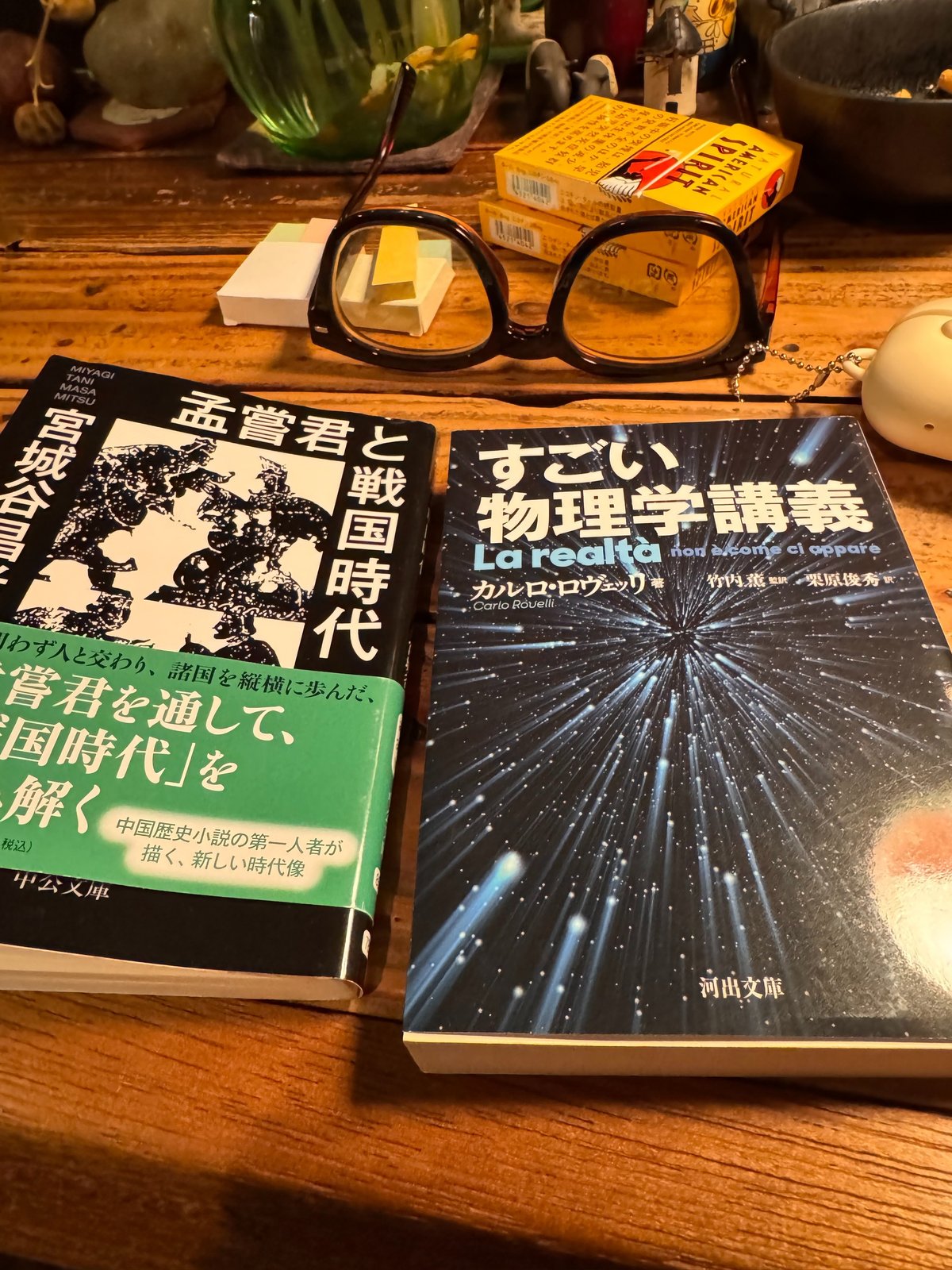
結論らしきものがなくて申し訳ない。
異論・反論はどしどし受け付けておりますが、よかったらイイねを押してくれたまへ。また哲学の世界でお逢いましょう。
(了) 2025 vol.004
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
